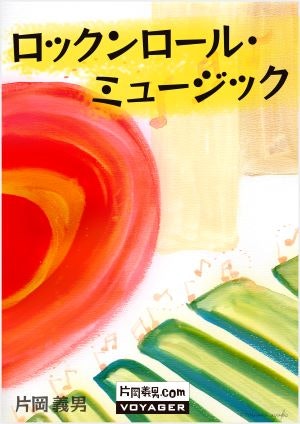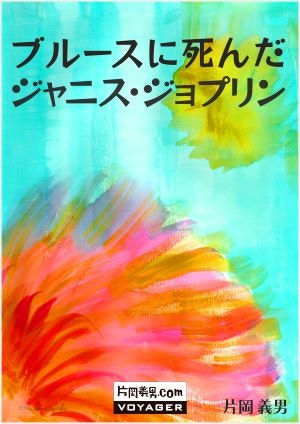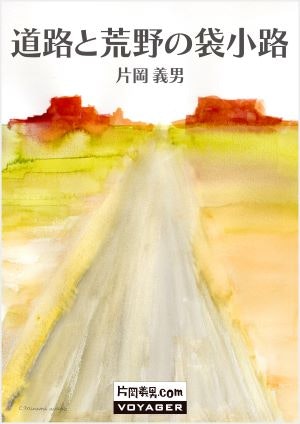エッセイ『10セントの意識革命』『アメリカに生きる彼女たち』から28作品を公開
『10セントの意識革命』(晶文社/1973年、底本は2015年版)、『アメリカに生きる彼女たち 一九四九ー一九九五 雑誌広告に見るアメリカ女性像』(研究社出版/1995年)から28篇の作品を本日公開いたしました。
ぼくにとっての1950年代は、ちょうど10歳から20歳までの期間だ。この期間のことに関して、なぜいまになって、アメリカの側から書くのか、その理由は、ごく単純だ。この1950年代に、ぼくというひとりのヒトの気質みたいなものが、ほぼできあがったか、あるいは、アメリカの1950年代の歴史的な進行のなかから、ぼくの気質がなんらかのかたちでかなりのっぴきならない影響をうけてしまったように、今になってやっと思えてきたからだ。ロイ・ロジャーズやカントリー・アンド・ウェスタン、10セントのコミック・ブック、ジェームズ・ディーンの『理由なき反抗』や『地上より永遠に』。決定的なとどめは、エルヴィス・プレスリーの最初のシングル盤『ザッツ・オール・ライト、ママ』だった。
1950年代アメリカのロックンロールは、正確には1954年から58年までのわずか4年間しか続かなかったのだ。この4年間に、エルヴィス・プレスリーと(DJの)アラン・フリードのふたりが、完全に燃焼した。しかし外へ出ていこうとする力を持ったビートは、わずか4年間で消えていくには強烈すぎた。チャック・ベリーの存在はまったく知らなくてエルヴィス・プレスリーだけにひかれていた白人たちにすら、ビートはなにかを語りかけることができた。なにを語りかけたかは明確には定義づけることはできないのだが、あいまいなかたちではあったけれども、ロックンロールのビートは、それを文句なしにうけとめることのできた人たちのなかに、ある種の確信をつくった。けっして真実をみつけたわけではない。なにものかを力強く肯定することのまずはじめのチャンスが、ロックンロールのビートだった。
1961年、アイゼンハワーを引き継ぎ大統領となったケネディが唱えたかけ声は「ニュー・フロンティア」であった。アメリカにとって、「フロンティア」は、軍備拡大とほぼ同義語である。その「フロンティア」に対して「ニュー」の形容詞を加え、アメリカにとって新しいフロンティアがまだどこかに存在するかのような錯覚をアメリカに与えた。アメリカにはいくつかの美点が疑いもなく存在する。そしてそのうちのひとつは、アメリカはいつになっても徹底的に一貫している事実だ。市場的な領土拡大のためにアメリカがおこなってきた戦争はすべて神が許してきた。アメリカは決して好戦的なわけではない。自分の国にない資源を外国で手に入れ、自国の余剰生産品を輸出して平和に繁栄したいと考えているだけだ。ただ、アメリカだけの都合ではなにも動かなくなり武力への訴えかけの機会が多くなり、全面核戦争を回避するための力のバランスを保つために軍事費が武器の進歩にあわせて増大していくだけなのだ。自分としてはごく当然のことをやっているだけだ。それをやっていながらなぜベトナムで勝てないのか不思議でならないというかわいそうな全能の神、それがアメリカだ。
『理由なき反抗』(1955年)のなかで、ジェームズ・ディーンはジャンパーを着て現れる。調べたところによると、マクレガー製の赤いスコッチ・ドリズラーの変形で、生地は化学繊維あるいは50パーセントほどの混紡ではないだろうか、ということなのだ。そして、ぼくの記憶のなかでも、そのジャンパーの色だけは、赤になっている。この赤いジャンパーは、1950年代後半のアメリカの服装に対して大きな影響力を持ったにちがいない。スポーツ・ウェアふうなカジュアルな服装がアメリカに広がりはじめたのは、1950年代なかばからだ。男もののシャツの思想が女性のブラウスにおよび、ブラウスはシャツに圧倒され、左ボタンは男とおなじ右ボタンにかわった。そして女性用ブルージーンズのジパーが正面につくようになって「女性用ブルージーンズ」が存在しなくなり、男と女との腰の大きさの違いによってひきおこされるサイズの差のみでわけられた「男性用」と「女性用」とは存在しても、それ以外の要素による「女性用ブルージーンズ」は、本質的にはなくなってしまった。
私立探偵マイク・ハマーを主人公にすえたミッキー・スピレインの第一作は、1947年に単行本として世に出た。太平洋戦争が終ってから2年たっていた。48年の冬には、簡易装丁の大量生産本となり、ベストセラーになっていく。マイク・ハマーのシリーズがよく売れた理由として、サディズム、セックス描写、共産主義敵視思想、マイク・ハマーのスピードのある行動性などがあげられているが、これは、すべて根本的にはまちがいなのだ。マイク・ハマーのすべては、「俺は自由だ」という観念に支えられて成立している。私立探偵を小説で読ませるかわりにテレビでみせるためには、ひとつの大きな工夫が必要だった。ひとりの私立探偵を、数人のグループに分割することだ。『サーフサイド6』『ハワイアン・アイ』『アイ・スパイ』『ルート66』『ナポレオン・ソロ』すべて主人公はふたり以上であり、ふたりの場合はどちらがより重要なパートであるのかは、たやすく決定することはできなかった。そして西部劇の世界でも、同じことがおこっていた。
アメリカの1950年代半ばから後半にかけて、エルヴィス・プレスリーをとりあげたファン雑誌の多くが、食べものに関するエルヴィスの好みを、記事の重要な一部としてのせていた。まず、ピーナツバター・サンドイッチについてだ。エルヴィスは、このピーナツバターが好きだった。しかも、ごく普通の白い食パンに塗りつけ、ピーナツバターは口のなかにはりつくものだから、ミルクやペプシコーラで流し込むのだ。ポーク・グレイヴィも、エルヴィスの好物だった。フライパンに油をひいてポークを炒めたあとに残る汁に味をつけたようなもので、家庭料理としても決して上等の部類にはいるものではない。エルヴィスにとって、ポーク・グレイヴィは、ピーナツバターに対立するものであったに違いない。と、同時にピーナツバターを、仮りに新しい世界だとするならば、ポーク・グレイヴィは、昔ながらの世界なのだ。ピーナツバターを、仮りに新しい世界だとするならば、ポーク・グレイヴィは、昔ながらの世界なのだ。しかしどちらもエルヴィスにとっては貴重なものだった。
アメリカのものが日本に入ってくる場合、ほとんどが、いや、もうすべてが、曲解され誤解され、その結果、ごくつまらない姿で日本に居つくことになる伝統が昔からあり、カントリー・アンド・ウェスタンも例外ではないという気がしている。カントリー・アンド・ウェスタンは、アメリカの源流、いや、音楽だけではなくて、アメリカそのものの原点だというようなことが盛んに言われるようになっている。こういうのは困る。ムーン・マリカンとかハンク・スノウとかキャル・スミスとかニュー・ライダーズ・オヴ・ザ・パープル・セイジとかが、ぼくのいうカントリー・アンド・ウェスタンなのだ。共通しているものは、ブギウギの生命力とかダイナミズムだとぼくは思う。定着者たちに対して、常に動きまわっている、旅の多い人生をおくっている人たちがいて、そのような人たちの音楽が、カントリー・アンド・ウェスタンではないのか。
ロックンロールは、ほかに近似の例さえみつけることのできない、希に見る珍らしい、しかも新しい歌だった。珍らしくて新しかったけれども、しかしそれはなんらかの思惑のもとに無理やりに造り出されたものではなく、どこかへ向かって動いていく歴史の必然みたいなもののなかから、神のタイミングを備えて、しぼり出されてきたものだった。ロックンロールがごく一般的な形でこの社会の表面へにじみ出して広がっていった、アメリカの1950年代初めの頃は、ロックンローラーたちの行手に、絶望の一角がちらりと見え始めた時代だった。自分たちの文明が、全体的に間違った方向へ曲がっていきつつあるという認識は、ある日いきなり、ごくぼんやりとした、あいまいなかたちで、なされた。その認識の当事者であるロックンローラーたちにさえ、明確には意識化できないような姿で。
エルヴィス・プレスリーの特殊性は、ごく簡単に言うと、ロックンロールのサウンドとして受けとめうる孤独な実感の抽象度が、ほかのすぐれて抽象度の高かったロックンローラーに比較すると、かなり低かった、という点にある。精神的にもやはり、ロックンロールは、基本的にはギター・ミュージックなのだ。エルヴィスは、ギターをなんらかの支えにしてはいたが、それを弾いて自分のサウンドを表現することはしなかった。そのかわりに、彼は、自分の内部にためこんでいたエモーションを、肉声による歌ひとつに託して、爆発させ、ぶちまけるように、表現していた。つまり、彼が抱え込んでいたエモーションは、激しくはあったけれども、範囲はちょっと狭かったようだ。その狭さのおかげで、一点に絞り込まれた、官能的ではありつつなおもキラキラとした透明で澄んだ感じの熱意が、増幅されている。
ジャニス・ジョプリンの不自由さには、ちょっとした感動みたいなものを覚えないわけにはいかない。「観客の目の前で、自分が歌うひとつひとつの歌の首を絞め上げるような」歌い方もさることながら、彼女には目の前に観客がたくさん座って熱狂しているステージというものが常に必要であり、ステージをひきずって歩いているような彼女の毎日が、レコードを聞いていてすら、いたたまれないほどの悲しい不自由さとして、迫ってきてしまう。自分は絶叫して歌わなくてはならないのだというブルース的な衝動は、極めて個人的なものだが、その衝動が一丁のギターをくぐりぬけるとき、あるいは、バンドをしたがえたひとりの歌い手が、ある種のステージ・プレゼンスを湛えて歌にかえていくとき、そのブルース衝動は、万人とまではいかなくとも、その場に居合わせた人たちのうちの何人かに、抽象化された形で、一瞬の普遍性をおびて、伝えられうることは、いまさら言うまでもない。
アメリカのユーモア雑誌『マッド』を古本で買うようになってから2、3年にはなるだろう。裏表紙の表に、ほぼ1ページ全面をつかって、ひとつのカラーの絵がのせてある。この絵は、シカケ絵で、指示どおり2個所でタテに折り、折ったところどうしつなげると、またべつの絵になる。線は引いてなく、折ったあとに出現する絵柄を頼りに改めてきちんと折ることになる。古本で買うとこの手間を省ける。『マッド』は、時の流れを適当にとり入れている。すでに世の中でとっくに起こってしまったことを、しばらくたってから、比較的穏やかな形でとりあげて笑わせるのだから、事後の消極的な笑いと言えるだろう。なるほど、いや、我々はまったくこのとおりだよ、と見る人をして身につまされた感じにおとし入れるテクニックは、ポピュラー・カルチャーの使い飽きない手口のひとつだ。
ブロードウェイと西37番通りとの交叉点だっただろうか。ぼくは歩いてきて、信号が赤だったので、立ちどまって待った。ラッシュ・アワーのひとまず過ぎ去った、朝の10時半くらいの時間だったと思う。横断歩道を渡ろうとしてぼくは歩きはじめ、一瞬とまどった。このまま、まっすぐはいかずに右へいこうか、と考え直したのだ。この二秒の間に、ぼくのうしろから白人の男性がひとり、足早に歩いてきて、横断歩道へ踏み出していった。そして横断歩道にはみ出している黄色なタクシーのノーズに片足を掛け、ひょいと高く浮きあがり、タクシーのエンジン・フードのうえを、ドン、ドンと、大またに二歩で歩き、三歩目をフードのむこうの端につき、それがごく当然のことのように、たったいま自分がそのうえを歩いたタクシーに一瞥すらくれるでなく、登ったときとおなじように身軽に、ひょいと飛び降り、すたすたと、西37番通りの向こう側へ歩いていってしまったのだった。一体、どういう人なのだろうか。
サーフィンは、人間の周りにある全体すべてと人間との一体感を具体的に説いてくれるシャーマニズムなのではないだろうか。そして、個々のサーフィンは、そのシャーマニズムを万人のものとして普及させていく、シャーマンなのだ。モーターサイクルも、一種の非常に有効で面白いシャーマニズムだとぼくは考えている。自然は、確かに人間に対していろんなことを教えてくれているに違いない。もちろん、教える意図が自然のほうにあるのではなく、自然はただ自然として生きているだけで、人間のほうがそれを見て学ぶわけだ。例えば、オアフ島北海岸の波乗りの現場に、キラキラと光った新品ないしはそれに近い、無改造のモーターサイクルで乗りつけると、その人をも含めて、そのモーターサイクルの周辺には、言うに言われない、一種なんというかとにかく異様な、どことなく確実に殺気だった狂暴な雰囲気が生まれてきて、いつまでもそれは去らない。モーターサイクルだけではなく、四輪の自動車にも、まったく同じことがあてはまる。
ネクタイをしめ、パムキン・レッドのプリムス・ヴァリアントのセダンに乗ったあの男(デニス・ウィーバー)にとって、カリフォルニアの自宅までの自動車のひとり旅は、退屈であることは言うをまたないとして、なにひとつかわったことのない、ごく平凡なトリップ・バック・ホームであるはずだった。もちろん、上下二車線のブラックトップ道路のあるところで、ふいと、なんの気はなしに、ほとんど意識すらないままに、あのトレーラー・タンクを追いこしたのも、彼にとってはまったく意味のない単純作業だった。そして、彼にとっての大いなる天啓の、じつに劇的なスタートは、トレーラー・タンクを追いこしたこの瞬間だったのだ。
スティーヴン・スピルバーグ監督による1971年のテレビ映画『激突』の映画評。
モンテ・ヘルマン監督による映画『断絶』(1971)は、原題を“TWO-LANE BLACKTOP”といい、アスファルト舗装の二車線の道路、つまりアメリカでは、田舎道とかわき道、といった意味だ。このような原題が『断絶』にかわるところに、この映画の不思議さが象徴されているみたいだ。不思議というよりも不可解、いや、さらにすすめて奇怪と形容してもさしつかえのない映画だからだ。シナリオはフィルムよりもずっと説明的であり、したがってわかりやすく、ロサンゼルスからメンフィスまで自動車で走りぬけていくことのテンポがうまく伝ってきて快い。シナリオに書きこまれている説明的な部分が、フィルムでは、ほとんど欠落している。意識して撮らなかったのか、撮りはしたけれどもエディティングで切り落とされたのか、よくわからない。三〇数人の撮影隊がキャンパーや車で実際にキャラヴァンを組んで西から南西部へむかって移動しつつ撮影していったという。登場人物の誰にも、名前がない。出演者たちにシナリオを前もって読ませることはせず、ロケーションの現場でそのつど見せ、あらかじめシナリオとして定着させてある演技ではなく、その場での自然発生的な演技をモンテ・ヘルマンは要求したという。
ふと、思い出した。泳ぐ、ということ、あるいは、実際に自分が気ままに泳ぐ行為が持っている、エロチックで官能的で、楽しくて無責任な、一種の芸術的な世界を。泳ぐ、と簡単に二文字で書けてしまうが、この場合には、普遍的な水泳とか海水浴とかのイメージは、まるであてはまらない。ジャングルのなかにある大きな池あるいは湖、いや、どちらかといえば水がわずかに淀んだような雰囲気を漂わせている、大きな沼のような池でなくてはならない。かつてこのような池が、ターザン映画のなかで官能的に息づいていた。ターザン映画の主役は、じつはあの不思議な密林のなかの、幻の池ではなかっただろうかと、いま、ぼくは思いはじめている。なにしろ、あの池は、すばらしい池だった。いつでも、じっとターザンを待っていて、ターザンのほうは、ふと気がむけば、いつでも飛びこめるような服装でいたし、事実ターザンは、必要に応じて自由自在にあの池に飛びこんでいた。ターザンというひとりの人物の全的存在の中心に、あの池は、すえられていた。なんといっても、水がいつも濁ったようになっているところがよかったのだ。
オクラホマ州のほぼまんなか、街と呼ぶにはもうあまりにもなんにもない、荒涼たるアスファルト道路から少し引っ込んだところにぽつんとある建物の中。その部屋には、ポケット・ビリヤードの台が、十二台、あった。客は、男ばかり。ゲームしている人たちの台のまわりには、職業的観覧者と言ってさしつかえないほどに本格的な雰囲気をただよわせてそのゲームを見ている男たちが、数人から十数人いる。ちょっと異様な光景だが、身の危険を感じるほどの狂暴性をはらんだ異様さではなく、男ばかりがポケット・ビリヤードというひとつのスキル・ゲームに神経を集中させていることからくる、かなり緊張した雰囲気なのだった。他の土地でも数回はプール・ホールに入って観察した。プール・ホールが、かつてのアメリカで栄えていた、あくまでも〈ヘテロセクシュアル〉でありつつ、女性の立ち入ることの出来ない、男たちだけの場所という文化遺産であることだけは実感としてたしかめ得たし、ロサンゼルスのリトル・トウキョウ近くのうらぶれたプール・ホールでは、白人男に二五ドルもまきあげられるという経験もした。
プロフェッショナルなハスラーたちにとって、プールホール(玉突き屋)は、自分の仕事場でありアジトであり、ときによっては寝ぐらでさえありうる。ハスラーの多くが、いや、ほとんどが、ビリヤードでのハスリング以外にこれといって別種の生活を持たず、いたって無趣味・不調法で、しかもたいていの場合、独身の旅がらすであるという。ハスラーは矛盾のさなかに常に身を置いていて、しかも、その矛盾の存在そのものを足場に、自分の生活のための費用をかせぎ出しているのだ。ポケット・ビリヤードのさまざまな哲学や技術の世界でハスラーはすさまじい腕を有していることをもちろんまず要求されていて、と同時に、彼らは、そのすさまじい技術をフルに発揮することを常に自ら厳しく抑制していなければならない。現金を賭けて行われるゲームには、ふた通りしかない。ハスラーとカモとがおこなう場合と、ハスラー対ハスラーの場合との、ふたとおりだ。
ハスラーの世界は、プールホールを出たところにある一般の世界とは、ほとんど接していない。ハスラーたち自身、一般の世界とは、たとえば雑貨店で歯みがきを買う程度の接触しか、おこなっていない。ハスラーの生活は、プールホールのなかで自己完結していて、その外へ出てくるのは、ハスラーにとってはほんの短時間の軽い気晴らしにしかすぎない。プールホールで仕事をしているときにハスラーである自分を批難したり排斥したり、あるいは、見下したりする人と接触することは、まずない。プールホールのほとんどはアクション・ルーム(現金を賭けたゲームがいつもおこなわれている店)であり、そうであるからには、プロフェッショナルなハスラーの存在は、ごく当然のことだ。そして、いつまでたっても、プールホールでのハスリングからは抜けていかず、ハスリングが自分の天職だと考えているハスラーが多い。なぜかというと、なににもまさってハスリングは面白いからだ。
チャールズ・ウィリアムズのサスペンス小説『町の噂』(1958)の冒頭部分は、ひとつの小さな町をただ通り過ぎてしまう(パッシング・スルー)実感が、見事に捉えられている。河を超えてから、赤信号でとめられていた最後の信号のところまで、自動車で現実に小さな町を走りぬけるときのテンポやスピードのようなもの、あるいは、車の内部から眺める光景の変化などが、実際に自分でステアリングを握って走っているのと同じに感じられるほどの的確さで、書きとめられている。リアリズムといえば確かにリアリズムなのだが、そのリアリズムは、走りすぎていく自動車のなかからとらえた、あるひとつの小さな町の描写に関わるリアリズムではないという最重要な一点に、私の興味は確実に引っ掛けられている。小さな町の、本当に見慣れてしまった日常性がほぼ描写されつくされると同時に、もうひとつ、完全に異なった次元の世界が、そこには描き出されてくる。それは日常性と完全に対立する非日常性ともいうべき世界であり、いつもは圧倒的な日常性の中に畳み込まれていて見えないのだが、あるとき、いきなり、日常性そのものの中から踊り出して来て、目の前に立ちはだかる。
アリゾナ州のトゥースンから北のフィーニックスへ、インタステート10をつかわず、その東のかなり離れたところにあるUSハイウェイ80・89を走っていくと、フローレンスとオラクルという小さな町を結ぶほぼまっすぐな道路の中間に石碑が立っている。てっぺんには一頭の馬の像が立っている。馬の背には鞍があり、鞍には誰もまたがってはいない。石碑の中央には、四角い銅板みたいなものがはめこまれていて、「トム・ミックスを記念して。この場所で彼のたましいは彼の体をぬけていった。……」とある。トム・ミックスは西部劇俳優だ。彼の西部劇その他のフィルムは、アメリカ映画をその基本的な部分から知るために、欠かすことのできない貴重なものなのだそうだ。だが、その貴重なフィルムは、フォックスのフィルム倉庫の火事でみんな焼けてしまい、あまり出来のよくないのが二、三本あるいはせいぜい数本、残っているにすぎないのだという。主演、監督、脚本の三役をたいていの場合、トム・ミックスは一人でこなし、代役をつかわずに自分でアクション・シーンをこなしたそうだ。彼が主演の映画は、たいへんな成功をおさめたという。
「雑誌広告で読むアメリカ」という本の「あとがき」のいちばん最後のパラグラフに、僕は次のように書いている。
「この本のための作業を終えたいま、新たに浮かんでくるいくつものアイディアを僕は楽しんでいる。そのうちのひとつは、第二次大戦中から現在までの時間の幅のなかで、女性が登場する広告を生活の全域にわたって集め、時間に沿って並べ、観察していったなら、アメリカの現代史を市民の生活の視点からたどりなおすことの可能な、面白い本となるにちがいない、というようなアイディアだ」
いまここにあるこの本、『アメリカに生きる彼女たち』は、そのアイディアを実現させようとしたものだ。視点によっては、広告のなかの女性たちは、奴隷かもしれない。しかし、別な視点を採択するなら、別のありかたが見えて来るはずだ。
一九四九年。僕は幼児から脱したばかりだった。その頃のアメリカについて、知っているわけがない。戦勝国のアメリカは、それまでの人類史上のなかでもっとも異常な事態と言っていいほどの、豊かさのなかにあった。あらゆる領域において、世界のなかで唯一アメリカだけが、ずば抜けて力を持ち、豊かだった。その豊かさや力が、一般的な雑誌に掲載された消費財の広告のなかに、どんなふうにあらわれていたか。そしてそのなかで女性はどのようだったか。一九四九年のアメリカの、一般家庭向けの雑誌の広告を見てみよう。誇張され美化されていることを承知で見ても、当時すでに到達していたアメリカの豊かさは、にわかには信じ難いほどだ。
アメリカという国は、実は最初から女性が主役だった国ではないのか。そのことが初めから表面には出ていなかっただけなのではないのか。時代の進展は、女性たちの低い位置が次第に高くなり、閉じられていた状態から解放されていく歴史ではなく、もともと解放されていて、しかも位置は主役だった事実が、はっきりしていく歴史だったのではないか。彼女たちはその魅力を全開にしている。どの絵のなかの女性も確実にセクシーだが、絵そのものの最終的なありかたとしては、主題である女性たちのセクシーさに関しては、まったく知らぬ顔をしているところが興味深い。確立された個人が独立しきって存在しているがゆえに獲得した、恐いものなしの状態という、世界を受けとめるにあたっての幅の広さと奥行きの深さのなかで難なく成立する魅力のひとつ、それがセクシーさというものだ。
アメリカでの彼女たちは、不当な抑圧はされていなかったし、おとしめられてもいなかった。すべての人がそうあるべきであるように、彼女たちもまた、確立された個の上に、アメリカ的な自由と民主をきわめてアメリカ的に体現しつつ、主役を務めて来た。その事実は、ひとつの堅牢な枠の内部での出来事である。その堅牢な枠とは、ごく簡単に言うと、家庭だ。家庭という、どこからも文句の出ない社会構成単位のなかで、妻として母として、コミュニティの人として、アメリカ市民として、引き受けるべきことはすべて引き受け、可能なかぎりフルに機能しているかぎりにおいて、そのような枠の内部で、彼女たちは主役だった。そして、家庭というものが持つ、さまざまな人との関係において、主役的な触媒として機能することを、彼女たちは社会システムから期待された。そしてその期待に応えることのなかに、自分の存在意義を、彼女たちは見ていた。
一九七〇年代の雑誌広告に登場した女性たちは、それ以前の時代の女性たちにくらべると、かなり大きく変化していた。良い方向への変化だった、と僕は思う。見た目の変化だけではなく、深いところでの質的な変化を、彼女たちはくぐり抜けていきつつあった。時代が、社会が、つまりアメリカそのものが、この時代で大きく変化したからだ。ひとりで美しくグラマラスに、しかもデザイン的に高度に完成している女性というものは、昔から雑誌広告の主役だった。彼女たちが一段と洗練されたかたちで雑誌のなかに目につき始めたのは、七〇年代からだと僕は感じている。告写真のなかで、男性が女性の後方に、あるいは背景へまわり、さらには少なくとも視覚的には女性よりも低いか二次的な位置に降りている、ということがひとつの傾向としてはっきりし始めたのは、七〇年代だった。
一九八〇年代のアメリカの雑誌で、女性が登場している広告を観察しながら、僕が手にした最も強い印象は、登場している女性たちの、ボディリーというかフィジカルと呼ぶか、とにかく圧倒的に身体的、肉体的な、表現のされかただ。彼女たちのボディは、八〇年代ではきわめてあらわだ。しどけなくルールなしにむき出し、というのではけっしてない。ボディにかかわる理念は、例によってアメリカ的にたいそう硬質なものだ。自分がその生活のなかで、なにごとか肯定的なこと、あるいは積極的なことをめざす日々を積んでいくのであるなら、すべてを基本から見直し、やり直していくための土台となるはずの、素材としてのボディという観念を、僕は彼女たちの表現のされかたのなかに読んだ。八〇年代のボディ主義は、個人主義がより強まり、民主主義はよりいっそう成熟した結果のものだ、と僕は思う。
八〇年代には“Greed is good for you.”というところまで、個人主義は到達した。半分はTシャツの文句的な冗談だとしても、残りの半分は本当のことだった。人権の拡大は、ひたすら前進して来た。ソ連との冷戦という枠をとおしてそのことを眺め直すとアメリカ国内では、人権のひたすらなる拡大という驚くべき事態が進行していた事実に、驚嘆しないわけにはいかない。家庭くらい崩壊したとしても、それはごく当然のことではないか。少なくとも、ありとあらゆる分断が、アメリカ社会のすべての領域に起こっても、それは不思議でもなんでもない、当然の成り行きだ。社会のすべての領域のなかに、さまざまな視点から一本の線が引かれ、その線の左右にその領域は裂かれる。社会全体でそれが起こると、社会は二極分化されていく。
2023年12月1日 00:00 | 電子化計画