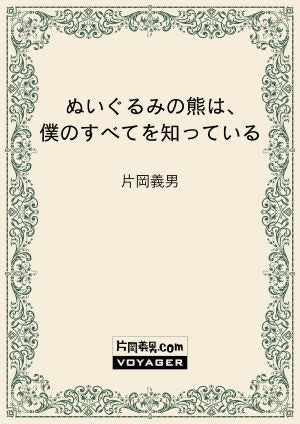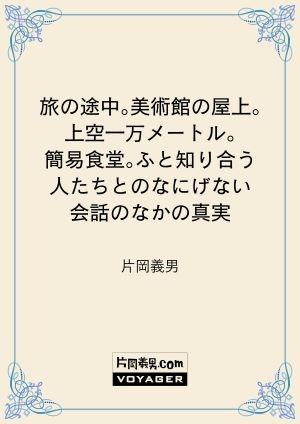エッセイ『絵本についての、僕の本』『万年筆インク紙』など12作品を公開
『絵本についての、僕の本』(研究社出版/1993年)、『半分は表紙が目的だった』(晶文社/2000年)、『文房具を買いに』(角川文庫/2010年)、『万年筆インク紙』(晶文社/2016年)の4作品、および『本についての、僕の本』(新潮社/1988年)、『水平線のファイル・ボックス 読書編』(光文社/1991年)から2篇の作品を本日公開いたしました。
僕というひとりの人の、僕らしさの基本を、例えば5、6歳頃までには作ってしまうことに関して重要な役割を果たしたという意味において、僕に対する絵本の影響ははかり知れない。絵本とは、ごく簡単に言うなら、現実にはどこを捜しても存在していない世界のことだ。それは想像力によって頭のなかに作られていく世界だ。幼い子供は、自分の頭のなかに想像力というものを作らなければいけないことを、本能的に知っているのだと僕は思う。身のまわりにあるものをとおして、幼児は必死に想像力を育てる。この本能的な必死さを、すっかり失ってしまった人たちが、いわゆる大人と呼ばれる人たちなのだろう。僕はいまでも絵本が好きだ。大人として絵本を楽しむ僕のどこかに、子供の僕が残っている、と僕は思いたい。
僕が持っているもっとも小さい絵本は、2冊のフリップ・ブック(パラパラ本)だ。綴じてある背を左手の指でしっかり持ち、ページの右端を右手で持って、親指の腹で調節しながら、全ページを均一な速度で、パラパラと親指の先から離していく。ページごとに少しずつ形を変えて描いてある絵は、動画のように連続した動きを見せる。
ばらばらのカードのままでもよければ、もっと小さいものがある。縦が5.5センチ、横は25センチの24枚のカードを、横につなげて並べると、連続したひとつのパノラマ的な光景が、そこに出来る。どう組み合わせても、現れる光景は、ひとつにつながったパノラマだ。組み合わせかたを全部数え上げると、1686553615927922354187744通りだ。
ゴールデン・ブックからはタッチ・アンド・フィール・ブックというシリーズが刊行されている。タッチ・アンド・フィールとは、子供が指先で触れて感触を楽しみ、そのことをとおして、本のなかに創り出されている想像の世界への参入の密度を高めようというアイディアだ。『普通の雪の日』という本で指先で触れて楽しむものは、ゴム長のゴム、帽子のてっぺんについているポンポン、コートの裏の温かいライニング、樹の枝に出来たつらら、そしてブランケットなどだ。プル・タブや紐を引くと動く部分があるというモビールも、何箇所か工夫がほどこしてある。
僕が持っている絵本すべてを出版社別に区分けしたなら、アメリカのゴールデン・プレス社が刊行した絵本は、相当に大きな割合を占めるに違いない。歴史が長くて出版点数が多く、面白いものがたくさんある。この会社が刊行している絵本を総称して、ゴールデン・ブックスと呼んでいるようだ。どの絵本の表紙にも、ゴールデン・ブックとうたってある。アメリカの本質につながる生真面目さを価値の中心軸に置いて、普遍的に効果のある基礎知識や素養を、出来る限り効率よく、しかも楽しく、子供たちに身につけさせることを目的として、さまざまな絵本および教育的な出版物その他を作り続けている。リトル・ゴールデン・ブックスの点数はとても多い。長い歴史のなかで、絵本としてカヴァーし得るあらゆる領域にわたって作られて来たからだ。題材、内容、文章、絵のタッチ、色の使いかた、レイアウトなど、絵本を作るにあたっての模範となる基準のすべてが、リトル・ゴールデン・ブックスのなかにある、と僕は思う。
絵本というかたちをとってなにごとかを描き、そして書こうとするとき、数多くの描き手あるいは書き手たちによって、これまでもっとも頻繁に採択されてきたのは、擬人法という手法だろう。擬人化は、なぜかくも頻繁に、絵本のなかでくりかえされるのか。幼い子供にわかりやすく親しみやすいから、というようなごく一般的で平凡な答えなら誰でも思いつく、などと考えながら、絵本『サニー・メドー・ストーリーズ』の裏表紙をなにげなく見たら、擬人化とはなにか、その正解がきわめて簡潔に書いてあった。それは、個人というものが持たなくてはいけない社会性というものの土台を、幼いうちに心の深い部分にしっかりと植えつけるためのものだ。まだ幼い個を、出来るだけ速くしかも効果高く、社会化の助走路に正しく乗せるための、有効性や機能の立証されているもっとも確かな手段のひとつ、それが絵本であり、擬人化はそのような大役を担った絵本を支える、大切な中心軸だ。
絵本というものは、そのなかに使う文や絵を描く人たち、そしてそれらを一冊の本にまとめていく編集者たちが持っている、個人的な才能を出発点としている。その才能はきわめて個人的なものであるから、才能とは言わずに主観と言ってもいいほどだ。その主観ないしは才能が一冊の絵本として出版され、広く世のなかに出ていく。出版されるということは、個人の領域を出て社会性を獲得することだ。ごく簡単に言うなら、社会にとって役に立つことだ。すぐれた絵本を無数に近く持っているその社会は、子供たちをどのように教育したいと願っているのだろうか。それは、子供たちの誰もが個人的な主観の世界を抜け出し、客観に到達するための能力を出来るだけ早くに身につけること。そしてその望みを具現していくひとつのたいへんに有効な手段として、すぐれた絵本は作り続けられていく。
芸術的な絵本も好きだが、教科書的な内容の絵本も、僕はたいへんに好んでいる。これはと思うものを見かけると、僕はかならずそれを買う。しかし最近はこのジャンルの絵本を買っていない。東京の書店で見かけなくなったからだ。芸術的にあるいはデザイン的に鑑賞することの出来る絵本、そして文芸的に接することの出来る絵本は書店に並びやすく、教科書的な内容のものは、並びにくいようだ。教科書的な絵本は見た目に華やかではなく、いわゆるアート的な雰囲気も一見したところ感じにくく、内容を詳細に読んでいくのは面倒だと、多くの人たちは感じるのだろう。実はこのジャンルの絵本にこそ、絵本作りに関するあらゆる才能や工夫が、もっとも広い範囲において、大量に惜しみなく注がれているのだが。
子供用とは言いがたい出来ばえの絵本、とも呼ぶべき種類の絵本が、絵本の世界にはたくさんある。大人が自分たちの創造的な喜びと楽しみのために作った絵本は、一枚の絵画や一個の作品ではないし、それら個別の作品を集めて一冊にした画集や作品カタログでもない、きわめて自由で魅力的な芸術作品だ。まず形態が、作る側にとっては、創造的な誘惑に満ちている。ほど良いサイズである限り、大きさは自由だ。ページ数も、適正であるなら何ページでもいい。その自由なスペースは綴じられて一冊になっている。一冊の本の、ページの内部という二次元は、人間の知力がもっとも人間らしく発揮され得る世界のひとつだ。そのようなスペースのなかで、才能のある人が思いっきり腕を振るうと、子供むきとは言いがたい出来ばえの絵本と僕が仮に呼ぶような種類の絵本が、この世に生まれてくることになる。万人が等しく楽しむことの出来る、子供のためという制約を離れて作られた絵本の数は、途方もなく多いはずだ。いま現在も刻々と増え続けていて、将来においても優秀な作品は次々に登場してくるにちがいない。
(以上7作品、『絵本についての、僕の本』研究社出版/1993年)
ひとつの部屋が一杯にふさがってしまうほどにたくさん、僕はアメリカのペーパーバックスを持っている。一九五〇年代の終わり頃から自分でペーパーバックスを買うようになった僕は、60年代と70年代の20年間は、ペーパーバックスを買い続けた。アメリカのペーパーバックはたいへん買いやすい。つい買いすぎてしまう。それらの本は、読まないままに積んでおくことになる。買うのは読む行為のいちばん最初の重要な部分なのだ、という言い訳をしながら。そしてペーパーバックスには物体としての魅力がある。簡易製本の見本のような質感と、それの外観である表紙の面白さを中心に、いろんなペーパーバックスをいろんなふうに写真に撮り、多数のカラー写真とそれを説明する文章とで、一冊を構成する。ペーパーバックスをさまざまに体験する楽しさが面白く伝わる本というものを、僕たちはなんとなく思い描いた。
(『半分は表紙が目的だった 100冊のペーパーバックスにアメリカを読む』晶文社/2000年)
泥板と岩板、そしてそこに刻まれた文字。しかしこれだけですべての用が足りた時代は急速に去ったようだ。試行錯誤を重ねた結果、一枚の紙というものが自然環境のなかから浮き上がり、そこを離れて自由を獲得し、人の手に持たれることとなった。ごく平凡な一枚の白い紙。きわめて普通の出来ばえをした一本の鉛筆。そして三十センチほどの長さの、これまた平凡な一本の定規。この三点を机の上にならべると、そこには人間の文明のすべてがある。鉛筆を削るための、小さな刃のついたナイフ。鉛筆で紙に仮に書きつけたことを、消し去るための小さな消しゴムひとつ。鉛筆に加えて、インクを用いる一本のペン。紙は一枚だけではなく何枚も、そしていろんな大きさを。机の上に増え続ける文房具によって、どこまでも維持される仮説の途上に、ほんの仮のものとしていまかたちを保っているのが、人間の文明であるようだ。
(『文房具を買いに』角川文庫/2010年)
パーカー21という万年筆を最初に見たのは一九四八年のことだ。その万年筆は異彩を放っていた。父親がパーカー21の構造を説明し、試し書きをさせてくれたとき、fountain penという言葉を使ったはずだ。その言葉の意味も僕は即座に理解した。Fountain penの視点は泉、つまりインクにある。しかし万年筆という言葉から感じて僕が受けとめるのは、いつまでもインクのなくならないペンあるいは筆ではなく、書きたいことをいつでも好きなだけ書くことによって生み出される何らかの価値とその実現への期待、というものだ。僕が考えたことが僕によって文章になっていく。その文章は、僕が手に持って動かしていく万年筆によって、端から文字として紙の上に書かれていく。僕という人の具体性も抽象性も、すべてがそこにあらわれる。
万年筆の軸のなかにあるインクが、ペンポイントから紙の上へ移っていく。字の形にペンポイントを動かすから、紙の上に移ったインクは字になる。字はいくつもつながって、意味を作っていく。意味とはなにか。字を書いていく人が頭で考えたことだ。字とは思考のことだ。思考をインクで紙の上に仮に固定したものが、字だ。
(『万年筆インク紙』晶文社/2016年)
テディー・ベアーをはじめて買ったときの記憶が、ほんのりとではあるけれど、今でも僕の心のなかに残っている。並んでいるどのテディー・ベアーも、僕を見ているような気がした。あるいは、どのテディー・ベアーも、僕の言葉をじっと聞いているようだった。同じデザインといっても、ひとつひとつどこかが微妙にちがっていた。これだ、これにしよう、と思いつつ両手をのばし、そのテディー・ベアーを抱きあげる瞬間、子供はなにかたいへんに大事なものを手に入れるのではないか。テディー・ベアーは、不変の存在なのだと、いまにして僕は思う。テディーはいつもそこにいる。いつも僕を見ている。いつも僕の言葉を聞いてくれている。いつのまにか、テディーは、僕のすべてを知ってくれている。ぬいぐるみの熊だからこそ、主である子供を、いつも変わらぬ態度で受けとめることが出来るのだ。
(以上1作品『本についての、僕の本』新潮社/1988年より)
ホノルルからサンフランシスコまで、僕は本を読んで過ごした。分厚いペーパーバックをちょうど半分まで、僕は夢中で読み続けた。ステュワデスが、大まかないい雰囲気で、PAをとおして乗客たちに伝えた。
「まもなく、サンフランシスコ空港への着陸態勢に入ります」
本を閉じた僕は、シート・ベルトを締める前に、大きくひとつのびをした。その僕にむけて、空席を間にはさんだ隣りの乗客が、僕にむけて上体を傾けた。僕を笑顔で見た彼は、十年来の友人にむけて喋る口調で、次のように言った。
「サンフランシスコ湾のかたわらで恋人の女性に捨てられたとき、俺の手に残ったものはなんだと思う?」
有名な歌の歌詞をもじった台詞だということは、とっさにわかった。
「きみの手の中に残るのは、ブルースだよ。それしかない」歌詞にそって、僕は答えた。
まさに正解だ、と言いたそうな表情で、彼は感心して首を振った。
「俺を捨てて、遠くへいっちまってさ」
「彼女との接しかたを、きみはまちがえたのさ」
歌詞を思い出し、適当にもじりながら、僕はそう言った。
『サンフランシスコ・ベイ・ブルース』という有名な歌の歌詞の、最初の一節を土台にして、僕たちの会話は以上の通り成立した。僕たちは上機嫌で笑いながら、シート・ベルトをしめた。
(以上1作品『水平線のファイル・ボックス 読書編』光文社/1991年より)
2023年11月24日 00:00 | 電子化計画