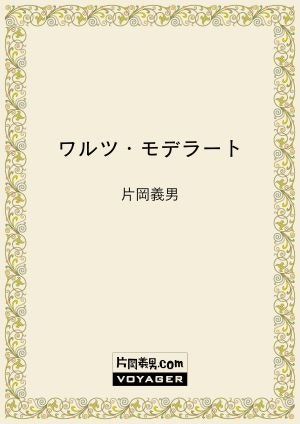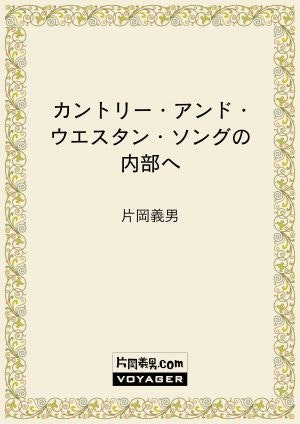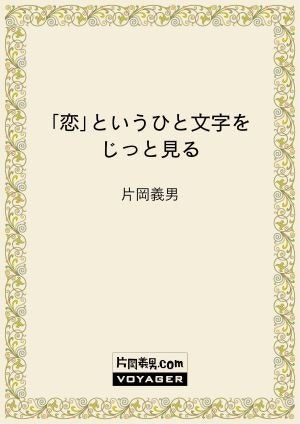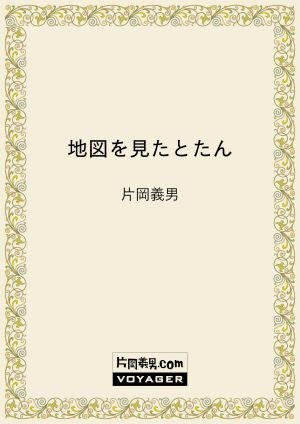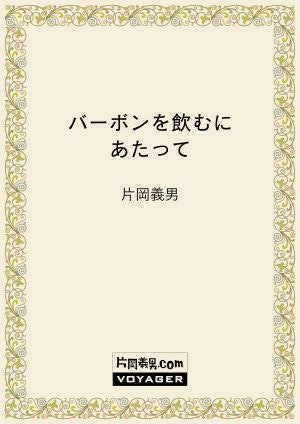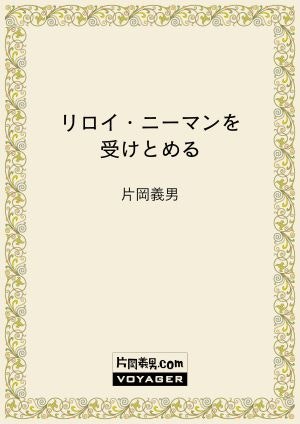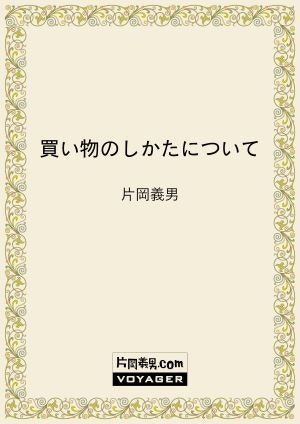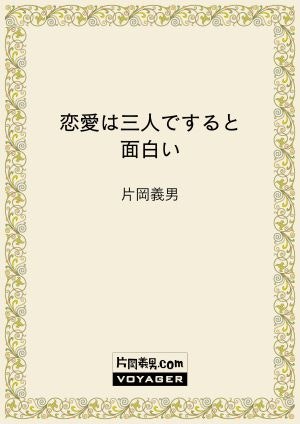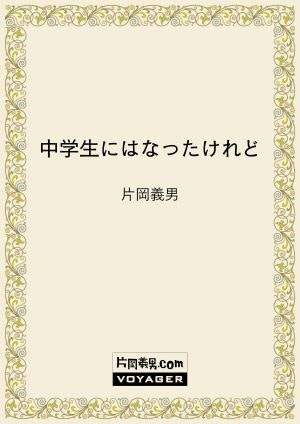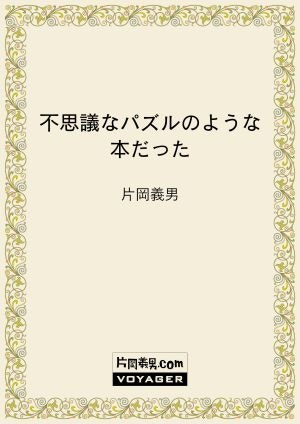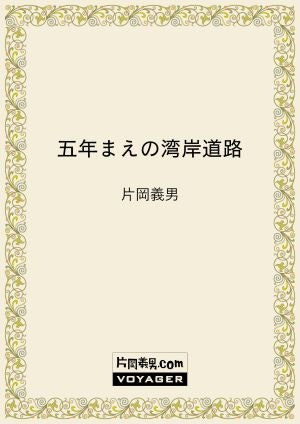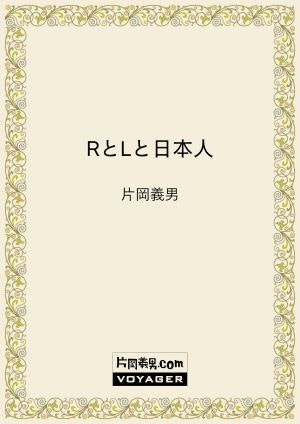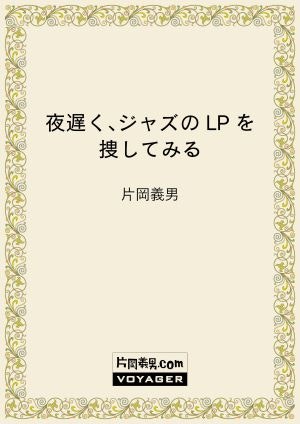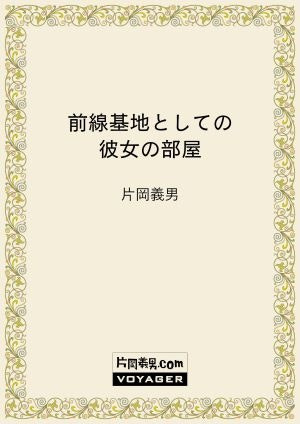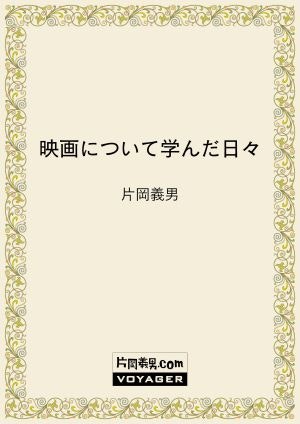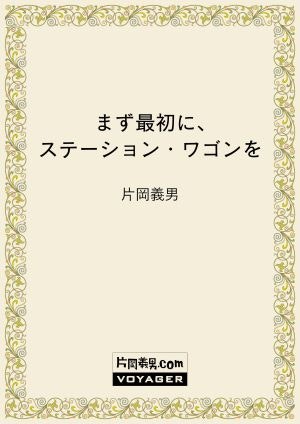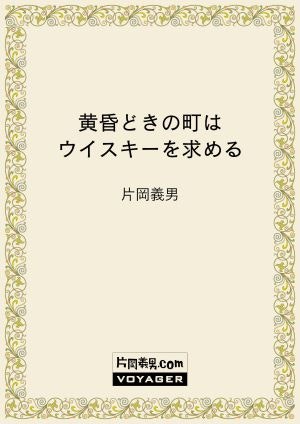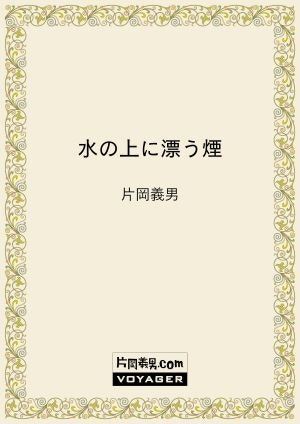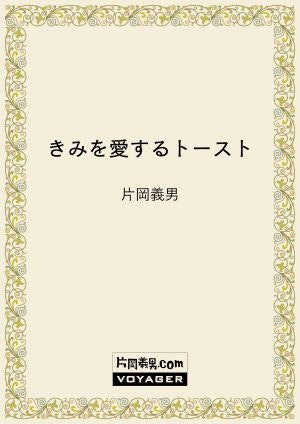エッセイ『きみを愛するトースト』より21作品を公開
エッセイ『きみを愛するトースト』(角川文庫/1989年)からの21作品を本日公開いたしました。
架空のぼくには、いま三人の女性がいる。仮にケイコ、ミツコ、そしてサチエとする。この三人は、ぼくにとって大事な人たちだ。この三人をめぐる物語にとって、もっとも重要なのは、『テンダリー』というワルツ曲だ。譜面の冒頭には、ワルツ・モデラートという指定がある。およそありとあらゆる場面で、この三人には、『テンダリー』がよく似合う。どんな状態になっても、『テンダリー』はまるでテーマ曲のように、彼女たちが登場する場面によく似合っていた。
カントリー・アンド・ウエスタンの名曲が生まれるに至った、ほんのちょっとしたきっかけに関するエピソードには素晴らしいものが多い。名曲はすでに無数に近く存在する。そして、それぞれの名曲がすくなくともひとつはエピソードを持っているから、エピソードもまた無数に近い。カントリー・アンド・ウエスタンの命題は、人は常になにかに感動したいのだというロマンティックなものであり、したがって名曲をたくさん集めれば、それはそのまま、感動せずにはいられないグッド・ストーリーの宝庫となる。
恋はボード・ゲームだ。しかし、ボード・ゲームは終わりがあるからはじめることも出来る、架空の世界だが、現実の恋を終わりのあるゲームにしてしまうのは、ちょっと能がなさすぎるのではないだろうか。終わることのない、恋というゲーム。これからはこれだと、ぼくは直感している。その方法、ないしは工夫。これをぼくは考え、実行してみようと思っている。終わらないとはどういうことかというと、高まるのはここまででいい、とふたりがきめた地点で高まりを抑え、そこまでの高まりをそのままいつまでも持続させていく。こういう恋が、もうあってもいいではないか。
ぼくのアメリカ人の友人に、カンザス州で生まれ育った男がいる。小学生の頃、女の先生がアメリカ合衆国の大きな地図を壁に広げて見せてくれ、あなたたちはいまここに住んでいるのですよと、地図上のカンザス州の、さらにそのまんなかあたりを、先生は示した。そのとたん、彼は閉所恐怖症となった。圧倒的に巨大な大陸によって、そのまんなかに自分が閉じこめられている、と彼は感じたからだ。
バーボンは女性の酒だ、とぼくは思っている。居心地の良いバーのカウンターに、いまぼくがいるとして、その隣りにいてくれる女性の手もとにバーボンの入ったグラスを置きたければ、その女性は、自分が女性であることから生まれてくる、女性としての当然の魅力に、あまり頓着していないような人でなくてはいけない。しかし、それでいて、充分に魅力的であってほしい。微妙なところだが、難しい注文ではない。
ディズニーの漫画映画を、僕は子供の頃、浴びるほどたくさん観た。観た数と時期、そしてその面白さや楽しさについていまあらためて考えてみると、僕はディズニーの漫画映画から、たいへんな影響を受けているはずだということがわかる。それ以外にもアメリカの漫画映画を僕はたくさん観ているから、影響力は渾然と一体になっていて、どこからがディズニーでどこからがそうではないのか、区別することは難しい。
リロイ・ニーマンの絵が掲載されている、一九六〇年のなかばから後半にかけてのアメリカ版『プレイボーイ』は毎号楽しみだった。スポーツの行われている現場と、その現場にいあわせている人たちとの両方を画面のなかにとりこんだ彼の絵は、見たとたんにぱっと視界が明るく開けていくような気持ちにさせる効果を持っていた。
ぼくは店で買い物をするのが、あまり好きではない。店へいってなにか買わなくてはいけなくなると、面倒だなあ、という気持ちがまず最初にくる。そんなぼくにとって、カタログによるメイル・オーダーは、たいへんいい。シーズンごとにカタログが郵送されてくる、というシステムが、まず楽しい。なにかを買わなければならないという義務感なしに、新しいカタログのページをくっていくのは、楽しいことだ。注文書を書いて送ってしまえば、その買い物に関しては、ただちにすべてを忘れてしまえる。これも、なかなかいいものだ。
これまでにずいぶんたくさんの小説を書いてきたが、タイトルのなかに恋という字を使った小説は、一編もない。考えてみれば、これはかなり不思議なことだ。現代の男女を主人公にした、広い意味での恋愛小説をぼくは書いているのに、なぜタイトルに恋の字が一度も出てこなかったのか。恋は、個人的な事情、という印象をぼくは持つ。当事者以外の人たちにとって、その事情のありかたはわからなくはないけれど、あくまでもそのふたりにとっての、個人的な事情、という感じがする。愛は、もっと広い。普遍につながっている。ただし、日本語の愛には、打算的な側面がいつもつきまとっているように、ぼくは感じている。
ぼくは中学生のとき転校を三度、体験している。一番初めの中学校のことは、いまでもかなり鮮明に覚えている。自宅から通うためのルートは、いくつかあった。中学一年生になりたてのぼくは、四月、五月と、毎日、小学生の頃の自分とは少しだけ違った存在になった自分を確認しては、その確認に伴う感慨のようなものを楽しんでいた。つまり、自分は成長しつつあるのだという自覚を持ったということだ。中学校の教室から見る海は、見下ろす角度が新鮮だった。なれ親しんできた海とは別の海がそこにあるような思いが次第にたかまり、ある快晴の日、ついにその魅力に逆らいきれず、ぼくは学校を途中で抜け出し、海へ降りていった。
学校における英語の勉強でいまでも記憶に鮮明に残っているのは、高等学校に入ってすぐに、一年生全員を対象にしておこなわれた英語のテストだ。英単語、英文解釈、和文英訳、文法、書取りと、五つに分かれているそのテストでのぼくの成績は、文法が三〇点で、あとはすべて一〇〇点だった。口惜しいので、それから参考書を何冊か買ってきて順番に読んでいくと、高等学校で教えている英語は、ほかの何にもつながることなく、大学の受験英語にのみつながっていることがわかった。全国の大学の、過去十年間に出題された受験英語の問題集という、電話帳のような本は、おなじような問題がくりかえし出てくる、ちょっと不思議なパズルのような本だった。
『湾岸道路』(角川文庫)という長編小説をぼくが書いたのは、もう何年も前だ。この小説の基本的なアイディアは、童話のジンジャブレッド・ボーイ(編注:人型のビスケット)だ。おばあさんがオーヴンを開くと、ジンジャブレッド・ボーイはそこから飛び出し、家の外へ走り出てそのまま畑や野原を走り、川まで来て、狐の背に乗ってその川を渡ろうとする。しかし、川の途中で彼は狐に食べられてしまう、という話だ。この話が子供の頃から好きだったぼくは、ある日、家を飛び出してどこかへいってしまい、それっきりとなる男性の話を小説として書いてみたいものだと、以前から思っていた。
部屋の片隅のTVがオンになっていて、ひとつのCMがはじまった。モノクローム写真による街角の風俗描写のようなスナップが、ワン・ショットずつ画面に出てきた。一九六〇年代の東京だということは、すぐにわかる。出るぞ、出るぞ、と思っていたら、案の定、出た。ビートルズだ。日本人の若い男性が歌う『ミスタ・ムーンライト』が、画面に重なる。一九六〇年代に連想ゲーム的にビートルズが結びつくのだろう。これだけでもすでに能のないCMだが、このCMの中の『ミスタ・ムーンライト』は、じつにみじめに、きわめて無残に、日本なのだった。RとLの音の区別をすることがその歌い手にはまるで出来ず、月の光は月の権利となっていた。
冬のよく晴れた日の午後、湖のほとりにあるリゾート・ホテルのコーヒー・ショップ。仲よしのグループ何人かと一緒だ。コーヒーが思いのほかおいしい。湖が見渡せる。BGMが聞こえてくる。それにしても情けないBGMだ。いい音楽を聴きたい、とそんなとき痛切に思う。ジャズがいい。ピアノ・トリオかな。もうすこし音があったほうがいい。そんな風に編成がきまって、ミュージシャンのとりあわせを頭のなかで考えてみたりする。今夜、自宅に帰ったら、ぜひともこんなのを自分のLPのなかから捜して、聴いてみよう、と思う。
書かなければならない中編小説の女性主人公について考えていて、ぼくは思いついた。一日の仕事を終わった彼女に、帰るべき自分の部屋が三つあったなら、きっと彼女の生活ぶりはさまざまに面白くなるにちがいない。これから必ず、このようなスタイルの生活が、新しいありかたとして登場してくる、とぼくは自信を持って予言する。部屋が三つあり、部屋ごとに異なった仕事をフリーランスでこなしていたりすると、その生活はじつに面白いはずだ。三つの場所を定期的に転々として仕事をしている人は、すでにぼくの身のまわりにも存在する。
ぼくの小説をきっかけにして角川映画ですでに四本もの映画が制作され、一般に公開されてきた。新しく映画が一本出来あがると、宣伝のためのさまざまな活動がおこなわれる。そのなかのひとつに、全国で行う無料招待による試写会というものがある。この試写会に、監督、プロデューサー、主演の女優たちの舞台挨拶や歌などが、ワン・パッケージとなっている。『スローなブギにしてくれ』のときには、ぼく自身も原作者として全国を宣伝キャンペーンで回った。宣伝ツアーも、あるいはぼくだけのサイン会も、いつもはほんとに静かな日々を送っているぼくにとって、一転して環境の激変する、そして時間の流れかたもまるで違ってしまう、刺激に満ちた一種の不思議なチャンスのようなものになる。
自分で自動車を買わなくてはいけなくなったら、ぼくはまず最初に、ステーション・ワゴンを買うはずだ。この気持ちは、とにかく自動車は実用的にこてんぱんに使いたい、という気持ちとつながっている。自動車というきわめて野蛮で品がなくてインセンシィティヴなものを、なんとかある一定の範囲内におさえこみ、制御していたい、ということなのだと思う。ステーション・ワゴンは、その応用範囲がかなり広い。さまざまな場面のなかに、ステーション・ワゴンは、実用的にぴたりとはまる。
一九六〇年代のなかば、アメリカのバーでシーグラムのセヴン・クラウンを注文するとき、いろんな注文のしかたがあった。「ザ・シュア・ワンをくれ」という言いかたは、そのうちのひとつだ。確実なやつ、自信のあるやつ、といったほどの意味だが、これはセヴン・クラウンとおなじく7の字をその名前のなかに持っている、有名な清涼飲料水で割ったものを意味することが多かった。
ぼくはサンドイッチが好きだ。もっとも好きなのは、自分で作って自分ひとりで食べるサンドイッチだ。それは、きわめて個人的な、そしてほんのすこしだけ間にあわせの感じのある食べ物だ。冷蔵庫のなかやキチンにそのときたまたまある材料を使って、いろんなふうに想像力をはたらかせながら、自分だけのためにサンドイッチを作るのは、かなり楽しい。駅の売店や新幹線の中で売っているサンドイッチだと思われては、困る。あれはサンドイッチとは呼びがたい。
彼女は、バーの左側のカウンターの奥に、ひとりでいた。ぼくに気づいて、彼女は笑顔になった。ぼくは彼女を見た。鼻や顎、そして喉もとへ流れるライン、さらには目の周囲、頰から耳へ、そして耳のうしろへとつながっていくあたりに、彼女独特のシャープさが、今夜もくっきりと出ていた。このシャープさは、いっしょにいる人、特にこのぼくを、安心させる。
「一時間、ぼくといっしょに、考えごとをしてほしい」
「するわ。どんなことを考えるかしら。考えごとは、とても好きよ」
「タイトルだけは、思いついた」
「ストーリーの話なのね」
いつもの同じキチンでも、真夏のキチンと真冬のキチンとでは、ほぼ完全に別のものだ。真冬のキチンは、閉ざされている。そのキチンで、朝食を作る。すこし濃いめに焼けたトーストの表面には、どちらにも、くっきりと白く、ハートの形が描かれている。褐色に焼けたトーストの表面に、ハートの形が白くくっきりと、焼け残っているのだ。
そして、子供が描いたようなそのハートのなかには、
I
love
you.
と、永遠のワン・センテンスが、一語ずつ三行となって斜めに、おなじくくっきりと白く、焼け残って浮き出ている。これは、口をきくトーストだ。
2023年9月22日 00:00 | 電子化計画