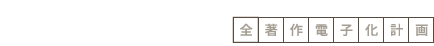エッセイ「その写真機を、ください」などから25作品を公開
雑誌『ラピタ』(小学館)にて連載されたエッセイ「その写真機を、ください」、『Free&Easy』(イースト・コミュニケーション)連載の「アメリカの色とかたち」「東京縦画面」などからの25作品を本日公開しました。
僕が初めて見たオリンパスの一眼レフ、OM–1は、高知市内のカメラ店のウインドーにあった。きれいなかたちをした写真機だなあ、という第一印象を僕は持った。かたちのきれいなものに僕は基本的にたいへんひかれる。かたちのきれいなものは使い勝手が良く、したがって実用性能が高いからだ。OM–1の小ささと軽さは、どちらも中心点をきっちりと持っていて、ふたつの中心点は見事に一致している。そしてその中心点は、OM–1を持つときの僕なら僕の手の、物を持つという機能の中心点とすんなりとつながる。このような種類の幸福感は、めったにあるものではないと僕は思う。23年間も使い続けた理由の核心はそこにある。
(『ラピタ』No.15 小学館/1997年3月号掲載)
1972年、サンフランシスコの写真機・機材店で僕はニコンFの黒塗りのボディを見つけた。手に取って観察すると、新品同然と言うよりも新品そのもののようなきれいさだった。これは買わなければならない、と僕は思った。これはいまここで自分が買っておくべきだという、義務ないしは責任あるいは使命感を僕は感じたからだ。それから10年ほどを経てようやく、僕はそのFを使いたいと思うようになった。どう使えばいいか。そうだ、テーブルの上で撮るために使えばいい、と僕は思った。セコニックのスタジオ・マスターという露出計と、マイクロ・ニッコール五十五ミリというレンズを買った。そして二階の人工芝のバルコニーにテーブルを出し、自然光でテーブルの上の小さなさまざまなものを写真に撮り始めた。
(『ラピタ』No.16 小学館/1997年4月号掲載)
ペンタックスのMZ–5を真正面から撮った写真を広告で見たとき、僕の気持ちは少し動いた。そんなに悪くはないな、と思ったからだ。上から撮った写真を見て、僕の気持ちはさらに少しだけ動いた。プリズム部の左右に丸いダイアルがひとつずつあり、液晶表示窓が小さいことがわかったからだ。世界最小最軽量だという。無理に最小ではなくてもいいけれど、軽量であるに越したことはないと考える僕の気持ちは、MZ–5に向けてもう少し動いた。「とてもいいよ。僕も一台、注文した」という写真家の佐藤秀明さんのひと言で、僕の気持ちは線を向こう側へ越えた。オート・フォーカスは初めてだ。フォーカスさせる部分をスポットで選ぶことの出来るボタンがある。そのスポット・フォーカスを使ってなおかつオート・フォーカスなら、街なかで素早くディティールを採集するのにいいのではないか。
(『ラピタ』No.17 小学館/1997年5月号掲載)
キヤノネットQL17が2台、いまも僕のところにある。二台とも健在だ。1台はただのQL17で、1968年頃に買った。もう1台はQL17のGⅢだ。三十年前のものがいまも手もとにあるのは、僕としては異例と言っていいほど珍しい。なぜいまもあるのだろうか。自問しても答えは見つからない。いま手にすると面白くもなんともない写真機だが、5年ほどの期間、僕はQL17をいつも持ち歩いていた。旅行にはかならず持っていった。シャッター速度優先のEEで、ピントは二重像合致式だ。距離リングには指をかけるレヴァーがあり、これは使いやすい。ファインダーの表示で適正露出を教えてもらうセミ・マニュアルではない、完全なマニュアルとしても使うことが出来る。がっちりした無骨な感触は、この写真機のもっともいいところだろう。
(『ラピタ』No.18 小学館/1997年6月号掲載)
7月のある晴れた日、僕はペンタックスMXで何本かの35ミリ・カラー・リヴァーサルを使って撮影した。MXはファインダーのなかの表示によって露出の過不足を教えてもらいながら、自分で露出を決定するマニュアル機だ。マニュアルで撮るのはなんという快感だろう、と僕は撮りながら思った。この連載で6種類にわたってオート撮影を続けたあとの、マニュアルの快感はひときわだった。僕が言うマニュアルの快感とはなにか。オートで撮ると、シャッター速度あるいは絞りリングの操作のどちらかを、撮影者は省略している。最終段階のはるか手前で、最後まで見届けなければならない光から、撮影者は視線を離してしまっている。このことが積もり積もると不快感にまでなることを、僕はいまになってようやく実感として知った。
(『ラピタ』No.22 小学館/1997年10月号掲載)
小田急線の成城学園前という駅で、女性がひとり車両に入って来た。姿のいい人だなあ、と僕は思った。彼女は僕の左斜め前に座った。その女性は僕に向けて「ヨシオちゃん!」と、言った。思い出した。僕がまだヨシオちゃんだった子供の頃、三軒隣の家に住んでいた、僕より確か6つ年上の、美人のお嬢さんだ。新宿に着くまで僕たちは話をした。いろんな話をしたが、いきついた先は「あれからずいぶん時間がたったわねえ」ということだった。近日中の再会を約束して、僕は新宿で彼女と別れた。彼女と偶然に会うまでは、その日の僕の時間はごく平凡な具体性の中を流れていた。彼女と会ってからの僕の時間は、質と方向が少しだけではあるが確実に変化した。部分的に1950年代まで引き戻された僕は、1997年の夏の現実の中を写真機を片手にさまよった。その写真機は1979年に発売された、キヤノンのAV–1というオート専用の普及版一眼レフだった。
(『ラピタ』No.23 小学館/1997年11月号掲載)
小田急線の電車の中で偶然に、20年ぶりに会った年上の女性、恵子さんから電話がかかって来た。僕は「下北沢で会いましょう」という平凡な返事しか出来なかった。約束の日、約束の喫茶店で、僕は恵子さんに会った。充分に時間が経過した状態、それはたいへん面白い。過去を記憶しているふたりの体が、現在の中で向き合っている。過去と現在は自在に溶け合い、過去現在あるいは現在過去とも言うべき不思議な状態を作り出す。下北沢では撮ってみたい、と思っている場所がある。狭い道の両側に雑居ビルが立ち、雑多さをきわめたような看板がどの階からも道に向けて突き出している。電柱が林立し、電線が頭上を這っている。そのような光景を露出アンダーで撮ると、『ブレード・ランナー』に出て来たあのトンネルの中の奇怪な街のようにも、撮ることが出来るのではないか。
(『ラピタ』No.24 小学館/1997年12月号掲載)
オードリー・ヘップバーンを主題とした絵葉書が、3枚あった。筆跡も文書の書き方も3枚とも同じだ。おそらく同一の女性だろう。差出人の名と住所が書いてない。その点も同じだ。消印は沖縄、京都、札幌。思い当たる人を探そうにも、手がかりはまったくない。書いてある字は、丁寧な印象はあるけれど、ごく普通のものだ。なぜオードリーなのか。気ままなひとり旅のつれづれに、絵葉書を書いては投函している30代後半の女性、というような印象を僕は持った。この3枚の絵葉書を、ある日の午後遅く写真に撮って遊んだ。よく出来た絵葉書は被写体としての可能性を広く持っている。この3枚もそうだった。撮影にはオリンパスのOM–4Tiを使った。ごく最近買ってみたチタンのブラック・ボディで、レンズは50ミリのズイコー・オート・マクロだ。
(『ラピタ』No.25 小学館/1998年1月号掲載)
1970年代の半ばから1980年代の初めにかけての期間、僕はコダックのインスタマティックX–15Fという、戦闘機のような呼び名の写真機を愛用していた。普通に使っていれば故障はまずしないし、軽くて単純明快で、しかもたいへんきれいに写った。カートリッジに入った126フィルムには、カラー・ネガの他に、ヴェリクローム・パンという白黒の12枚撮りがあったし、コダクローム64とエクタクローム64の2種類のカラー・リヴァーサルまで市販されていた。フィルムの画面サイズは、28ミリ四方という正方形だ。そのインスタマティックX–15Fを、ちょうど1年前の引っ越しの際に徹底的に探したのだが、ついに見つからなかった。製造はとっくに停止されている。しかし126フィルムとフラッシュ・キューブは供給が続いている。インスタマティックでまた写真を撮りたい、と僕は引っ越しの前あたりからしきりに思うようになった。
(『ラピタ』No.26 小学館/1998年2月号掲載)
ニコンFが発売されたのは1959年、そしてF3は1980年に発売された。これを知った上でこの2台の写真機を眺めていると、感銘に近いものを感じないわけにはいかない。造形物としての表面だけ、つまり形とそれが醸し出す雰囲気だけを基準にして、どちらかひとつを選ぶとしたら、果たしてどちらになるだろうか。Fは亀倉雄策のデザインだという。F3のデザインがジウジアーロによるものであることは、よく知られている。買う買わないは別として、どちらかを選ぶならFかなあ、という気がして来る。いったんそう思うと、気持ちはFへとさらに傾いていく。Fの造形は、根源的なものがそのまま形になっている、という印象が強くある。特にいいデザインだとは思わないが、視線を邪魔する余計なものが一切ないから、Fの形全体が、視線にとって飽きない。
(『ラピタ』No.29 小学館/1998年5月号掲載)
25歳のとき、それまでに何枚もたまった自分の写真を、僕はすべて捨ててしまった。これで僕に過去はない、などと僕は冗談を言っていた。それ以前のものが残っていれば、たいそう面白く使えるのにと、今の僕は多少の後悔をしている。僕が20歳くらいの頃から知っていて、ひょっとしたら1歳か2歳だけ年上の女性と、今もたまに会う。知り合った頃から君の写真を意識的に撮り続けていたなら、今頃は素晴らしい蓄積になっているだろうね、というようなところから僕は写真論を始めた。昔の自分の写真を1枚残らず捨ててしまって後悔している、という話にまで到達したとき、「私、1枚持ってるわよ」と、彼女は言った。「私が撮ったのよ。銀座4丁目の三愛の前で」という彼女の言葉を裏づけるべき僕自身の記憶は、何ひとつなかった。使った写真機は僕が肩からかけていた一眼レフだったという。
(『ラピタ』No.33 小学館/1998年9月号掲載)
20代の前半に僕はミノルタの一眼レフを買った。ミノルタであることは確かなのだが、機種や使い勝手、機能などに関しては、なにひとつ記憶していない。持って歩いた記憶はごく淡くある。一体何を撮ったのか、今のところ全く思い出せない。20代前半の僕の写真を撮るのに、僕が肩にかけていた一眼レフを使ったと、シャッターを押す役を引き受けた女性が証言した。僕が写真の年齢に達するまでの期間内に買うことの出来たミノルタの一眼レフは、発売順に列挙して次の5種類しかなかった。SR–2(1958年)SR–1(1959年)SR–3(1960年)SR–7(1962年)ニューSR–1(1965年)。SR–1の形状も使い勝手も、僕の記憶にはまるでない。SR–7をSR–1と並べて観察すると、SR–7のボディ形状のほうに、はるかに親近感を覚える自分を発見した。
(『ラピタ』No.34 小学館/1998年10月号掲載)
西部開拓というアメリカ史の中の現実は、ハリウッドによって改ざんと美化をほどこされ、西部劇という種類の娯楽映画となった。その西部劇もいまでは絶滅したと言っていい。西部劇の主人公をつとめた西部男たちには、歌う男たちもいた。彼らはシンギング・カウボーイと呼ばれ、今からかなり遠いその昔にはたいへんなスターだった。カントリー・アンド・ウエスタンのLPジャケットには、歌う西部男たちの艶姿、ないしは美化された西部男や西部のイメージが表現されている。陳腐なイメージばかりだが、これもアメリカの色とかたちのひとつであり、観察や鑑賞の対象として、僕はまだ興味を持続させている。
(『Free&Easy』2000年2月号掲載)
まだ若かった戦後のアメリカは、1950年代に大繁栄の豊かな時代を迎えた。人類史上前代未聞の、異常事態とも言うべき繁栄だった。元気なお父さんに美しいお母さん、そしてふたりないしは三人の子供たち。郊外の広い敷地に大きな家、緑の芝生……誰もが幸せの極点を追い求めた。ザ・マクガイア・シスターズが歌った歌は、こうした幸せ追求というテーマにとってのテーマ・ソングだった。幸せの追求は、疑いなく最重要な主題として、いまもアメリカの人々によって、営々と継続されている。そしてハピネスの極点にあるのは、家族関係が作り出す幸せを自分も獲得することが出来るかどうか、という大問題だ。
(『Free&Easy』2000年9月号掲載)
今世紀に入る前から、ハワイは早くも南海の楽園だった。最初は上流階級の休暇や娯楽あるいは社交の場として構築されたが、時代が進むにつれて、楽園は少しずつ大衆のものになっていった。その大衆化をいっきに促進した巨大なきっかけは太平洋戦争であり、戦後のアメリカがハワイに大衆の楽園を作った。楽園には甘美でロマンティックなテーマ・ソングが必要だ。これらはアメリカ製のポピュラー・ソングのヴァリエーションだが、地元の人たちも多く参加したから共同作業と言っていいだろう。甘く美しく滑らかにけだるい、懐かしき楽園への追悼に満ちた、実に見事なメロディーが多いから、侮ってはいけない。
(『Free&Easy』2001年1月号掲載)
グレン・ミラーが自分のバンドを持って活躍した期間は、1937年の最初のバンドから、陸軍に入隊して航空隊で大編成のバンドを組織した頃まで10年もない。入隊するまでで区切るともっと短い。レコードとして市販されたオリジナルはすべてSPだ。ミラー自身はこの世になく、彼のバンドも存在しなくなった戦後、グレン・ミラー楽団の戦前の演奏がどんな形でEPやLPとしてまず発売されたのか、僕は知らない。1950年代半ばにヒットした映画『グレン・ミラー物語』以後にはLPの数は多いという印象がある。録音されている内容である彼のバンドの音楽は、ポピュラー音楽におけるヴェンチャー精神の、いまも変わらぬ最高のお手本だ。興味があるなら聴いてみるといい、報われるところは大きい。
(『Free&Easy』2001年4月号掲載)
僕は高校生の頃からLPを買い始め、今でも買っている。手あたり次第になんでも買うわけではない。買うか買わないかをくっきりと分けるいくつもの基準が、多くの場合はフレーズとなって、僕の頭のなかにある。そのうちのひとつに「LPジャケットに描かれたジャズの人たち」という基準がある。ここからまるで細胞分裂するかのように分化して独立したのが「描かれたシナトラ」という基準だった。写真ではなく絵に描いたフランク・シナトラ。絵のそれぞれが、フランク・シナトラ自身のイメージ化されたものだ。歌う彼の声が聴き手のなかに喚起する感情のイメージ、と表現してもいい。
(『Free&Easy』2001年9月号掲載)
個性や自分らしさなどは、自分はこれではなくあれを買ったという程度の、あるかないかの差異にもとづく形而下の出来事でしかない。普遍性という形而上の出来事への加担こそ最大の生きがいであるはずなのに、そこからは思いっきり遠いところにいるひとりひとりの自分という種類の人が持つ最大の特徴は、自分の内部で考えられることしか考えない、すなわちなにひとつ正しくは考えられないということだ。
(『Free & Easy』2002年8月号掲載)
この写真のような景色を僕はこよなく好いている。ただ見るだけでは気がすまない。晴れた日、少なくとも夕方までは空に雲の現れない日、ペンタックスLXにアグファのカラー・リヴァーサル・フィルム、CTプレシーサを入れ、僕にとってはいまだ未踏の地である、あちこちにたくさんある初めての道を歩く。初めてという高揚した気持のなかでこのような景色を見つけると、僕はそれを写真に撮る。
(『Free & Easy』2003年7月号掲載)
東京に生きる人の幸福という舞台を装置するにあたって、欠かすことの出来ないふたつの要素が、それぞれ見事なまでの光景となって、この2ページにある。ひとつは路地の夜を照らす裸電球、そしてもうひとつは、トタン屋根の受けた雨を地面へと導く樋だ。どちらの装置も、現実という無秩序のきわみに、最小限でいいから筋道をつけようとする試みだ。
(『Free & Easy』2003年11月号掲載)
きれいな晴天の日がひと月のうちに10日はあるとするなら、そのうちの半分の5日は、僕は外にいる。写真を撮り歩いているからだ。写真機だけを持った僕ひとり、という小さな単位にとって、東京はたいへんに広い。絨毯爆撃はとても不可能だから、今日はこのあたりを撮る、と見当をつけた場所へ出向き、陽が落ちるまでその一帯をさまざまに歩き、36枚撮りのフィルムで10本は撮る。
(『Free & Easy』2003年12月号掲載)
月はかつてすさまじく巨大だった。その巨大だった月を、僕は記憶している。巨大な月を実際に肉眼で見て、その体験を記憶しているのではなく、何万年も昔の人が見た巨大な月の記憶が、僕に伝えられた遺伝子の内部にほとんどそのまま存在している。ぽっかりとひとりで浮かんでいたこの地球にむけて、あるとき、月がどこからともなく接近してきた。何億年という時間のなかで、月は地球にむけて接近してきた。現在の月と地球との間にある距離よりも、ずっと短い距離のところまで、月は近づいてきた。そして、それ以上には接近しなくなった。
(『トランヴェール』1989年8月号掲載)
小さな丸いテーブルにむかって、僕と彼女は隣りあわせに座っていた。彼女の前に、僕は小型のライト・ボックスを置いてスイッチをオンにした。箱のなかにあるいくつかの豆球が点灯し、ライト・ボックスの表面は明るくなった。そこへ、僕は1枚のカラー・スライドを載せ、彼女に見てもらった。
「午後遅く、まだ明るいけれど、すこしずつ夕方になっていきつつある時間の、いい空だわ。一日じゅう、きれいに晴れていた日なのね。……この一枚の写真から、ストーリーを作ろうとしているの?」
(『トランヴェール』1989年12月号掲載)
子供のころ、相当に長い期間にわたって、ぼくにとっての主たる食べ物は、ビン詰、カン詰、袋詰のいずれかであった。野菜ですら、例えばホウレン草のカン詰のようにカン入りだったのだ。こういったものはすべてアメリカのものだったから、ぼくにとっては、今でもビンやカンや袋が食べ物の一部になったままだ。パッケージも食べ物であり、アメリカのパッケージはことのほか派手に雄弁に購買者にむかって語りかけてよこすから、その語り掛けにこたえて、これはおいしそうだと期待をこめて買う。
(『Mr. Action!』1979年3月号掲載)
これまで実にいろんな本を読んできたけれど、こんな本は初めてだ。題名は、『ファット・ガール』という。この何とも言いようがないほどに端的な題名に、ほんとの話、という副題がつけてある。アメリカ人の多くがずっと以前から相当な肥満体だった。彼らの肥満化がよりいっそう進み、オビース(肥満)な人たちがどこへいっても目立つようになったのは、いまから30年ほども前からか。それ以来、彼らが際限なく肥っていく傾向は国をあげて進行していて、ここにきてさらに一段と彼らの肥満化は顕著になってきている。肥らないほうがおかしいような食生活だが、彼らが肥り続ける真の原因はそんなところにあるのではないという、かねてよりわかってはいたことが、この本を読むにいたって、僕なりの確信へと固められることとなった。
(『Free & Easy』2006年11月号掲載)
2024年12月20日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ