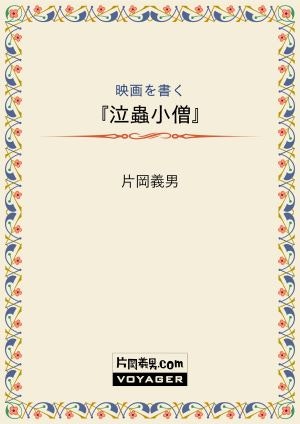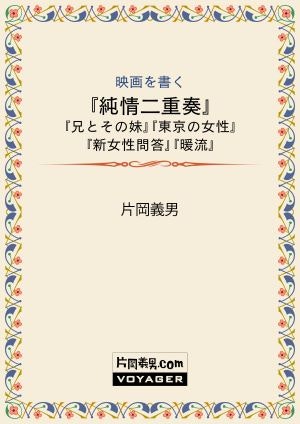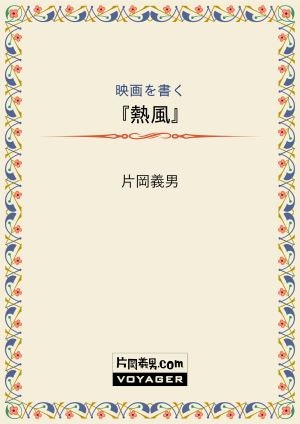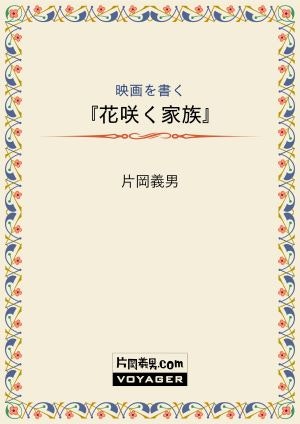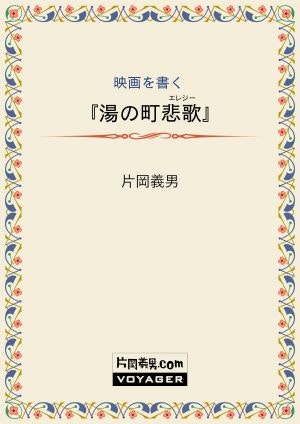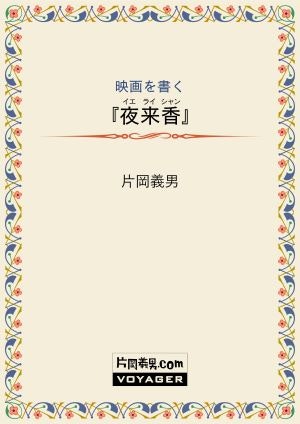映画評論『映画を書く──日本映画の原風景』より15作品を公開
映画評論『映画を書く──日本映画の原風景』(文春文庫/2001年、単行本は1996年にハローケイエンターテインメントより発行)所収の15作品を本日公開いたしました。昭和20(1945)年を中心軸として、その前後10年の20年間を、娯楽映画を通して俯瞰したものです。
『母の曲』という娯楽映画は、英百合子演じる稲という名の女性の、妻として母としての身の上話だ。お稲さんは、昭和12年の基準で言う、上流階級の奥様だ。しかし、若い頃は女工をしており、初めから上流社会で育って来たわけではないから、その世界には今でもなじめずにいる。彼女がいわゆる縦糸だとすると、横糸には彼女の夫、娘の桂子(原節子)、昔の男友だち、夫のかつての恋人などが配置され、娯楽としてじつに巧妙に織り上げられている。この話を支える一本の中心軸は、結局のところ、いいところへ嫁にいく、ということか。お稲の身の上ドラマは、結婚相手つまり嫁にいく先を間違えたことから、そもそもはスタートさせてあるのだから。
『泣蟲小僧』を見て、まずその全体に関して僕が感じるのは、昭和13年の映画に描かれた東京とその中での物語は、どこか異国のもののようであるということだ。展開していくにしたがって辛さが増していくのが身の上話の特徴のひとつだとするなら、『泣蟲小僧』の物語はまさに身の上話にふさわしい。しかし、仕上がりは決して身の上話ではない、と僕は思う。さほど悲観的に考えるまでもなく、誰の行く手もそれぞれに厳しいが、先行きに関して一切何のあてもないままに、対等に解き放たれているという点において誰もが対等だ。身の上話につきものの、破綻した論理のなかに閉じ込められてはいない。この映画の製作に携わった人たちの志は、もっと高いところにあった。そして幸運なことに、いまもそのままに残っている作品の質も、充分に高い。日本映画がその歴史のなかに残した佳作のひとつに数えていい。
『純情二重奏』は身の上話ドラマだが、作りのあざとさが嫌な後味となって残るようなことはなく、逆に誠実な作りかたが印象に残る。映像つきカラオケの原型として大変よくできている。観客という大衆のために、この歌と高峰三枝子をかたく結びつけ、ついでに歌も覚えてもらうのが、実はこの映画の真の目的だ。両者を結びつけるための工夫は、全編にわたって凝らしてある。現代の観客である僕は、その工夫を充分に楽しむ。
佐分利信が優秀な経理課員を演じた『兄とその妹』は、ひと言で言うなら昭和14年のサラリーマンものだ。彼は訳あって移籍した会社で、大陸での事業拡大にぜひとも君の力が必要だ。満州へいってもらいたい、と頼まれて満州へ旅立つ。妻と妹が一緒だ。飛行機の中のショットで映画は終わるが、現実世界ではもはや大陸での事業拡大どころではなかったはずだ。
『東京の女性』は、昭和14年の東京で自動車のセールスをする女性のストーリーだ。主人公の節子を原節子が、そして妹の水代を江波和子が演じている。江波杏子のお母さんだ。この映画で描かれる世界は、観客の名もなき庶民にとっては、憧れたり夢に見たりするに足る世界であったことは確かだろう。当時は国家による国民の管理や統制など、精神面でも物質面でも悲惨な次元に達していた。そのひどさが、この『東京の女性』には何も出て来ない。出て来ないことによって、憧れや夢は成立したのだろう。
『新女性問答』は、当時の女性映画だったということだ。だから主たる観客は女性であると最初から想定され、内容は女性の関心を強くとらえる方向で工夫された。主役を中心に、人気女優が何人か揃って出演しているが、中心となる三人の女性のキャスティングには、絵に描いたようなわかりやすさがある。最先端の人として想定されている桑野通子、家庭劇の部分を担っている良妻賢母は、三宅邦子だ。そしてメロドラマの部分を受け持つ薄幸のヒロインは、川崎弘子となっている。彼女たちのそれぞれの役割つまり内容を、最もわかりやすい形で観客に伝えるために、それにふさわしい容姿の持ち主が動員されることとなった。
『暖流』は恋愛映画だ。日本映画が描いた恋愛、しかも昭和14年の恋愛としては、たいへん良く出来ていると僕は判断した。『暖流』はいまの言葉で言う文芸大作に相当すると思う。ドラマを正面からとらえ、一定のテンポを崩すことなく、丁寧にストーリーを進展させている。一定のテンポで継続される丁寧さは、しかし、技巧の抑制などではない。数々の単純な綾は、きわめてわかりやすい効果を発揮する。
妻を亡くした父親とその娘2人をめぐる物語だが、『嫁ぐ日まで』は、さほど無理のない日常描写を、起伏の少ない具体性の中につなげて、物語の展開としている。嫁ぐということ、そして嫁ぐことによって生まれて来る状況の全面的な肯定、それがこの映画の主題だ。1949年公開の小津安二郎監督『晩春』の設定は、この『嫁ぐ日まで』によく似ている。『嫁ぐ日まで』を、自分ならこう作るという試みが、9年後の『晩春』だったのではないか。もし本当にそうなら、その試みはおなじ主演女優でおこなわれたことになる。このように対比させると、『嫁ぐ日まで』はさらに少しだけ余計に楽しめるかもしれない。『嫁ぐ日まで』と『晩春』との決定的な違いは、父親にあるということだけをつけ加えておきたい。
『ハナ子さん』の冒頭と同じく「撃ちてし止まむ」の言葉が画面に出る。「情報局国民映画」と画面は続き、さらに「下関要塞司令部、長崎要塞司令部、検閲済み」と出る。ロケーション撮影された場所が、かつての八幡製鉄、いまの新日鉄だからだ。この製鉄所の7本の溶鉱炉のうち、第四溶鉱炉は36パーセントの能率しか上げていない。すでに何人かの犠牲者を出して魔の溶鉱炉と恐れられている、この第四溶鉱炉をどうすればいいか。強制的に集められ過酷に使役されていた労働者たちが向かっていく。国家によって強制的に製作させられたこの映画が描かなければならない、もっとも中心的な主題はこれだ。この単純だが制約の多すぎる物語のなかには女性の登場する余地は全くなく、必要もなかったのではないかと、ぼくは思う。
男女が接吻をする場面が日本の映画には全くない。これはひどく不自然なことだから、ぜひとも接吻の場面のある映画を製作するように。と、GHQの民間情報教育部の映画演劇課の課長デイヴィッド・コンデは日本の映画会社に強く要請した。要請に応え、1946年の5月23日に、『或る夜の接吻』と『はたちの青春』という2本の映画が公開された。どちらの作品にも接吻の場面があることが宣伝され、両方とも大ヒットしたという。しかし『或る夜の接吻』を、戦後世相史のなかに「接吻映画第一号」というようなところだけに留めておくことは避けたい。非常にいい部分をこの映画は持っているからだ。求心力を持つ主演俳優のふたりの演技から、細やかに順を追って高まっていく恋愛感情の物語がひとつ、無理なくきれいに生み出されている。ふたりには、例えば過剰さという余計なものが一切ない。だからふたりをもっと丁寧に描ききったなら、『或る夜の接吻』は日本の恋愛映画として歴史に残ったはずだ。
夫を何年も前に亡くした妻が主人公だ。彼女は女手ひとつで3人の子供たちを育てて来た。敗戦後2年目とは到底思えない、安定して静かに満ち足りた日々の中にすべてはある。しかし彼女には、子供たちについて消すことの出来ない不満がいくつかある。この家族をめぐって、81分の娯楽映画をどう作るかはかなりの難題だ。僕には出来ない。作りようがないではないか。ならば、無理に作ればいい。ひとつどこかに無理を作ってそこからドラマを発展させ、無理を出来るだけ感じさせることなく、最後はすべてを丸く収める。昭和二十二年の東京ではこれが現実だった、とは誰も思わないにしても、いまはもうどこを探しても絶望的に消え失せたなにかが、この映画には封印されて残っている。それは、なになのか。家族の日常が円満に連続していくことを共通の目的として、全員が自分の役をよく心得てこなしていく様子に、まず注目すべきだろうか。もし今の映像のドラマで作ったなら、惨憺たるものになるのではないかと僕は思う。
溝口健二監督には、祇園や吉原などのように、別世界としての大枠があって初めて作り得た、と言っていい作品が多い。しかしこの『夜の女たち』においては、彼は女などまったく描いてはいない。ではいったいなにを描いたのか。『夜の女たち』の主人公は、戦前に両親と共に満州へ渡った妹と、日本に残った姉のふたりだ。姉妹の受難の物語は、なぜこうならなければならないのか理解に苦しむ、というかたちで始まって展開していく、よくあるパターンの話でしかない。悪いことばかり重ねて描いていくことによって、彼女たちふたりにおける論理の筋道は描かなくてもすむ、という道を監督は採択している。夜の女になろうがなるまいが、この姉妹が魅力的な存在として観客の目前に立ち上がりきっていなければならないはずだ。そして夜の女になったなら、その現実と対応することを通して、彼女たちの魅力はさらに大きくなっていかなくてはならない。そのことにこそ、観客は共感を覚えるはずだ。ところが彼女たちふたりに、ほとんど魅力がない。魅力というものをふたりに付加する作業を、この監督はけちった、と僕は言いたい。
『誘惑』は一編の娯楽映画としてはただの凡作だと僕は判断する。生まれ故郷で亡くなった恩師の墓参りに来た教え子の男性と、恩師の娘。このふたりが主人公だ。このふたりがお互いに抱いた恋愛感情の高まりを、どこへどのように落ち着かせるか、それが『誘惑』という映画の主題だ。恋愛感情そのものは主題ではない。それをどこにどう落ち着かせるかが、主題となっている。恋愛感情をお互いに対して抱き、それを高めていくのは彼らふたりだが、その恋愛が成就するにあたってはふたりだけではいけない、と『誘惑』の監督と脚本家は言っている、と僕は解釈した。
『湯の町エレジー』というかつて大ヒットした歌謡曲のレコードは、1948年の5月に発売されたという。幼い頃、自宅のラジオで、あるいは街のラジオ店やレコード店から街に向けて流れ出る音として、僕はこの歌を聞いているはずだ。しかし、はっきりした記憶はない。「一世を風靡した」というやや旧式な言い方がまさにぴったり来るほどに、この歌は大ヒットした。ヒットさせたのは当時の日本の大衆の力だ。そして新東宝という映画会社が、さっそくその力に便乗した。ひと言で感想を述べるなら、出来そこなった不条理劇だ。『湯の町エレジー』という歌には、イメージの広がりは充分にある。映画はその歌に便乗しながらも、歌が持っているイメージの広がりという力を、何百分の一にも縮小した。その理由はシナリオがまったく出来ていないからだ。なんでもいいから作って公開すれば、ヒット曲の映画だから客は来るにきまっている、という考え方が基本方針だと言っていい。観客の質は問題にされていない。来る客の数、つまり収益だけが問題だ。観客は映画を見るのではなく、収益の上げかたの、当時は有効だったひとつの形を見せられた。
『憧れのハワイ航路』という歌のヒットに便乗したこの同名の映画は、1950年の4月1日に公開された。便乗映画としては公開までに時間がかかっている。1945年の敗戦から1949年へ、そして1950年へという、戦後の混乱期の5年間をポピュラー・ソングで総まとめすると、かたや『湯の町エレジー』であり、かたや『憧れのハワイ航路』だった。ヒットした歌謡曲に便乗した映画というものの出来ばえに関して、僕はもうまったく期待していない。それでもなお、いったいどんなストーリーを画面の上に見ることが出来るのか、多少は期待する。映画の中では親子生き別れのストーリーがふた組、一軒のおでん屋を舞台に喜劇的に展開されていく。ハワイもハワイ航路も、いっさい関係ないしまったく出て来ないと言っていい。愕然とした、とまではいかないが、見終わって僕が啞然としたことは確かだ。おでん屋の二階に住む、日系二世という歴史的必然を持った男性だけがハワイ航路の人となるが、この点に僕は注目していいかと思う。『憧れのハワイ航路』という歌だけを1950年という時代のなかに置いて観察しなおすと、ハワイに憧れる気持ちに憧れるという、その当時の日本人がまだ守るべきだった節度としての、二重性ないしは間接性が感じ取れるからだ。
『夜来香(イエライシャン)』という歌に対する印象をひと言で言うなら、純情可憐だろうか。すでに終わった物語の思い出の歌であることは、一度聴けば誰にでもわかる。映画『夜来香』は、山口淑子の歌うこの歌を正式に主題歌として使っている。しかし、この歌の使いかたについては、まったく巧みではないと答えざるを得ない。ヒットした歌が大衆に対して持っていた力への、単なる便乗だったのか。ドラマの前半、戦争のなかでひと組の男女に恋が生まれる。そして戦争のなかで、ふたりは生き別れとなる。ドラマの後半のテンポは早い。最終的な悲劇に向けて、いっきに盛り上げていこうとしているからだろう。主要な登場人物たちそれぞれのなかに残され、同時に彼らの関係をつないでもいる戦争という一本の糸の上を、後半のドラマは走っていく。走っていくドラマは、幅が極めて狭い。見終わった観客の胸に残る印象は、戦争が遠因となって戦後に命を落とした男の、不運な身の上話なのではないか。肯定的には見どころのないこの凡作の、否定的な最大の見どころはここにある。
映画『上海帰りのリル』は、戦中と戦後のはざまで引き裂かれ、命を落としたひとりの男の物語だ。彼が引きずっていた戦中は、戦後に彼が身を置いたアンダー・ワールドと重ね合わされることによって、悪のイメージとなった。『上海帰りのリル』という歌が日本で全国的にヒットしたのは、昭和26年、1951年のことだった。敗戦から6年後だ。4月にマッカーサーが解任されて日本を去った。1952年の日本にとって、前方は早くも完全に見えていた。前方とは、日本経済の確かな復興だ。しかも、その方向に向けてかなりのところまで日本は進んでいた。振り返るだけの余裕、振り返って情緒的に懐かしんだり楽しんだりする余裕が、人々のあいだには生まれていた。『上海帰りのリル』は歌から小説になり、映画化され公開されるまでの所要期間は10か月であったという。相当な早業だ。早業という高回転を支えてくれるだけの観客が、大衆として存在していたことの証拠だ。
『夜来香』でシナリオを共作したのと同じ脚本家が、この『ハワイの夜』の脚本を担当している。映画は(公開当時の)現在のハワイから始まり、そこから1940年に戻り、戦後へと時代を追って話が進んでいく。この映画にとって、戦争そのものはどうでもいいようだ。ごく表面的な事実を、ドラマの中での必要に応じて、簡略に並べておけばそれで充分、ということだろう。そのドラマとは、ひと組の若い男女(日本人男性と日系二世の女性)の間に芽生えた恋が戦争によって引き裂かれ、実ることのなかった悲しい恋に終わる、というドラマだ。『夜来香』とまったく同じことが、ここでも行われている。ひとりではどうすることも出来ない不運や不幸として、戦争が個人の悲しい身の上話に閉じ込めてある。戦争を個人の身の上話にしてしまおうとする志向は、1950年代前半の日本の大衆にとって、早くも主流的な気持ちとなっていたのではないか、と僕は推測する。このような心情に娯楽映画は目をつけ、その心情を主として悲恋のドラマに仕立てて大衆に提供するという、時流への便乗のしかたを発揮した。
『雲ながるる果てに』という映画は、特攻隊の青年たちを主題としている。部隊の宿舎で若い兵士たちが出撃命令を待っている。雨が降り続き、飛べる日はなかなか来ないという毎日が、『雲ながるる果てに』の物語の舞台だ。もの静かにまんべんなく語られる誠実な映画であることは確かだが、そのことと同時に、あのときはこうだったのだよと、懐かしむ気持ちを多少は込めて、物語は語られていると僕は感じる。敗戦から8年もたってこれなのか、という思いを僕は否定出来ない。しかし、これなのか、という評価とは別の次元で、この作品は立派に機能を果たしている。振り返ってなにほどかの懐かしさとともに語られる戦争のエピソードを、観客たちもまた振り返りつつ懐かしさとともに受けとめる。そしてその作業をとおして、戦争は極めて滑らかに個人の身の上に封じ込められていく。
久米正雄原作の『月よりの使者』は映画化されるのは3度目であり、極め付きのメロドラマだそうだ。関心の対象とはとてもなり得ないような出来ばえだ、とだけ書いておこう。このストーリーを支える法則は、行って当然のことを一切何も行わずに自己中心的にしていると、運命のほうで勝手にもつれてくれて、そこに悲恋のメロドラマが生まれる、というような法則だ。するべきことを一切何もしないとは、論理を無視するということにほかならない。論理はとにかく無視するのだから、そこにはいかなる非論理的なメロドラマも成立する。この映画では、自分の責任を明確にすることを一切しない男が、かいがいしく彼の世話を焼く女をひとり手に入れる。昭和30年前後からその存在が定着していった、日本の会社男とその妻にまさに適用可能な法則を『月よりの使者』は、はからずも描いたのではないか。この映画は大映にとって3本めのカラー映画だという。カラーで作るという意気込みの末端が、おそらくその意図は完全になかったはずだが、新しい時代の法則をひとつ、すくい取った。
ジャンケン娘とは一体何だろう。娘とは、この場合は、美空ひばりと江利チエミ、そして雪村いづみの3人のことだ。考えているとやがてわかって来た。ジャンケンとは、石、紙、鋏の三者だ。ひばり、チエミ、いづみの3人は、グー、チョキ、パーに相当する。どれもが他のどちらをも補完し合うことで、3人はさながらジャンケンのように成立している。ジャンケン娘とはそういうことのようだ。映画の作りとしては、三人の娘たちが主役だ。しかし、その彼女たちが立っている土台としての物語は、脇に置いてあったり背後に回ったりしている大人たちの物語だ。その物語には、古ぼけた型紙をただなぞっただけの古いストーリーが用意されており、彼女たち3人がスターとしてそれぞれに持っていた力にただ便乗しただけだ。『ジャンケン娘』に、そして類似の多くのものに満足した当時の日本の大衆とは、いったいどのような人たちだったのだろうか。この疑問を解く手がかりのひとつとしての視点は、『ジャンケン娘』の監督の、その後の活躍を見渡すことによって得られる。三人娘のシリーズのあと、急速に進展していく時代のなかで、お姐ちゃんシリーズというものをこの監督は手がけた。街のお姐ちゃんではなく、大学のお姐ちゃんたちであったらしい。続けて社長シリーズを演出し、さらにそのあと、若大将シリーズを彼は演出した。
2023年10月27日 00:00 | 電子化計画