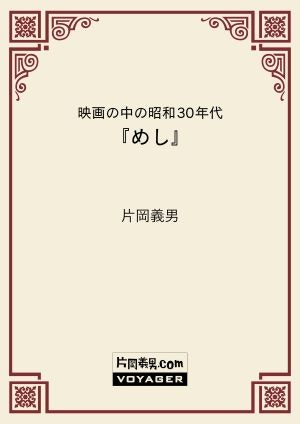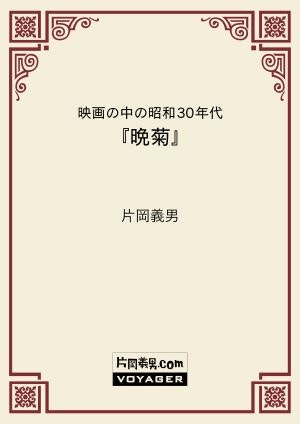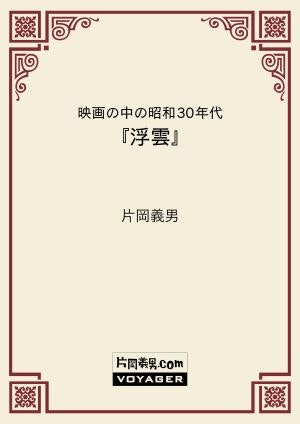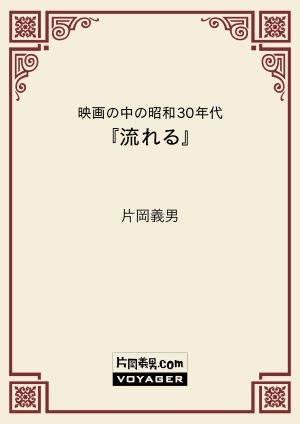映画評論『映画の中の昭和30年代──成瀬巳喜男が描いたあの時代と生活』より14作品を公開
映画評論『映画の中の昭和30年代──成瀬巳喜男が描いたあの時代と生活』(草思社/2007年)からの14作品を本日公開しました。
成瀬巳喜男が監督した最初の映画作品は八十八本ある。戦前と戦後で監督した作品数はほぼ均衡している。僕が興味を持ったのは一九五〇年代の成瀬作品だ。僕が初めに最も大きく期待したのは、それぞれの作品で描かれる時代の女性たちが喋る、女言葉だった。僕はこれまで日本映画を題材に三冊の本を書いた。戦前、戦中、戦後の娯楽的な映画を何本も観て記憶に残ったことのひとつは、女性たちが思いのほか闊達であり、多少の曲折はあるものの、最後には自分たちの意思や思考どおりに現実のなかに活路を開き、思っていたこと、願っていたことなどを達成させていく様子だった。もうひとつは、一九五〇年代の成瀬作品を時代順に観ていくなら、今の自分がかつての一九五〇年代に再会出来るのではないか。単なる再会を越えて、いま初めて体験する新鮮な発見が、必ずやいくつもあるはずだ、という方向へも僕の期待は広がり始めた。時代とはけっして無関係ではあり得ない娯楽映画は、かならずやそれぞれの時代を反映させているはずだ。
『銀座化粧』(1951)は、まっとうに働く大人へと成長してほしい、と自分の子供に伝えるための、どんな教育よりも有効なはずの実証として、いまここでの母親の日々がある、という主題の作品だ。そしてそのような実証の日々を支えるのは、母親のけっして多くはない稼ぎであり、切りつめた支出のなかで帳尻をいかに合わせるかという、幸福と経済の追いかけごっこだ。そのような主題が正面きっては提示されていないところが、この作品のいいところだろう。映像ではかつて東京の中心地帯を流れていた、水路ないしは運河とも呼ぶことの出来る川と橋が描写されている。また、登場人物たちの生活ぶりや所作など、今は消え尽くしてしまったが、フィルムに虚構として残されたかつての現実を見ることができる。
『めし』(1951)は林芙美子の同名小説が原作だ。大阪を舞台に岡本初之輔(上原謙)とその妻、三千代(原節子)のふたりを主人公としている。1951年の日本ではすでに、何をおいてもまず経済、という国をあげての方針が、社会全体の現実そのものとなっていた。あらゆるものが経済の上にのみ成立する日本の話の1951年版として、僕はこの『めし』をとらえておきたい。この作品をシナリオと突き合わせて見ると、監督が必要ないと判断した部分は全体にわたって刈り込まれており、そのために何人かの人物像がいまひとつはっきりしなくなる、という副作用がある一方で、撮影で付け加えられたシーンもある。また、主人公夫婦が住む長屋とその内部はセットだが、当時はまだ現実に存在していたものを参考に、ほぼ当時の現実のままに再現されている。物語の主要な部分は、この長屋で展開していき、その空間はすべて物語のために使いきられている点にも興味は尽きない。
田中絹代主演の『おかあさん』(1952)は「どこでもない、どこか」が舞台だが、それが映画全体にとっては物語や状況の質的な純度を高める方向へ確実に機能している。その中で主人公の家族など登場人物の間に発生する関係がどんなふうに推移していくのかを描いたのが『おかあさん』という物語だ。この映画は「森永・母を讃える会」という組織が全国の子供たちから母親を主題とした作文を募集し、その中から選んで一冊にした『全国児童綴方集』という本からいくつかのエピソードを抽出し、ひとつの家庭の話としてシナリオにまとめたものだという。物語の途中のいろんなところで「早いものねえ」という言い方がまさにあてはまるほどに、状況は変わっていく。感嘆しながら過ごす日々に、ささやかな夢がどこまで実現するかしないか、出て来る玉は白か紅かの、大売り出しの福引のような日々だ。
1950年代の初めから1960年代半ばまでの日本は、市井の片隅における庶民生活の悲喜こもごもという題材が、娯楽映画として多くの庶民の強い共感を集めることの出来た時代でもあった。この期間の成瀬監督は、映画監督として最も幸福な時間を過ごした。それは、彼にとって最大の関心事であったと僕が推測する、撮りかたの問題に最大限に注力出来たからだ。撮りかたとは、物語のための空間として作られたセットという空間の中で、俳優たちが演じる物語を、どの位置からどんなレンズと照明で、どのように切り取り、観客にどう見せるか、ということだ。『稲妻』(1952)でも、こうした空間を巧みに切り取ってみせることで、登場人物の感情を観客に感じさせることに成功している。
『夫婦』(1953)は井手俊郎と水木洋子が書いたオリジナル脚本による作品だ。『めし』『夫婦』そして『妻』の3作は、成瀬の夫婦もの、と呼ばれることもあるようだ。上原謙と杉葉子が演じる夫婦が転勤で5年ぶりに東京へ戻り、住む場所を探すのだがなかなか見つからず、最初は妻の実家、次に夫の会社の同僚で妻を無くした男の家の1階に引っ越すことになる。途中、何度か挟まれる当時の銀座の実際の風景が、現実の重みとその奥行きのようなものを、いま僕が見ても強く感じる。3人が一軒の家に生活することで生まれる誤解とその展開はコメディ映画のようだが、シリアスとまではいかないとしても、充分にストレートでまともに、しかもときとしてリアルに描かれている。公開時に作られたポスターには、次のようなコピーが使われていた。
市井の片隅に揺れている
侘しい夫婦のささやかな愛の灯
妻の倖せとは…
全女性に献げる愛の珠玉
『晩菊』(1954)は林芙美子の短編『晩菊』『水仙』『白鷺』から設定や話を摘まみ出し、1本の映画にしたものだ。戦前に芸者などをしていた、ほぼ同年代の4人の女性たちが主人公だ。敗戦から間もなく10年がたついま、この4人の女たちの人生は如何に……。『晩菊』の物語はそれにつきる。成瀬監督の多くの作品で目にするのは、同じ時間の中で何人かの人たちそれぞれに行う、日常的な小さな動きの描写だ。カットからカットへの移行の滑らかさを実現させるために、別人のそれぞれに異なる状況のカットを、同じ動作の描写でつないでいく、という手法だ。結果としてそれが演出の特徴として目立つことになる。しかし、もっとも重要なのは終わりかただろう。終わりかたがぴたっときまらないと、そこまで画面を見てきた観客の気持ちは、中途半端なところで宙づりになったままとなる。冒頭の画面からエンド・マークまで、大きな波瀾などいっさいなしに、可能なかぎり滑らかにつながった一本のフィルムを作りたくて、成瀬巳喜男という映画監督は映画を作ったのではないか、と彼の作品を見ながら僕はしばしば思う。
『浮雲』(1955)は真珠湾攻撃の少し前にフランス領インドシナで出会った、日本から派遣されていた農林省の役人で妻のある富岡と、役所に雇われたタイピスト・ゆき子の敗戦直後の日本における物語だ。2人の背景はほとんど語られず、ある種の典型としての役割を担わされている、というのが僕の感想だ。水木洋子の脚本は抑制が利いているが、それでも成瀬によって撮られていない部分はある。強い感情を表現する言葉と、それにともなうアクションだ。だから特に男性については、彼は何を考えているのか、何をどうしたいと思っているのか、いまひとつその場ではつかみきれず、観客は映画の進行に少しずつ遅れながら理解が進んでいく、という体験をすることになる。
『驟雨(しゅうう)』(1956)は岸田国士が大正時代の終わり近くに書いた一幕物の戯曲が原作となっている。描かれている物語の中心にいるのは若いひと組の夫婦だ。すべては彼らをめぐって進行していく。彼らの周辺に配置されているエピソードは、物語全体にとって、さほど効果を上げているとは思えない。片方にコメディがあり、もう一方の端には、深刻な事態をめぐるシリアスなドラマがあるとするなら、『驟雨』はこの両者のちょうど中間、つまりそのどちらでもない、という位置におさまるような出来ばえだ。責任はシナリオにある。ことさら辛口に採点しなくとも、平凡以下であるという評価だって充分に成立するだろう。成瀬監督が得意としたこのような内容の映画にとって、終わりかたをどうするかはたいへんに重要だ、と『晩菊』のところで書いた。まったく同じことが『驟雨』にもあてはまる。
『妻の心』(1956)は、地方の古風な薬局の次男に嫁いだ女性が主人公だ。彼女は生まれにおいても育ちにおいても、時代背景としては全くついていない。どうしてこうなのだろうと心のどこかで思いながらいまを生きているそんな30歳の人妻・喜代子を高峰秀子が完璧に演じている。それにしても何をどうしたかったのか、よくわからない映画だ。シナリオの通りに撮ったらこうなった、ということでもないような気がする。物語を発生させる力、そしてそれを展開させていく推進力としてもっとも強いのは、喫茶店の開店をめぐる喜代子という女性の存在だと僕は思う。彼女のありかたをもっと工夫して最初から最後まで前面に出し、喫茶店は実現しないにしても、少なくとも喜代子はもっと変化をとげるべきだった。映画の冒頭から流れる音楽はせつなくやるせなくもの悲しい曲だが、成瀬監督の演出の妙技とじつに相性がいい。監督が家のセットを使いきる様子も、気をつけていれば堪能することができる。成瀬監督の演出には見逃しがたいディテールが豊富にある。
『流れる』は1956年の作品で、物語の背景となっているのはその年だと思っていい。1956年と言えば、戦後の日本がまず体験した、時代の裂け目のような激変が始まった時期だ。原作は幸田文の小説で、当時のベスト・セラーだという。山田五十鈴。高峰秀子。田中絹代。栗島すみ子。岡田茉莉子。杉村春子という豪華な女優陣による、借金を抱えた芸者置屋を中心に流れる時間を捉えた映画だが、なにをどうしたい映画なのかよくわからない出来ばえだ、と僕は思う。しかしそれを成瀬巳喜男が撮るなら、成瀬の映画が出来上がることは確かだ。だからそれでいいのだと言われたら、僕に異存はない。撮りかた、特にセットの使いかたは、『めし』や『晩菊』とまったく同一だと言っていい。柳橋の路地にある主人公の家の、その路地に面したおもて側のセット、一階そして二階の内部のセット、路地を出たところで交差する道のセットなど、成瀬作品における撮影セットとその使いかたは、『流れる』でその頂点をきわめた、と僕は思う。そしてこの映画にも「失われた昭和」がいくつか見られる。
『杏っ子』(1958)は作家を父に持つ妻・杏子と、小説家志望で会社勤めが続かない夫・亮吉を主人公とした作品だ。この映画で監督や脚本家が何をどうしたかったのか、僕にはわからない。その意味では、ここまで書いてきた成瀬作品のなかで、これが僕にとってはもっとも奇妙な作品だ。奇妙とは、観客である僕によって、かなりの深さに達するほどの読解を必要とする、というような意味だ。作家である父親の保護力とも言うべき範囲内に生きている杏子。そして彼女と結婚した、作家としての才能のない亮吉。主題と直接に関わるはずのこの三人から、どんな物語を観客の僕は読み解けばいいのか。父親と夫を極端の両端だとすると、まんなかに位置して両極端のいずれとも少しずつ重なり合っているのが娘であり妻である杏子だ。だから彼女を厳しい視線で点検していくと、この映画の主題が見えてくるのではないか。
かつてはその辺り一帯の地主だったが、農地改革で自営農家となった「本家」と、その「分家」の家族についての物語が『鰯雲』(1958)だ。本家は、この映画では農村共同体の象徴なのだろう。時代が変わり、共同体は成員たちの人生のすべてを賄うことが出来なくなった。変わっていく時代とは戦後の日本の場合、経済だ。激変していく経済のなかで、共同体は明らかに置いていかれようとしている。本家の3人の息子は農業を離れる。それぞれの幸せを追うなら、それぞれが本家からそして農業から離れなくてはいけない。彼らが進む方向は、農業に背を向けて見つけ出す方向だ。そしてひとりずつばらばらに、東京つまり都会へと向かう。そこにしか経済はないからだ。この作品からは脚本に橋本忍が加わっており、それまでとは何かが確実に違っている。おおまかに言って、違うのは時代の反映のさせかただ。成瀬作品の登場人物たちの身の上にこのような変化が起きることは、少なくとも僕が体験したかぎりではこれまで一度もなかった。それでもシナリオと映画をつき合わせると、削られた部分を次々に発見することになる。そこにも成瀬巳喜男は監督として存在している。
『娘・妻・母』(1960)という題名は、成瀬監督の好み、という範疇にすんなりと入るもののひとつだろう。母がいるなら父が、妻には夫が、そして娘とおなじ位置には息子がいるはずだが、男のほうはすべて省略され、『娘・妻・母』となっている。ここで描かれる家族に起きてくる問題は、例によって金銭問題だ。それに対する家族それぞれの反応をひとめぐり描いて『娘・妻・母』という映画はきわめて曖昧に終わる。ほとんどなにも解決されないまま、解決へのかすかな展望や淡い予感すらなく、穏やかではあるけれど曖昧に終わるのは、成瀬監督の作品の多くに共通する特徴のひとつだが、その特徴がひときわ好ましくない形で現れた例だろう。明確に力強く全体を貫く一本の柱、というものをこの物語は決定的に欠いている。柱がどこにもないかわりに、物語が依存する背景として、時代性のようなものが取り込んである。変化していく時代こそ客観情勢だと誤って判断しつつ、それを主観的に捏造して提示し、そこに自分たちの主観のすべてを託した。時代性という永遠に一過性のものに、きわめて安易に依存したと言うほかない。
2023年10月20日 00:00 | 電子化計画