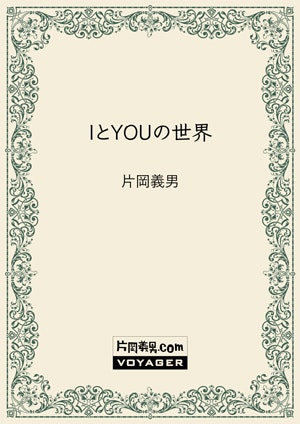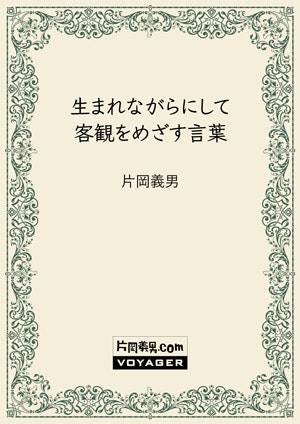評論『日本語の外へ』より11作品を公開
『日本語の外へ』(底本:角川文庫/2003年)より11作品を本日公開いたしました。
1992年、アメリカ大統領選挙で民主党、共和党のどちらも支持しかねる人たちにとって、ロス・ペローは一時的にではあれ充分に情熱的になり得る対象だった。ブッシュとクリントンの両方を好きなように攻撃出来る立場、あの気質などは、選挙戦の最終盤をかなり面白くしてくれた。国家の運営も、政府と市民の関係も、彼にとってはビジネスのひと言で割り切ることができた。もとより大統領の器ではなかったが、面白い存在だった。ちなみに『クレイジー』は、ウィリー・ネルソンによるカントリー・アンド・ウエスタンの曲。
アメリカ大統領選挙(1992年)での共和党ジョージ・H・W・ブッシュ候補のスピーチは終盤に近くなるにつれて、ひどさの度合いを急速に深めていった。民主党ビル・クリントン候補の主張する経済政策を「エルヴィス・プレスリー・エコノミックス」と揶揄したが、クリントンは「変化を!」と主張して、最終的に当選した。その「変化」の根源的な真の深さを理解している人は多くなかったはずだ。カーター政権のときから始まった税制の矛盾は、レーガンとブッシュの12年間で極限に近いところまで拡大し、米国の赤字額は3兆ドルを超えていた。
アメリカ大統領選挙では、既存の政府に対する反感や離反の感情を、野党は見逃さずさまざまに利用する。そしてそれが効果を上げるなら、大衆の支持や共感は野党へと大きく振れていく。ただそれだけのことだが、とうてい解決は不可能な難問の解決を、どちらの陣営も交互に約束する。しかし現状は好転していかない。その結果、大統領候補として選挙運動をしていたときにおこなった、守ることなどとうてい不可能な約束を、大統領になってから誰もが修正したり削除したりしなければならなくなる。
英語の主語はその文章全体にとっての論理の出発点であり、責任の帰属点でもある。主語は動詞を特定する。動詞は前へ前へとアクションを運んでいき、最終的には主語を責任と引き合わせる。日本人が英語を喋るのを聞いていると、いたたまれなくなるほどのきまりの悪さを覚える。その中で最大のものは、センテンスの半ばあたりで主語を忘れてしまっている気配がある、という恐るべき事実だ。主語を忘れているからには、動詞も彼らは忘れている。主語と動詞を忘れてしまったなら、センテンスが最後まできちんとしているということは、とうていあり得ない。
アメリカのパブリックTVのニュース番組で、日本とアメリカとの関係全体への、ごく一般的で文化論的なアプローチによる特集があった。経済記者をつとめているポール・サルマンが、アメリカの会社で働く日本人の中年男性社員に取材を重ねていくが、彼の話す英語は日本語で発想したものをひとつひとつそのまま頭の中で英語に置き換える、というタイプの英語だった。取材の過程で行った「私をこれまで以上に好くために、これまで以上の努力をあなたは将来においてしてくれますか」という質問に対する答えは、「私が私のままでいられるなら、その限りにおいて」という、実に不思議なものだった。
人が自分の母国語を使うときには、自分を守りつつその自分に出来るだけ多くの利益をもたらすことを目的に、極めて主観的に利己的に自由自在に、母国語の性能を駆使する。駆使すればするほど、人は母国語の性能の内部に閉じ込められていく。外国人を相手に外国語を使うとは、母国語によって自分の頭のなかに精緻に構築された世界、つまり発想や思考そして表現のしかたすべての、外に出ることだ。そのためには、母国語の教育を徹底的に作り換えたあとに、英語なら英語の抽象性を学ばなければならない。それが外国という異質なものとともに公共の場に立つ第一歩である。
人が頭のなかで行うこと全ては、言葉を媒介にしておこなわれている。日本の人たちにとっては日本語が母国語だ。何かについて少しでも考えるとき、その考えは母国語の構造や性能のなかでしか行われない。英語のIに相当する言葉は、日本語にはない。Iがないということは、その対立項であるYOUもまったく存在していないことを、自動的に意味する。言葉とは社会の成り立ちそのものだ。そしてIとYOUは、その成り立ちが持つ基本的な性格を、もっとも鋭く一点に向けて抽象化したものだ。
日本語が主観的であるのに対して、英語にはすべてを客観へと向かわせる力が、基本的な性能として構造全体のなかで強く作用している。英語は正用法に関する文法上の枠が、日本語にくらべるときわめて厳密だ。英語によるものの捉え方や考え方の基本は、積極的な提案や改革の意志の中心軸および推進力としての、前進的な攻撃性だ。これに沿って、出来るだけ多くの人を望ましい方向へ動かしていく力をもっとも強く発揮するのが、客観性というものである。
日本人の対話は、対人関係の場という現実的で具体的な世界に常に則している。場ごとに、相手ごとに、そして関係ごとに、自分が用いる言葉は違ってくる。一方が他方に強い力を突然に加えると、関係は変形したり壊れたりする。これはなんとしても避けなければならない。関係は一定に安定させて長く持続させてこそ、そのなかでの利害調整が可能になっていく。日本語のなかには、対立を回避するための言葉およびその性能が豊富に用意されている。それをひと言で言うと、表現の曖昧さだ。すべての事態は、いつのまにかそうなる。事態はいつのまにかそうなった。その結果として、いま事態はそうなっている。これが利害関係をもっとも重要な基準とする日本人の思考である。
幕末以降の日本は近代化の過程において、西欧の技術だけを取り入れた。日本語の性能の傾きを母国語として一身に引き受けていた結果、なぜ、という客観的な因果関係に思考が及ばなかった。取り入れたのは、製品や機械のようなもの、つまり技術とその成果、そして使用説明書あるいは組立説明書としてのみ受けとめた、文献だけだった。別の言い方をすると、名詞を吸収しても、動詞には興味を示さなかったということだ。動詞とはアクションであり、それは理念があって成立する。そして行動には責任が伴い、理念とは対立とほぼ同義だ。
日本には対話がない、日本人は対話が不得手だ、対話の重要性が認められていない、といった、日本人が自らに対する批判は無数にある。客観性を犠牲にしないかたちで、問題や出来事あるいは事柄などについて的確に表現する、感情を主観に染めてねじ曲げたりせず端的に他者に伝えるための母国語のトレーニングを、日本人はまったく受けていない。話すためのスタイルがなければ、聞くことも本当にはできてないことになる。対話がない社会とは、話すことと聞くことに関して、本質的にその重要度を認めていない社会ということだ。
2022年8月16日 00:00 | 電子化計画
次の記事へ