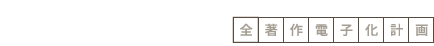連載エッセイ「先見日記」より12作品を公開
「先見日記」(「先見日記 Insight Diaries」)は、株式会社NTTデータのWebサイトにて2002年10月から2008年9月までの6年間にわたり、延べ16人の執筆者によって連載された日記形式のエッセイです。片岡義男は創刊時から2005年4月までの約2年半、毎週火曜日を担当しました。今回は2004年7月から2004年10月にかけて掲載された12作品を公開します。いずれも単行本などには未収録の作品ばかりです。
ゴルバチョフがレーガンと核の軍縮をめぐってやり合っていた頃、ゴルバチョフはアメリカを訪れ大歓迎を受けた。ゴルバチョフがあれほどの好意的な歓迎を受けた理由はただひとつ、ゴルビーの持つ魅力だった。ゴルビーというニックネームが生まれることじたい、そもそも彼がアメリカの人たちから高く評価されていたなによりの証拠だ。あの頃のゴルバチョフは、風貌、体つき、かもし出す雰囲気、衣装など、ほとんどすべてにわたってアメリカの人たちには懐かしくも身近な、中西部の典型的な叩き上げ実業家のアメリカ人そのものだった。
(『先見日記』NTTデータ/2004年7月13日掲載)
参議院の普通選挙で自民党がTVで放映したCMには驚いた。まず首相が登場して、この国をどうするこうすると言っていた。どうもこうも出来ない、ただもっと悪くなるだけだ。だからそれはそれでいいとして、それに続いたカラーの静止映像は、衝撃的だった。いくらイメージと言ったって、あまりと言えばあまりではないか、と僕は思った。いまこの期に及んで、自分の国である日本をこんなふうに表現する感覚とは、一体なになのか、と僕は思った。
(『先見日記』NTTデータ/2004年7月20日掲載)
9・11の出来事のあと、アメリカは自分を守る、だから敵に対しては戦争をする、という方向へと進路を取ったブッシュ政権は、ほんの一時だったにせよ、90パーセントに近い支持率を獲得した。しかしこの瞬間は、そのあとに来る深刻な事態の助走路だった。国がまっぷたつに分かれてしまう、という事態だ。秋の大統領選挙に向けて、アメリカの二分化はよりいっそう明確になりつつある。単独の武力行使を主張する共和党と、国際協調による話し合いを掲げる民主党への二分化だ。
(『先見日記』NTTデータ/2004年7月27日掲載)
娘ふたりを伴ってジェンキンス軍曹が北朝鮮を出国したとき、彼の左胸には北朝鮮のバッジがつけてあったという。細かく意味が規定されていて、つけていなかったりなくしたりすると、厳罰に処せられるというあのバッジだ。このバッジで僕が久しぶりに思い出したのは、日本の会社が社員につけさせるバッジだ。商社に就職した僕の会社経験のひとつにバッジがある。このバッジは給付されるのではなく貸与されるのだから大事にしてなくさないこと、常に上着の左胸につけていること、などと厳命されたのをいまでも僕は覚えている。
(『先見日記』NTTデータ/2004年8月3日掲載)
終戦記念日の日本で首相が式典の会場で読み上げる式辞の中には、ポイントが常にふたつある。2004年に首相が読んだ式辞のなかでも、そのふたつのポイントがちゃんと用意されていた。首相だけではなく誰もが、同じような言葉を述べるだろう。こうとしか言いようがないという種類の定型の一種であり、それ以上でも以下でもないと理解するなら、式辞としてはこれで充分なのだろう。しかし現実とはまるで異なっている。そしてその事実には、あらためて愕然とする。
(『先見日記』NTTデータ/2004年8月17日掲載)
大きく変わるべきときに変わらなかった当然の結果としての現在の状態。いまの日本はこれなのだと僕は判断している。バブルが崩壊してから10年たっても立ち直れずにいることが、「失われた10年」と表現されているけれど、その10年はいま15年へと確実に延長されつつある。そのバブルの崩壊のあと始末がまだ出来ていない理由はただひとつ、これまでどおりをなんとか踏襲しようとしているからだ。そしていまでも変われていない。
(『先見日記』NTTデータ/2004年8月24日掲載)
また買ってしまった。今回は1冊だけ買ったのだが、自宅へ帰って数えてみると、すでに11冊あった。買ったばかりの1冊を加えて、合計で12冊。たいへん強く惹かれるものがある。だから買う。おそらくスペイン製だ。ノートブックか、それとも手帳というべきか。中世以来の伝統がいまもそのままここに生きている、という雰囲気で、この量感、そして実用に徹した質感に僕は勝てない。表紙の色はすべてオリーヴ・グリーンだ。さらに買うだろう。しかし、なにを書けばいいのか。
(『先見日記』NTTデータ/2004年8月31日掲載)
『オー・ヘンリー賞短編集』の2003年版をこの8月に買った。昨年の9月にアメリカで出版されたものだから、ほぼ1年遅れで手に入れたことになる。この短編集の第1巻が出版されたのは、オー・ヘンリーが他界した翌年、1819年のことだった。それ以来今でもずっと刊行され続けているのだから、冊数や収録された短編の数もさることながら、消えることなく残っているアメリカ文化のなかの、良き伝統のひとつだと言っていい。
(『先見日記』NTTデータ/2004年9月14日掲載)
今日はビートルズの『ノーホエア・マン』を銀座、日本橋、神田の3カ所で聞いた。どの商店でもBGMとして店内に流れていた。ビートルズはいまでは単なるBGMの機能も果たしている。『ノーホエア・マン』とそのまま片仮名で書くのは、僕が言うところの50パーセント翻訳という手法だ。本当は何もわからないのだが、片仮名であるだけに何となくわかったような気持ちになり、何の抵抗もなく『ノーホエア・マン』と言ってしまう。そして口にすればするほど、わかったような気持ちは濃厚になっていく。日本語が主として戦後に獲得した新たな機能の、特徴的なひとつだ。
(『先見日記』NTTデータ/2004年9月21日掲載)
9月21日の夕方(現地時間)、国連総会で日本の首相が演説をした。内容は別に何がどうというものでもなかった。武力行使と憲法との関係については言及はなかった。国連の常任理事国になることと憲法の改正、つまり第九条の改正とを、いまは結びつけないでおこう、という方針なのだろう。演壇に立った首相は、英文の原稿を指先で追いながら、棒読みに終始した。こういう場面での経験が悲劇的に不足している。声だけは張らなくてはと、強い発声をすればするほど、英語の抑揚から遠ざかる。
(『先見日記』NTTデータ/2004年9月28日掲載)
1954年5月25日、写真家のロバート・キャパは、インドシナでフランス軍の戦闘行動に同行して写真を撮っている途中、地雷を踏んでその生涯を終えた。彼の生涯に関しては、膨大で克明な伝記があるが、生涯の最後にフランス軍に同行してのラスト・ショットに至るまでの経緯は、きわめて簡x略にしか書かれていない。彼の残した写真や他の人たちの記録、さらにはヴェトナム現地の人たちの証言などをもとに、ロバート・キャパの「最期」をつきとめたノンフィクション作品『ロバート・キャパ最期の日』を僕はたいそう興味深く読んだ。
(『先見日記』NTTデータ/2004年10月5日掲載)
1954年4月、ロバート・キャパは日本にいた。日本へ来る前、日本では生きた人間を撮りたい、とキャパは言っていたという。彼は銀座、東京駅、熱海などで熱心に撮影をし、日本は「ピクトリアル・パラダイスだ」と叫んだそうだ。ここは被写体の宝庫だ、というような意味に解釈すればいいだろう。日本という異国における、日常を生きる人たちのありかた、つまり自分の目にとまった彼らの姿態の面白さに、キャパはきわめて敏感にそして率直に反応して写真を撮った。しかし出来上がってくる多くの写真に対して、写真の専門家たちはもの足りなさと不満を覚えたという。
(『先見日記』NTTデータ/2004年10月12日掲載)
2025年5月2日 00:00 | 電子化計画