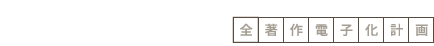連載コラム「アメリカン・マッスル」より10作品を公開
雑誌『Free & Easy』(イースト・コミュニケーション)にて、2004年から2006年にかけて連載されたコラム「アメリカン・マッスル」からの10作品を本日公開いたしました。1940年代から70年代頃までの、アメリカを象徴するさまざまなモノや文化を通して、今はもうない「アメリカらしさ」について考察したものです。真壁一智さんのイラストとともにお楽しみ下さい。
アメリカらしいかたちをした物が急速に消えつつある。アメリカらしさ、つまりアメリカン・マッスルを一身に体現するような色づかいと造形の物が、1980年代から消え始めた。二度と新品では目にすることが絶対にないと言っていい、もはや完全に絶滅したアメリカらしさの典型として、かつて大流行したファスト・バックの自動車をいま、僕は純粋な気持ちで懐かしむ。アメリカのパワーすなわちアメリカン・マッスルの、もっとも美しい造形例のひとつではなかったか。
(『Free & Easy』2004年7月号)
水着美人、と日本語で書くと、歳時記のなかにある夏の季語のようだ。字面にやや古風なものが漂う。のどかな雰囲気も感じる。清楚な華やぎ、といったものも感じる。日本のどこに水着美人がいたのだろう。どこにもいなかった幻だからこそ、いまでもまるで季語のように、日本語の語彙集のなかにひっそりと静かにしているのか。ベイジング・スーツを身につけたビューティー。これは1930年代のハリウッドが作り出した、虚空に浮かぶ美という幻想の価値のひとつだ。
(『Free & Easy』2004年8月号)
日本やナチス・ドイツと第二次世界大戦を戦っていた頃のアメリカでは、ありとあらゆる民間企業が、戦争に必要な途方もない種類と用途そして量の物資を分担して生産した。例えばポンティアックはジェネラル・モーターズのポンティアック・モーター部門で、普段は自動車を作っていた。そしてほかの多くの企業と同様、ここも一夜にして軍需産業へと転換し、陸軍と海軍のために魚雷や野戦砲など六つの領域で最大限の協力を果たした。
(『Free & Easy』2004年9月号)
男と女との間の外見上の性差、つまり簡単に言って服装の差が、アメリカではきわめて大きい。文明国とは思えないほどの大きさだ。腕力や武力がいまでもあっさりと決め手になるのだから、根っこのところでは野蛮国なのだ。男のマッスルが要求してやまない女性の性的魅力を、商業的なかたちの作品としてひとまず完成させたのが、ピンナップというものだ。第二次大戦に従軍したアメリカ軍の兵士たちというアメリカン・マッスルのきわみが、ピンナップをいっきに完成の域へと高めた。
(『Free & Easy』2004年10月号)
『ライフ』の1943年9月27日号に掲載された、キャンベル・スープ・カンパニーの戦争遂行協力と戦意高揚広告では、兵士たちがジープのエンジン・ルームの中に固定して温めたレーションの缶詰スープをお昼の食事時に食べている。当時の日本では、政府が厳しい制限のなかで配給されていた塩や醬油で道ばたの野草を煮た「決戦料理」を奨励していた。勝負は大勝と大敗とに分かれて当然だろう。
(『Free & Easy』2004年11月号)
スミス・コロナ社の1965年のタイプライター「ギャラクシー2」は、人が指先の力でキーを打つマニュアル式のタイプライターとしては、最も進化した完成型と言っていいものだ。このあとアメリカのタイプライターは電動になった。指先で叩くキーと複雑な機械じかけでひとつひとつ連動していた印字活字が、プラスティック製の一枚のホイールにまとめられた。電動までのタイプライターは、個人がデスクの上で行う活版活字印刷なのだ。この事実には今でもまだ強い感銘を僕は覚える。
(『Free & Easy』2004年12月号)
アドミラル社製の1952、3年頃の冷蔵庫と、1959年の冷蔵庫を比較してまず驚かされるのは、冷蔵庫の内部の容量の増大ぶりだ。5倍くらいにはなっているのではないか。その内部にぎっしりと詰め込むパッケージド・フードという工場製品も、単純な理屈で言えば5倍になったのであり、それはとりもなおさず、アメリカの人たちが夜となく昼となく食べて尽きることのない量の増加であり、その結果の肥満と病気の、これまた果てしない上昇カーヴだ。
(『Free & Easy』2005年1月号)
1973年の夏の終わり、カンザス州のカンザス・シティで、僕は竜巻を追いかける男と知り合った。高校生の頃、両親と一緒に住んでいた家が竜巻に巻き上げられ、粉みじんに砕け飛びながら消えていくのを、フォードのピックアップで逃げながら、至近距離に見た体験をしたという。逃げるより追いかけたほうがいい、というアメリカ的な逆転の発想により、彼は竜巻を追いかける人となった。そのための専用の車が、1964年モデルの赤いマスタングのクーペだ。
(『Free & Easy』2005年2月号)
トランス・ワールド航空(TWA)の「トランス」とは、それを越えて、そのさらに遠く向こうへ、といった意味だ。当時のTWAの路線図を見ると、ニューヨークから直行でパリとロンドン、そして乗換えでフランクフルト、チューリッヒ、ローマ、アテネ、テルアヴィヴと、ヨーロッパから中近東までを押さえていた。最新鋭の旅客機でさらに遠い彼方へと、アメリカは自らのために世界を拡大し続けた。世界に広がったアメリカ文化の力は、要するにすべてを押しのけ踏みつぶしながら前進する力であり、それは端的に言って軍事力そのものだ。
(『Free & Easy』2005年3月号)
ヨーロッパではドイツと、そして太平洋では日本と戦争をしていた頃、アメリカではいろんな種類の農作業専用車が作られた。大地を平らにし、邪魔なものをどかし、畑になるよう耕し、溝を掘ったり畝を作ったり、人がこなさなくてはいけない複雑で多様な作業は山ほどもある。それらすべてを機械化しようとしたのだ。多くの農作業車が縦横に活躍する農業国アメリカのイメージは、日本ではいまだに希薄なままだが、半世紀も前にアメリカはすでにこうだった。
(『Free & Easy』2005年4月号)
2024年11月15日 00:00 | 電子化計画