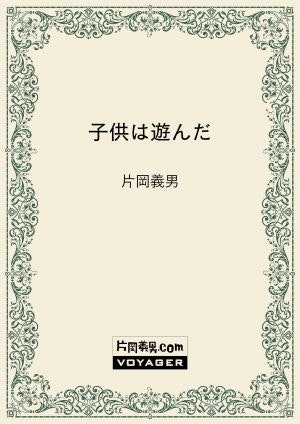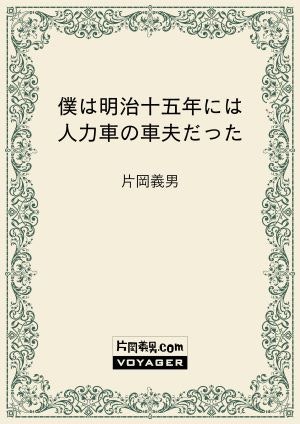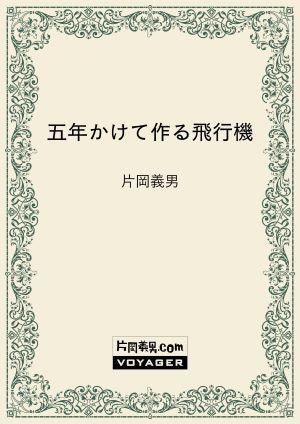エッセイ『坊やはこうして作家になる』より10作品を公開
エッセイ『坊やはこうして作家になる』(水魚書房/2000年)からの10作品を本日公開しました。
小学校の六年間を「自主的なお休みモード」で過ごした僕は、ひとり遊びのひとつとして、なんの用事も目的もなしに歩くのが大変に良い、ということを発見した。全く知らない隣町まで歩くと、自分の町とはずいぶん様子が違うことに驚いた。そこで自分がよく知っている風景をノートに絵で描いてみる。そして自分が描いた場所へ行ってみる。思い出しながら描いた自分の絵と、その絵の発生源になった現実とでは、ずいぶん違うのだ、という思いが僕の頭のなかに残る。そして自分は現実とは別の何かであると決めるよりも先に、現実とまっ正面から対立している存在である事実を、幼い僕は認識しなくてはいけなかった。
僕がまだ十歳になったかならないかの頃、記憶によれば真夏の日曜日の午後、たまたまかかっていたラジオで、僕はハワイ音楽の番組を聴いた。『ハワイ・コールズ』という番組であったことは、まず間違いない。放送していたのは当時の占領米軍だ。僕の気持ちを、ひときわ強くとらえた曲があった。演奏が終わると、そばにいた父親が「いまのはヒロ・マーチという曲だよ」と言った。初めて聴いてほとんど覚えてしまったほどに、僕はその曲を好きになった。『ヒロ・マーチ』は傑作曲だ。僕の好みとしては、『ヒッロ・マーチ』と書きたい。ハワイを音楽にしたらこうなるという、才能豊かな人たちによる実例が、ハワイの音楽のなかに充満している。
小田急線の電車に関する僕の最初の記憶は、二両連結であったということだ。やや押し黙った暗い印象のある、しかし堅実きわまりない働き者としての印象も併せ持った、あずき色の車体だった。さらに淡い記憶として、ドアは客が手で開けていた、という記憶がある。いつ頃のことですか、と訊かれても僕には答えようがない。高校生の頃には、学校へ電車でいくなら小田急線だった。今でも小田急でまず新宿なのだが、連結してある車両の数が増え、急行や準急が頻繁に走るようになり、車体の色が変わり、プラットフォームが長くなり、というような変化一切に関して、記憶はほとんどない。ロマンス・カーにはオルゴール電車と呼ばれた期間があり、納涼ビール電車と呼ばれたこともあった。ただの特急電車が、なぜ、どうして、ロマンスなのかという問いに、僕はまだ答えを得ていない。
四月の一日から六月の三十日まで、僕は会社に通勤した。初めのうちは起床の時間が一定していなかった。慣れてくるに従って起きる時間が定まっていった。結果として、月曜日から金曜日まで、毎朝、僕は同じ電車に乗るようになった。毎朝同じ人が、プラットフォームで僕の周辺に立つことに、やがて僕は気づいた。その中に女性がひとりいた。僕とほぼおなじ年齢だったと思う。彼女は四十年くらい前の時代における、会社勤めのお嬢さんの典型だった。きちんとしてきれいな、そして良く似合う服で統一して端正に着こなした、姿のいい、もの静かな普通の美人だった。興味を抱いたとか関心を持ったというところまではいかなかったが、毎日彼女を見ていてやがてわかったのは、服や靴、そして化粧や髪などに関する、彼女の好みないしは方針のありかただった。
ウーグ・クラフトというフランス人男性は、一八八二年、世界旅行の途中で、明治十五年の日本を訪れた。彼は、シャンパン財閥の長男だった。彼が五か月に及ぶ日本滞在と旅行について書いた文章を読んでいくと、現在の日本と直線でつながる部分がたくさんある。明治十五年も現在も、本質は同じなのだ。そして現在では、変わらぬ本質は捩じれるだけ捩じれていて、正常さへの復元はおそらく不可能だろう。当時の最新の写真術を、ウーグ・クラフトは習得していた。そしてこの五か月の日本滞在中に彼は日本を写真に撮った。明治十五年の日本の男たちは、たいへんいい。まず肉体的にたいそう精悍だ。そして自分たちのありかたに、いっさい無理がない。女性たちも男たちとおなじく、自分のありかたに無理がなく、誰もがじつにすんなりと自分自身だ。僕はふと思った。明治十五年の日本の男たちのなかに、僕によく似た人はいるだろうか。
父親がつきあっていた人たちのひとりに、相当に風変わりな男性がいた。実にきれいに晴れた初夏のある日、彼は「これから出かけるけれど、ついて来るかい」と、僕に言った。キャデラックで出かけるという彼に僕は同行した。町はずれの、とある一軒の家の広い内庭に入ると「ここで待っててくれ、すぐに戻ってくる」と言い残し、彼はどこかへ消えた。二時間以上たってから彼は戻り、車で家の外へ出た。家の前にはびっくりするほどに美しい大人の女性がいた。彼女を乗せてドライヴを楽しんだ帰路、彼は「運転してみるかい」と、僕に言った。運転するにはなにをどうすればいいのか、僕はすでに知っており、彼が右隣からコーチした。シートの縁にかろうじて尻の端を置き、僕はキャデラックを運転した。本物の自動車の操作感や、走っていく車体の動きの感覚、外を流れ去る風景、窓から入る風など、十歳の僕はいっきにキャデラックで体験した。あのきれいな女性の残り香が、その体験におまけのようについていた。
興味や関心の度合いを測る計器が僕の頭のなかにあるとすると、その計器盤の針が少しでも動いたものは、すべて三穴バインダーのリフィルに保管してある。切り抜いて貼ったり、要点を走り書きしたり、という方法による保管のしかただ。小説で使えるかなと思いつつ保管したものが多いような気がするが、実際にこの何冊ものバインダーの中に見つけたものを小説に使ったことは、僕の記憶では一度もない。ただとっておくだけなのだ。とっておき始めて、十七、八年になるだろうか。その中に、読者から届いた手紙の貼ってあるページがあった。二十二歳の女性が、なんの無理もなしに、いまの自分について書いている。いつ受け取った手紙なのか、記録してないから不明だ。どこの誰だったかも、わからない。手紙だけが貼ってある。
二十五歳のある日、ふと思いついた僕は、ゼロ歳から四歳まで住んだ家を、見にいった。四歳の春に引っ越しをして、それ以来のことだから、二十一年ぶりだった。幼い僕が体感として記憶した道順が、僕の体の中にまだ残っていた。一度も迷うことなく、いつも歩いている道を歩くのとまったくおなじに、幼い自分が住んでいた家の前に、僕は立つことが出来た。家はまだあった。戦前に建てられた木造二階建ての、きわめて平凡な一軒の民家だ。ゼロ歳から四歳までの自分が現実に住んだ家を見ながら、そして昔とそれほど変化していない周囲を歩きまわりながら、二十年以上前の自分をいまの自分のなかにはっきりと感じ、そのことについて思う、というのはいい体験だった。現実にかまけ、それしか見えていない状態に対して、自分自身の遠い過去は、均衡を図ったり回復したりしてくれる力として、いつも必ず、きちんと作用してくれるはずだ、と僕は考える。
ロッキードC–130という輸送機の胴体に、僕は手を触れたことがある。愛称はハーキュリーズという。途方もない力持ちの、誠実さをきわめた働き者、という印象を誰にもあたえる輸送機だ。このハーキュリーズが轟々と離陸していく様子を眺めるのは、僕のひときわ好きなことのひとつだ。気にいったプラモデルをときたま買うという、趣味とも言えないようなごく軽度の趣味が、僕にはある。買ったまま、ほとんどは組み立てない。そんなプラモデルが百点ほど手もとにあり、飛行機が多い。ロッキードC–130のプラモデルも、ある日のこと外国製のを見つけ、買ってしまった。僕のように、とにかくかたちが出来ればそれでいいという方針だと、作ろうと思えば短い時間で作れてしまう。C–130も簡単に作ることが出来るが、僕は一気に作ることをしなかった。少し作っただけで作業を中断させ、そのまま五年という時間が経過した。その理由を僕は五年ぶりに思い出した。
実は僕は英語のクロスワード・パズルが大好きだ。手もとにクロスワード・パズルがあると、僕はそれをかたっぱしから解いていくことだけに、時間を使いかねない。それは極めて純度の高い時間なのだと僕は考えている。僕の実感では、眠っているときよりも純度は高い。クロスワード・パズルはきわめてすぐれて人間のものだ、という考えも僕は持っている。人間は言葉によって生きる。言葉がなかったら、どうにもならない。だからいかなる抽象物でも、そしてどのような具体物であっても、それらにはすべて呼び名がある。この無数の名称を手がかりにして、人は世界を創造し、世界を認識し理解する。アルファベット二十六文字で人間世界のすべてを言いあらわすと同時に、そのすべてを認識し理解していくことの可能な言語、それが英語という言語だ。そして英語によるそのような世界理解の派生物のひとつが、クロスワード・パズルだ。
(以上10作品『坊やはこうして作家になる』(水魚書房/2000年))
2023年7月4日 00:00 | 電子化計画