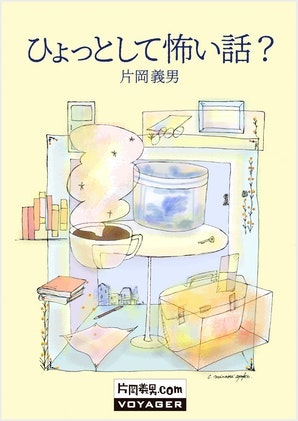短編9作品を公開!



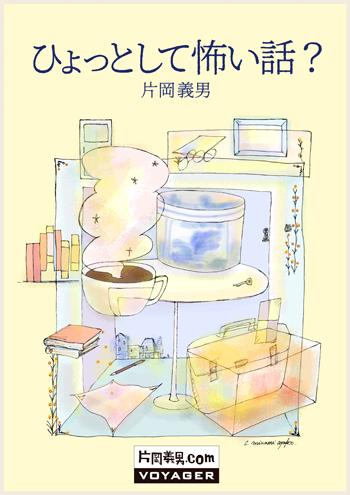
雑誌『NALU/ナルー』(エイ出版社)掲載の6作品、『群像』(講談社)掲載の連作短編3作品を本日公開いたしました。
・雑誌『NALU/ナルー』(エイ出版社/2008年)より6作品
片岡義男の小説には、この『黄色い水玉の八月』に登場するような、写真が撮れて、文章が上手くて、絵も描けるフリーランスの女性がしばしば登場します。いかにも小説の登場人物っぽい設定なのですが、出版業界に長くいると、そういう人に出会うことは、そう珍しいことではありません。しかも、そういう人は女性であることが多いように思います。そういう人は、どんな風に仕事をするのか、それをリアルに描写したのが、この短い物語です。これは文章書きでも絵描きでもそうですが、手を動かせば、イメージは形になって、形になれば、それをプロの仕事のクオリティで仕上げられるものだったりします。不思議だけれど、当たり前のように出来てしまうそれを、片岡義男は形として残そうとしているように見えます。
大学の芸術学部で写真を学び、現在四十代半ばの写真家である主人公が、学内のアルバイトとして水着写真のモデルを務めるシーンが、この『左右非対称の陽焼け』に出てきます。その報酬が「三十六枚撮りカラー・リヴァーサルフィルム二十本」というのが、当時の写真科の事情を伝えていて、とても印象的です。フィルムが無いと写真が撮れなかった時代、フィルム代は写真を志す学生にとって、カメラ以上に厳しい現実でした。ましてやカラーのリヴァーサルフィルムは、高価であり自分では現像が出来ないので、作品のためにしか購入できないものでした。彼女の左右非対称の陽焼けを強調する白い水着の写真がモノクロのプリントなのも、そういう事情の中でのリアルを感じさせる描写です。
テーマがあって、後は何でも良い、好きに書いて欲しいという依頼は、物書きの世界ではしばしばある依頼です。片岡義男の小説には、頻繁にそういう依頼仕事に何を書こうかと主人公が考えるシーンが出てくるのですが、そういう仕事は本当に沢山来るし、多分、片岡義男も随分とそういう依頼を受けたのだろうなと思うのです。2008年に『NALU』に掲載された、この一連の短い小説のシリーズは、そういう依頼について考える作家や写真家を描くことで、思い出というものの正体や、エッセイ的な依頼に対して、作家はどのように考えるのか、つまり、自分をどういう風にフィクションにしていくのかを書こうとしているのではないかと思うのです。体験を文字にするというのはどういう事かを考える、そのこと自体をフィクション化する作家という仕事についての小説とも言えるのかも知れません。
雑誌『NALU』掲載作品としては5作目の『ボックス・セット』では、依頼をテキパキとこなしていく画家が主人公です。その明快な仕事ぶりから、彼女の溢れるような才能が感じられる片岡義男の書きっぷりもまた見事です。2000文字に満たない物語の中に描き出される才能の眩しさは、同時に、描ける人とはそういうものであるという残酷な現実でもあり、それを書くのが片岡義男という作家の表現に対する敬意であり自負なのでしょう。その一方で、ハガキ大とはいえ、100枚の絵に対して彼女が受け取るのは1枚につき2000円、100枚でたったの20万円です。あっという間に描けるからこそ引き受けられる金額ですが、100枚書いても1ヶ月の生活費程度であるという、これもまたリアルなクリエイターの現実なのです。
この2009年に書かれた物語『九月一日のアイスキャンディ』の中には、2011年に発売された短編集「木曜日を左に曲がる」所収の『アイス・キャンディに西瓜そしてココア』に登場する挿話と同じ出来事が語られており、しかも、どちらも、過去の思い出についての物語で、登場人物の名前や背景もよく似ています。つまり、この小説を取り込む形で書かれたのが、『アイス・キャンディに西瓜そしてココア』ということなのでしょう。この物語の主人公・理恵子は、色褪せていくことを受け入れながら、あの夏はもう二度と来ないことに驚きます。悲しむのではなく、懐かしむのでもなく、それが事実であることに驚きます。その感覚を、もっと分かりやすく、もっと冷徹に捉えたのが、後者の物語。なので是非、併読をお勧めします。
実体験と作品の関係というのは、実際のところ、あるようなないような、というのが本当のところだと思うのです。体験したことでないとリアルに書けないというのなら、世の中に溢れるミステリやSFの傑作は、いったいどのように書かれたのか、ということになってしまいます。「想像できないようなことを書きたい」と言った作家もいます。モデルがいないと描けないという画家もいるし、モデルは要らないという画家もいます。『指先に海を』には、その答えが書かれているような気がします。海を具体的に体験していない作家が、海について書きたいと思った時に考えたのは、海を体験することではなくて、幼い頃、一度だけ指先で触った海を再確認しようということでした。必要なのは自分の中の海であって、実際の海ではないのです。
・雑誌『群像』(講談社/2016年)より3作品
物語は、書かれなければ、どんな可能性も含んでいます。だから、小説の構想中というのは、実際の執筆の孤独と対になるように、とても楽しい時間を孕んでいます。この『金曜日の幸せなグラッパ』は、そういう、頭の中で物語のタネを転がしている状態の楽しさを、そのまま小説に仕立てたような物語です。女性がバスに乗るのを見て、乗れば降りる、そこから物語は動くという不思議な理屈で、女性がバスを降りるのを見ます。それは楽しいに決まっています。この小説に登場する作家・北荻は、その楽しさも小説の材料になることも分かった上で、しかし、冷静にストーリーを組み立てています。この二重構造が、ラストの入れ子構造へと繋がる美しさは、平凡な物語であるはずがないのです。
事件性はなく、死因も亡くなった時の状況にも不審な点はなく、西野友美子というまだ若いフリーのライターは、彼女がかつて住んでいたアパートの敷地内で倒れて死んでいました。この物語は、彼女の友人3人が彼女について話すことで、彼女の不在がくっきりと浮かび上がるような、そういう構成で進むのですが、彼女のアパートの後始末を進めていたある日、思いもかけぬ出来事が起こります。といっても、その出来事自体は怪談的なものではなく、物語はミステリ的な展開を迎えます。実際、その事件が起こる伏線は張られているし、友美子がどうして当日深酒をしたのかなど、多くの謎が提示されます。しかし勿論、この小説はミステリではなく、謎は宙に浮いたままです。怖いことは何も起きていませんが、不気味な空気だけが空っぽの部屋に沈んでいるような、そんな感触の小説なのです。
『金曜日の幸せなグラッパ』『ひょっとして怖い話?』『スリープ・タイト』と続く、2016年に『群像』に掲載された連作短編は、それぞれが独立しながらも、実は、北荻夏彦が書いたひと続きの物語であったことが、この『スリープ・タイト』で分かる仕掛けになっています。その意味でも、この三作品は、『金曜日…』、『ひょっとして…』、『スリープ…』の順で読まれることをお勧めします。そうすることで『スリープ・タイト』のラストの一言が、本当に見事に効いてきます。ラストに向けて「せっかくの(中略)言葉だから、いま少し活躍してほしい」という北荻の言葉はまるで小説の真髄のように響くのに、その解答まで提示してもらえる、正に小説の書き方のような連作。贅沢な体験です。
2022年3月18日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ
次の記事へ