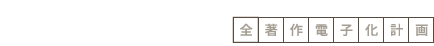連載エッセイ「先見日記」より10作品を公開
「先見日記」(「先見日記 Insight Diaries」)は、株式会社NTTデータのWebサイトにて2002年10月から2008年9月までの6年間にわたり、延べ16人の執筆者によって連載された日記形式のエッセイです。片岡義男は創刊時から2005年4月までの約2年半、毎週火曜日を担当しました。今回は2003年10月から2004年3月にかけて掲載されたもののうち、その後単行本等に転載されていない作品を公開します。
瀬戸内から東京へ戻ってきてほどなく、12歳の僕は立川の米軍基地で軍人として働いている日系2世の人のオフィスを訪ねた。デスクに向かって椅子にすわりその人は机の上の英語表記の大きな東京全図を見ていた。彼は「東京にはこんなに地下鉄があるのか」と言った。当時の東京では地下鉄の営業線は銀座線だけだった。だから「東京の地下鉄はひとつだけですよ」と僕は答えた。その人はかなり複雑な微笑を浮かべ、そこからさらに地図の上に向けて視線でたどり、「ユー・ジャスト・ドント・ノー・ヨシオ」と言った。
(『先見日記』NTTデータ/2003年10月14日掲載)
イラクの復興を支援するために、日本から自衛隊員が年内に派遣されることが確実となった。出発の当日、その現場へ、内閣総理大臣は見送りにあらわれるだろうか。来ない、と僕は予測している。なぜか。その理由は単純だ。もしイラクで自衛隊員に犠牲者が出たなら、隊員たちを送り出す儀式をしている首相の姿とその音声は、ことあるごとにTVで引用され、そのつどイメージの上でマイナスに作用するのは、わかりきったことだ。これを前もって回避しておくために、首相は見送りにあらわれない。
(『先見日記』NTTデータ/2003年11月11日掲載)
首相になって最初にアメリカを訪れたとき、キャンプ・デイヴィッドの山荘に招待された日本の首相は、爆撃機搭乗員が身につける革のジャンパーを大統領からプレゼントされた。首相はたいそう上機嫌でこのジャンパーをはおってみせた。このときに彼が発したひと言は「ジャスト・フィット」というものだった。次に首相の英語を僕が耳にしたのは、9・11のあとにアメリカを訪問した際、ホワイト・ハウスの庭でアジア向けに記者たちから取材を受けたときだった。記者たちに向けて我が首相は、Attack on one is attack on all.と言った。首相は見得を切っている、という印象を僕は持った。彼は見得を切るのが好きなのだ。
(『先見日記』NTTデータ/2003年12月16日掲載)
北朝鮮。韓国。中国。ロシア。アメリカ。そして日本。この6つの国が集まって開く会議が、6カ国協議と呼ばれている。主題は北朝鮮の核開発問題だ。この協議の第1回が昨年(2003年)に開催された。北朝鮮はこれはやらせではないかと思えるほどに、虚勢を張ってみせた。第2回目の協議は、そのうち始まるのか。北朝鮮が繰り出す駆け引きを、5カ国がそれぞれに受けとめて苦慮するのか。本当なのだろうか、と僕は思う。いまようやく、こんな段階なのか。まさか。そんなはずがあるわけない。
(『先見日記』NTTデータ/2004年1月6日掲載)
産油国という言葉のとおり、石油は特定のごく一部の地域にある。最も強い権力を持っているのは産油国なのだが、その産油国を自在にコントロールしている国は、単なる産油国よりもはるかに強い。石油をめぐる争いというクラシカルな争いは、今でも続いている。石油というエネルギーが偏在しているから、こういうことが起きる。偏在しないエネルギー、装置さえあればどこででも作り出すことの出来るエネルギーを世界中の人たちが持てるようになると、石油エネルギーが決定した世界権力の構造が、いったんは崩壊する。
(『先見日記』NTTデータ/2004年1月13日掲載)
両親の間に生まれた、ほかの誰でもないこの自分という人は、否定することが出来ない。したところで意味はない。今ここにいるこの自分を、自分そのものとして、すべて納得して全面的に引き受けていけるようになるためには、どう考えても他者という種類の存在が不可欠だ。男性の場合ならひとりの女性で充分なのではないか。彼が自分自身を引き受けていく過程のほぼすべてが、彼女との関係のなかにある。そしてこの過程は、最も一般的には恋愛だろう。
(『先見日記』NTTデータ/2004年1月20日掲載)
傷つく、という言い方が、極めて気楽に多用され始めたのは、いつ頃のことだったか。僕のおぼろげな記憶によるなら、それは1980年代の初めあたりだったようだ。いまは多少おさまっているような印象もある。毎日をなんとか生きていれば、苦楽は常に半々である、というのが標準ではないか。傷つくことが苦のなかに含まれるなら、それはすべて楽と表裏一体のものであり、傷の蓄積が自分の人生である、ということになる。そしてこれは、たいそうあたりまえのことでしかない。
(『先見日記』NTTデータ/2004年2月3日掲載)
冷戦はアメリカが長期公演した大芝居だと理解すると、それからあとのことがわかりやすくなる。旧ソ連はこの芝居に相手役として乗せられてしまった。それがソ連の犯したそもそもの失敗だった。これほどの失敗を侵したからには、ソ連は国家として無能だったと言っていい。冷戦は終わり、資本主義と自由が勝利したと言われたが、それを真に受ける人たちはさすがに多くはなかった。世界が抱えている問題は、なにひとつ解決はされなかった。さて、次はどうすればいいか、とアメリカは考えた。
(『先見日記』NTTデータ/2004年2月24日掲載)
外国の文化作品を日本語に翻訳する際、微妙なニュアンス、いわく言いがたい雰囲気や感触、文化的なあるいは歴史的な奥行きの共通認識、自明の理、冗談、語呂合わせ、裏の意味などは、なかなか翻訳しきれない難しいものである、ということになっている。翻訳によって失われたもの、それがロスト・イン・トランスレーションだ。その中でも決定的に失われ続けるのは、原文が持つ構文ではないか。ひとつひとつのセンテンスの組み立て。言葉と言葉のつながりかた。これが翻訳によって失われない、ということはまずあり得ない。
(『先見日記』NTTデータ/2004年3月2日掲載)
オウムとは日本そのものである、と多くの人が指摘してきた。オウムと日本は合わせ鏡であり、その鏡には戦後の日本が映っている、ということだが、これはなかなか自覚されにくい。オウムと日本との間に会社と政府を挟むとわかりやすくなる。会社はオウム、政府もオウム、だから日本という全体は、オウムという鏡にくっきりと映る。戦後の日本は経済絶対主義の企業社会主義だ。経済絶対主義を企業群が受け持ち、それに大きくよりかかった政府が、企業社会主義の国家を運営した。
(『先見日記』NTTデータ/2004年3月9日掲載)
2025年4月4日 00:00 | 電子化計画
次の記事へ