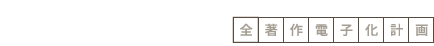「片岡義男のぼくのお気に入り道具たち」よりエッセイ10作品を公開
雑誌『BE-PAL』(小学館)に1983年から1985年にかけて連載された「片岡義男のぼくのお気に入り道具たち」からの10作品を本日公開いたしました。雑誌での連載終了後、1988年に刊行された『彼らと愉快に過ごす』の元となった連載ですが、書籍化の際には大幅に改稿されています。
秋と冬とのちょうど中間の季節、ぼくは標高2000メートルの山の南側の山裾にある、風情ゆたかな無人駅にやってきた。澄んだ空気のなかに静かに満ちている芳しい香りは、ぼくの思っていたとおりだった。下り列車から降りてきた彼女は、ヴィブラムのソールのついた8インチのブーツにマウンテン・パーカを着ていた。そのようないでたちを彼女がするとは思ってもみなかった。駅を出て、ぼくたちは山裾の道を歩きはじめた。歩きながら、彼女はパーカの下で肩にたすきがけしていたショルダー・バッグから、地図をとり出して見せてくれた。このとき彼女が肩にかけていたのとまったく同じショルダー・バッグが、いまぼくのライティング・デスクの脇にある。すっきりとしたデザインのもとに、いい材料を使ってしっかりとつくりあげたブレイディの〝ダヴ〟という呼び名のこのショルダー・バッグは、手にとってながめているだけでも、すがすがしい気持になってくる。
(『BE-PAL』1984年1月号掲載)
初冬の美しく晴れた日、東京からさほど遠くない場所の山裾を一緒に歩いた彼女には、絵を描く才能があった。その絵を見て、ぼくは、びっくりした。とびきりのいい絵だった。描こうとするものの輪郭を鉛筆で淡くおおざっぱに下描きし、水を含ませた筆に絵の具をつけ、パレットの上でほかの色と混ぜあわせ、思いきりのいい適確なストロークで、色をつけていく。ストロークごとの色が加わって、あっという間に1枚の完成したウォーター・カラーが出来あがっていくのを見るのは、ちょっとした魔法を目のあたりに見るのと、同じような気分だった。ウォーター・カラーは、たいへんにイギリス的なアートだ。曇天の日や小雨、あるいはミストの日が多く、風景のいろんな部分に静かに透明な光線が平均的にまわっていて、遠景になるにしたがってにじんだようにぼけた度合いが深くなるから、水彩画の技法でひろいあげるのにぴったりなのだ。日本にもこういう感じの日は多い。
(『BE-PAL』1984年2月号掲載)
12月から2月ごろにかけて、北太平洋のグレイ・ホエイル(こくじら)が、ベーリング海から南下してきて、カリフォルニア湾の海に向かう。体長40〜50フィートのこの巨大な鯨が南下していくとき、南カリフォルニアへ行けば雄大なホエイル・ウオッチングができるはずだ。大海を堂々と泳いでいく鯨は、ほんとうに素晴らしい。この鯨が、自分のペースで普通に泳いでいるときのスピードは、4ノットくらいだろうか。1頭の鯨を自分の鯨ときめ、双眼鏡で追っていくと、うまくいけば1時間近く、その鯨を双眼鏡ごしの視線でぴったりと追っていくことができる。たて続けに潮を吹きあげてダイヴするところを双眼鏡でたぐりよせてはっきりと見るのは、生き物のウオッチングとしては最高にスリリングだと言っていいのではないだろうか。円型の視界のなかの世界は巨大なリアリティと官能性とをたたえた、まさに現実の世界だった。
(『BE-PAL』1984年3月号掲載)
外房の海から歩いて15分ほどのところにある、すでに人の住まなくなった大きな農家に、ぼくはかつて1年ほどひとりで住んでいたことがある。持主から、ただ同然の安い料金で借りて、ひとりで住んだのだ。電気がとまっているわけだから、夜になってからの照明はロウソクだった。居間のように使っている部屋とか奥の寝室、広い土間には直径10センチの大きなロウソクを立て、テーブルや台のうえに置き、いつも同じ場所にある明かりとして使っていた。これとは別に小さなランタンをふたつ、ぼくは愛用していた。ロウソクを使うランタンだ。ふたつとも、山歩き用の道具を扱っている店へいくと、いまでも簡単に手に入る。ひとつは、ホープのチロル・ライトという名前でマーケットに出ている、もうひとつはアメリカ製のロウソク・ランタンで、燃えるにしたがってハウジング底部のコイル・スプリングの力によって上へ押しあげられてくるというしかけのランタンだ。
(『BE-PAL』1984年4月号掲載)
コーヒー・ショップを出た彼女は、すぐ近くにある、いきつけの写真用品店に寄りたい、と言った。彼女に写真を撮る趣味があるのだということを、ぼくはこのとき初めて知った。カメラは、マニュアルで撮ることを優先につくられた一眼レフだそうだ。天気のいい土曜日とか日曜日には、東京を起点に朝から汽車で2時間から3時間くらいまでのところへふらっと出かけていき、気持のおもむくままに歩いたりバスに乗ったりしながら、50から135ミリのズームレンズをつけたカメラで、写真を撮って回るのだそうだ。このようにして楽しみながら撮りためた写真を、夜、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間、スライド・ヴューアーでワン・カットずつながめては、楽しむのだ。思いがけないカット、何年も前のカット、懐かしいカット、すっかり忘れていたカットなどが、順不同でスライド・ヴューアーのなかに豆球の光をうしろから受けて、浮かびあがる。
(『BE-PAL』1984年6月号掲載)
毎年10月を過ぎる頃になると、明くる年のための手帳やスケジュール・ノートなどが書店などに並ぶ。ぼくは日記をつけないし、スケジュールというものは大嫌いだから、それを手帳に記入しておきいつも見ては確かめる、というようなこともやらない。しかしアメリカ、イギリス、西ドイツ、フランスなどの国から輸入したものは、店頭に並び始めるといつも興味を持って見る。そして、デザインの良さや質感が気に入ったりすると、何種類でも買ってしまう。買っても、実際に使うことは、まずない。買い込むたびに、このような手帳やダイアリーに、毎日びっしりとなにごとかを書きこんでいく人のことを、不思議な気持で思いおこす。とはいえ、一冊の手帳もなしに過ごすことは、やはりできないようだ。仕事の段取りを中心にして、そのスケジュールを書きとめておく手帳のようなものが一冊必要になってくる。
(『BE-PAL』1984年7月号掲載)
東京発のひかり号のグリーン車で、偶然女性の友人たちのうちのひとりに会った。いつも熱心に仕事をこなしており、ぼくと会ってもらえるのはひと月に1度くらいだ。仕事で神戸へ一泊の出張に出るのだという。仕事で新幹線に乗るときには隣のシートも買い、2人分の席にひとりで座って仕事をしたり本を読んだりしてひとりの時間を有効に使うのだという。1時間くらいなら隣に座ってもいいというお許しを頂いたぼくは、小1時間、つもる話を楽しく取り交わした。彼女のような素敵な女性が仕事で一泊とか二、三泊の出張に出るとき、バッグの中に何を入れていくのか、少しだけ興味がある。何が入っているのか見せてくれないかとぼくが提案したら、彼女は応じてくれた。このとき彼女のバッグのなかに入っていたもののうちのひとつが、ここに紹介するブラウン社製のトラヴェル・クロックだ。
(『BE-PAL』1984年8月号掲載)
リッズデイルが発売しているポートフォリオを、手に入れた。全体の形、雰囲気、質感、造り方などが気に入り、そそのかされて不覚にも買ってしまった。たいへんよく出来たポートフォリオだと、ぼくは思う。だが、ぼくにとって絶対不可欠のものではないし、これがなかったら非常に困るというようなものでもない。したがって、買ってから用途を考え出さなくてはいけなかった。まず、雑誌4冊にVHSのヴィデオ・カセット3本を入れても、さらにペーパーバックが4冊は楽に入る。厚さが一センチくらいの写真集を買ってから、ペーパーバックを4冊、できるだけ広いジャンルにわたるよう、選んでみたい。30センチLPを入れるには高さが3センチほど足りない。だから、円盤に対する執着はいまはやめておき、カセットを買おう。
(『BE-PAL』1984年9月号掲載)
ステージの上の高いストゥールに座り、12弦ギターを美しく抱え、白いフラット・ピックで弾きながら、自分の顔のすぐ前にあるマイクに向かって彼女は歌っていた。きれいなディクションの、すこしかすれ気味の歌声は、ストゥールの上の彼女の姿を眺めつつ聴いていると、相当に快適だった。知的なユーモアでひとしきり笑わせてから、また何曲か歌いますけど、リクエストはあるかしら、と怜悧な表情で客を見渡すと、客の男性のひとりが、ハーモニカを吹いてくれ、とリクエストした。ちょっとした拍手があがった。彼女は困ったように笑い、冗談じゃないわよ、ハーモニカっていったいなになの、そんなジャパニーズ・フード、私、食べたことないわ、と言って笑わせた。そして、やおら、スカートのポケットから、小さなハーモニカをとり出した。ホーナーのブルース・ハープだった。
(『BE-PAL』1984年11月号掲載)
デュラビームというブランド名の、自動小銃のバナナ弾倉のようなかたちをしたコンパクト・フラッシュライトには、数多くの人がなじんでいると思う。便利だし明るいので、ぼくもいくつか持っている。今回のこの小型ランプも、デュラセル社がデュラビームのブランドで出したものだ。安価で簡便ではあっても安っぽい感じはしないし、いかにもグッド・デザインでございという雰囲気ではなく、適当に気がきいている。性能はたいへんいい。部屋の中で使うための、デスクの上に置いておく愛すべき小物になってくれそうな気がする。単3乾電池2個に豆球ひとつのランプだと、暗くした部屋全体はほんのりと明るくなる程度だが、このほんのりと明るい状態はなかなか悪くない。もの思いにすこしだけふけってみたり、あるいは頭のなかをブランクにしてしまうために、このかわいらしいランプは、役に立つようだ。
(『BE-PAL」1984年12月号掲載)
2024年10月18日 00:00 | 電子化計画