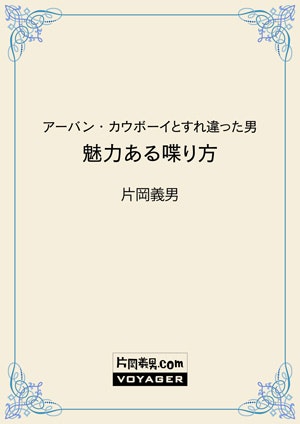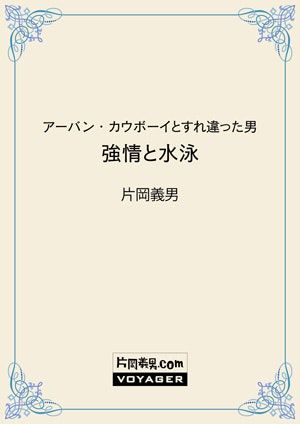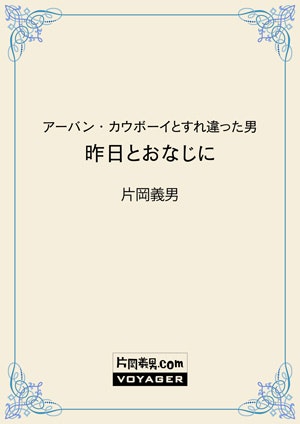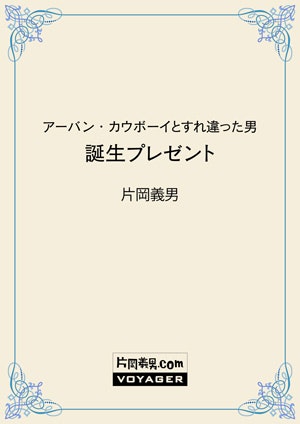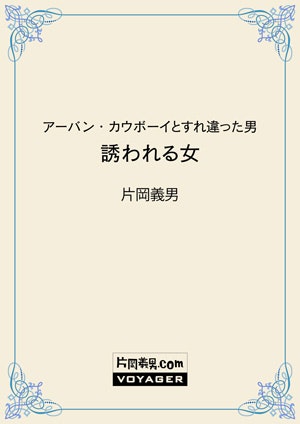エッセイ『アーバン・カウボーイとすれ違った男』から9作品を公開
エッセイ『アーバン・カウボーイとすれ違った男』(小学館『GORO』/1981年2月〜1982年5月まで連載)からの9作品を本日公開いたしました。
魅力的な喋り方というのは、男だけでなく、特に若い女性にとってはたいへんな財産になるとぼくは思うのだが、そんなことなど最初からまったく興味も関心もないような喋り方しかしない日本人女性が多いのは、どういうことだろうか。例えばアメリカへ行ってうれしく思うことのひとつは、女性の声が低いということだ。知的で教養があり、社会のなかに自分の足場をしっかり持って活躍している女性ほど、深みのある腹式呼吸の低い声で、ゆっくり、ていねいに、選びぬいた言葉をしっかりと組み立てて、喋っている。人がどんな言葉をどのように使うかということに関して、ぼくは大きな興味を持っている。喋り方も、その興味のなかの重要な一部分だ。
(『GORO』 1982年1月14日号掲載)
久しぶりにパチンコをやった。三年ぶりくらいだろうか。親友とふたりで入った巨大なパチンコ店の、自動販売機で、ぼくは五〇〇〇円札で、玉を五〇〇円分、買った。玉の入った容器を持って、パチンコ店の中をひとめぐりすると、昔とは明らかに変化していた。その変化が顕著に見えるのが、パチンコをする人たちだった。人々は、台の前のストゥールに腰かけて、じつに整然として、電動パチンコ台のノブをにぎり、釘の間を右に左にはねつつ落下していく玉を、視線で追いかけていた。
(『GORO』 1982年1月28日号掲載)
彼女は、水泳ができない。泳げるようになろうと思って何度も修得を試みたのだが、そのたびにごくあっさりと挫折し、いまだに泳げないままだと言う。「でも、まったく泳げないわけではないのよ。25メートルは、なんとか泳げるの」。25メートルならなんとか泳げるという状態は、全く泳げないに等しい。ぼくの個人的な実感によると、練習してもなかなか泳げるようにならない人は、強情で横着なのだ。「そう言われると、思い当たるわ」と、彼女は素直に言う。この素直さが、実はくせものなのだ。強情さは、それを指摘されるといまの彼女のようにあっさりと認めてしまう素直さや優しさのようなものによって、包まれている。
(『GORO』 1982年2月11日号掲載)
(「強情と水泳」の続きです)
ぼくたちはスポーツ・クラブのプールへ行った。25メートルは泳げると彼女は言っていたが、水に入ってくるときの動作や雰囲気だけ見ていても、少しも泳げないのだということは、すぐにわかった。体が全然水に浮かないのだ。2時間かけて、何とか体を水に浮かすことができるようにしてあげようとぼくは頑張ったが、駄目だった。頭では理解できても体がついていかなかった。素直な人なら、最初からすんなりと水に浮けるはずなのだが、頑固な都会派である彼女は、二時間かけても泳ぐことにかけては一切何の進歩もなかった。
(『GORO』 1982年2月25日号掲載)
日本の夏のように湿気が高く、気温が高い日には、犬はよくベロを出してハアハアと息をしている。犬が口の外に出しているベロの冷却効果に関して、ぼくは長い間疑問的興味を持ちつづけていた。そして数年前の、ある日。この日は日本列島が高気圧のなかにすっぽりとはまりこみ、日本の歴史始まって以来ではないかと思ってしまうほど狂ったようなビーカンの日だった。この日、ぼくは日本国内では最も気温が高くなった盆地をオートバイで走りながら、あの日の犬の、口の外にだらりと出したベロのことを思い出した。そしてオートバイで走りながら風の中に舌を出してみた。
(『GORO』 1982年3月11日号掲載)
ボールペンというものをぼくが最初に手にしたのは、七歳くらいのころだったと思う。書き味と、書ける線や文字の感じに不思議な感銘を覚えたのを、今でもうっすらと記憶している。仕掛けがどうなっているのかということに関して強い興味を持つ子供だったぼくは、初めて手にしたそのボールペンを分解してみた。ボールポイントのボールは、小さくて実に可憐だった。人間は人間のために相当に不思議なものを作り出すのだなという、感銘に似た気分をぼくは楽しんだ。このときの体験が何らかの形で尾を引いているのかどうか、新しいボールペンを見ると、ほぼ必ず買ってきて、使ってみるという時期があった。
(『GORO』 1982年3月25日号掲載)
ぼくの寝室の壁のてっぺんから天井まではガラス張りの天窓だ。ある日、窓から風が吹きこんできた。春の風だ。冷たさがほんのりと残っているが、肌に触れるときの感触や香りは、春のものだ。この寝室は、北側をのぞく三つの壁に窓がある。真冬の、ごく寒いときでないかぎり、窓は開けたままだ。子供の時からの癖で、風を感じつつ眠る心地よさを知ってしまうと、窓を閉じて眠ることなんて、とうていできない。起き出してシャワーを浴び、朝食を済ませ、届いた郵便物をバルコニーで読んだ。そして何通かに返事を書いたら、ウサギとともに昼食だ。
(『GORO』 1982年4月8日号掲載)
東京駅の八重洲口側を歩いていたら、かつて一緒に酒を飲んだり話したりした友人の女性にばったり会った。忙しく仕事をしていて、来週は神戸へ出張しなくてはならず、いまから新幹線の切符を買いにいくところだと、彼女は言った。
「いいことを思いついた」
「なにかしら」
「ぼくの切符も、買っておいてくれ」
3日後、西に向かう新幹線の座席に、ぼくと彼女は隣合わせに座った。グリーン車の座席に体を預け、らちもない話をするのは実に快適だった。ぼくたちは「巡ってくるだけで十分に幸せだ」という彼女の誕生日のプレゼントについて、アイデアを出し合った。
(『GORO』 1982年4月22日号掲載)
金曜日の午後、ぼくは人の群れの中をひとりで街を歩いていた。斜め後ろから、名前を呼ばれたような気が、ふと、した。振り返ってみたのだが、知っている人の顔がみつかったりはしなかった。顔を正面に向け直し、たくさんの人の中を縫うように歩いていくと、すぐうしろから呼ばれた。ぼくは、振り返った。……街でこんなふうにばったりと会ったりすると、4か月ぶりでもかなり久しぶりだという気持になってくる。彼女は、ぼくと違って忙しく仕事をしている。今日は昼で仕事を終え、午後の時間はゆっくり街を歩くことにあてたのだそうだ。しかし、ひとりでゆっくり歩いていると、いっしょに遊びませんかとか、とにかく片っ端から誘われてしまうので、心ならずも忙しそうに急ぎ足で歩いていたのだ。そんなとき、暇人のぼくにばったり会えて、ああ、よかった、とこういうわけだ。
(『GORO』 1982年5月13日号掲載)
2023年4月25日 00:00 | 電子化計画