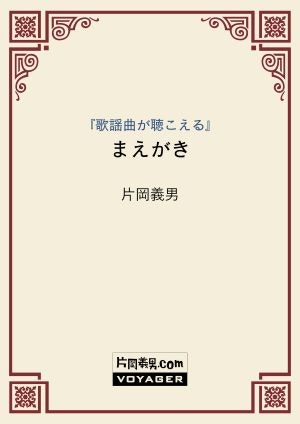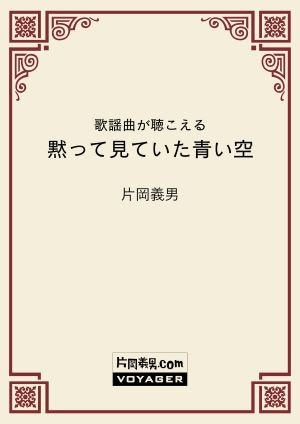音楽エッセイ『歌謡曲が聴こえる』13作品を公開
音楽エッセイ『歌謡曲が聴こえる』(新潮新書/2014年)所収の13作品を本日公開いたしました。
1944年のおそらく10月の後半に、幼かった僕は東京から岩国へ疎開した。岩国も充分に危険だったが、アメリカ軍の空爆から、東京にいるよりは遠くなるはずだ、と両親は希望的に思ったのだろう。次の年の夏、広島の方向の空に立ったキノコ雲を見て、僕は物心がついた。岩国には7年ほどいた。その7年間のなかで僕にとって、もっとも謎に満ちていたのは、そしていまも謎であるのは、とにかく四六時中、歌謡曲が聴こえていたことだ。あれほどまでに次々と、数多くの歌謡曲を受けとめた人々とその日常とはなにだったのか、という謎は解けないままだ。
1962年、大学の4年生だった僕は夏を千葉県の館山で過ごした。館山の海の近くに大学の寮があり、そのすぐ隣の旅館に夏の客として逗留しようと友人に誘われた。当時、学生たちは大学4年の春から就職活動を始めていた。就職って、なんだ。というのが僕の状態だったが、別な友人の助けを得て、9月の終わりには僕の就職先が見つかった。
館山から帰る日は、館山港あるいは金谷港から小さなフェリーに乗り、竹芝桟橋で埠頭に上がると、女性の声による歌謡曲が聴こえた。再生されているレコードではなく、生き身の女性が現実に歌っている声だった。こまどり姉妹のものだ、とやがて僕にもわかった。美しい着物をまとって強風のなかで歌うおなじようなふたりは、この世ならざる美しさをたたえた異星からの来訪者のように見えた。
『ソーラン渡り鳥』(こまどり姉妹)
歌謡曲全集で『カチューシャの唄』の譜面を最初に読んだとき、この歌は母親がしばしば歌っていたものだ、という発見をした。オリジナル歌手による7インチ盤が見つからないかわりに、まったく別な歌手によるカヴァーが手に入る、という体験のいちばん最初が、僕の場合はこれだった。カヴァー、という新たなジャンルの発見だ。ヒット歌謡曲全集に収録されたいくつもの譜面、そして気に入った歌があればレコード店で買った7インチ盤の数々で、僕は戦後の歌謡曲を知り直していった。戦後すぐのまだ子供だった頃、街を歩けば、そして自宅にいても、当時のさまざまなヒット歌謡曲が、ほとんど常に耳に届いていたという記憶がある。街をいく人々に向けて歌謡曲を放っていたのは、街では広告塔とラジオ店だった。そして自宅では、どの部屋にもあったラジオの放送だった。
『カチューシャの唄』(フランク永井)
『青春のパラダイス』(岡晴夫)
1945年、10月11日の日本で戦後の日本映画の第一号である『そよかぜ』という娯楽映画が公開された。8月15日から、まだふた月たっていなかった頃で、観客の反応は思わしいものではなかったようだ。新聞では酷評されもした。あってなきがごとき作品であるこの映画を、僕は十数年前にヴィデオで観た。主題歌は『リンゴの唄』で、主演の並木路子が主題歌を劇中で歌った。当時小学校1年生だった僕は、自宅のなかで、そして外で何度となく聴いた。自宅ではラジオだ。奇妙な歌だ、と思った小学校低学年の自分が、いまでも自分のなかにはっきりと蘇る。どこがどのように奇妙だったか。けっして明るくはない歌だ、あるいは、悲しい歌だ、と思った記憶もある。聴けば聴くほど、この思いは増幅されて自分のなかに強く残った。
『リンゴの唄』(並木路子、霧島 昇)
『カチューシャ』(森繫久彌)
歌謡曲にとってはなぜか恋が最大の主題であり、いろんなかたちと内容の恋があるとして、僕が見るところではほぼ4つの類型に分けることが出来る。かなえられそうな気配の恋。どうやらかなえられそうにない恋。やはりかなえられなかった恋。かなえられることのなかった恋への未練。この4つだ。二葉あき子の歌で昭和21年にヒットした『別れても』という歌は、かなえられることのなかった恋への未練の歌として、もっともわかりやすい一例だ。田端義夫の『かえり船』も、同じ類型のなかに入るものだ、と僕は判断している。ひとつの歌によって、或いはいくつかの歌によって、ひとまとめにされた思い出は、初めのうちはくっきりとした姿を持ち、どこからどう見てもその人にとっては共感そのものなのだが、時間は容赦なく経過していく。時間の経過につれて思い出は遠のく。しかしあの歌を聴けば、あるいは記憶しているかぎりを心のなかで歌えば、思い出はほんのいっときにせよ、輪郭のめりはりを少しは取り戻す。
『黒いパイプ』(近江俊郎、二葉あき子)
『悲しき竹笛』(奈良光枝、近江俊郎)
ナンシー梅木という名前はジャズ歌手としての芸名で、本名は梅木美代志という。1929年の生まれだ。太平洋戦争に日本が大敗した年に彼女は16歳だったから、感受性の形成期の少なくとも前半は、戦前そして戦中だった。1953年、『サヨナラ』という歌がヒットした。ごく普通の人たちの日常生活のなかにもジャズが入り込むほどに、ジャズはこの頃の日本で盛んだった。ナンシー梅木はジャズ・ソングとポピュラー・ソングを歌う歌手として、日本だけでなく日本のなかのアメリカでも、高い人気を獲得した。1955年、アメリカに移ったナンシー梅木は、本名のミヨシ・ウメキに戻った。そしてハリウッド映画『サヨナラ』(1957)でカツミという日本女性を演じ、その年のアカデミー助演女優賞を獲得した。歌の才能は当然のこととして、容姿と演技のチャーミングな様子にさらに加えるなにものかは、自身の中から見つけ出さなくてはいけなかった。そしてそれは、かすかにではあったが確実に存在した、オリエンタルのアクセントだった、と僕は推測する。
『アイム・ウェイティング・フォ・ユー』(ナンシー梅木)
『時計のささやき』(ナンシー梅木)
『青春歌年鑑』という歌謡曲のアンソロジーCDで、昭和22年のヒット曲13曲をいま聴きとおして、昭和22年が僕の内部によみがえるかというと、それは無理だ。どの歌も、当時の社会と直接に体を触れ合わせて生きる毎日のなかでの、忘れがたい思い出には、とうていなってはいないのだから。歌謡曲全集の譜面でほとんど新たに発見し、7インチ盤のレコードを買っては聴いた、という思い出しかない。歌謡曲と結びついた思い出としては、存分に抽象的だと僕は思う。レコードの他に、僕にとって歌謡曲の思い出はテナー・サックスの教材というかたちをとる。「広瀬正とスカイトーンズ」というビッグ・バンドを率いた広瀬正さんは、長編小説『マイナス・ゼロ』で作家となる以前は、自動車の模型ビルダーや雑誌のライターとしても活動していた。1960年代のなかばから後半にかけてのことだ。その頃、20歳近く年下の僕に、彼はテナー・サックスの基本を手ほどきしてくれた。彼から数多くあたえられた教材のなかに、歌謡曲もあった。
『長崎エレジー』(ディック・ミネ、藤原千多歌)
『山小舎の灯』(近江俊郎)
2013年4月25日に、田端義夫はこの世を去った。享年94だった。1954年、公演で大阪にいた田端義夫は、それまで使ってきたギターをなくした。その数日前、田端は銀座のヤマハで見て気になっていた、アメリカ製の電気ギターを急いで購入した。59年にわたって、田端はこのギターを愛用した。どこで歌おうとも、そして練習のときにも、彼はこのギターを胸に抱えた。右胸を越えて右肩に近い位置までこのギターを抱え上げる田端のスタイルは、歌手・田端義夫のデザイン全体のなかで、見る人の注目を特別に集めるものだ。ギターの位置は弾きかたそのものだと言っていい。そして公演の会場、その舞台、伴奏のバンド、照明、そして歌う自分と電気ギター、というふうに道具立てを総動員することによって、田端義夫の歌つまり悲しみは、観客が受け取りやすい次元にまで中和された。
『島育ち』(田端義夫)
『かえり船』(田端義夫)
1962年、大学の4年生だった僕は、9月の初めに『全音歌謡曲全集』の最初の1冊を高田馬場の書店で買った。その全集の新刊が書店の棚にならぶごとに、僕はそれを買い、半年から1年遅れほどで、当時の日本の歌謡曲を全集の譜面と7インチ盤のレコードによって、追いかけることになった。新刊と並行して、すでに刊行されているものも、1冊また1冊と、こちらは過去に向けて、買っていった。また、ヒット歌謡曲全集、というようなタイトルの全集も刊行されており、第1巻から手に入れて譜面と歌詞を読んでいくと、戦前からのヒット歌謡曲を、時代順におさらいすることが出来た。以上のような3とおりのアプローチで、僕は歌謡曲との接触を持ち始めた。接触とは言っても、譜面は歌の外枠だけがそこにあるのだから、きわめて抽象的な存在だ。レコード店で手に入れたばかりの7インチ盤を何枚か、全集とともに持ち、たとえば昼間に喫茶店に入ると、顔なじみのウェイトレスが目ざとく7インチ盤に目をとめ、品定めをした。「これ、いまかけていい?」と彼女が言えば、店の再生装置でその7インチ盤は再生された。
『霧笛が俺を呼んでいる』(赤木圭一郎)
『なみだ恋』(八代亜紀)
1965年の『フランク永井ゴールデン・シリーズ』という2枚組LPや、1966年の『魅惑の低音 フランク永井ベスト・ヒット』など、彼のLPには火のついた煙草を指ではさんでいる写真がいくつかある。1950年代から70年代のなかばあたりまで、日本の大人たちは盛大に煙草を喫った。ただ単に喫うだけではなく、煙草の喫いかたの上手な人は、いまの言葉で言うところの、お洒落な人とされた。フランク永井の煙草は絶対に洋モクだと僕は思う。1963年にはアメリカのステュードベイカーという自動車に乗っていた人だ。彼のレコード・デビューとなった最初のシングルは、1955年の『恋人よ我に帰れ』というアメリカのジャズないしはポピュラー・ソングだった。そして最後の録音となったのは、1985年の『あなたのすべてを/まわり道』というシングルだった。活動歴30年の最初の少なくとも20年間は、戦後日本の煙草の時代と重なっている。
『有楽町で逢いましょう』(フランク永井)
『恋人よ我に帰れ』(フランク永井)
ジャズのピアニストとして、ビッグ・バンドのリーダーとして、アメリカで活動を続けて来た穐吉(秋吉)敏子に『ジャズと生きる』(岩波新書 1996年)という著作がある。2、3年前に読んだ僕は、ひとつのアイディアを思いついた。秋吉敏子のLPやCDを可能なかぎり買い集め、もっとも最近のものから年代順に過去に向けてひとつずつ、自宅で再生しては聴いていく、というアイディアだ。当時もっとも新しい作品だった『秋吉敏子ソロ・ライブ2004』というCDから僕は聴き始め、何枚ものLPやCDを秋吉敏子の過去に向けて聴いていった。1963年に東京で録音されLPで発売された『トシコ・マリアーノ 魅惑のジャズ』の中には歌謡曲がひとつだけある。吉田正が作曲し佐伯孝夫が作詞して松尾和子が1960年にレコードにした『再会』という歌だ。『松尾和子 ステレオ・ハイライト』のA面の1曲目である『再会』を聴き始めたとたん、このLPが1960年代の東京では、喫茶店やバーの必需品だった事実を思い出した。
『再会』(トシコ・マリアーノ)
『再会』(松尾和子)
美空ひばりは1937年の生まれだから、僕より2歳だけ年上だ。1937年の7月には日中戦争を日本は始めた。戦中、幼い彼女は歌で軍隊の慰問活動をおこなったという。しかし彼女は戦前や戦中の人ではなく、戦後の人だ。戦後の始まりは美空ひばりの始まりでもあった。『港町十三番地』は美空ひばりが歌ったオリジナルのなかで、僕がもっとも好いているものだ。作詞と作曲の素晴らしさに編曲が見事に仕上げをほどこし、それを20歳のひばりが、良い歌そのものとして歌いきっている。美空ひばりの歌を美空ひばりの歌たらしめるための技術的ないくつかの工夫が、まだほとんどないと言っていい最小限の様子に、僕はレコードを再生しては聴く人としての至福を、聴くたびに感じる。世間知らずであるがゆえに、なんの屈託もなしにまっすぐ、あっけらかんと明るいこの歌の主人公たちを、ひばりの歌は完璧に体現している。『蘇州夜曲』は全音の歌謡曲全集の譜面と歌詞で、大学生だった僕が知った歌だ。
『港町十三番地』(美空ひばり)
『蘇州夜曲』(美空ひばり)
和田弘とマヒナ・スターズの『菊千代と申します』という歌を僕が知ったのは、ピンク・マティーニというアメリカのグループが、本拠地であるオレゴン州ポートランドので行ったコンサートを記録した、2009年のDVDによってだった。なんという美しい歌であることか、と僕は思った。このときには、『菊千代と申します』がマヒナ・スターズのレパートリーだったことを、僕はまだ知らずにいた。続いて『ア・レトロスペクティヴ』という題名の、ピンク・マティーニのCDを僕は手に入れた。このCDに収録された21曲のなかに、『菊千代と申します』があるではないか。「ザ・ヒロシ・ワダ・ミックス」と副題がついている。和田弘のスティール・ギターが前面にあり、その背後のかなり遠のいた位置にクレディットされているだけで八名の、歌と演奏がある。東京で和田弘のスティール・ギター演奏を録音し、ポートランドで背景の歌と演奏を録音して重ねたのだろう。素晴らしい出来ばえだ。美しいメロディを自分のスティール・ギターでさらに美しくする、という和田弘の方針の最終的な到達点と言うべきものだ、と僕は思う。
『男ならやってみな』(和田弘とマヒナスターズ)
『菊千代と申します』(和田弘とマヒナスターズ)
『菊千代と申します』(Pink Martini)
2023年8月29日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ