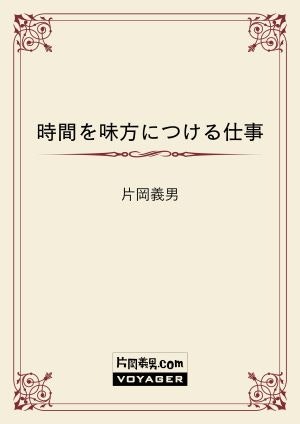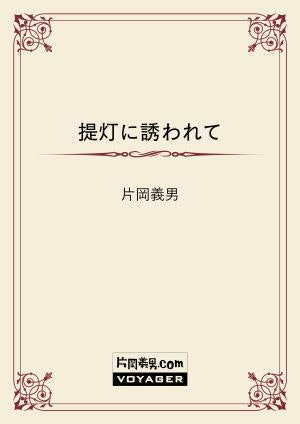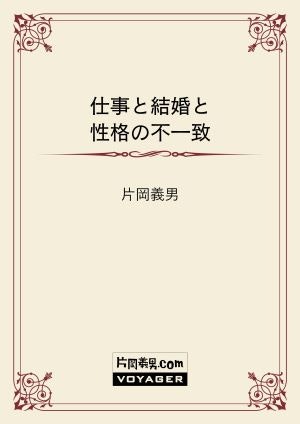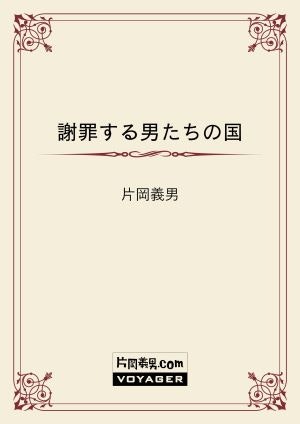『自分と自分以外──戦後60年と今』より15作品を公開
『自分と自分以外──戦後60年と今』(NHK出版/2004年)からの15作品を本日公開しました。
セメダインと出会ったのがいつだったか、正確なことは書けないが、戦後まだ間もなく、子供向けの科学雑誌に掲載されていた広告で知った。なんでもよくつくセメダイン、といったコピーが添えられてあったような気がする。広く一般的に市販される小さな物品のなかで、セメダインを越える強さや大きさの感銘をうけたものは、ほぼ同時期に「バンドエイド」と「スコッチテープ」があるだけだ。このふたつは当時のアメリカの製品だった。そのなかで、セメダインだけが日本製であることも僕が受けた感銘に寄与している。セメダインから受けた決定的な影響とはなにですか、と訊かれると答えに困るが、セメダイン以前と以後とのあいだには明確な一本の線があり、その事実をいまに至っても鮮やかに自覚している。
作家がもの作りの営みであることは確かだ。そしてもの作りというなら、作家という営みはもの作りの原点のひとつだと言っていい。ではどのようにそれは原点なのか。自分の仕事デスクを作家の製造現場だとしよう。そこへ注文が入る。内容と納期を聞きながら検討する。注文されているものが自分に製造可能だと判断したら、その注文を受ける。在庫はない。どんな注文がいつ入るのか、まったく予測はつかない。製造現場には常に作家ひとりしかいない。すべてをひとりでおこなう。これは典型的なセル生産だ。作家によるもの作りは、多品種少量生産をつきつめた、多品種一点生産という、理想的に純粋なかたちでもある。
五歳の僕といまの僕とが、どのように隔たっているのかとなると、僕自身にもよくはわからない。が、つながりならひとつくらい、わかってもいいような気がする。五歳の頃の僕といまの僕とをつなぐ、当時もいまもなんら変わらないもの……。もっともわかりやすいのは、かたちあるもの、たとえば指紋や耳たぶだろう。これらはまぎれもなくかたちだ。かたちを持たないもので変わらないものを探すと、性格や気質が浮かび上がってくる。東京の光景を写真に撮っているときなど、空間とそこにある物体の、視線によるとらえかたが、五歳のときといまとで、まるでおなじなのだ。
会社に勤めるのをやめると、次の日から自分はどんな状態になるか。これを僕が知ったのは、二十代まだ前半の、ある夏の日のことだった。自分には自由があるのかどうか、それすらよくわからないほどに、自分は自由になる。完璧なまでに不定型だった当時の自分にとって、もっとも頼りになったのは、結局のところ、この身体性というものだった。なぜそれがそれほど頼りになったかというと、それは時間というものと常に接触しているからだ。時間は経過していく。逆らうことは出来ない。無視することは可能でも、そう長くは続かない。時間を止めることも、逆に進行させることも出来ない。目の前の仕事を時間内に終わらせること。これは小さいけれどもきわめてリアルな目標だ。
学生さんとは、大学生のことだ。僕が馬鹿な大学生だった一九六〇年代の前半には、日常的なごく普通のこととして、人々から学生さんと呼ばれていた。ただの大学生を、なぜさんづけで呼んだのか。若い人たちが大学へ進学することに対して、社会全体が大きな期待を寄せていたからだ。しかしそのような時代は急速に終わった。僕が大学生となった頃は、進学率は十人にひとりだった。一九六〇年代の後半から一九七〇年代にかけて、十人のうち三人までが大学へ進むようになると、大学生という存在に特別の価値はなくなる。このプロセスと並行して進んだのは、経済の拡大と成長による、企業立国としての日本の発展だ。
スパムというのは商品名だ。豚肉を細かくつぶしたようにして加熱し、調味料を加えて缶詰としたものだ。横置き長方形の缶は、僕がまだ幼かった頃にあったのとおなじだ。味も変わっていない、と僕は思う。横に三枚に切ったものを、ほどよく色がつくまで炒める。そして皿に取る。スパムのもっとも正しい料理法はこれだ。白いご飯と完璧に調和する。スパムの缶を目にするたびに、愛想もなにもつき果てたような表情となり、ゆっくり首を左右に振りながら「ノー」とつぶやくのは、僕が記憶している日系二世だった父親の癖のひとつだ。スパムがたまに食卓に出てもけっして手をつけない彼に、なぜそんなにスパムが嫌いなのかと僕が訊いたら……。
ある日あるとき、庭に一匹の雌猫があらわれた。どこかの庭猫だったのではないか。人になぞらえると三十代のなかばあたりか。姿の良い、賢く鋭そうな顔をした、ものに動じることのない、よく心得た猫だった。庭の向こうの片側にこの猫がすわっていることに、コーヒーを飲みながら僕は気づいた。猫のほうでも僕の存在を認識した。そしてその認識は一瞬のうちに完了し、自分は今日からこの庭にいることにしよう、とその猫はきめたのだと、いまでも僕は思っている。僕と猫とのあいだに、おたがいの存在を全面的に認め合う了解のようなものが、そのときのその一瞬のなかで成立したからだ。
生食用、という言いかたを目にしたときには、かなりの違和感を僕は持った。それ以前の生ものとなると、以前からそう言われてきたことがごくあたりまえのもの、たとえば生ビール、生中継、生牡蠣、生菓子、生節などいろいろあるし、食べられなくてもいいなら、生欠伸、生半可、生兵法、生爪、生返事、生唾など、生のひと文字がまさに生きている言いかたが、多彩にある。食べるものであってもなくても、なんらかの状態を言いあらわすための、直截にそして端的にその感触を伝えることの出来る一語として、生という言葉は、日本語による生活にとって、相当に重要なものだったと僕は思う。魚介類を生で食べる習慣と、それはかならずやどこかで結びついているのだろう、とも思う。
僕が子供だった頃から青年期の終わりにかけて、街の映画館のほとんどは、上映されていないときのスクリーンには幕が降ろされていた。上映時間が来るとブザーが鳴り、照明が暗くなっていくのと合わせて、スクリーンを隠していた幕が、上に上がり左右へと開いた。いまでもこんな映画館はあるのだろうか。スクリーンが常にその姿を観客席に見せている映画館が多いような気がする。どちらでもいっこうに構わないのだが、スクリーンが観客席と向き合って常にあらわだと、上映されているとき以外の時間に視線がそれにとまるたびに、スクリーンとは異様なものだ、という思いが頭のなかを走り抜ける。
東京には提灯がたいへんに多い。縦長の楕円形をした赤い色の提灯が、東京におそらく万単位で下がる提灯の、原器とも言うべき基本形だ。東京の夜の薄闇に赤提灯が灯るなら、そこには酒とそれにふさわしい食べ物がある。そしてその過去に向けてさかのぼるなら、さほど遠いとも言えない江戸に、ただちにたどり着く。東京に数多く灯る赤い提灯は、江戸の思い出だ。この赤い提灯が、じつにフォトジェニックなのだ。写真集を作るとき、提灯のある光景は欠かせない。写真集のなかの光景ぜんたいに対して、それらを地につなぎとめる錨のように機能する。
食べるものその他、いろんなものを買って人は日々を生きていく。不足なく買うためには、自分で不足なく稼がなければならない。そして、稼ぐためには仕事をするのだけれども、これまでのようなことではどうにもならない。僕が話を聞いた彼女たちは、いまのところ結婚を望んでいない。その理由はきわめて端的だ。どこかのサラリーマンにとってのうちのかみさんとなり、そのことをとおしてこれからの日本にさらに深く巻き込まれても、そのことのなかに自分にとっての利益そして幸福はまったく期待出来ないからだ。
僕が大学生となった一九六〇年の日本では、大学への進学率は十人にひとりだった。私立大学の文科系というまったくの無風状態のなかで、モラトリアムのはしりとしての四年間を僕は過ごした。駅からの商店街は通学路でもあった。学生たちを主たる顧客とした賑わいは、ただごとではなかった。日本社会は経済的な激変と拡大のただなかにあった。学生街に活気があったのは当然だろう。この時代の大学を卒業してから、四捨五入して半世紀ぶりに、駅から大学まで、そして大学の周辺を、僕は歩いた。雑誌に東京の写真を連載していて、その最終回のための写真を撮るために、卒業後初めての母校再訪を思いついたからだ。あらゆる場所の、変わりようのすさまじさに、僕は驚いた。
社会全体と言っていいほどの圧倒的多数の人たちが先を争って買い、使った人たちは大満足して喜び気持ちが高まる、というような製品が次々に登場し、企業の収益は上昇して個人の所得は増えて消費は活況そのもので、人々は生活の向上を実感し謳歌する。このような状態を好景気と呼ぶ。好景気の状態は、日本にとっては、いつか来た道という過去の体験、つまりもはや思い出という領域に属するものだ。社会全体を機能させてきたシステムのすべてと、その基本原理のすべてが、効用の期限切れとなったのだ。その現状をわかりやすくとらえる数字のひとつが、年間で五十兆円の供給過剰という数字だ。
自分たちの会社が犯した、社会的な犯罪と言っていい失策や判断の誤り、対応や対策の不備などについて、男たちが通り一遍な言葉で謝罪する。そして揃って椅子から立ち上がり、記者たちに向かっておじぎをする。いまの日本で企業がひっきりなしに起こす不祥事の、いちばん表向きの後始末の風景だ。新聞に掲載されたこの風景の写真を僕は切り抜いてとってある。その一年分を観察してみた。どの写真のなかでも、会社の男たちが頭を下げている。その男たちのかもし出す雰囲気、顔つきや態度、人品骨柄などの、揃いも揃ってなんと言う貧相さであることか。これがいまの日本なのだ。テーブルに広げた切り抜き写真を見渡して、僕はつくづくそう思う。
イラクに対しておこなった戦争とその後の対応をめぐって、いまのアメリカの大統領(注:ジョージ・W・ブッシュ)は国際社会での信用を大きく失いつつある。アメリカ国内でも大統領への支持は低下しつつある、と日本の報道では伝えられている。レーガン大統領の時代から現在までずっと、アメリカは保守陣営が運営する国へと、大きく傾き続けてきた。先代のブッシュ政権は明らかにリベラル寄りの保守だったし、クリントン政権は戦略として保守に傾いたリベラルだった。そのあいだ保守陣営は力を拡大し続け、現政権でいっきに限界を突破したのではないか、と僕は思う。今度の大統領選挙では、投票の結果をめぐって保守の側はなにをやるかわからないというところまで、保守の価値観や世界観がアメリカのシステムとなっている。
2023年8月8日 00:00 | 電子化計画