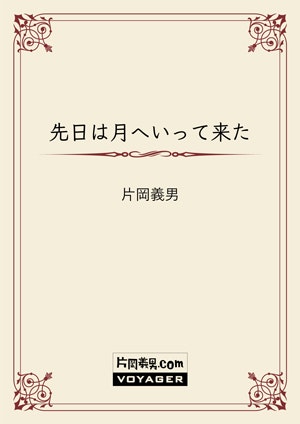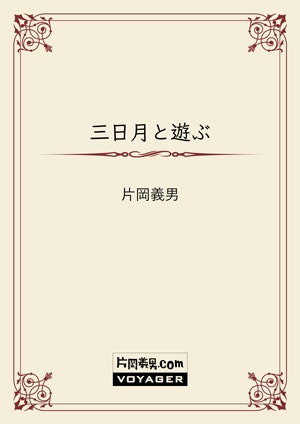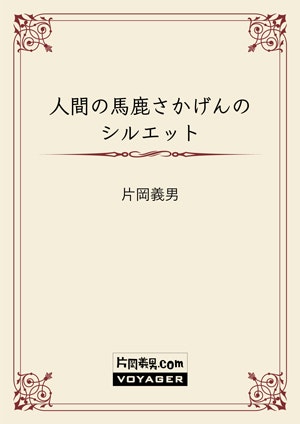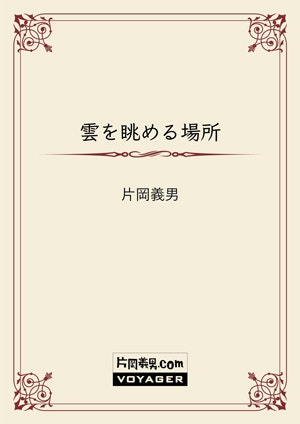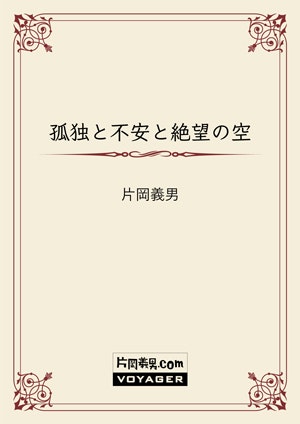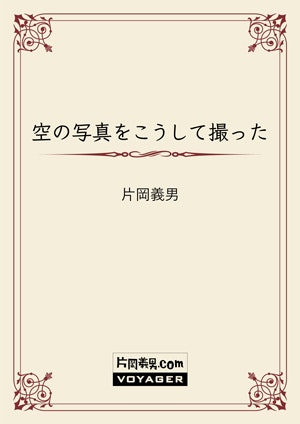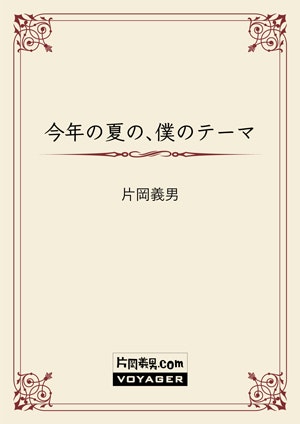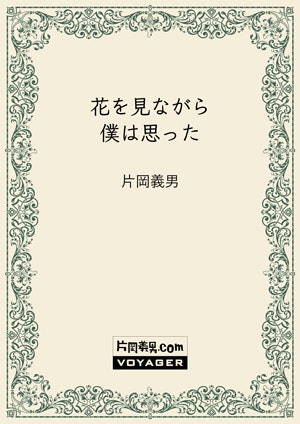写真エッセイ『昼月の幸福──エッセイ41篇に写真を添えて』より12作品を公開
写真エッセイ『昼月の幸福──エッセイ41篇に写真を添えて』(『晶文社』/1995年)より12作品を本日公開いたしました。
先日、月食を見た。人間の手が届くことのない、すさまじく大きな宇宙現象の、ほんのちっぽけな一端でしかない月食だけれども、僕は久しぶりに感動を覚えた。空には太陽があるし、月もある。太陽は自ら光を放っているけれど、月はその太陽の光を反射させているだけだ。こういう奇妙な受け身の存在に、僕は強く心を引かれる。月を見ていれば、たとえば小説に登場させる女性など、いくらでも創造出来るように、僕は思う。カタオカさんの小説に出てくる女性たちには現実のモデルがあるのですか、とよく僕は質問される。彼女たちのモデルは、すべてあのひとつの月です、と僕はここで答えておこう。
夜のまっただなかに、ほどよい起伏の丘が連続している。どの丘も魅力的な森に覆われていて、その中を抜ける一本の道がある。その道を、僕はひとりで歩いている。下り坂がはじまる。その途中で、ふと、僕は坂道のいちばん下で、白くぼうっと輝く物体が、坂道の下に立っているのを見つけた。三日月だ、と僕は気づく。僕と同じほどの背丈の三日月は、それまで僕が一度も見たことがないような、不思議な光をあたりに放っている。無数の真珠を溶解して光にし、ほんのすこしだけ三次元を越えて空間としたような、そんな光だ。それは静かに立っている。僕を待っている。だから僕は、それにむけて歩いていく。
農業をやめてしまった人から、外房にあった廃屋同然の家を借りて住んでいたときは実に快適だった。電気がないので、夜になるとロウソクを使った。直径は四十センチほどのガラスの盆の中に、ぎっしりと立てた何本ものロウソクを立てた。夜になると、このロウソクのうちの何本かに、僕は火をつけていた。そのときの気分によって本数は異なる。月が出ると、その光も僕を照らした。人の心を作るのは、真っ暗な夜と、そのなかに静かに登場して反射光を投げかける月なのだということが、僕にはよくわかった。
空を写真に撮ろうとするとき、カメラのファインダーごしに見える画面のなかを電線が一本横切っていると、その電線はとてつもなく醜い。仰天するほどに人工的で不自然で不気味だ。空は、人間の存在など、前堤のなかにまったく入れていない。あらゆるものの上に君臨して、すべてを超越した、もはや神と呼んでもさしつかえないほどの絶対的な存在だ。このような空を背景にして見る一本の電線は、人間の象徴だ。そしてその象徴は、ひと言で言うなら、やはり醜い。地表に増殖する、ありとあらゆる人工物が空と向き合う星、それが地球であるようだ。
空の雲を眺める時間は、僕にとってたいへんに重要な時間だ。子供の頃から雲を見てきた僕は、雲を眺めて半日を過ごす場所として、絶好の場所をいくつも知っている。人間が作った場所のなかで雲を眺めるのにたいへんに都合がいいのは、古くからある鉄道の、地面よりも高く作った線路の土手のスロープだ。雲を眺めるという静かな時間にとって、通過していく列車の音は、適度なアクセントになってくれる。しかし、現在の鉄道列車の速度は速すぎて、音としては不合格に近い。ローカル線ののんびりした音なら、空に浮かぶ雲に、聴いていて心地良く寄り添う。
物心ついてから現在にいたるまで、空は、僕にとってひとつの絶対的に信頼出来る基準だった。ありとあらゆるものを空と対比させ、価値判断を下すことが出来た。空に自分を写してそれを見ると、自分がなにものであるかもののみごとに理解できた。自分がなにほどのものなのか、空はいつも明確に、僕に教えてくれた。空は僕の唯一無二の親友だった。最高に偉大なる師であり、絶対の尺度だった。空は、自分ではなにをどうすることも不可能な、途方もなく巨大な絶対の不変だった。空は、とにかく、どんなときでも頭上にあった。あらゆる変化を、空は超越していた。
エドゥヴァルド・ムンクの絵の展覧会を、僕は東京で見た。ほとんどおなじポーズの、同一人物と言っていい女性が、いくつもの絵のなかに登場している様子は、それぞれ独立したいくつかの作品をつなぐ、目には見えないけれども確かに存在する、かつてムンクがそのなかにいた時間と空間のトンネルなのだ、と僕は思った。おなじ主題で繰り返されるヴァリエーション。小説でも試みると面白いのではないか。
外国のファッション雑誌の広告ページに、晴れた空の写真を使ったものがあった。そのページから、空の部分を、横に長い長方形として、僕は切り抜いた。そしてそれを黒い紙に両面テープで貼り、写真に撮ってみた。空の片方が背景の紙から外れた。わ、空がはずれた、と僕は思った。これはシャッター・チャンスというものにちがいないと思い、その様子も僕は写真に撮った。
すこしも寒くないある冬の日、僕は絵葉書を買った。アレックス・カッツの一九五七年の作品が、その絵葉書には複製してあった。『筏』というタイトルだ。描かれているのは夏の海、あるいは湖だ。水には四畳半ほどの広さの、厚みのさほどない木製の頑丈な箱が浮いており、その上に飛び込み台がある。アレックス・カッツはこの筏にふたりの人物を作っている。ここに作り出されている情景ぜんたいに、僕は強い共感を覚えた。この夏はぜひこのような光景を捜そうと、僕は思った。
初夏の美しい日の午後遅く、メルボルンの町を僕はひとりで自動車を走らせていた。交差点にさしかかった時、信号が赤に変わった。歩道に花売りの少年が出ていた。少年は花束を持って、花はいかがですか、と停まっている先頭の車から順に運転席の人にすすめた。花束をふたつ買うと、その少年が持っている花の色がすべてそろうように思ったので、僕は花束をふたつ買った。両腕に抱えるほどの量だった。
今年の夏、僕は久しぶりにドライヴイン劇場に入った。場所はとある高原地帯の片隅だった。1940年代に製作されたモノクロ映画は、深い夜の中にうまく溶け込み、幻のようだった。しばらくすると、スクリーンの彼方から、三日月が斜めにゆっくりと昇っていき、映画の一部分のように思えた。アメリカでは、ドライヴイン劇場をめぐって、さまざまに奇妙な体験をしている。そのなかで最高にブラック・ユーモア的だったのは、ハワイのオアフ島で、ある夏の日の夜、ふと入ったドライヴイン劇場だ。上映していた映画は、『トラ、トラ、トラ』だった。客の自動車から見てスクリーンのむこう、さほど遠くないあたりに、真珠湾が黒く横たわっていた。
僕は英語のクロスワード・パズルが大好きだ。クロスワードのために僕が費やした時間を、子供の頃から現在まで積算すると、千単位になっていることはまずまちがいない。クロスワードは、しかし、時間を食う。だからこそ快適なのだが、ほかの多くのことのためにも時間を使わなくてはいけないときには、クロスワードの誘惑を僕は勇気を持ってしりぞけることにしている。クロスワード・パズルに使う時間というものは、自分がなにかのために使う時間としては、きわめて純度の高い時間だ。もっとも高いのではないだろうか。僕の実感では、眠っているときの純度よりもはるかに高い。この純度の高さは、気分のいいものだ。
2022年12月27日 00:05 | 電子化計画
前の記事へ
次の記事へ