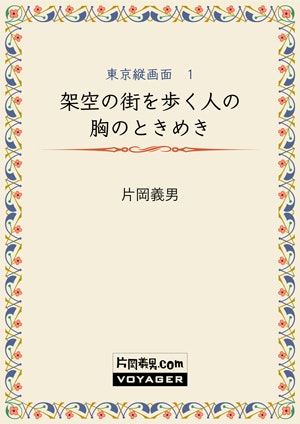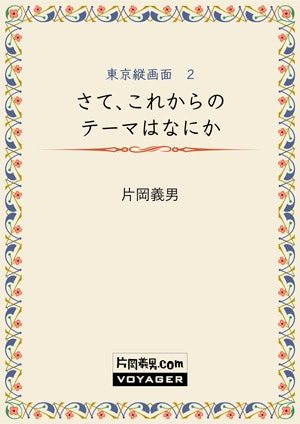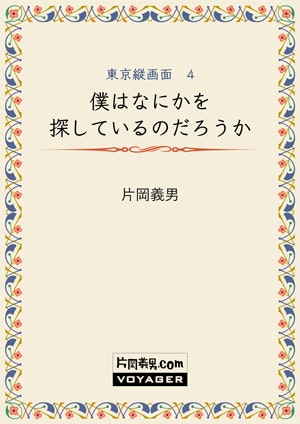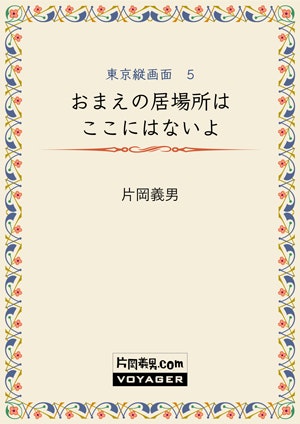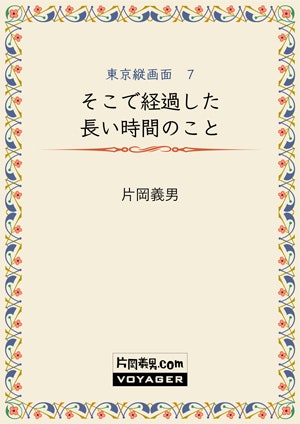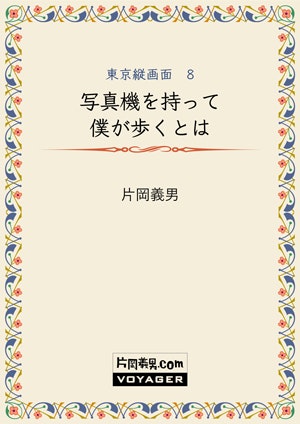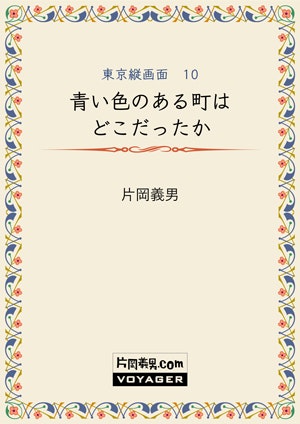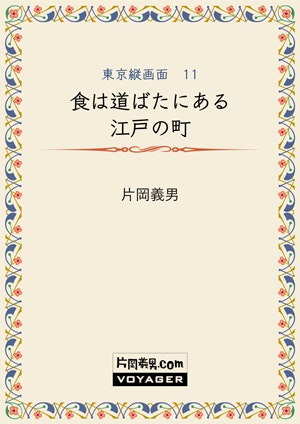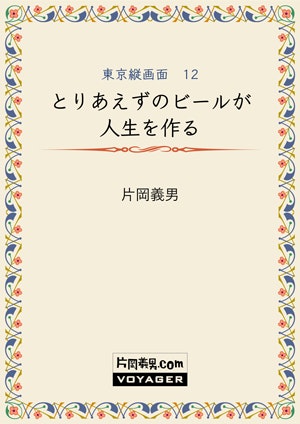写真エッセイ『東京縦画面』12作品を公開
写真エッセイ『東京縦画面』(『日本カメラ』/2005年)12作品を本日公開いたしました。
ただ歩いて観察しているだけでは、どこであっても、僕の胸はときめかない。一眼レフを持って歩き発見する光景をかたっぱしから撮影すると、気持ちは高揚して胸はときめく。なぜだろうか。発見する光景を写真機によってフィルムに記憶するからだ。記録するのではなく、記憶するのだ。僕にとっては未踏の秘境だったJR中央線の阿佐ヶ谷には、2004年の8月後半と9月なかばに訪れた。写真機を持って日光の直射する現実の街を歩いているとき、すでに僕は架空の街を歩いている。
(『日本カメラ』 2005年1月号掲載)
東京はテーマに殉じてきた、と僕は思う。江戸がそもそも、テーマそのものだ。西に対抗して東に都を作る、そしてその都は政治の一極集中地点である、というテーマだ。一億総火の玉、一億総白痴、一億総中流、などというテーマを見ればわかるとおり、東京が追いかけたテーマはすべて、日本ぜんたいに覆い被さる性質のものだった。そのときどきのテーマを追求するとは、その代償としてなにかを、人身御供のように差し出すことにほかならない。得たものと失ったものとの、収支決算をいっさい問わずにここまで来て、さてこれからのテーマはなにか。
(『日本カメラ』 2005年2月号掲載)
皇居、つまり江戸城を中心にして、山手線という環状鉄道がある事実は、東京にとってたいへんに特徴的なものだ。この鉄道の内側が首都なのだろう。首都に流入した労働者層は東京をびっしりと埋めていき、その西側へと移動していき、環状線から西へとのびる鉄道によって郊外へと出ていった、という説がある。環状線から西へと向かう鉄道駅からは、南北両側に伸びる商店街が何本かある。駅から遠のくかたちでこの商店街を歩いていくと、やがてどこに到達するのか。
(『日本カメラ』 2005年3月号掲載)
僕が好むような被写体は、写真機を持って僕が歩こうが歩くまいが、そんなことには何の関係もなく、被写体そのものとして、いろんな場所に存在している。だからこそ、偶然の遭遇、たまさかの発見がある。わざわざ歩くからには、どこに何があるかはわからないけれど、どこかに何かはあるだろう、という程度の期待は持っている。そしてそのような期待があるからには、僕はどこかに何かを探しているのではないか。
(『日本カメラ』 2005年4月号掲載)
三月なかば、薄曇りの日の午後、下北沢で撮った180齣のなかから選んだ6点がここにある。この6点の景色は、撮影者である僕が相当に強く反応した景色なのだが、自分の中にあるセンサーは、こうした景色の何に反応しているのだろうか、と自問すると答えはなかなか見つからない。下北沢から歩いて5、6分のところに、14歳から25年間ほど僕は住んだが、昔の下北沢を懐かしんだり回顧したりする趣味は、僕には全くない。では、今の下北沢の景色を写真に撮って、僕は何をしようとしているのか。
(『日本カメラ』 2005年5月号掲載)
東京の景色がひとつの謎だとすると、その謎の核心は道路だ。僕はこの道を写真機を持って歩く。多くの場合、未踏の秘境と言っていい、まったく初見の景色の中を、僕は歩いていく。そして僕のなかにあるセンサーの感知するままに、遭遇する景色を写真に撮る。その景色は不特定多数の人たちに向けて解放されている道というものに面しており、繰り返され積み重ねられてきた日常というものが、そのいちばん外側でかたちを持ったものへと転換されている。
(『日本カメラ』 2005年6月号掲載)
西武池袋線の椎名町や東長崎そして江古田で撮った景色の中から選んだ6点がここにある。撮るときからしてそうなのだが、選ぶにあたっても意図のようなものは一切ない。撮っているときの僕とは別の人だと言っていい、選ぶ人という僕がいて、その人が意図もなにもなしに、6点を選んだ。たいそう気に入った景色であることは確かだ。気に入った基準のようなものも、これまたいっさいない。だが、このうちの何枚かは少なくとも一九六〇年代なかばあたりまではさかのぼることが可能なほどに、蓄積された時間の厚みを持っている事実に、気づかないわけにはいかないはずだ。
(『日本カメラ』 2005年7月号掲載)
夏のいちばん暑い日に、阿佐ヶ谷で撮った写真だ。中央線の阿佐ケ谷駅で下りてその周辺を歩くのは、僕にとってはこのときが最初だった。その初見の阿佐ヶ谷でまず発見したのは、一番街という通りだった。写真機を持っているときの僕の好みに合致するところの多い、歩いてうれしい通りだった。ああ、いいなあ、と思いながらまずこの景色を撮り、そのまま奥へと歩いていき、通りが終わりとなるあたりで発見したのが、次の写真の景色だ。
(『日本カメラ』 2005年8月号掲載)
梅雨のあいまの薄く晴れた日の午後に、北新宿から西新宿にかけて歩き、写真を撮った。現像したフジ・クロームをライト・テーブルで観察する段階になると、カラー・リヴァーサルのフレームの中にとらえられたどの景色に対しても、僕はきわめて冷静で客観的な人となっている。そしてその人の視点で、自分の撮った景色をあらためて観察すると、最終的に確認出来るのはどのようなことなのか、はっきりわかる。そら恐ろしいまでに政治権力が一極集中した、中央集権国家がその裾野に持つ、民間の庶民の一般的な日常生活の景色がここにある。
(『日本カメラ』 2005年9月号掲載)
写真を撮るときには、一度だけにせよ、そしてほんの一瞬にせよ、被写体となる光景を必ず僕は見ている。何冊ものバインダーの中にあるカラー・リヴァーサルのフレームは、僕の頭の中にあるべき記憶だろう。しかしすべてを覚えていることは不可能だから、外付けの脳のように、何冊ものバインダーを持つわけだ。ライト・テーブルの上でスリーヴを見ていくと、あるときふと、青い色が記憶の底からにじみ出るかのように、浮かび上がった。
(『日本カメラ』 2005年10月号掲載)
東京には食べ物屋がたいへんに多い。その多さは尋常ではないように思える。かつて江戸の町にはいまなら浮動層と呼ばれたりするはずの、地方から流入したまま定職も定まった住居もなく、まさに文字どおり浮動していた人たちがたくさんおり、彼らの食事をまかなったのが屋台だった。食べる必要が起きたとき、すぐ目の前に食べる物の店があるという、需要と供給のきわめて短絡した結びつきは、屋台で間に合わせにちょっと食べる、といった場面を越えて、他のさまざまな局面においても、いつとも知れずいつのまにか、一定の方向に向けて決定的な影響力を、発揮していくのではないか。
(『日本カメラ』 2005年11月号掲載)
とりあえずのビールの最初の一杯を飲み干す。仕事で発生したストレスを最初の一杯で発散しているように見えて、実はご丁寧にもそのストレスを確認している。ストレスの人たちをとりあえずのビールへと誘うポスター、立て看板、提灯、幟などが、東京のサラリーマン地帯にはいたるところにある。数多いポスターのなかで、ビールの満ちたガラスのジョッキをかかげ、常に明るい笑顔でいる若い女性たちを、どのように理解すればいいものか。
(『日本カメラ』 2005年12月号掲載)
2022年12月27日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ