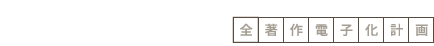「片岡義男のぼくのお気に入り道具たち」よりエッセイ11作品を公開
雑誌『BE-PAL』(小学館)に1983年から1985年にかけて連載された「片岡義男のぼくのお気に入り道具たち」からの11作品を本日公開いたしました。1988年に刊行された『彼らと愉快に過ごす』の元となった連載ですが、書籍化の際には道具や内容などを含め大幅に改稿されています。
ありとあらゆるすべてのことを書きとめておくための1冊の万能ノートというものは可能かどうか、ぼく個人の日常的な現実に即して考えてみた。書きとめておきたいこと、例えば読みたい本のタイトル、聴きたいレコードのタイトル、気になる映画の題名、何日か先の約束事など、ちょっとメモしておきたいことを、気に入ったその1冊のノートブックに片っ端から記入していったらどうなるだろうか。例えばスケジュールや電話番号は、順不同に片っ端から書きこんでいくという便利さは、あとになって何らかの不便さを必ず生み出すのではないかと思う。そう考えていくと、結局たどり着くのは、いくつものそれぞれ独立したセクションをルーズ・リーフ式に1冊のバインダー・ブックにまとめたシステムだ。イギリス製のファイロファクスというシステムがこれにあたる。ぼくは一冊のファイロファクスを自分にとっての万能ノートブックにすることに決めてみた。開いて右側のページにだけ書き、その裏には書かない。昔からの主義であり、どんなノートでもそうだ。
(『BE-PAL』1985年1月号掲載)
モノポリーで遊んでいる人たちは、いろんな状況のなかで何度も見かけた。最も強く記憶に残っているのは、シカゴのオヘア空港のロビーで見かけた、白人の中年男性たち4人だ。全員ビジネスマンのようだったが、どことなくかたぎではないような雰囲気があり、その雰囲気とモノポリーの取り合わせ、そして空港ロビーの一角で立ったまま行っているという態度が、なかなかさまになっていた。バックギャモンに興じている人も、同じくよく見る。サンディエーゴのシーフード・レストランのバルコニーでバックギャモンに興じていた2人は、まるで俳優が演じているかのように、さまになっていた。クリベジ(クリベッジ)はあまり見かけないが、ロッキー山脈をこえるハイウエイの、高い標高にあって夏でも夕方からは薪ストーブを赤々とたかないと寒いという町のジェネラル・ストアで、初老の男性と女性が、店の人といろんなお喋りをしながらクリベジをやっていた。薪ストーヴの暖かさ、そして夜のロッキーの空気の澄みきった鋭い冷たさと一緒に記憶の中に残っている。
(『BE-PAL』1985年2月号掲載)
友人の家に、太平洋に面してフロアから天井まで大きくガラス張りとなっている居間のような広い部屋がある。絶壁のはるか下の力強い岩場と、そこへいつも砕け続けている同じく力強い波とが見える。月も星もないある日の夜、友人と一緒にその部屋にいると、いつもは聴こえない海の音がかすかに、しかしはっきりと聴こえていることに気づいた。友人がプロ用の機械を使って録音した海の音が、スピーカーを通して部屋の中に放たれているのだった。……そんな思い出をきっかけに身の周りを探してみると、海を感じさせた〝音〟は、思いのほかにたくさんあった。『スロー・オーシャン』は砂浜に寄せる波の音のレコードだ。今では珍しくないが、1979年に発売された時は新鮮だった。読書、リラックス、睡眠、メイキング・ラヴ、勉強、瞑想などに用いると効果的です、と説明してある。ちょうどよい暗さの、広さのある静かな部屋で、トーンに注意してかけると大変面白い効果がある。他にも『老人と海』の朗読、そして音楽による海は、探せば実にたくさんあるに違いない。
(『BE-PAL』1985年3月号掲載)
なんの変哲もない白いコーヒー・カップとその受け皿を、かねてよりぼくは探している。ぼくが探しているのは、コーヒー・カップやその受け皿というものに関して長い歴史と伝統を持っている国の、平凡でいいから誠実な職人が、ほとんど何も考えずに自動的に手を動かした結果として出来てきたようなコーヒー・カップおよび受け皿なのだ。外国、特にヨーロッパの大きな工場の従業員食堂とか海軍の食堂、あるいは小さな田舎町でおばさんがひとりでやっているようなめし処などで使っているコーヒー・カップは、おそらく海軍の食堂のものにはそれらしい雰囲気が、そして工場の従業員食堂のものにはやはりそれにふさわしい特ち味がどこかにあるはずだ。いまコーヒーを飲んでいるコーヒー・カップは東京のデパートでみつけたものだが、ぼくが探しているなんの変哲もない白いコーヒー・カップに、かなり近い。フランス製で、APILCOとブランド名が入っている。
(『BE-PAL』1985年4月号掲載)
子供のころキットを買って来て自作したピンホール・カメラのことを、ぼくは今でもときどき思い出す。ピンホールが、すりガラスの上につくる倒立した映像を初めて見たときには極めて強い感銘があった。すりガラス上に逆さまに出来た樹の映像は、まるで魔法であり、そこに映っている幻の樹は、光と影を完璧に作り変えた、全くの別世界の出来事だった。シアトルにあるアーリー・ウィンターズ社のカタログに、ピンホール・カメラが載っていて以前から気になっていた。これを入手し撮影をしてみた。ボール紙で出来たボディは、なかなか夢のある形をしている。フィルムは、コダックのカートリッジ入りのフィルムのうちの、126というシリーズを使用する。カラーならコダカラー、モノクロならヴェリクローム・パンだ。パン・フォーカスでアングルは広く、しかもリニア・ディストーションがないから、人の目とよく似ていると言えば言える。ピンホール・カメラなんて玩具だと思う人は多いだろうけれど、科学や芸術の最先端で今でもさまざまに役立っている。
(『BE-PAL』1985年6月号掲載)
横たえた体から力を抜き去り、よく晴れた空の彼方に視線をむけている時間というものは、ぜひとも必要な時間だとぼくは思う。空を見ることによって、たとえば頭のなかを掃除しようと思ったら、あおむけに寝るに限る。空と自分との位置関係が、座って空を見ているときや立って空を見ているときとは、まるで違ってくる。まわりの光景を寝そべって眺める時間も大切だ。横たわると目の位置が低くなるし、心の態度も他の姿勢に比べると、おおいに違ってくる。横が184センチ、縦が90センチの大きな長方形、色はきれいなグリーンのタオルをどこに広げようか。部屋の中なら畳の部屋がいい。勢い盛んな草の上に広げると、草にしろ樹にしろ自然の緑は色としては凄まじい色なのだということが、タオルのグリーンとの比較のうえでよくわかる。1枚の大きなタオルは、人をしばし横たわらせるためにあるようだ。どこに広げてどんなふうに横たわり、何を見て何を考えるかは、横たわるその人にかかっている。
(『BE-PAL』1985年7月号掲載)
ロディアというブランドの、フランス製のメモ・パッドは、実によく出来ている。サイズはたくさんある。紙の色もぼくの知る限りでは4色ある。どの色もたいへんによく出来た微妙に淡い色であり、視覚を通して気持ちの上で邪魔になるというようなことが絶対にない色だ。紙の色が変わっても、方眼の色は変わらない。方眼は5ミリであり、この色もまた、考え抜かれた色だとぼくは思う。ぼくがいつも愛用しているのは、写真の中では一番小さい11番、そして16番と19番の3通りだ。まず11番だが、これほど完成された、使い心地のいいメモ・パッドをぼくは他に知らない。ほんのひと言、ふた言の、短いちょっとしたことをメモする紙として、このサイズは完璧と言っていい。デスクの上にいつも置いておくメモ・パッドとしても、ポケットに入れて持ち歩いても、この大きさならかさばらない。メモ帳のかわりにこれをバッグにいつも入れている女性を、ぼくは何人も知っている。どの彼女たちからも、11番は絶賛されている。
(『BE-PAL』1985年8月号掲載)
このコーヒー・ショップは、彼女のお気にいりの店だ。彼女がこの店を知ってから、すでに1年以上になる。何度もここに来てコーヒーを飲んでいるが、同じデミタスでコーヒーが出てきたことはまだ一度もないと言う。この店を彼女が気にいったのは、コーヒーの種類や味もさることながら、来るたびに必ず違うデミタスでコーヒーを出してもらえるからでもあった。朝、オフィスに行く前に必ずこの店に寄る、ということが6か月以上も続いたことがあったが、同じデミタスにあたることは一度もなかった。「聞いてみたの。お店には、デミタスが一体いくつあるのですかって。500以上あると教えられて、びっくりしたわ」と、彼女はぼくに語ってくれた。そして、彼女自身もデミタスのコレクションをするようになった。気にいったものが目にとまるチャンスがあれば、その都度買っているそうだ。コーヒーを飲んだあと、彼女がひいきにしている陶器の店へ寄ってみた。外国製のデミタスが、たくさんあった。ひとつひとつ眺めていると、コレクションしたくなった彼女の気持ちがよくわかるのだった。
(『BE-PAL』1985年9月号掲載)
フランスのクレール・フォンテーヌというブランドのこのノートブックには、強くひかれるものがある。17センチ×11センチというプロポーションは、ヨーロッパではスタンダードなサイズだが、このプロポーションが持っている安定感は、ぼくの気持ちがひかれていく理由のひとつに違いない。14ミリという厚さもいい。表紙の造りが少しだけ凝っている。背中の布が、普通の造りなら表紙の厚紙のうえに出てきてしまうのだが、このノートブックの場合、背中の布は表紙の厚紙の内部に挟み込まれている。ほんのちょっとしたことだが、このようなちょっとしたことが、出来上がった製品の雰囲気を決定してしまうことがよくある。このノートブックの場合もそうだ。表紙の色やデザインは、手間のかかっていない、ごくあっさりとしたものだ。しかし手間をかけないところが逆に雰囲気となって生きているから、やはりフランス的だなあと感心してしまったりする。気に入ったので何冊か買ってあるのだが、まだ一冊も使っていない。どんなことに使うといいのだろう。使い道が、ぼくにはまだ決まっていない。
(『BE-PAL』1985年10月号掲載)
デミタス一杯だけのコーヒーをいれるコーヒー・メーカー。その出来具合をよく見てほしい。ぼくはただ見つけて買って来ただけなのだが、このくらいよく出来ていると、どうだ、この美しさを見てくれ、と自慢したくなってくる。自慢するに値するハンサムなコーヒー・メーカーだ。全体の構造は、大まかにいうとひとつのポットだ。上下ふたつに分かれており、下のポットは、水を沸騰させるところだ。だから下のポットは、ボイラーと呼んでもいい。上のポットにはサイフォンがついている。水が沸騰すると、熱湯はストレーナー下部の細い管を通ってストレーナーに噴きあがり、コーヒーの粉の中を瞬時に通過し、コーヒーを抽出する。そして、上のポットのサイフォンを通過し、出来あがった熱いコーヒーが、ポットの中に注ぎこまれる。機能も造形も、ほぼ完全に完成されていると言っていい。これだけ小さくてしかも美しいと、アウトドアに持っていきたくなる。このときの最も手軽な熱源は、エスビットのポケット・クッカーだ。雰囲気はよく似合う。
(『BE-PAL』1985年11月号掲載)
彼が彼女と知りあう。お互いに相手に対して、何ごとかを強く感じあう。そこから恋人同士となるまでに、普通どのくらいの時間がかかるものだろうか。5か月目くらいだろうか。恋人同士になってしまうと、時間の経過していくスピードは早い。1年ほど経ち、ふたりは残念なことに別れてしまう。理由はここでは問題にしないこととして、とにかくふたりは別れる。自分の身辺からいなくなってしまった彼女のことを、彼は例えば自分が撮った彼女の写真をとり出して眺めたりする。写真は20枚近くある。その中にモノクロームが2枚あり、その写真の彼女は美しい。思い出はすべて美しいとは、このことだったのかと彼はしみじみと思う。このプリントを1冊のアルバムに貼ろう、と彼は思う。……こんなストーリーがもし現実にあったなら、イタリー製で155ミリ×103ミリの大きさの素敵なアルバムに、彼女を思い出すよすがであるスナップ写真を貼っていくと、何か特別なもののように思えてくる。
(『BE-PAL』1985年12月号掲載)
2024年11月1日 00:00 | 電子化計画