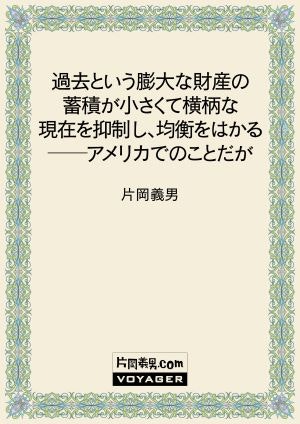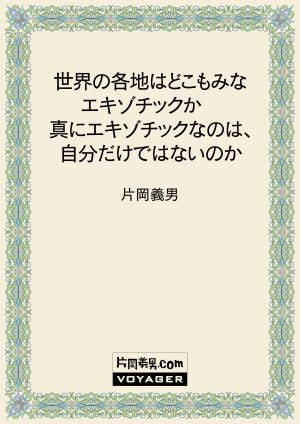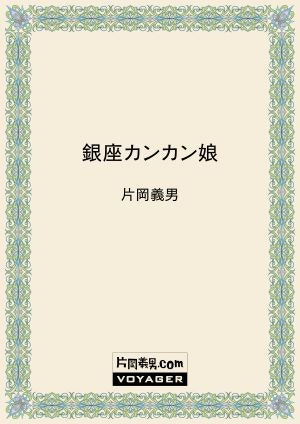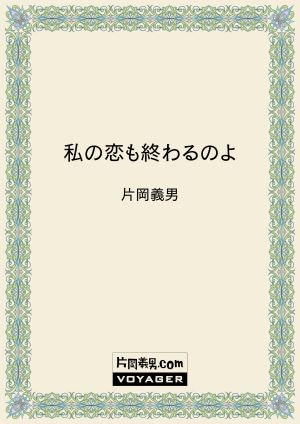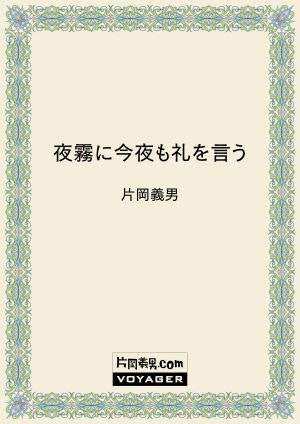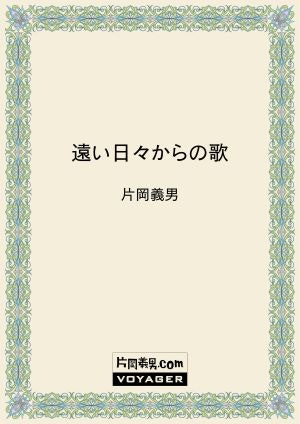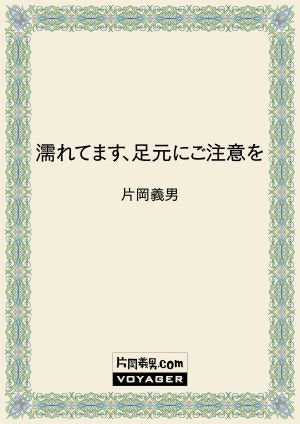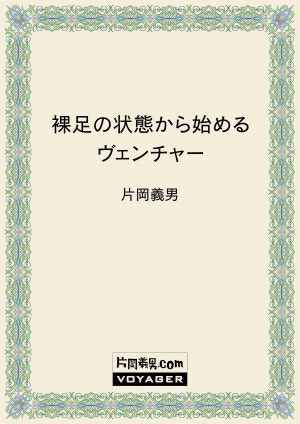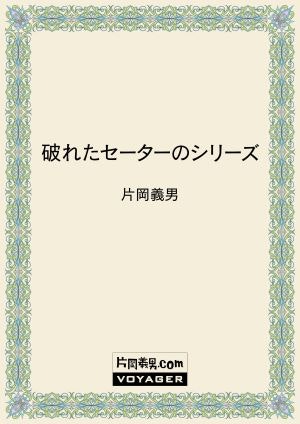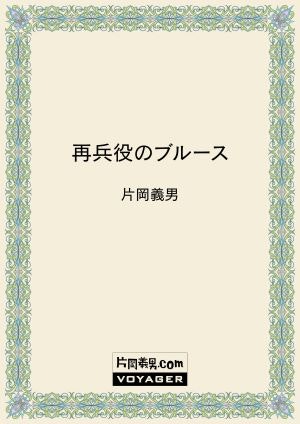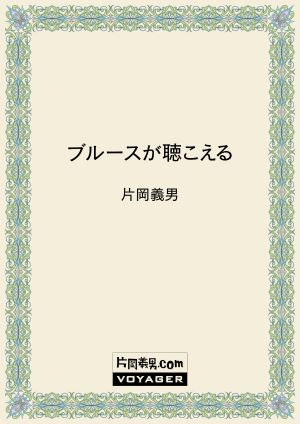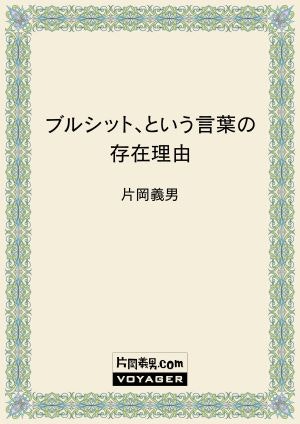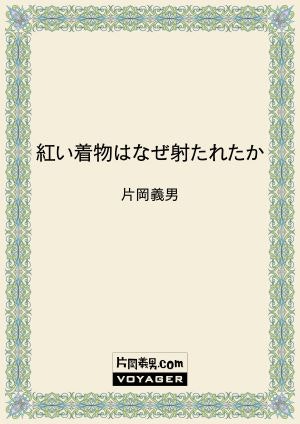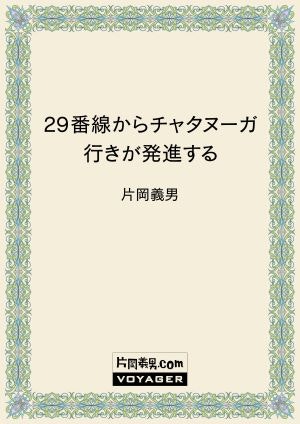音楽論集『音楽を聴く』『音楽を聴く2——映画。グレン・ミラー。そして神保町の頃』より17作品を公開
エッセイ『音楽を聴く』(東京書籍/1998年)より7作品、『音楽を聴く2——映画。グレン・ミラー。そして神保町の頃』(東京書籍/2001年)より10作品を本日公開いたしました。
音楽がCDという小さなディスクになり、メガストアが出現した。そこへ行きさえすればすべての用が足りる大きな店を、CDの時代の人々は求める。どれもみな最新のものだと多くの人は錯覚する。しかしCDというディスクに録音されている音楽は、どれもみな過去のものだ。過去は、実は現在などと比べ物にならないほどに巨大で深く複雑だ。その過去の貯蔵庫のなかで、意図的に過去を探す楽しみを僕は発見している。カーター・ファミリー、グレン・ミラー、アンドリュース・シスターズ、ザ・マクガイア・シスターズ……。とっくの昔に過ぎ去った時間が、CDから再生される歌声によって、ほんのいっときだけ蘇っては消えていく。グレン・ミラーからジョニー・レイまで聴いてきてあらためて確認できることは、問題の核心はジャズである、という事実だ。個人が徹底しておこなう勉強や修練。その上に組み上げ広げていく、工夫や独創、そして創意。ブルースから出発してたとえばジャズへと発展していくプロセスは、じつは科学そのものなのだ。
地方の商店街にあったCD店で「ここに幸あり」の入った李成愛(イ・ソンエ)のカセットテープを買う。歌謡曲にはエキゾチックを感じる。それは幼い頃にいたるところで流れていた歌謡曲を大人のものであると受け止めていたからかもしれない。エキゾチックは、進駐軍の楽士たちによる日本の音楽の演奏をレコードにしたものや、澄淳子によるジャズ化された歌謡曲にも感じられ、それらはネーネーズの歌、インドネシアの「ブンガワン・ソロ」、ハワイアンの甘くせつないスティール・ギターの音色、イージー・リスニングへと繋がっていく。原典そのものはエキゾチックでもなんでもないのだ。エキゾチックであるかどうかは、こなしかたの問題だ。そしてその場にものの見事にふさわしい音楽を偶然に聴くと、その場のこと、そしてその音楽のことは、いつまでも記憶のなかにあり続けるようだ。
春まだ浅い日、ひとりで乗ったタクシーのラジオのリクエスト番組から、石原裕次郎の「白い町」という歌が流れた。僕はこの曲を知らなかった。いい歌だった。メロディがいい。その良さを、編曲がふくらませ、支えていた。歌詞も悪くなかった。そして歌いかたは、これは裕次郎そのものだ。白い町とは名古屋のことだった。しかし、ご当地ソングと言ってそれっきりにしてしまいたくないほどの良さが、その歌にはあった。こういう歌をいまはもう誰も作らなくなったという意味において、僕は「白い町」をもっとも気に入った。いまは夢でしかないような遠い日々には命を持っていた、なにかたいへんに純なものを、僕はその歌のなかに聴き取った。と、僕は思った。
石原裕次郎「白い街」
幼児を脱した僕が、町のいたるところで聞いたのは「銀座カンカン娘」という歌だった。不思議な歌だという感想を子供心に持った。その感想はいまも変わらない。不思議であると同時に、その歌は相当にロマンティックだ。良くできた歌だ。明るい。そして、その明るさはどこかせつないが、無理して元気に振る舞う現在の明るさとは、まったく別種の明るさだ。まさに時代のなかで生まれてきた歌だ。時代が、そのような歌を強く求めていた。その求めに応えた才能が、この歌を生み出した。この歌がじつは映画の挿入歌だったということを、僕はつい最近まで知らなかった。タイトルは『銀座カンカン娘』といい、一本の娯楽映画としてはまったく落第としか言いようのない出来ばえの、コメディだった。
高峰秀子「銀座カンカン娘」
日活が製作した『銀座二十四帖』(1955)をビデオで見た。1本の娯楽映画としてはまるで駄目だったが、その後購入した織井茂子のCDの中にこの映画の主題歌として使われた「銀座の雀」という歌があった。彼女が歌った、映画『君の名は』3部作の主題歌を時間順に聴くと、敗戦直後の時代の純情な夢が、次の時代のものへと変質していきつつある様子を、はっきりと見ることのできる。これらの曲から想起されるのは、月刊娯楽雑誌『平凡』が一般から募集した歌「嘆きのセレナーデ」だ。この曲は1番も2番もその最後のセンテンスが「私の恋も終わりなのよ」となっている。都会という日常生活の場のなかで、その巨大な矛盾はさまざまに形を変えては、人の心や生活のひずみとなってあらわれ続け、蓄積されていった。矛盾自体も、その複雑さやスケールを、時代の進展とともに何乗倍にも、膨らませていった。愛の夢を見た次の時代には、愛という夢など、とてもではないが成立しなくなったのだ。
織井茂子「嘆きのセレナーデ」
浜口庫之助が作詞作曲した「夜霧よ今夜も有難う」は、石原裕次郎が歌い、大ヒットになった。誰がどのような事情のもとに、夜霧に対して礼を述べるのだろうかと、小さな疑問が僕の頭の中にふと生まれた。そこで、この曲が含まれる3本のテープを購入し聞いてみた。謎は、すぐに解けた。人目を忍ばなければいけない自分たちを、今夜もそっと包み隠してくれる夜霧という主題は、恋愛関係にある男女というものが基本的に持つ排他性を、純情に可愛らしくロマンティックに、美化したものではないのか。その排他性がいかに窮屈で利己的で不便であるか、今の人たちはすでに知っている。だからこそ、排他性の格段に少ない男同士、さらにはもっとも排他性の希薄な女同士の関係がより豊かな可能性として、いまの人たちの意識の前に立ち上がっているのではないのか。排他性そのもののような、ひと組の男女の恋愛関係が、自由で豊かな開放感そのもののような女どうしの関係と、ゆるやかに滑らかに対比されてひとつの世界となっている短編小説を書いてみようか。
石原裕次郎「夜霧よ今夜も有難う」
『グランド・ピアノで奏でる石原裕次郎の世界』というタイトルのカセット・テープを聴きながら、歌詞を目で追っていった。裕次郎、或いは他の歌手が歌うのを聴くのとは、また違った趣があって楽しい体験だった。これらの歌の良さとは、ロマンティックさであると言って間違いない。現在の歌にくらべると、とてつもなく上品なものだと僕は感じた。いまの歌は、途方もなく、底なしに、限度いっぱいに、下品だ。現実をなぞることをとおして、安心したり納得したりするだけでことは足りると大衆が態度をきめたとき、フィクションとしての歌謡曲の運命は、そこでいきなり終わったのだと僕は思う。グランド・ピアノが奏でてくれた石原裕次郎の歌十四曲は、今となってはどう取り返すことも不可能な、遠い日本の日々からの歌だ。そのなかに成立しているロマンティックなフィクションは、現在を埋めつくしているまったくロマンティックではない現実がどのようなものであるのかを、あらためて僕に教えてくれた。
(以上7作品、『音楽を聴く』東京書籍/1998年所収)
『スペース・カウボーイ』(2000)という映画を見た。百点満点で七十五点、旧タイプの映画、としておこう。今はとっくに引退している宇宙飛行士たちをシャトルに乗せ、落ちてくる衛星を途中でつかまえて修理させるという、冗談のような映画と言うよりも、冗談そのものだ。この映画の途中と最後に「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」が出てくる。一九五四年にアメリカでヒットした歌で、すでにスタンダードのような位置にある。『スペース・カウボーイ』はこの歌から思いついたものに違いない、と僕は思う。ラストに流れるのはフランク・シナトラの歌う「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」だ。この歌から思いついた冗談です、という断り書きのようなものだろう。
Frank Sinatra「Fly Me To The Moon」
ブルース・ブラウンの最初の波乗り映画『スリパリー・ホエン・ウェット』(1959)は、音楽にバド・シャンクの率いる四重奏団によるジャズを使っている。波乗りの映画にモダン・ジャズというアイディアには、首をかしげた人も多かったようだ。ちょうどその頃は『死刑台のエレヴェーター』のマイルス・デイヴィス、『危険な関係』のセロニアス・モンクなど、映画にジャズの新しい使われ方が出てきた時代だ。ブルース・ブラウンがバド・シャンクに音楽を頼んだのは、この時代のこうした新しい発想のひとつだったのだろう。その演奏は、LPを再生してスピーカーから解き放てば、今でもそれを受けとめる人に対する作用力をなんら失ってはいない。
Bud Shank「Slippery When Wet」
ブルース・ブラウンの波乗り映画の3作目『裸足の冒険』(1960)も音楽はバド・シャンクの率いたグループが演奏していた。サウンドトラックLPの録音は1961年11月だという。映画のために演奏した音楽を整理しなおして演奏したものだろう、と僕は推測している。全体がひとつの物語であり、それが8つの章に分かれていると思うのが、このLPを聴くにあたっての正解ではないかという気がする。映画はきちんと組み上げられたストーリーが語られていくわけではない。当時の彼とその仲間たちが、日々の仕事としていた波乗りという面白い遊びの、当時のテンポによるスケッチ集だ。好きなことに多くの時間とエネルギーを使っていると、その好きなことをめぐってさまざまなことを考え、工夫をこらし、試行錯誤をいくらでも行うことが出来る。そのことの蓄積が、それまで誰も考えつかなかった新たな地平を切り開く。それはそのまま、実はヴェンチャーなのだ。
Bud Shank - Barefoot Adventure
バド・シャンクからの連想で、ロバート・アルトマン監督の『ジェイムズ・ディーン物語』(1957)という映画を思い出した。この映画のサウンド・トラックのジャケットにはバド・シャンクとチェット・ベイカーの名がうたってある。この頃のベイカーはまだ20代なかばだった。スコア全体を書いたのはリース・スティーヴンスだ。ジャズを基調としたサウンド・トラックのオーケストレーションを、1950年代的な洗練の極みまで高めた人のひとりだ。『ジェイムズ・ディーン物語』のLPを再生すると、1957年のある日あるときの時間が、いまの僕の目の前でよみがえる。そしてその時間のなかへ僕は連れ去られる。1975年には『ジェイムズ・ディーン』というLPが出た。『エデンの東』『理由なき反抗』『ジャイアント』の3本の映画から、それぞれの主題旋律、そして場面からの引用で編纂した内容だ。台詞の音声に効果音を重ねて受けとめると、映画はアーツとサイエンスの、きわめて複雑で立体的な融合であるという事実を、いまさらのように認識することができる。
Chet Baker · Bud Shank - Jimmy's Theme(Theme Music From "The James Dean Story")
『地上より永遠に』がアメリカで公開されたのは1953年だ。僕が大学生の頃、百軒店の映画館で見たときには、それから10年近くが経過していた。この時で20回目くらいではなかっただろうか。何度も見た理由はマール・トラヴィスだった。ハワイのスコフィールド兵営に駐屯していく兵士たちが、夜にビールを飲んで歌う場面がある。歌われているのは「再兵役のブルース」という歌で、トラヴィス本人が兵隊に扮し、歌う場面に出演していた。トラヴィスの扮した兵隊が弾くギターのうまさ、そして「再兵役のブルース」という歌の良さは僕を強く捉えた。洗練の効いた実に好ましいブルース曲で、歌詞と完璧に一体だ。兵士たちの中にモンゴメリー・クリフトもいて、兵隊用の喇叭のマウス・ピースだけを使い、歌に対して合いの手を入れる様子にも、僕は完全なノック・アウトをくらった。『ザ・ベスト・オヴ・マール・トラヴィス』いうCDのなかに「再兵役のブルース」が収録してある。映画のあの場面で聴けるものと、ほとんど同じ仕上がりとなっていて、何度聴いても素晴らしい。
Merle Travis - Re-entlistment Blues(From Here To Eternity/1953)
映画『ブルースが聴こえる』(1988)は、ニール・サイモンの戯曲『ビロークシ・ブルース』を彼自身が映画の脚本にし、マイク・ニコルズが監督したものだ。ミシシッピー河にかかる鉄橋を、蒸気機関車が越えていく。1945年の5月の終わり近く、あるいは6月の初め、という設定の光景だ。この光景にパット・スズキの「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」の歌が重なる。大変に雰囲気のある歌い方だ。歌が悲しさを画面にかぶせる。しかしその悲しさはすでに遠く、いまは多分に懐かしさをともなった思い出へと、転換されている。この頃のパット・スズキは24歳だった。1945年の光景にかぶさる歌として、時間的には整合しないのだが、画面との違和感はまったくない。歌ひとつで、単なる光景がこのような内容あるいは性質を獲得する。音楽を担当したジョルジュ・ドゥルリューの判断は冴えている。しかしこの映画は失敗作だ、というのが僕の判断だ。
Pat Suzuki - How High The Moon
1960年代前半のヴェトナム戦争とアメリカの若い兵士たちを描いた映画に『恋のドッグファイト』(1991)という作品がある。主演はリヴァー・フェニックスだが、佳作という言葉がなんの無理もなくあてはまる、たいへんいい映画だと記憶している。設定されている時代は1963年、場所はサンフランシスコだ。主人公の海兵隊員バードレイスは、まもなく19歳で、明日は沖縄に向けて出航し、そこからヴェトナムの戦場へ送り出される。自由な一夜を仲間たちと過ごす彼は、小さな食堂でローズという名の同世代の女性と知り合う。ローズはジョーン・バエズが大好きで、彼女のように歌う自分を夢見ている。そのローズがマヴィーナ・レイノルズの「彼らは雨になにをしたのか」を歌うシーンがある。いかにも未熟で下手である、と誰もが感じるような歌いぶりだが、マヴィーナの曲を聴いてみると、ローズを演じているリリ・テイラーは、ローズがマヴィーナをなぞった様子を、実に巧みに表現していることがわかった。現実にはもっとうまく歌える人なのではないだろうか。
Malvina Reynolds - What Have They Done To The Rain ?
サミュエル・フラー脚本・監督のスリラー(サスペンス)映画『ザ・クリムゾン・キモノ』(1959)の音楽を担当したのはハリー・スークマンだ。スークマンの『コマンド・パフォーマンス』というタイトルのLPにサミュエル・フラーが短い文章を寄せており、この映画のストーリーに音楽をつけていく作業は、スークマンにとっては挑戦となったはずだ、とフラーは書いている。映画が始まると、女神の全身像が「コロムビア・ピクチャーズ」というロゴとともに、画面いっぱいに現れる。このときに聞こえてくるメロディは、日本の童謡であるあの「赤とんぼ」なのだ。西欧そのもののオーケストレーションで「赤とんぼ」のメロディが冒頭に流れるアメリカ映画は、この『ザ・クリムゾン・キモノ』をおいてほかにない、と断言していい。
Harry Sukman - music from The Crimson Kimono
グレン・ミラーの何枚ものLPを聴きながら僕が思うのは、良く出来た曲と見事な演奏、そしてそれらに添うきれいな歌いぶりが、どのようにして生み出されたのか、ということだ。自分はどのような音楽を作りたいのかという目標が、グレンには細部にわたって、きわめて明確にわかっていたようだ。どこをどうすればどうなるか、すべてを知り抜いているのだから、それはそのまま、編曲の腕前や才能であったはずだ。あるいは、優秀な人材を正しく選別して採用し、彼らに作・編曲をさせるという、楽団運営の基礎にかかわる才能でもあった。自分たちはこういう音楽でありたい、というイメージや理想の構想力、そしてそれを実現させていく実力は、ひと言で言うなら科学だ。いくつもの正しい要素が正しく配置され、それらすべてが正しく機能すると、そこにはめざしたものが実現されている、という種類の科学だ。
ビリー・ヴォーン楽団の演奏する「エル・チョクロ」を再び聴いてみたい、と僕は思った。彼らのLPを僕は1枚も持っていない。さっそく中古レコード店へいってみた。探すまでもなく、『ビリー・ヴォーン・ゴールデン・ラテン・ミュージック』というタイトルのLPを見つけ、自宅で「エル・チョクロ」を聴いてみた。確かにこの「エル・チョクロ」なのだが、こんな編曲だったかな、と思う部分がなくもない。長い時間のなかで、僕の記憶のほうが、かなりの変形をとげている。3か月ほどの期間に渡ってビリー・ヴォーンのLPを買い集めた僕が、店頭で受けたもっとも大きな印象は、デラックスやゴールデン・デラックス、あるいは大全集といったLPがたいへん多い、というものだった。日本でも人気があって売り上げの数字が見込めるから、そのような数字が必要になるたびに、毎度おなじみの変わりばえのしない選曲で、デラックスその他が何度も発売された。そうしているうちに時代は進展していき、選曲や売りかたが信用を失うことと並行して、ビリー・ヴォーンは少しずつ忘れられていった。
El Choclo - Billy Vaughn And His Orchestra
(以上10作品、『音楽を聴く2——映画。グレン・ミラー。そして神保町の頃』東京書籍/2001年所収)
2023年10月6日 00:00 | 電子化計画