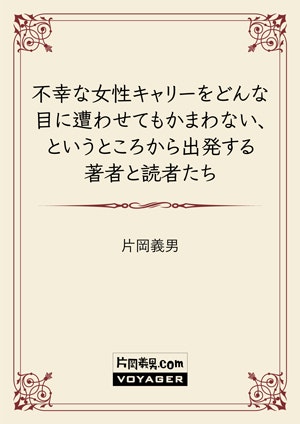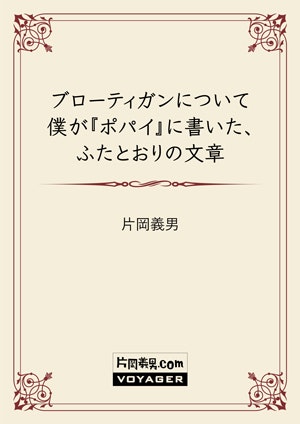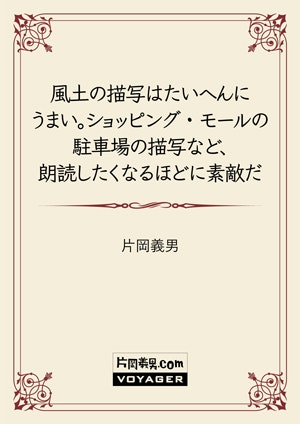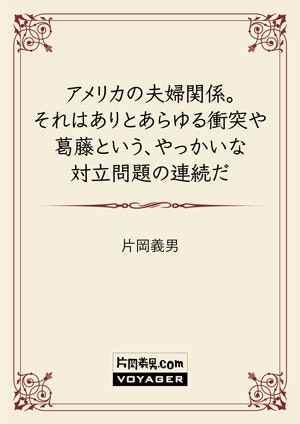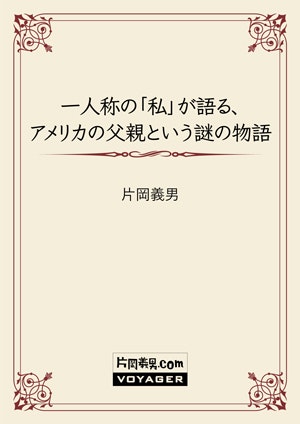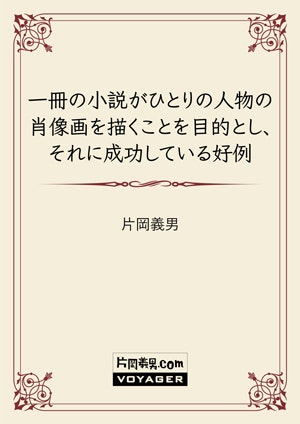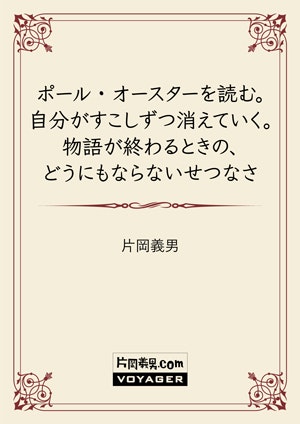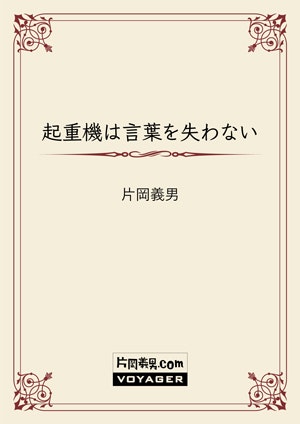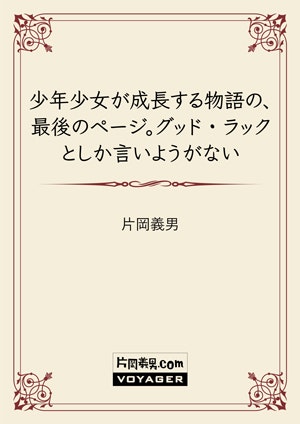エッセイ『本を読む人──片岡義男エッセイ・コレクション』より9作品を公開
エッセイ『本を読む人──片岡義男エッセイ・コレクション』(太田出版/1995年)より9作品を本日公開いたしました。
スティーヴン・キングの長編小説『キャリー』の主人公、キャリエッタ・ホワイトは、テレキネシスという特殊能力の持ち主だ。自分の意志の力だけで、さまざまな物体を思いのままに動かすことが出来る、という能力だ。これは悪魔にずいぶん近いことと同じだ。キャリーは持って生まれたこの能力ゆえに、どんなひどい目に遭ってもかまわないのであり、この小説の読者にとっての中心的な興味は、物語の終わりに彼女がどんな最期をむかえるかだ。
リチャード・ブローティガンの『東京モンタナ急行』のことを、僕は1982年の6月に雑誌『ポパイ』に書いた。その翌年2月、東京でブローティガンに会うことができた。作家というものの真髄を、ひとりの生きた実像として目の当たりにしたという印象を僕は受けた。幼いころから、彼にはたいへんな自由があり、いつ、どんなときでも、自分の好みや気持ちの赴くままに、自分ひとりで出かけていく自由があったのだそうだ。そうしたことを再び『ポパイ』に書いた。
僕がフレデリック・バーセルミを最初に読んだのは、『ムーン・デラックス』だった。現代の、まさにいまのアメリカの生活環境を風土と呼ぶならば、バーセルミの作品のなかには、多少は偏ったかたちにせよ、風土性がはっきりとある。その風土の描写はたいへんにうまい。僕が読んだ四冊の作品の風土はみな同じだ。そしてそのような舞台のなかに登場してくる人物たちも、同一人物たちではないけれど、見わけのつかないほどによく似た人たちばかりが、どの作品にも登場してくる。
ローレンス・ノーモフの『泣いている女たちの夜』は、構造的にはたいへん面白い小説だ。ひと組のまだ若い夫婦を接点にして、それぞれの両親というふた組の夫婦の関係を描いている。ひと組の夫婦という基本的な単位の関係が、いかに多くの問題の発生地点であることか。夫婦そして親子のあいだでは、およそありとあらゆる衝突や葛藤が絶えることなく起こってくる。
エリック・ラーセンの小説『アン・アメリカン・メモリー』は、一八八一年から一九七五年にまたがる、中西部におけるひとつのファミリーの三代記だ。祖父、父親、そして自分と続く三代のうち、自分という三代目の男性が、一人称ですべてを語っていくが、父親と祖父に関する記述が大部分を占めている。その「私」にとって父親は謎のままだ。なにを考えているのか、なにをしたいのか、どんな世界を思い描いているのか、ひとつとしてわからない。そしていまの「私」は、たいへんに頼りなく、はかなげだ。時代の進展とともに、父親はどんどん存在感の希薄な人になっていくという原則のようなものが、社会的に機能しているのだろうか。
一冊の小説が、ひとりの人物の肖像画を描くことを目的とし、それに成功している例が、外国にはたいへん多い。チャールズ・ポーティスの『ノーウッド』もその成功例のひとつだ。だからこそ評判になり、いまでも引き合いに出して語られる。主人公のノーウッド・プラットはもと海兵隊員。テキサス州の小さな田舎町ラルフにしっかりと両足を下ろし、フィロソフィーと呼んでもよいものを持っている。物語は、彼がラルフからニューヨークへいく道中の出来事を中心に小さなエピソードを積み重ねながら描かれている。
ポール・オースターの『ニューヨーク三部作』は、どのストーリーも謎解きのような物語として語ってある。読みはじめると途中で中断するのがたいへんに惜しい気持ちになる小説だ。しかしひと息に読みとおすには量がありすぎる。ふつふつとたぎる純粋なエモーションを、透明感のあるくっきりと正確な、端正で深みのあるリズムをともなった理性の力へと、オースターの文章は転換し、その力で読む人を引っ張り続ける。
デイヴィッド・レーヴィットの『失われしクレーンの言葉』の主人公フィリップ・ベンジャミンは、自分がゲイであることを両親に隠しながら、理想的な恋人と幸せな生活を送っている。やがてフィリップは、ごくあたりまえのことのように、両親にカミング・アウトするが、そのことが彼らに葛藤を引き起こす。タイトルの「起重機の失われた言葉」とは、この物語の脇役の女性にまつわるエピソードとして登場するが、この小説のテーマとも関わっている。
アメリカという文化は、完全に成熟をとげた男たちが、仕事をする文化だ。子供が子供としてそのまま存在できる場所はない。成長しないことには、自分の居場所がどこにもないから、少年少女たちは完全に自前で成長と取り組まなければならない。しかも、他の人と同じではなく、本当にその人として、他の誰とも大きく異なった存在として、しかも社会にとって有用なように、大人にならなくてはいけない。このように考えてからグロウイング・アップ小説を読むと、じつに面白い世界がそこにあることがよくわかる。
2022年8月2日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ
次の記事へ