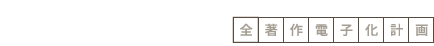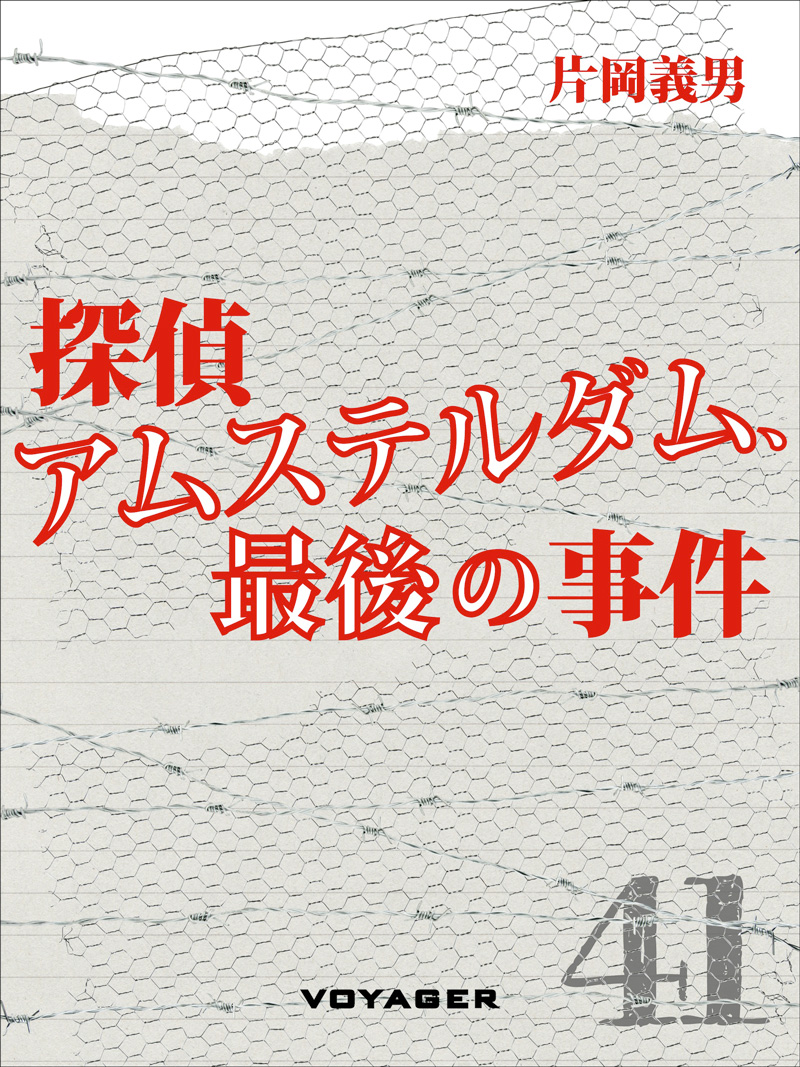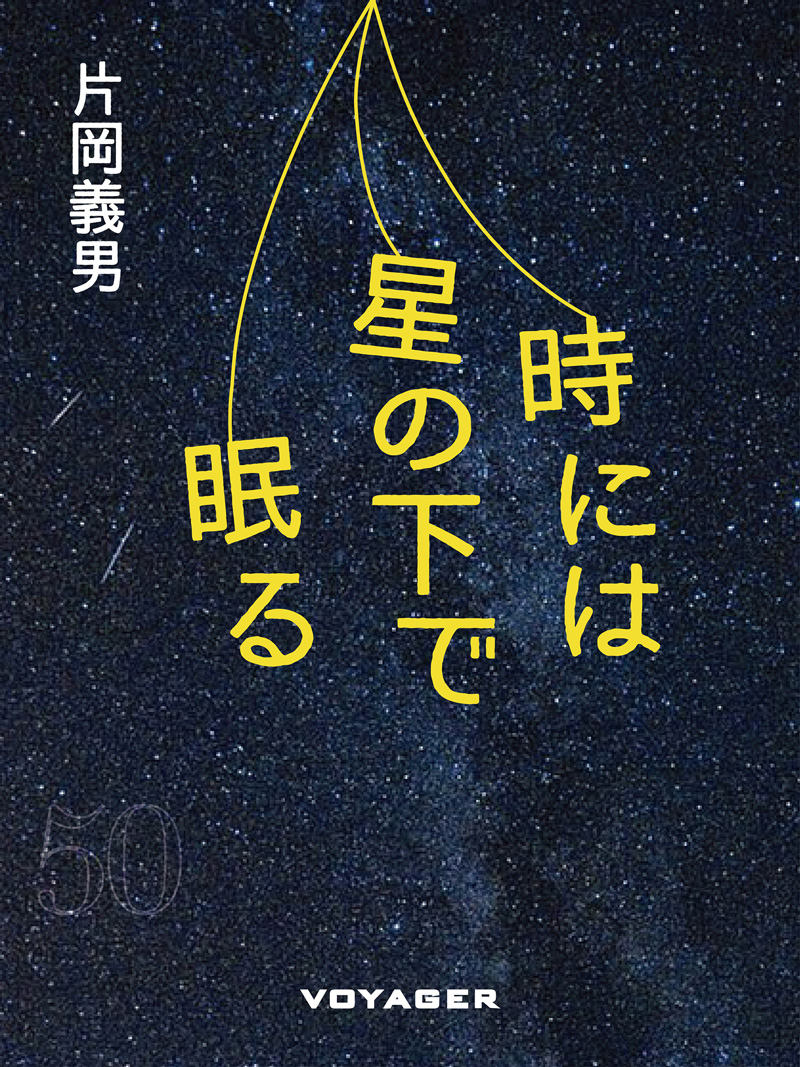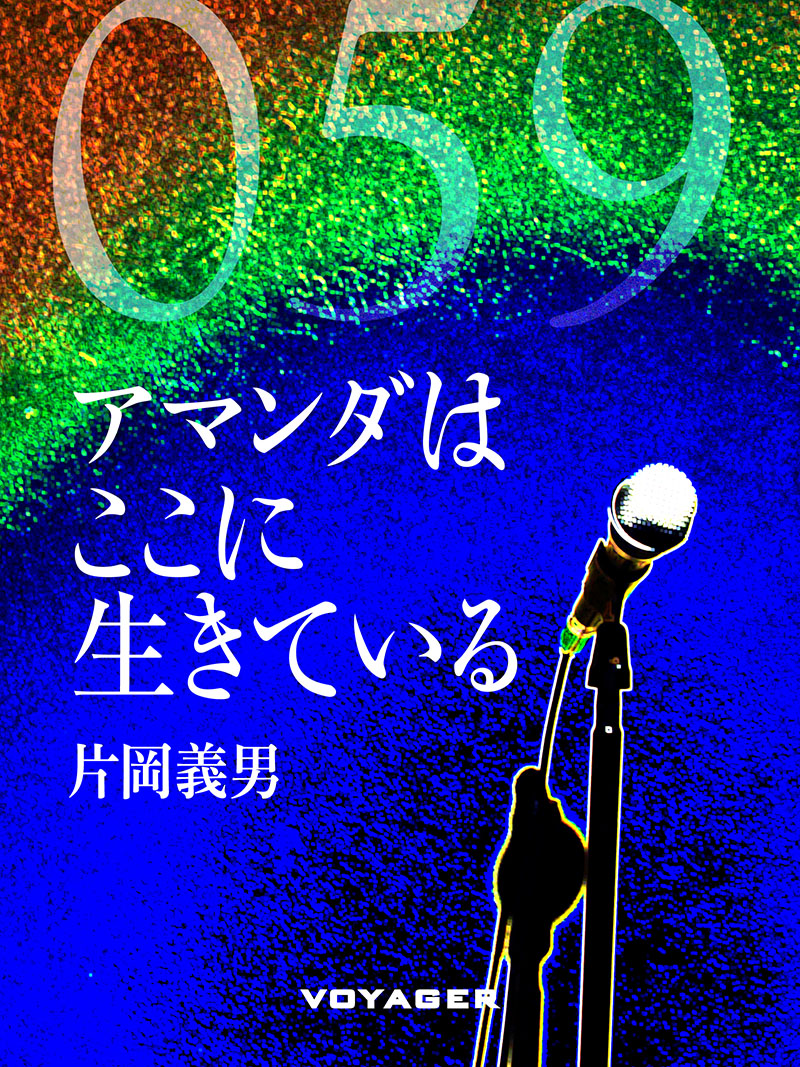特集「探偵 アーロン・マッケルウェイ シリーズ」
青いチェックのカウボーイ・シャツに、着古したリーヴァイスのジーンズ。腰には手作りのガン・ベルト。ジープ社製の四輪駆動ピックアップ・トラック、ホンチョを駆り依頼人の元へと赴く21歳の私立探偵アーロン・マッケルウェイ。片岡義男の作品ではほぼ唯一と言ってよい、同一のキャラクターが主人公のこのシリーズ作品が最初に発表されたのは1976年。その後1984年までの間に全11篇が断続的に雑誌『ミステリマガジン』(早川書房)誌上にて掲載されました。
「事件が大きな山を超え、ほぼ解決したところへ、ふと、風のように現れるという運命の探偵」「当事者全員に対して共感は充分にするけれど、事件の解決にむけて自分が手を下すのは、必要最小限の範囲内」と設定された、ちょっと不思議な、その存在自体が架空の若き探偵、アーロン・マッケルウェイが関わるさまざまな事件と、そこに見えてくるさまざまな人間模様をご堪能ください。
※作品をすべてお読み頂くためには会員登録が必要です。
『ハンバーガーの土曜日』
人生は野菜スープ、でなく、時に冷たいハンバーガー。弱冠21歳の若き私立探偵アーロン・マッケルウェイの初登場作品。ガン・ベルトを携えた、保安官さながらのいでたちで彼は人々のさまざまな依頼に応える。本作でアーロン・マッケルウェイに与えられた使命は白血病で自らの命を絶った女性からの伝言を伝えること。しかし伝えるべきその相手もまた、悲しい運命にあった。心優しきアーロンが共有するのは共に味わう冷えたハンバーガーだけだ。
『旅男たちの唄』
男は消えて、唄が残る。その唄を男たちは愛し、女たちは……人違いで射殺されてしまった不運なカントリー・シンガー。彼が作ったヒット・ナンバーについて、それがどんな状況でどうやって作詞作曲されたかを調べてほしいとかつての恋人が依頼する。アーロンが調査の旅で出会う男たちはことごとくその唄を愛し、対して女の口から出る言葉は「身勝手」「負け犬」といった言葉ばかり。おそらくは依頼主の彼女もまた……。女と男の心の平行線をベースにしたビターな一篇。
『ミス・リグビーの幸福』
なぜ? と問わずにいられない人々の向こう側で、「彼女」たちは一人で事を起こす。世間から見れば、何不自由ない生活をしているように見える女性に起こった突発的な悲劇。悲劇は新聞記事になり、その記事を目に留めた女性からアーロンは仕事を依頼される。依頼主の彼女は記事に出ている女性と同じ年齢で、仕事も同じだった。アーロンは記事の女性の素性調査を進めていくが、その途中で依頼主である彼女に電話をすると……。彼女が突き進んだ道とは……?
『ダブル・トラブル』
男・マッケルウェイ、21歳。素っ裸の探偵稼業に勤しむ。人はそれぞれ裸の一個人でありつつ、職業を持つことによって、社会から認知された存在になる。しかしその職業から微妙に逸脱し、あるいはそれがボーダーレスのゆらぎの中にある時、小説を推進する出来事が起動する。今回、アーロンが巻き込まれるトラブルはカリフォルニアに巣食う犯罪によって起きたもの。今度の探偵は、文字通り「素っ裸」だ。
『探偵アムステルダム、最後の事件』
「エゴの殻は、銃弾でないと、破れない」。善悪の彼岸へ向かって、最後の仕事が唐突に終わる。この短編での主人公は、アーロン・マッケルウェイよりもむしろ彼が所属するアムステルダム探偵事務所の上司であるジョニー・アムルステルダムだ。2つ重なった三角関係をめぐり、メッセージを届ける依頼を受けたジョニーとアーロンはさっそく仕事に取り掛かる。しかし、アーロンは常に出来事に遅れ、ジョニーはどんどん先に進み、ついに決定的な途方もない「ケリ」をつける。私立探偵の権限をはるかに逸脱したその行為の、突発性にはただただ途方に暮れる。
『ムーヴィン・オン』
ミス・マージョリーの信条はただ一つ。「動いていくこと」(ムーヴィン・オン)だけ。この物語でアーロンは、パトロールマンからヒッチハイカーの老婦人を乗せてやってくれと頼まれる。老齢でありながらヒッチハイクで長距離を移動しようと試みる彼女はやはり並の女性ではなく、今は亡き伝説のカントリー・シンガーの恋人だったことが判明する。道中、細心の敬意を払いつつ、昔語りに耳を傾けるアーロン。そしてその彼女の話から、それが単なる昔日の回顧ではなく、現在をムーヴィン・オンする力そのものであることを学ぶ。
『時には星の下で眠る』
互いの明日が、まるで違う道になろうとも、人は時に、星の下で眠る。この物語でのアーロンは、ついてない。不意にとばっちりをくらう羽目になるのだ。しかも二度も。二度とも銃弾が飛び交うハードな状況だ。とある偶然から、クルマを運ぶ役割を引き受けたかと思うと友人が犯罪に手を染め、手錠につながれる場面に居合わせることになる。生きていくことのままならなさ、誰もが明日をも知れぬ存在であることをアーロンは身を持って知ることになる。
『ビングのいないクリスマス』
戦友、という間柄の2人の男にとって、悲劇は戦後になってからやってくる。今回のアーロンへの依頼は、行方不明になっている男を探し当てることだ。辻褄の合わない謎の絵葉書と、男に婚約者がいたことだけを手がかりに、女性探偵のアストリッドと助手であるアーロンは調査を開始する。しかし残念ながら何の進展も見られない。行方不明の男は原爆投下に係わる仕事をしており、その戦友を訪ねても何の手がかりも得られない。だが、作者はあっさりとこの失踪の謎を読者に明かす。最後まで知らないのは物語の中の探偵2人だけ、というトリッキーな一篇。
『アマンダはここに生きている』
「ただのラブ・ソング」と「アナザー・ラブ・ソング」。月明かりのハイウェイを、巡業用バスが走っている。運転しているのはアマンダ。女性として、妻として、母として完璧な彼女に、カントリー・ミュージシャンの夫は、あらためて惚れ直している。その結果、20年前のヒットに並ぶ傑作「アナザー・ラブ・ソング」が生まれた。だがしかし、巡業やカントリーを取り巻く様々な人々がすべて幸福なわけではない。だからこそ、アマンダの充実した人生は輝いている。事件らしい事件の起こらない地味な一篇ながら、読後に深い余韻を残す作品。
『駐車場での失神』
突然のシンクロニシティなんとも不思議な短篇である。そして、小説としての不可思議な、割り切れない、ニュアンスに富んだ魅力が充満している作品。片岡義男は、なぜ? ではなく どのようにして? を書く作家である。とても起こり得ないようなことがなぜ起こったか、ではなく、それが確かに起こった、ということが重要であり、突発的だろうがアクシデントだろうが、それがどのようにして起きたのかが問題だ。そして交錯する生と死の傍らに、まるで中間地点のように失神がある。
『いつか聴いた歌』
2人の女性に託された歌不幸な亡くなり方をした父親から唯一の財産として娘は歌を贈られた。長じてカントリー歌手になった娘は父の曲に自ら詞をつけて歌うようになる。ところがその歌を、どうやらもう1人、歌っている女性がいるらしい。自分しか知らないはずの歌なのに、なぜ? アーロンはこのミステリーの謎解きを託される。もう1人の女性はいったい誰なのか。全篇、電話による会話だけで進んでいく、ちょっと哀切さの漂う物語。
■ もっと片岡義男を知るために
-
『日本語の外へ』(インデックスページ)
1990年8月に始まった湾岸戦争をアメリカのテレビ放送だけで追う、という試みから始まる本書は、アメリカとは何か、その母国語である英語とは何か、そして日本語とは、日本とは何かを解明していきます。5年の年月をかけて書き下ろされた長編評論。1997年に筑摩書房から刊行。その後2003年に角川書店で文庫化。2024年12月には、ちくま文庫から復刊されています。
【特集】『僕は珈琲』
若き日、フリーランスのライターとしていくつもの雑誌記事を抱えていた片岡義男は、東京・神保町にある複数の喫茶店をハシゴしながら原稿を執筆していたといいます。コーヒーを心から愛する片岡義男による、コーヒーにまつわるエッセイの数々をどうぞ。
【特集】僕の戦後、あなたの戦後
太平洋戦争終結間近の1945年8月6日、片岡義男は疎開先の岩国市で広島に投下された原爆の光とキノコ雲を見ており、その日を片岡は「自身の物心のついた日」と定義しています。少年の日の片岡に多大な影響を与えた戦後の日々や、その後現在に至る日本社会について考察したエッセイを集めました。
【特集】「作家は、なぜ写真を撮り続けるのか」
写真家としての顔も持つ片岡義男は「僕が書く小説は写真だ」と言います。小説家である彼は写真についてどう考え、捉えているのか。いくつかのエッセイから読み解いていきます。
『言葉を生きる』(インデックスページ)
作家・片岡義男の独特の文体や思考はどこから来ているのか……。著者自身がその誕生から少年期、青年期を経て作家として歩み始めるまでのこと、そして書くこととその周辺を綴った自伝的エッセイです。
Previous Post
Next Post