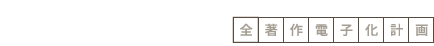連載エッセイ「そしてその他の物語」より10作品を公開
雑誌『Free & Easy』(イースト・コミュニケーションズ)にて2010年7月から2013年3月まで連載されたエッセイ「そしてその他の物語」からの10作品を本日公開いたしました。本編に挿入されている写真と共にお楽しみください。
初夏のある日の午後、千代田区神保町の古書店の店先で、僕は日本の古雑誌を何冊か見かけて興味を惹かれ購入した。1963年頃のもので、当時の日本女性の結婚適齢期と言われた層を主たる読者として想定した家庭・婦人雑誌だ。最新のファッションを伝えるカラー・ページには、すぐあとの時代に一億総中流と呼ばれることになった人たちの、ちょっとしたお出かけの、ちょっとしたおめかしのスカートとパンプスをはいた女性の写真がある。いまでもどこかの町を歩いていそうな気もするが、タイトぎみなスカートの裾の膝下ぶりは、さぞや歩きにくかったのではないか。ファッションとは、謂われのないままに引き受けさせられる、さまざまな拘束や制限なのだ。それ以上に当時の日本そのものをそっくりそのまま体現しているのは、僕が材料に使ったその雑誌のカラー印刷だ。この当時のカラー印刷の技術は、すでにとっくの昔に遠く追い越され、捨て去られ、したがっていまはもうどこにもない。
(『Free & Easy』2011年5月号掲載)
立春を2、3日過ぎたある日、アメリカのニュージャージー州から航空便が届いた。昔のとあるアメリカ映画のDVDをインターネットで探し、注文してそれっきり忘れていたものだ。中に入っていたDVDを取り出した僕は、白いヴィニールの封筒に興味を惹かれた。なんの変哲もない、ごく平凡で標準的な作りの、実用性だけで成立しているような封筒で、表に税関の申請書など必要な書類が接着してある。その紙の右下に、エア・メール/パー・アヴィオン(Air Mail /Par Avion)という言葉があり、その言葉を中心にして、僕の想像力の中に一枚の写真が閃いた。これは写真に撮れる、そして撮ればそれなりを少しだけ越えて面白くなるはず、という閃きだ。撮影された写真からは、日本らしさのようなものを一切感じない。そのかわりに、グローバルな広がりのなかで希釈されきってはいるけれど、それでもなお、形と内容を保っている英語圏とその周辺、という種類の外国らしさを、僕は感じている。
(『Free & Easy』2011年6月号掲載)
アメリカの写真家ウィリアム・ユジーン・スミスは、世界中でそれ以後の写真ジャーナリズムに計り知れない影響を残した写真を雑誌『ライフ』に連続して発表した。1954年の終わりに『ライフ』との関係を終わらせたスミスは、1955年の2月にはマグナムの一員となり、同年3月、ピッツバーグに移り住んだ。鉄鋼産業の町として知られたピッツバーグの、創設200年を記念する出版物に写真と文章を寄稿するというのが最初の目的で、滞在予定は3週間だった。しかし滞在は1年におよび、56年、そして57年にも、スミスはピッツバーグを訪れて写真撮影を行った。その結果生まれたのが、17,000点の白黒の写真だった。白黒の写真は光とその影であり、両端を明確に抑えるなら、あとはその中間のどこででもいいから本質を求めてさらなる深みへともぐり込めばいい。光と影によって膨大に集積された対位法を、錯綜する交響曲的で巨大な叙事詩へと、スミスは展開しようとした。
※マグナム(Magnum Photos)は、世界を代表する国際的な写真家のグループ。
(『Free & Easy』2011年7月号掲載)
僕は1992年にマガジンハウスから、『日本訪問記』という題名の本を出版した。僕にとっての最初の写真集だ。薄い本だが、すべて横画面のカラー写真が300点収録してある。絶版となって久しいから、もはや存在しないも同然の、その意味では珍しい本だ。外房。箱根。郡上八幡。京都。奈良。倉敷。下津井。児島。明石。神戸。淡路島。尾道。門司。下関。小諸。清里。東京。撮影地は以上のような場所だ。1991年の1年間、オリンパスのOM-1という一眼レフに、35-70ミリという2倍ズームのレンズを使って撮影した1万ショットから選んだものだ。このレンズは、日本の地方都市の主として駅前あるいはその周辺の町なみに、たいへん好ましく適合した。久しぶりに『日本訪問記』のページを繰りながら去来するのは、もはやどこにもない日本だろうなあという、つくづくとした喪失の感慨だ。わずか20年前なのだが、もはやそれはどこにもなく、再び現れることは絶対にない。
(『Free & Easy』2011年8月号掲載)
昔からあるキャンディの商品名で、アメリカの庶民にはいまでも親しまれているトゥーッツィー・ロールというソフト・キャンディをロリポップに仕立てた、トゥーッツィー・ロール・ポップスというキャンディがある。1本のロリポップの長さは11センチ。直径と厚みがともに3センチほどの球体であるロリポップに、細い把手が突き刺さっている。包み紙は、レッド・ホワイト・アンド・ブルーという、愛国の証の配色だ。だから例えば愛国的なパレードを見物しながらこのロリポップを口にくわえてしゃぶっていると、愛国的な感情はおおいに増幅されて好ましい、ということなのだろう。第二次世界大戦の太平洋戦線あるいは欧州のあちこちで、敵だか味方だか判別がつきかねるとき、アメリカの兵士たちはその相手に向かって「セイ・ロリポップ(ロリポップと言ってみろ)」と要求したという。味方なら過不足なしの正しい英語風の発音で、ロリポップと言えるはずだ、もし言えないのであれば、その相手はおそらく敵だろう、という判断だ。
(『Free & Easy』2011年9月号掲載)
1945年6月、のちにアメリカの大統領となった俳優のロナルド・レーガンは、アメリカ陸軍の第1モーション・ピクチャー・ユニットという部署で大尉を務めていた。レーガンは、若い兵士デイヴィッド・コノヴァーに、戦争遂行のために仕事をしている若い女性たちの姿を写真に撮るという任務を与えた。コノヴァーが赴いたカリフォルニアのレディオプレーンという会社には、19歳のノーマ・ジーン・ドウアティが働いていた。のちにマリリン・モンローとなる女性だ。彼が撮影したノーマの写真は、イーストマン・コダックの担当者が現像しプリントした。「この女性はいったいどこの誰だい」と、熱意に満ちた興味を露わにした最初の人はその担当者だった。写真機のレンズとフィルムとによって作り出されていったマリリン・モンローの物語は、こうして始まった。映画女優としてのマリリン・モンローには代表作はない、という意見はさほど厳しいものではない。しかしスティル写真のモデルとしては、その生涯のなかで撮られたすべてのショットが、どれもみな代表作だ、と僕は思っている。
(『Free & Easy』2011年10月号掲載)
1962年に発行された一般向けの住宅雑誌。想定された主たる読者は、庭つき一戸建てへの願望を胸に熱く抱えていた一般の人たちだった。庭つき一戸建てはいまやあらゆる種類の抑圧装置だが、当時にあっては、それは明るい希望の根拠地だった。表紙を含めて全200ページ。1ページずつ眺めていくと、心の底から泣けてくる、という心理状態となる。この頃の日本は今よりはるかに洒落ていた、と断言していい。それに何よりも明るく開放的だ。日本が現在の究極と言っていい状態にまでよじれたのは、いつの頃からだったか。1962年から10年後の1972年の日本はもう駄目だった、と僕の体の中にある記憶が言う。ということは、1960年代の後半、少なくともその終わり近くには、それまでの日本を根本的に変える大改革を実現しておくべきだった。しかし企業を中心に誰もが自分の都合を追求した結果、バブルをへて失われた20年のあと、企業も行政も何の役にも立たない会議の連続のなかに退行し、そこから出て来ない、という状況の中にいる。
(『Free & Easy』2011年11月号掲載)
ずいぶん前、『食堂とオートバイ』という本を作ろうとした。オートバイで日本中を旅する途中、屋号に「食堂」というふたつの漢字が使ってある店を見つけたら、そこでオートバイを停め、その店の全景と料理、店主とその奥さんを写真に撮り、本を作るんですけどその中に使っていいですか、と訊いて承諾を取りつける、というものだ。オートバイ雑誌の連載でどうか、というところまで行ったがそこで沙汰やみになった。最近になって、直訳すると『皿と皿』になる実に面白い本を、ひとりの美女が僕にくれた。アメリカのロードサイド・ダイナー、つまりハイウエイ沿いに建つ食堂をぐるっとひと回り走破し、ダイナーで食事をし、その料理とサーヴしてくれたウェイトレスも写真に撮り、右ページにはウェイトレスのポートレート、そして左ページにはそこで食べた料理の写真を配して、1冊の見事な本にまとめ上げたものだ。これは素晴らしい。こんなことを思いつき、実行し、1冊の本を現実に作ってしまう人が、アメリカにはいるのだ。
(『Free & Easy』2011年12月号掲載)
彼女は北国の大人の美女である。彼女はオートバイに乗る人だ。今は確かハーレーに乗っている。何年も前、彼女のオートバイがハーレーになる以前、彼女から僕のところにカラー写真のプリントが届いた。当時の彼女の、おそらくヤマハだったろう、愛車のヘッドランプとその周辺を、何げなく撮った写真だった。構図、つまり切り取りかたが面白いので、僕はその写真をずっと保管しておいた。その3年ほど前に、コーヒーの写真が届いた。オートバイのプリントの下に、コーヒーの入ったカップふたつの写真がある。これも切り取りかたを面白く思った僕は保管しておいた。オートバイの写真が重なっている左上には、コーヒー豆の缶が写っている。この缶とマークには見覚えがある。小田急線・千歳船橋駅から近い商店街に、ホリグチというカフェとコーヒー豆の店がある。その店の缶だ。忘れていたことを僕は思い出す。そうだ、このコーヒー缶は、そのなかにホリグチのコーヒー豆を四百グラムほど詰めて、僕が北国の美女に送ったものだ。
(『Free & Easy』2012年1月号掲載)
ブルース・スプリングスティーンのCD『ザ・プロミス』。パティ・スミスのCD『イースター』。そしてジェイムズ・エルロイの『ビコーズ・ザ・ナイト』という題名の小説。この3点セットは、Because the night という言葉でつらぬかれている。『ザ・プロミス』の中には Because the night という歌がある。良く出来ている、と言っていい。パティ・スミスの『イースター』の中にも『ビコーズ・ザ・ナイト』が収録されている。スプリングスティーンの歌詞とは、ほんの一部分が異なっているだけだが、おそらくそれ故に、パティのCDでは彼女はこの歌の共作者としてクレディットされている。曲は平凡なものだと僕は思うが、彼と彼女を聴きくらべると、パティの方がいいかな、という判定になる。そしてスプリングスティーンあるいはパティ・スミスの『ビコーズ・ザ・ナイト』を聴いたジェイムズ・エルロイが触発され、そこから生まれた刑事ロイド・ホプキンズのシリーズに同じ題名をつけた、という可能性は推測としては成立する。
(『Free & Easy』2012年2月号掲載)
2025年1月24日 00:00 | 電子化計画