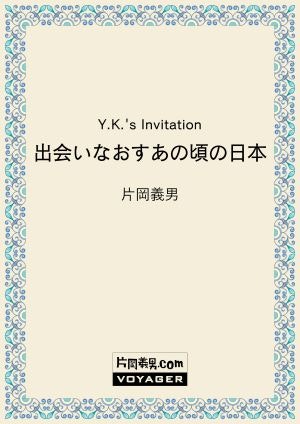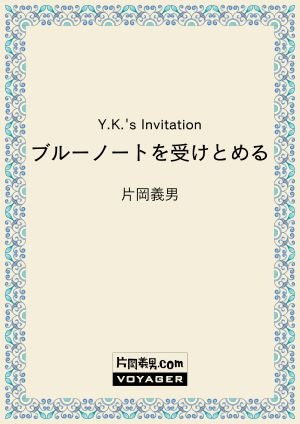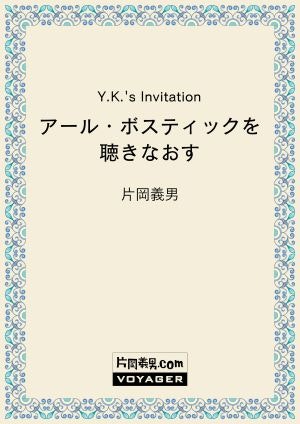音楽エッセイ『Y.K.'s Invitation』、小説『ドノヴァン、早く帰ってきて』など19作品を公開
音楽エッセイ『Y.K.'s Invitation』11篇、『ドノヴァン、早く帰ってきて』など小説2篇、連作詩『より良いことを選択しながら』から後半の5篇、ショートストーリー『彼とぼくと彼女たち』〈番外三篇〉の計19作品を本日公開いたしました。
ドロシー・ホルストマンの『カントリー・ボーイよ、心のたけを歌いなさい』は、1975年からさかのぼること半世紀という期間のなかから、カントリー・ソングの名曲や傑作を300曲以上選び出し、その歌がいかにして作られたか、作った当人からそのときの状況や創作のきっかけなどを直接に聞き出しまとめたものだ。あの名曲が、この傑作が、こんなふうにして作られたのかという感銘には、底の知れない深さがある。カントリー・ソングは、アメリカ的なポピュラー音楽のなかでも、たいそう特殊にアメリカ的な大衆音楽、という理解のしかたが一般的だろう。しかし、この本を読めば、そしてそこに採録されている歌の数々をきちんと聴くなら、そのような理解はあっけなく霧散する。
(『芸術新潮』/2009年2月号掲載)
アメリカのもので最も強く心に残っているものはなにですか、というような質問をされたなら、それはアメリカの英語です、としか答えようはないのだが、何か具体的なイメージやかたちを持ったものをあげるなら無理を承知で、それはロイ・ロジャースです、と僕は答える。6歳から10歳くらいまでの期間、1年に10本ほどのロイ・ロジャース西部劇映画を観ていた。ロイとデイル・エヴァンスは1944年に共演して知り合い、47年にふたりは結婚して夫婦となった。ロイは「キング・オヴ・ザ・カウボーイ」、妻のデイルは「西部の恋人」と呼ばれた。カウボーイとその恋人は、ともに見事に歌った。
(『芸術新潮』/2009年4月号掲載)
シャープス&フラッツというジャズのビッグ・バンドのリーダー、原信夫さんの「(自分のバンドは)いまがいちばんいい音だ」という言葉に強く惹かれた僕は、神奈川県座間で彼らのコンサートを体験した。素晴らしかった。世界のどこを探してもこんなバンドはない、と僕は確信した。日本にはこれひとつ、アメリカにはありっこない。結成されてから58年という長い歴史のなかで、進化し続けてついに到達した最高の地点に、シャープス&フラッツはあった。リーダーの言葉は正しかった。
(『芸術新潮』/2009年6月号掲載)
戦後すぐの日本に発生したジャズのブームのなかで、僕にとってもっとも印象が深いのは、ナンシー梅木だ。英語の歌詞で歌うときの英語に、少年の僕が違和感を覚えなかった唯一の歌手だった。忘れがたい理由のもうひとつは、オキュパイド・ジャパン(占領下の日本)を象徴し体現する、僕にとって唯一の人が、ナンシー梅木であるという理由だ。
「拳銃無頼帖シリーズ」で知られる赤木圭一郎の歌も素晴らしい。聴くたびに僕は深い感銘の底へと沈みきる。この時代の日活のスター男優には、歌う能力が要求された。どれか1曲を選ぶなら、それは迷うことなく「霧笛が俺を呼んでいる」という、同名の主演映画の主題歌だ。
(『芸術新潮』/2009年8月号掲載)
良く出来た美しい脚を、可能な限り広い面積で外に出してみせている女性歌手を、立ち姿で写真にとらえたジャケットのLP、というものを自宅にある1万枚のなかから探したら、3枚あった。ジュリー・ロンドン、コニー・ラッセル、ポリー・ポウドウェルだ。良く出来た美しい脚と優れた歌唱力とは、なかなか結びつかないのだろう。幸運にも結びつけばそこに噓はない。三人が三様に美人である事実は、良く出来た脚と優れた歌唱とに、ごく当然のことのようについてくる、おまけのようなものだ。
(『芸術新潮』/2009年10月号掲載)
ある日、CD店でビージー・アデールという初めて目にする名前を、僕の呑気な視線がとらえた。ある特定の時代のヒット曲を適当に12、3曲選び、編曲をほどこして演奏したカヴァー集が、LPの時代のアメリカにはたくさんあった。いまの時代のオリジナルCDでは、こういうのは珍しい。表題となっている「モーメンツ・トゥ・リメンバー」は、ザ・フォア・ラッズのオリジナルによって、高校生だった僕の心身に深く浸透していまもそのままだ。というような理由で、僕はこのCDを買って聞いてみた。
(『芸術新潮』/2009年12月号掲載)
12月半ば、平日の夕方、僕は銀座にいた。交差点のすぐ手前の楽器店では通行人たちに対してCDのデモンストレーションと販売が行われていた。スピーカーからは販売されているCDが再生されていた。その光景を見るともなく見ながら、僕は店の前を横切ろうとした。その瞬間いきなり、全身で受けとめたのは、忘れもしないブルーノートというジャズ・レーベルに1958年に録音された、ソニー・クラークのアルバム『クール・ストラッティン』のなかの「ブルー・マイナー」の一節だった。その曲の一節は突然、僕の全身に浸透し、感覚の内部全体を走りまわった。高校生そして大学生の頃、繰り返し何度聴いたかわからないあのジャズだからなおさら、こういうことが起きる。
(『芸術新潮』/2010年3月号掲載)
音楽は多様性の極みだ、と僕は思う。人間のもので音楽ほど、その種類がさまざまに存在するものは、他にないのではないか。そして時間的な奥行きは、人類の歴史の始まりまで届いている。何らかの形で音楽を主題にしたり材料にしている書籍もまた、音楽の多様性とその歴史の深さに呼応して、現在までに出版されたものの数は、無数と言うしかない。一般大衆向けの大量生産されたものに気持ちを惹かれることの多い僕は、LPやCDとともに、音楽書籍もしばしば買っている。新刊を丁寧に追いかけるのもいいが、古書という領域のなかでの発見は、順不同、領域混沌、まったくの偶然まかせの出会いなど、スリリングな要素がいくつも重なり合うから、僕は好んでいる。
(『芸術新潮』/2010年5月号掲載)
ある日の午後、喫茶店で友人と世間話をしたあと、僕はレコード店へ向かった。友人もついて来た。ほどなく彼が僕のかたわらへ来て、3枚のLPを僕の目の前に並べた。アメリカの女性ジャズ・ヴォーカルのLP3枚だった。ジョーン・メリル。エイプリル・スティーヴンズ。ジェリ・アダムズ。聞いたことがあるような、ないような名前の3人だ。数日後、3枚とも聴いてみた。3人の歌声はそれぞれに素晴らしいものだった。半世紀以上も前のある日あるとき、アメリカのどこかで、演奏をバックにして彼女たちが歌った歌声が、LPの音溝の中にいまも眠っている。その歌声を再生して現在に蘇らせると、僕を中心点として、反作用の法則が美しく成立する。
(『芸術新潮』/2010年7月号掲載)
秋吉敏子さんという名前を僕が最初に聞いたのは、米軍放送AFRSでの音声としてだった。片仮名で書くと、トシーコ・アキヨーシ、とでもなるだろうか。それから数年後、高校の3年生だった僕に、近所に住んでいたジャズの好きな年上の女性が、1枚のLPを見せてくれた。1956年にボストンに渡った秋吉さんが、その年ニューヨークで録音した2枚のLPのうちの1枚、『ザ・トシコ・トリオ』という作品だ。かつてアメリカ人の音声として受けとめたトシーコ・アキヨーシとはこの女性なのか、そしてこういう字を書く名前なのか、と僕は思った。
(『芸術新潮』/2010年9月号掲載)
ラ・ヴァーン・ベイカーの代表作とされている「トゥイードル・ディー」を僕が最初に聴いたのは、1954年から55年にかけての冬だった。間奏にほんの数小節、テナー・サックスソロがある。これで僕はリズム・アンド・ブルースのテナー・サックスというものに目覚めた。自分のテナー・サックスを自分で吹いて音を出したのは、それからおよそ10年後の26歳の頃だった。僕をこの上なく刺激したものはたくさんあった。中でも僕を強力に捉えたのは、たまたま聴いてみたアール・ボスティックの「ブルー・ダニューブ」という演奏だった。原曲は日本でもかつてはよく知られていた、有名なあの曲だ。
(『芸術新潮』/2010年11月号掲載)
1968年に三条美穂名義で「ミステリマガジン」誌に寄稿された、ブラック・ユーモア短編小説。陽気でふくよかなヒロインの京子は、夫の徹からもっと痩せてくれと言われる。しかもそれは期限つきだった。徹には彼なりのれっきとした理由があるのだが、それを京子に明かそうとはしない。京子は以前にもダイエットを試みており、できればその辛さを再び味わいたくはない。しかし痩せることを迫る徹の言葉に真剣さを見て取った京子は、ひとつの決断をする。ちなみに二十三貫五百八十匁は換算すると約88.5Kg。
(『ミステリマガジン』/1968年10月号掲載)
1969年、本格的な小説家デビュー以前に、片岡義男が翻訳の仕事で使っていたペンネーム「三条美穂」名義で、1969年に『ミステリマガジン』誌に寄稿した短編小説。ベトナム戦争から帰還した青年ドノヴァンは、4年間待たせていた恋人ジャニスと会うためにオクラホマ州のある町にやってくる。しかし彼は戦地に届く彼女の手紙の変化に何かを恐れていた。そんな彼を待っていたものとは……。
(『ミステリマガジン』1969年7月号掲載)
月刊誌で公開されたもの、片岡義男.comで公開された作品など、自身の書いた短編作品のタイトルをできるだけ時間順に列挙したものだ。列挙されると、それを観察することが出来る。観察していると、さまざまな感想を得るはずだ。その感想のなかに、僕がかつて短編小説の題名として使った言葉が、ごく短い時間、よみがえる。題名はまだたくさんある。いくらでも作れるのではないか。題名だけを作っていく、という試みをいま思いついたところだ。
(『現代詩手帖』/2019年3月号掲載)
自分が書いた小説の会話から、部分的に文言を無作為に切り取り、無作為にそれらを百五十行にわたってならべていくなら、それは見た目には詩であり、読んでいくならなんらかの感銘のようなものを受けるのではないか、というアイディアはなかなかいい、と僕は思った。夕食の席でそれについて語ったら、ぜひ試みたいです、と篠原恒木さんが言った。だから彼にまかせ、すぐに出来上がったものを見たら、それはまったく無作為ではなく、恣意に満ちたものだった。
(『現代詩手帖』/2019年5月号掲載)
『くわえ煙草とカレーライス』という短編集は2018年の6月に刊行された。7つの短編が収録してある。この7つの短編から、会話の中の言葉だけを部分的に拾い出し、その順番にならべていく、ということを僕は思いついた。7篇あれば充分だろうと思ったのだが、最初の1篇だけで間に合った。このような試みは、少なくとも書いた当人の僕にとっては、初めての試みだ。じつに興味深い作業となった。
(『現代詩手帖』/2019年7月号掲載)
この連載の6回目で、いつも乗る小田急電鉄の電車の中で見ることの出来る、主として広告のコピーを採取した順に並べてみる、という試みを僕はおこなってみた。一回だけでは物足りない、という思いを肯定に変えるなら、二回目を試みるほかない。だから僕はそのとおりにしてみた。採取を始めたのは4月のなかばであり、採取を終わったのは7月のなかばだった。小田急の各駅停車の電車のなかで、これだけの言葉に接することが出来る。順番を意図的に変えることは、おこなっていない。
(『現代詩手帖』/2019年9月号掲載)
『アメリカ映画作品全集』という本がある。1972年にキネマ旬報社から刊行された。19458月15日から1971年12月31日までの期間に、日本で公開されたアメリカ映画すべての情報を収録した本だ。ただ、僕がしばしばそうであるように原題名だけを知っている人が、日本で公開されたときの題名を知る、というような使いかたは出来ない。この本の中から、気になる日本語題名を、あいうえお順にならべていくなら、その全体は詩になるのではないか、とあるとき僕は思った。
(『現代詩手帖』/2019年11月号掲載)
ボストンにあるイースタン・マウンテン・スポーツというアウトドア用品店から、メイル・オーダーで買った2人用のテント。今年の夏は早くに終ってしまったが、秋もキャンプには最適な季節だ。キャンプに付き合ってくれることになった女性は、キャンプもテントも寝袋もはじめての体験だった。
※晶文社から1983年に発行された『彼とぼくと彼女たち』はその3年後、新潮文庫として発売されたが、全40篇のうち5篇は未収録となった。そのうち2篇はエッセイ集などに収められているが、どこにも収められなかった3篇(22、26、29章)をまとめて電子版として公開。
(『彼とぼくと彼女たち』晶文社/1983年)
2024年3月29日 00:00 | 電子化計画