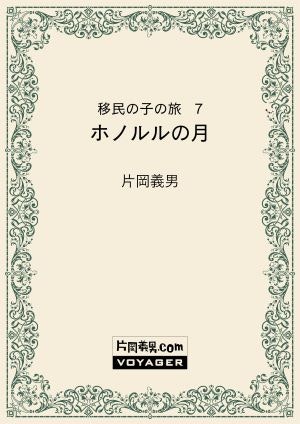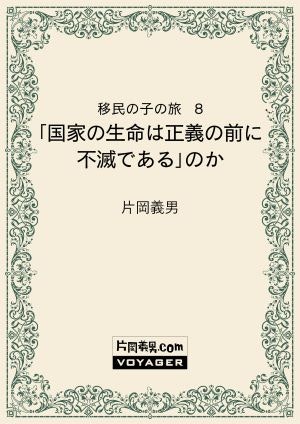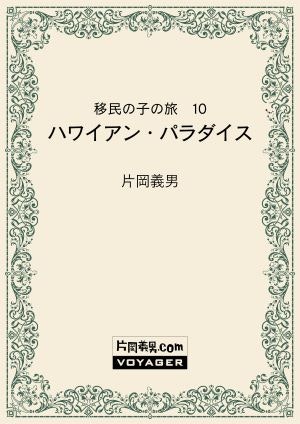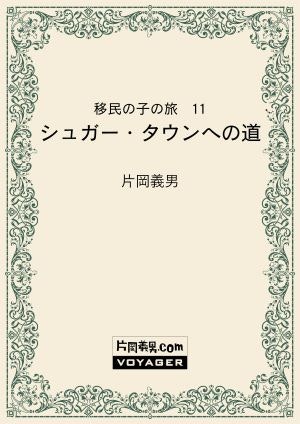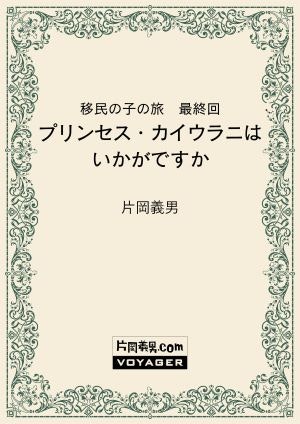エッセイ『移民の子の旅』6作品(第7回〜最終回)を公開
『ミステリマガジン』(早川書房)に1975〜76年にわたって連載された『移民の子の旅』からの6作品を本日公開しました。なお、『移民の子の旅』の連載第1回から第6回まではこちらからお読みいただけます。
フレッド・ローレンスが1926年に作詞・作曲した『ホノルル・ムーン』という歌がある。覚えやすいメロディで雰囲気を出すことができるので、今でもよく演奏され歌われているスタンダード・ナンバーのひとつであるに違いない。ホノルルにちなんだ古い歌としては、他にも『ホノルル・ハネムーン』『ホノルル・フラ・ホリデー』『ホノルルの瞳』などがある。どの歌も当時のホノルルないしはハワイ全体が人に与えていた心地良い夢のような印象を、いったんまぼろしに転化させた上で、描いている。これらの歌の彼方に、ホノルルが見えてくるとするなら、そのホノルルとは、いったい何なのだろうか。自然地理学的なハワイ諸島の成り立ちや、白人たちによって発見されて以降の歴史をひもといてみても、ホノルルは常にその歴史の中心にあった。
(『ミステリマガジン』1976年2月号掲載)
1819年、ハワイを統一したカメハメハが没し、カメハメハⅡ世リホリホの代になった。それまでのタブー制度(カプー)が廃止されると共に様々な神も葬られ、ハワイは宗教のない国になった。1820年、アメリカのニューイングランドからプロテスタントの宣教師たちが、キリスト教を携えてやって来た。ハワイの「蛮人たち」を悪から救い、天国に導くためだ。ハワイそのものと深く関わりあうようになった宣教師たちがどうしても気づかずにはいられなかったのは、ハワイに有効な政治のシステムをつくりあげる必要がある、ということだった。1840年頃には、ホノルルに住んでいる白人の数は、このころ、千人をすでにこえており、ハワイ王国にとっての不安の種となっていった。ハワイは独立したひとつの国なのだということをアメリカ、イギリス、フランスに承認させるのがいちばんいい、と考えたハワイの酋長たちは、まずハワイ国憲法の草案づくりに着手した。
(『ミステリマガジン』1976年3月号掲載)
1847年、カリフォルニアで黄金が発見された。ゴールド・ラッシュがひきおこされ、人々は西へ向かって大きく激しく動いた。春と秋、年に二度の捕鯨船シーズンに港に入ってくるアメリカの捕鯨船は、いろんな形でハワイの人たちの経済を支える大きな中心になっていったが、1947年から'48年にかけては景気が良くなかった。仕入れた商品をかかえて困っていたホノルルやラハイナの商人たちは、ゴールド・ラッシュで急に人のたくさん集まったカリフォルニアに商品を送りこんだ。やがてハワイの商人たちは、土地への投資を始めた。だが、1851年にゴールド・ラッシュが終わると、ハワイにとってのカリフォルニアの市場は崩壊し、例えハワイがアメリカに併合されても、土地に投資した自分たちが借金の底から這いあがってくることはとてもできない、という考え方が一般的になっていた。土地に過大な投資をした人たちの中には、砂糖耕地の経営者たちもいた。
(『ミステリマガジジン』1976年4月号掲載)
昔のハワイアン音楽は、その演奏や歌に注ぎ込まれているあらゆる要素が、ぼくの知らない「昔」を感じさせてくれる。かつて存在し、すでに過ぎ去った「昔」ではなく、SF的な意味あいでの遠さを持った「昔」だ。この古いハワイアン音楽の中に、古き良きハワイをうたった歌がいくつもあるから驚きだ。「昔」の中に、さらにもうひとつ別な「昔」が、入れ子になっている。古き良きハワイは、かつて大昔には存在したかもしれない。しかし、その古き良きハワイについての歌をつくる人たちは、現実にはそのようなハワイを体験したことがなく、もし体験できるとすればこれから先だろうと、淡い期待をかけながら、古き良きハワイについて歌を作り、うたう。こういう状況のほうが、少なくともぼくには面白い。なぜなら、過ぎ去った良きものへの追慕の念は感情の浪費だが、これから自分たちの目の前に現出するかもしれない未曾有の良きことや良き状態に対して積極的に思いをかけるのは、新たなる感情の生産になるからだ。
(『ミステリマガジジン』1976年5月号掲載)
砂糖キビはハワイには野生で大量にあった。これを使って砂糖を作るという試みは、十九世紀の初めから何度も行われてきた。ハワイの砂糖はアメリカの西海岸で売ることができ、1871年にはハワイで生産された砂糖の輸出額が、すべての輸入物の額をこえた。しかし砂糖産業は、労働力が決定的に不足しているという問題に直面していた。1852年、中国からクーリー(苦力)がハワイに来たが、耕地での労働に対して、彼らは基本的に興味を持っていなかった。一方、アメリカと互恵条約を結ぶことで、ハワイの砂糖を関税なしで輸出することができるようになり、ハワイの経済的な繁栄も約束されるだろうということで、条約締結が早くからハワイのアメリカ人たちの間での関心事になっていた。19世紀末には、ハワイの砂糖はアメリカでの市場の10パーセントを占めるようになったが、労働力と砂糖耕地経営者の数は減少していった。労働人口が増えることを切に願っている点は、政府も砂糖業者も同じだった。しかし砂糖業者たちは単なる労働力としてしか人を欲しがっていなかった。それに反して、政府はハワイ国民としての労働力を欲しがっていたのだ。
(『ミステリマガジジン』1976年6月号掲載)
ハワイの砂糖耕地の経営者たちが欲しがっていたのは、奴隷に近いような労働者だった。しかしハワイ政府は、ハワイ原住民たちと「近い」人種によって人口の増強をはかりたいと考えていた。そして最終的には日本人と中国人に落ちついた。しかし中国人は何があっても同化することは決してなかった。一方、日本人に対する白人たちの評価は、かなり高かった。ハワイを支えているものは砂糖産業であり、ハワイ全島の砂糖産業は白人たちの手に握られていたが、国王は一向に意に介しなかった。その頃、国王は世界旅行を思い立ち、まず日本に向かった。1884年3月4日、カラカウア王は、日本が鎖国を解いて以降初めて訪れた外国の元首となった。そして3月10日の夜、国王は赤坂離宮を密かに訪問し明治天皇と会見し、もてなしの感謝と日本に対する賛美の言葉を述べた。そして国王は、ハワイの苦境を明治天皇に語り日本の協力を仰いだ。その協力とは、日本人移民の実現、日本とハワイの友好による太平洋の発展への寄与、そして、やがてハワイの王位をつぐはずのプリンセス・カイウラニと日本皇族山階宮定麿親王との婚約の申しいれの三点だった。
(『ミステリマガジジン』1976年7月号掲載)
2023年6月27日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ
次の記事へ