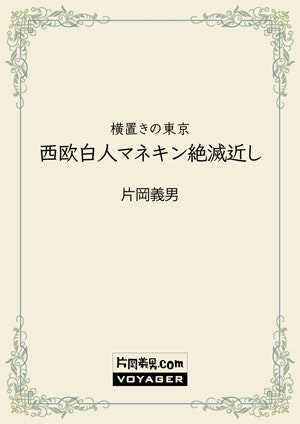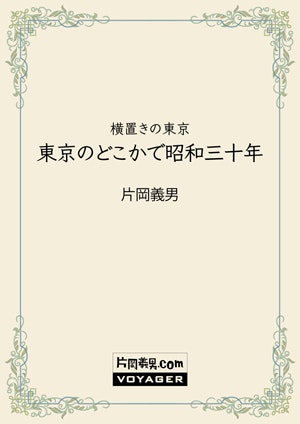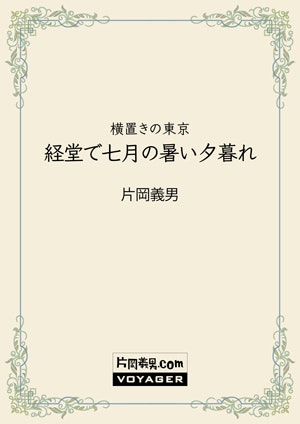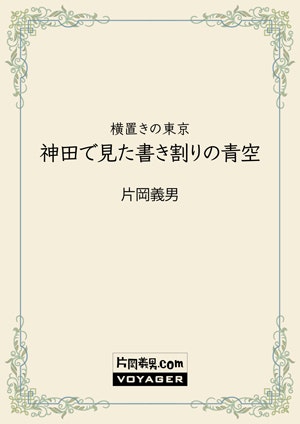写真エッセイ『横置きの東京』より6作品を公開
写真エッセイ『横置きの東京』(『日本カメラ』/2004年)より6作品を本日公開いたしました。
写真機を持ってさまよい歩く僕にとって、たいへん面白い住宅地と、面白くもなんともない住宅地の2種類が、東京にはあるようだ。この場合の面白いとは、素晴らしい被写体に数多く出会うことが出来る、というほどの意味だ。どれだけ歩いても被写体が見つからないと、気持ちそのものが沈んでいく。逆に数歩ごとに目の醒めるような光景に出会うと明らかに興奮する。面白くない住宅地には、人が手をかけることをとおして、そこに留められた時間の蓄積が全くないのだ。
(『日本カメラ』2004年6月号掲載)
都心のデパートや商店街など、かつてマネキンは日本の街なかのいたるところで目にすることができた。しかし最近は数が減りつつあり、いわば絶滅危惧種のような状態だ。西欧白人の体型と顔立ちを模したマネキンは、近代日本がかかえた業の、ごくわかりやすいアイコンのようなものではないか。日本は何に追いつき、何を追い越そうとしたのか。マネキンそのものは奇妙な官能性をたたえたオブジェでしかないのだが。
(『日本カメラ』2004年7月号掲載)
昭和30年代の10年間。1956年7月、政府が経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言する前の年から、1964年の東京オリンピックの翌年までの10年は、僕にとっては子供から青年へと移っていった時期だ。昭和30年代の東京の街なみを撮った写真集を見るたびに、いまの自分がいまの写真機を持ってこの街なみのなかを歩いたら、フィルムがいくらあっても足りないほどに撮るだろうな、と思う。なぜそんなに撮りたくなるのか。理由は簡単なものだ。そのような光景はたいそうフォトジェニックだからだ。つまり恰好いいということだ。
(『日本カメラ』2004年8月号掲載)
異常気象の7月のひときわ暑い日の夕方、商店街の夏祭りの提灯に明かりがともった。それはさまざまな要素がぎっしりと詰まっている商店街を、統一性のあるものへと変化させた。あらゆるものがひとつに溶け合う理想郷としての村落共同体への、あるかなきかのかすかな未練。これを人の心から摘出し、ごく素朴なかたちをあたえれば、それは商店街につらなる夏祭りの提灯となる。夜も更けてその明かりが消えるまで、幻の故郷の呼ぶ声を、人々はそれぞれに聞くのではないか。
(『日本カメラ』2004年9月号掲載)
快晴の暑い日曜日の午後、僕は神田で写真を撮った。あまりにまっ青な空は映画の書き割り(背景などを平面的に描いて置いたもの)に見えた。そう思うと、その下にひしめいて建ちならぶ大小さまざまなビルディングは、映画の撮影用に建造された、精緻なリアルさをきわめたセットという、架空のものに見えた。平日の神田では決してこんなことは感じない。ファインダーの中に見る青空についてのそのような感じかたは、街が廃墟になった次の日、新品の廃墟を僕に思わせた。
(『日本カメラ』2004年10月号掲載)
「エトアール」という通りが高円寺南にある。500メートルほどの長さの、広い意味での商店街だ。東京の子供はごく狭いエリアを自分の場所にして育つ、という傾向を明らかに持っている。少なくともかつてはそうだった。僕もその例にもれず、東京の中にいまだに未踏の秘境を広くたくさん持っている。この高円寺はそのひとつだ。生まれて初めて足を踏み入れた残暑の高円寺で、未踏の秘境を僕は充分に写真機で楽しんだ。
(『日本カメラ』2004年11月号掲載)
2022年12月20日 00:00 | 電子化計画