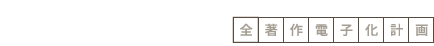写真エッセイ『記憶を撮る』より6作品を公開
写真エッセイ『記憶を撮る』(『日本カメラ』掲載/2006年)より6作品を本日公開いたしました。
一眼レフで写真を撮ろうとしてファインダー越しに対象をとらえ、それを35ミリ・フィルムのフレームでどのように切り取るかをファインダーのなかで決定した瞬間、いまの自分のこのような視線は、子供だった頃の自分の視線とまったくおなじだ、と強く感じることが僕にはしばしばある。幼年期の僕の視線が残っているのだ。四歳、五歳といった年齢の頃の僕と現在の僕とが、その視線でふととらえる物は、同じなのだ。幼くして早くも僕そのものであった自分を、いまの僕はそのようにして発見する。
(『日本カメラ』2006年1月号掲載)
冬がその奥行きを深めつつあった快晴の日の午後、僕は下北沢北口のマーケットを通り抜けていった。あと数歩でマーケットを出る地点で僕が目の前に見た景色に、これは写真に撮らなければいけない、と僕の神経は反射的に反応した。地元である下北沢一番街の飾り看板アーチ。この写真の背景に見えはしないが、僕の体験の蓄積のぜんたいが、確実に存在する、記憶になっている。今回のこの景色だけを僕は写真に撮ったのではなく、商店街としての下北沢の記憶のすべてを、僕はこの写真で撮ったのだ。
(『日本カメラ』2006年2月号掲載)
僕にとっての昭和三十年代は、自分のことで常に手いっぱいであり、それ以外のことに関心を持つ余裕はなかった。だから、あの頃の自分がなにをしていたのか、まったく思い出せない。あの時代に僕はいたけれど、体験はなにひとつしていないからだ。しかし、ごく小さなディテールなら、まめに歩いていればときたま出会うことが出来る。たとえば偶然に見つけたひとつの窓。それを写真に撮ることによって、僕はこの窓を体験する。さらに文章を添えることを通して記憶する。ひとつの窓という現物を頼りに、いま、僕は自分のなかに記憶を作ろうとしている。
(『日本カメラ』2006年3月号掲載)
東京の板橋で、午後の陽ざしを受けとめている板壁を写真に撮った。40年くらい前までは日本のいたるところにあった、珍しくもなんともない景色だった。いまは絶滅寸前だろう。造形的に純粋に惹かれるものはあった。だが、この写真を撮ったとき、その陽ざしと板壁とのあいだに、幼年期から青年期の終わりまでの期間の、さまざまな自分を僕は見たのではなかったか。陽の射す板壁の記憶は、ひとつひとつが微粒子のようになって、僕の記憶の底に沈殿している。その記憶のぜんたいを、板壁や陽ざしとともに、僕はこの写真の中にとらえようとしたのではなかったか。
(『日本カメラ』2006年4月号掲載)
かなり広い敷地のなかにある、邸宅と言っていい大きな家の、道から玄関へとつながるアプローチのような部分。この景色を自分がいつ写真に撮ったのか、正確には記憶していない。だが、この景色に僕の胸は奇妙に騒ぐ。重なり合ういくつもの謎の、微妙なニュアンスのなかに、経過した時間が潜んでいる。その時間の粒のひとつひとつが、明るく澄みきって楽しく、ほの暗く憂愁をたたえて理由もなく悲しく、奥深い襞のそこここに、性的とすら言っていいほどの興奮とその秘密の源泉が、静かに宿って息づいている。
(『日本カメラ』2006年5月号掲載)
故郷はどちらですかと訊かれたら、それは東京です、と答えるほかない。その東京とは、いったいどのようなところなのか。誰の目にもわかるかたちで、たとえば写真に撮って、提示することは可能なのか。それはたやすく可能だ。写真機を持って住宅地の中をただ歩いていくだけで、その一歩ごとに、そうした景色が目の前にあらわれる。いま少しだけ正確に言うと、僕の故郷は東京の住宅地です、ということになる。東京という故郷の記憶は、住宅地という現場にある重さの記憶なのだ、と言ってみよう。住宅地のなかの道を写真に撮ることを通して、僕は自分の故郷を確認しているのだろうか。
(『日本カメラ』2006年6月号掲載)
2022年11月15日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ