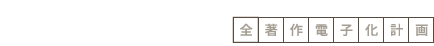連載エッセイ「そしてその他の物語」より10作品を公開
雑誌『Free & Easy』(イースト・コミュニケーションズ)にて2010年7月から2013年3月まで連載されたエッセイ「そしてその他の物語」からの10作品を本日公開いたしました。文章だけでなく、写真も片岡義男本人によるものです。
4月の初めの平日の午後、下北沢北口の喫茶店で僕は旧知のイラストレーターと打ち合わせをしていた。彼はカントリー・ソングが好きで、自宅で仕事をするときには常にカントリーを聴いているという。下北沢の南口にアメリカ盤のカントリーを置いている店があることを思い出した僕は、彼を誘ってその店へ久しぶりにいってみた。僕はロカビリーの箱のなかからボブ・ルーマンのLPを見つけた。1959年から1962年までの録音を14曲収録したものだ。エルヴィス・プレスリーより1歳だけ若いルーマンの、髪を見事なダックテイルにまとめたハンサムな横顔は素晴らしい。もう1枚はロカビリーのアンソロジーLPだ。イタリー製だった。この2枚をLPのぎっしり詰まった箱の上にならべてみたときに僕が受けた衝撃は、半端なものではなかった。僕は何度も感嘆の声を上げた。「その2枚のジャケットを見てるだけで、小説が書けそうだね」とイラストレーターは言った。小説どころか、これは人生そのものだ、と僕は思った。
(『Free & Easy』2010年7月号掲載)
謎の美女を中心に何人かの知人や友人たちと夕食のテーブルを囲んだとき、彼女は食卓を同じくする人が守るべきマナーのひとつとして、口数の少ない僕に対して、ごく軽くちょっかいを出した。
「最近はなにをなさってるのですか」と、美女は言った。
「つい昨日は風船ガムを写真に撮りました」と、僕は答えた。
風船ガムとは、マルカワFELIXのことだ。日本ではフェリックスでとおっているようだが、FELIXはどう考えてもフィーリックスだと思いながらよく見たら、フィリックスフーセンガム、と包装紙に印刷してあった。フィリックスはさすがだとして、風船ガムはフウセンガムではなく、フーセンガムなのだ、気をつけなくてはいけない。
というようなことを、僕は謎の美女に語った。
(『Free & Easy』2010年8月号掲載)
外国のファッション雑誌から切り抜いたとおぼしき空の写真。捨てるには惜しい、しかし、1ページ全体を切り取っておくほどの空でもない。だとしたら切り抜くほかない。雑誌のページに印刷された写真のたどる運命のひとつに、切り抜かれる、という運命がある。切り抜きかたはごく平凡なものだ。どんなふうに切り抜こうとも、もとの写真の出来ばえを越えることは出来ない。それほどつまらない空でもない、やがて使い道はあるだろう、と思いながら僕はこの空の切り抜きを、書類ボックスのなかに入れた。そして梅雨の晴れ間、風のない日の午後まだ早く、黒いケント・ラシャ紙を貼ったホリゾントの、垂直面と水平面とが直角に交わるところに、切り抜いた空の写真を置いてみた。白い雲が直射光を受けとめている様子は、じつに好ましい。
(『Free & Easy』2010年9月号掲載)
毎年夏の間、僕は水鉄砲を買う。今年はその数がやや多いような気がする。猛暑となんらかの関係があるだろうか。スーパーマーケットの家庭用品売り場の片隅、夏の玩具が集められている中に、プラスティックで作ったピストルの形をした水鉄砲が必ずある。今でも子供たちは水鉄砲で遊ぶのだろうか。雑貨店の前を通りかかってふと見ると、店の外に宇宙戦争タイプの水鉄砲が色違いで2通りあったりもする。いずれの場合も僕は買う。その日、2種類目の水鉄砲を買ってすぐに、雨が降り始めた。自宅に帰りつき、コーヒーを飲みながら買って来た水鉄砲を点検していると、射ってみたくなった。ヴェランダのガラス戸を開き、僕は豪雨を水鉄砲で射ってみた。かなり遠くまで水は飛んだ。銃口から細くまっすぐに飛び出していく水の先端が、放物線となって落ちかけるところで、豪雨の雨粒に衝突することが、何度もあった。降る雨を水鉄砲で射って命中させることは、充分に可能なのだ。
(『Free & Easy』2010年10月号掲載)
おそらく居間として使っているはずの広いスペースには、その広さと気持ち良く調和した、長方形の大きなガラス窓があった。窓のすぐ前に立って、彼は外を見ていた。彼の視界の幅いっぱいに、窓の外は林だった。森と呼ぶには、重さや深さがやや不足しているから林だ。その林はいま、台風の影響による突風と豪雨を受けとめていた。さまざまな方向から、林は台風の影響による容赦ない強さの風を、常に受けとめ続けた。受けとめて林の内部へと取り込み、取り込んだ内部のどこかで、風はあっけなく中和されているように見えた。豪雨についてもおなじだった。豪雨は林を叩きのめす。しかしいくら叩かれても林はびくともせず、雨に濡れ続けることをほんのりと楽しんでいる風情だった。このような光景を自分が間近に見るのは、ひょっとしたら今が生まれて初めてのことではないか、と彼は思った。
(『Free & Easy』2010年11月号掲載)
待ち合わせの場所であるそのバーに、作家の水谷は約束の時間ちょうどに現れた。親友の写真家である日比野はすでに来ていた。水谷は日比野の右隣に座った。
「このあたりは魅力的な路地の重なり合いだね。東京にいまもまだこんな場所があるとは。来るたびにそう思う。だから来るたびにいつも、路地をぐるぐると歩きまわる」
水谷の言葉に日比野はうなずいた。そして、
「小説に使えるだろう」
と言った。
「この路地の重なり合う一帯だけを舞台ないしは背景にして、小説が書けるような気がする。いろんな人がいて、さまざまな関係があって」
「その関係と展開を読んでいくと、さまざまな関係のありかたが、読んでいく人にとって、まるで自分の触覚が感じ取っているかのように、錯覚することの出来る小説」
「いいことを言うじゃないか」と、言った作家の水谷は、次のように言った。
「すべては触覚だよ。関係とは、人と人との、なにかとなにかが触れ合うことだ。なにであってもいい。今夜は雨模様だけど、この路地一帯に雨が降れば、そのときそこにいる人たち全員が、雨を感じ取ることになる。人ごとに違った物語を、雨が用意する」
(『Free & Easy』2010年12月号掲載)
次の写真にあるのは、『ライ麦畑でつかまえて』という、J・D・サリンジャーの小説の、1957年のペイパーバック第六版だ。表紙に描かれているのは、この小説の主人公である、ホールデン・コールフィールドという少年だ。彼がニューヨークに到着して、マンハッタンをでストリップ劇場の前を通りかかり、看板やポスターを見ている場面だ。絵に描かれたホールデン・コールフィールドとして、このペイパーバックの表紙は、今にいたるも恐らく唯一のものではないか、と僕は思う。僕が高校生の頃に買ったこのペイパーバックをいまでも持っている理由はここにある。絵の右半分が白い長方形につぶしてあり、そこに宣伝コピーが印刷してある。少なくともこのペイパーバックの初版では、全体は画家の描いたとおりの絵だったのではないか、と僕は推測する。ストリップ劇場の入口に半裸の女性が立っていた、あるいは、入口近くに貼ってあるポスターに、踊り子の裸体が煽情的に描いてあったのではないか。それに対して苦情がきたか、あるいは、出版社が自主規制した結果、問題となった部分は宣伝コピーのスペースへと転換されたのだ。だが、初版を手に入れてみたいという思いはまだ果たせていない。
(『Free & Easy』2011年1月号掲載)
彼は40代半ばの独身で、職業は翻訳家だ。中堅を越えヴェテランの域に到達しつつある。彼女は彼より10歳は年下だ。同じく独身で、作家として小説を書く。冬が始まりつつある気温の低い日の午後、ふたりはひと月ぶりに会った。用件はなにもない。午後のコーヒーと、それに伴う会話だけだ。
「ふたりで話を考えようか」
「ぜひ、そうして」
「知らない町を歩きたい、という願望が僕には常にある。ずっと以前から。おそらく子供の頃から」
「知らない町ならどこでもいいの?」
「どこでもいい」
「ひとりで歩くのね」
「基本的にはひとりだろうね。よく知っている人に、知らない町で偶然に会う、というのはいいかもしれない。ひとときをともに過ごし、別れてふたたびひとりになる」
「知らない町。それはストーリーかしら、それともストーリーの始まりかしら」
「始まってさえしまえば、そこから先は自動的に展開していく」
「楽観的ねえ」
「翻訳家の楽天性」
「知らない町へいく話。あるいは、知らない町を夢想する話」
「どちらでもいい。今日のきみは、知らない町に向いている」
(『Free & Easy』2011年2月号掲載)
オレゴン州のポートランドに住んでいるステファニーと、メイン州のポートランドに住んでいるマリアは、同じような年齢で家庭を持ち、クラフトという範囲に入るようなクリエイティヴな仕事をして、静かに毎日を送っている。ふたりはそれぞれにブログを持っており、お互いのブログに毎日のようにアクセスしては、相手が書くことを読み、そこへコメントを添える、ということを繰り返してきた。何かを強く感じたマリアは、一度だけでもいいですから実際に会ってみませんか、という提案を行った。実りの多い出会いだったようだ。
2006年12月初めのある日、ステファニーのブログにログ・インしたマリアは、そこにアップされていた1枚の写真に驚嘆の声を上げた。その写真が捉えている光景は、自分の日常そのものだった。ステファニーとは重なっている、繋がっている、と改めて意識したマリアは、ふたりで共同のブログを新たに作り、そこへ毎日、午前中に撮った写真を一点ずつ、掲載してみませんか、とステファニーに提案した。
ふたりの女性たちによるブログは、こんなふうにして始まった。ブログのタイトルは、3191にきめた。オレゴン州ポートランドとメイン州ポートランドの距離が、3191マイルだから。このブログから1年分の写真を1冊にまとめた本が2008年にアメリカで出版された。
(『Free & Easy』2011年3月号掲載)
ずっと以前、まだ子供だった頃、こんなパッケージの石鹼が、ごく日常的に、家庭のなかのあるべき場所にあった。「ミツワ・クラシック・ソープ」とうたうからには、懐かしさ、つまり、まだ日本は貧しかったけれど、誰もが明るい明日を信じて元気だった昭和の日々に寄り添ったものだと言っていい。昭和の初め頃、あるいはひょっとしたら大正時代に、アール・ヌヴォーの様式が大流行し、庶民生活の末端にまでまざまなかたちで浸透した。この石鹼のパッケージ・デザイン、特に英文字のMの左側の長く下へ伸びた様子にそれが伺える。懐かしさを感じると同時に、箱の大きさのバランスは完璧に近く、その六面にほどこされた平面デザインには、ほどよく落ち着いた安定感がある。庶民生活の基本としてもっとも重要なのは、その生活を生きる人たちが心の底で感じ続ける安定感だ。ミツワ石鹼のこのパッケージのようなものを、僕は箱物と総称している。ほかにも箱物はないだろうか、と僕は思った。まだ貧しかったけれども、みんなの気持ちが明るくて元気だった昭和を体現しているような、当時の日常そのもののような箱物は。
(『Free & Easy』2011年4月号掲載)
2025年1月10日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ