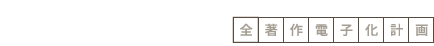『酒林』随筆特集よりエッセイ4作品を公開(5)
香川県琴平町の酒造会社・西野金陵(にしのきんりょう)株式会社が、昭和30年から発行している雑誌『酒林』の「随筆特集」で掲載されたエッセイ4作品を本日公開いたしました。いずれも書籍化されていない作品です。
東京で外国の人をたくさん見かける。しかも観光ではなく東京に住んで働いている様子の、ヨーロッパからの人たちを。夏の終わり近いある日の午後、カフェにいたら、僕から通路とテーブルをへて正面に、どこかヨーロッパの、30代の男性がひとり席についた。くすんだ金髪を面倒くさくない短さにまとめ、半袖のポロ・シャツにダーク・ブルーのパンツ、そして足音のしない平凡な靴に、例によって大きくふくらんだバック・パック。真横から観察する彼の横顔のなかに、鼻は大きく尖った三角形として、突き出ていた。彼のすぐ手前の席には日本の若い女性がいて、彼女の横顔も僕の正面に見えた。彼女の鼻はことさらにぺちゃんこではなく、ごく普通に自信を持っていい鼻だったが、その向こうにいる彼の鼻にくらべると、なきに等しいものだった。
(『酒林』随筆特集 西野金陵株式会社/第89号[2015年1月発行]掲載)
雨の日の午後に喫茶店で待ち合わせた人が、「雨の歌は日本にいつ頃からあるのかしら」と僕に訊ねた。「大正時代にはあるよ」と僕は答え、「子供の歌として」と、つけ加えた。確かな根拠は何もなかった。調べてみたら、大正8年に『雨』という題名の歌が、子供に向けられたものとして、発表されていた。北原白秋が詞をつけ、弘田竜太郎が曲をつけた。「遊びに行きたし 傘はなし」という部分を、かつては実に多くの人たちが知っていた。大正14年には、『あめふり』という歌も作られた。母親が唐傘をさして学校まで迎えに来てくれた嬉しさと、雨のなかを母親とふたりで帰っていく楽しさという、失われて久しく、しかも2度とあり得ない日本が、この歌の中にある。雨の中をふたりで歩く楽しさが、「ピッチピッチ チャップチャップ ランランラン」と表現され、かつてはほとんどの人たちが、メロディとともに知っていた。
(『酒林』随筆特集 西野金陵株式会社/第90号[2015年9月発行]掲載)
ボールペンというものを僕が初めて手にしたのは、八歳あるいは九歳くらいの頃ではなかったか。ボールペンの構造は、そのときすでに知っていた。僕が子供だった頃にくらべると、現在のボールペンは精密度や材料の質が飛躍的に向上している。しかし基本的な構造は、なんら変化していない。軸の先端にある三角錐の中から、小さな一個の球体を取りはずしてみよう、と思った僕は、十歳にはなっていたと思う。日本製のボールペンが、ごく普通の人たちの日常生活のなかに、あって当然のものとして、出まわり始めた頃だ。ペンチで割った三角錐の先端から、直径0.5ミリのボールペンのボールを1個、僕は指先につかまえた。持つ、という表現は当てはまらないほどに、その光る球体は小さかった。指先にとまらせる、とでも言えばあのときのあの感触の、10分1くらいは伝わるだろうか。
(『酒林』随筆特集 西野金陵株式会社/第91号[2016年1月発行]掲載)
小説のためのメモを書くのに僕はいま万年筆を使っている。万年筆を選ぶのは簡単だろう、と僕は思っていた。簡単ではなかった。購入して自分のものにしたあと、自宅でいろんな紙に文字を書いてみないことには、その万年筆が自分に適しているかどうか、判断できないからだ。この作業を一体何度、繰り返したことだろうか。購入した万年筆の数は百本には到達しただろう。その果てにようやく見つけたのは、プラチナ万年筆のセンチュリーというシリーズの中字だ。ペン先の出来の良さに加えて、全体の大きさ、重さ、その配分のバランスなど、右手に持って字を書いていく道具だから、微妙としか言いようのない要素がかなり複雑にからんでくる。そのような要素の絡み合いの中に、これならいいかもしれない、という一本の筋道が見える。
(『酒林』随筆特集 西野金陵株式会社/第100号[2021年9月発行]掲載)
2024年9月27日 00:00 | 電子化計画