写真エッセイ『ホームタウン東京──どこにもない故郷を探す』より35作品を公開
写真エッセイ『ホームタウン東京──どこにもない故郷を探す』(筑摩書房/2003年)より35作品を公開しました。
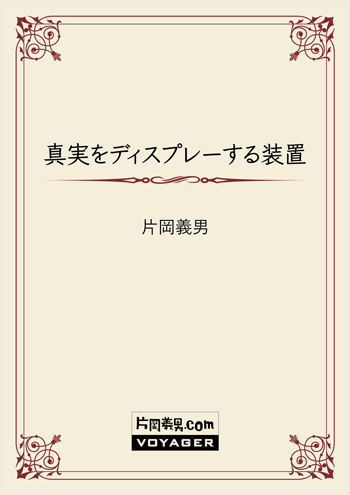
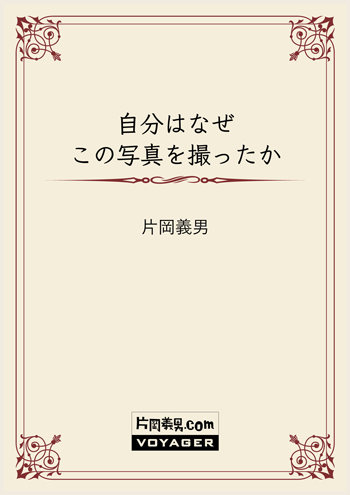
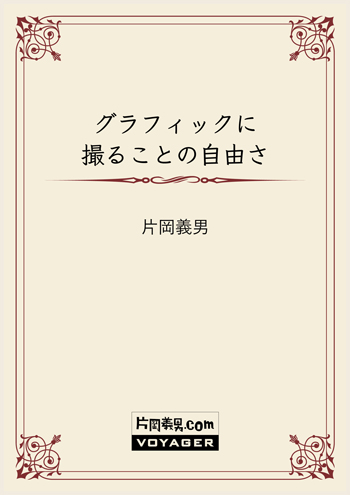
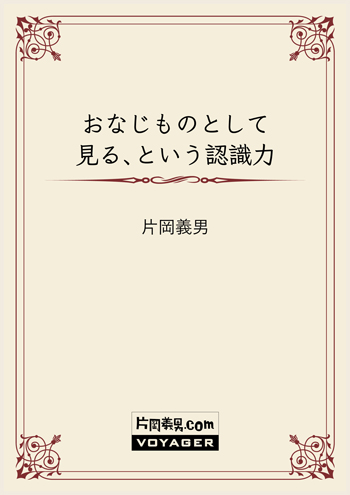
「矛盾の美を愛でる」
日本はありとあらゆる矛盾の複合体だ。その意味では一筋縄ではいかない存在なのではないか。日本に個性が希薄だとは、どこを見て言っていることなのか……。
「美しき脳故郷よ」
僕の故郷は、いまはこういう景色のところなのか、とつくづくと思う。なんとも言いようのないこの景色は、これはじつは脳なのだ。僕は東京という脳の中に生きている。なぜなら……。
「秋の化粧に大根の幸せ」
シャッター・ボタンに指先をかけたとき、被写体の隙間から僕の視線はのびていき、八百屋の店先に陳列されている大根をとらえた。これだ、これこそ幸せというものだ、と僕は思った。時は秋、場所は駅前商店街。二次元の化粧美人を撮った僕は……。
「東京情緒との逢瀬」
この二点の写真の景色こそ東京の情緒だと僕は力説する。露出の補正だけが僕の意思で、あとはすべて写真機まかせだ。そのことがこの東京情緒には、この上なく似つかわしい。
「時計とカレーライスの日」
日常が日常そのものとして営まれ繰り返される安堵の地のただなかで、時計は誰もが自分の前方に持ちたいと願う、無事な時間の象徴だった。
「真実をディスプレーする装置」
つい昨日まではそこにあった景色が、今日は跡かたもないのが東京だから、この景色もこれから先どうなるかわからない。けれど少なくともいまはまだ、そこへいけば確かに現実のものとして、そこにあるはずだ。
「けっして対比ではなく」
まるで両極にあるようなふたつの景色を対比させて悦に入る、という趣向は僕のものではない。しかしふたつならべれば、そこに対比がほぼ自動的に生まれてしまうのを、僕はどうすることも出来ない。
「これを撮れと光が言う」
フィルムにとらえた光景と現実の光景とのあいだに、撮る人の予測を越える乖離がどのくらい生まれるのか? 撮ってみてフィルムをルーペで観察しないことには、確かなことはなにも言えない。
「見開いた二ページという世界」
一冊の本を開くと、目の前にあらわれるのは、左右の二ページだ。人の視覚によるとらえかたは、左右のページを不断に交互している。それを繰り返すことでふたつの写真を視覚的に体験し頭のなかで統合させる。
「布張りの街」
木材でごく簡便に作った枠組みに、白ないしはそれに近い布を巻きつけると、遠目には石造りのものに見える、という技法がある。布という二次元による、二次元半のような世界の創出。壁面があればそこに掲げる。なにもない空間なら幟を立てる。
「自分はなぜこの写真を撮ったか」
この2つの写真は、路面を底辺にして構成されている空間を斜めに見下ろして、まったくおなじように撮影されている。このような空間をなぜ僕は写真に撮るのか。
「大根と電柱が景色を作る」
フォトジェニックであるということは、景色を作るということにほかならない。八百屋の店先で群を抜いてフォトジェニクなのは……。
「せつなさを写真におさめて冬至かな」
同じ景色をほぼ同じ画角で、数カット撮影したフレームのおしまいに、焦点をわずかにはずしたカットがあった。僕が自動焦点をわざわざ解除し、焦点をはずしてワン・カット撮ったのだ。
「写真機は現実を抽象化するか」
現実にはもっと広い範囲で見えている光景を、百ミリのレンズでトリミングすることによって、日常はなにほどか抽象化される。そこに具象がひとつ加わると……。
「安心はどこまで続くか」
建物の頂上から、黒地に黄色の端的な三文字が、民のかまども厠も、すべてを啤睨している。純粋に写真による遊びとして、僕の写真機は街のなかにこのような光景も見つけていく。
「道、というタイトルはどうか」
大きなもの、長いもの、広いものなどを、ひとつの小さな点にしてしまう快感は、確かに写真のものだ。なにしろひとつの小さな点なのだから、理論的にはそれは無数に撮ることが出来る。
「グラフィックに撮ることの自由さ」
具体物や具体性のいっさいから離れ、日常も生活も人々もなんら関係なく写真を撮ることが僕にはたいへん多い。光景を構成しているあらゆる要素が、僕にとってはたまたまこういう色とかたちをした、グラフィックなもの以外のなにものでもなかった。
「いったいなんのことだか」
写真機を持って歩いているとは、いつでも撮る用意が整っている、ということにほかならない。撮る行為に向けて、精神は通常よりもはるかに濃密に増幅されている。
「二〇〇三年一月五日、午後から夕方にかけて」
地面と平行な視線よりも上に向けてのびる視線と、下へと向かう視線の、無限と言っていい繰り返しのなかに、世界のほとんどが存在している。その視線をことさらになにかに向けてそこに到達させる装置、それが写真機だ。
「お外の道、という精神外傷がそこにある」
三歳、そして四歳といった年齢の頃の僕がこのような道を歩くのは、乳母に手を引かれた散歩のときだった。目の前にあらわれるのは、家の外に何重にもある迷路だ。現実はまず迷路のかたちをとって、幼い僕の心に外傷をあたえた。
「よく似たふたつの景色」
ここにあるふたつの景色はとてもよく似ている。少なくとも僕の目にはそう見える。ひとつ目の景色がオリジナルの位置にあり、ふたつ目の景色はそのオリジナルから派生した近似値である、ということだ。
「日常とは不気味な世界のことなのか」
日常のなかの不気味さ、という言い方があるけれど、日常とはその全体が、そもそも不気味なものなのだ。その不気味さの中にちょっとした美が潜んでいる。
「説明なんかするな、と光が言う」
この二点の写真には撮った、という行為だけがあり、その行為に意図はまったくないし、撮ることによって手に入ったこの二点の写真には、なんの意味も重ねられてはいない。こう撮った、と説明することが出来るだけだ。
「そのときの光が命じるままに」
光がなければなにも撮れないのだから、そのときそこに当たっていた光に促されて撮る、という行為はたいへん正統的なものなのではないか。このふたつの写真を、最もふさわしい名前で呼ぶとしたら……。
「徳利はやはり芸術なのか」
写真に撮られるのを待ちかまえている被写体というものが、街のなかに確実にある。ふとした思いがけない片隅で、被写体は、写真機を持った呑気な人の到来をじっと待っている。
「傘と道路が本のなかで出会う」
白いヴィニールの傘が窓の外の鉄格子にかけてある様子は、光景としては謎そのものだ。この光景に取り合わせるものとして、僕は道の写真を選んだ。
「おなじものとして見る、という認識力」
このふたつの光景はよく似ている。絶対に同一ではなく、確かに別物ではあるけれど、僕という人にとっては、ほとんど同一の光景だ。写真にあるような光景を見ると、僕はそれを写真に撮ることで認識のなかに折り畳んでいく。
「道を掘る人、黄色く咲く花」
歩道橋の上からその下に向かう階段全体の様子を撮ろうとした写真と、道の様子を撮った写真。別々の時と場所で写真を撮りながら、意識下では同一と言っていいパターン認識を、僕はおこなっているようだ。
「エトランゼとなる午後」
写真の光景をカラー・リヴァーサルのなかに、ルーペごしにライト・テーブルで僕は確認する。そのときの自分がどんな自分だったかを知るための手がかりを、自分がかつて撮った写真のなかに、僕は見つけようとする。
「西ヶ原三丁目の窓」
このふたつの光景は、撮影者である僕にとっては、完璧に同一の光景だ。こんな風景を偶然に見つけることができるのだから、歩いているときの視線の働きは、それ自体がひとつの完結した生き物なのだと、いまさらのように僕は思う。
「青いトタン板と向き合う」
広い面積をトタン板で覆うためには、何枚かをつなぎ合わせなくてはいけない。だから僕の記憶のなかにあるトタン板は、何か所もつないであるものばかりだ。つなぎ合わされたトタン板。そこに人生がある。人生はトタン板だ。
「安堵して撮る被写体とはなにか」
写真機を持って歩いている僕の足を止めさせる光景。このような被写体に対して、僕は安堵を覚えている。落ち着き、安心、安堵、といったものの上に立って、僕は撮ることを楽しんでいる。
「同級生の母と歩いた道」
高校で同級だった友だちに、母ひとり息子ひとりだった男がいた。彼が大阪に就職した年の夏の初め、駅の近くで彼の母親に偶然会った。その駅からかつての彼の自宅のあった場所まで、40年ぶりに歩いてみた。
「東京の情緒 その2」
陽ざしによってその光景がなにほどか劇化されている様子を目にするのは、写真を撮る人にとっての幸せのひとつだ。ある鉄則をひとつ守ると、それと引き換えに幸せがひとつ、手に入る。
「東京の幾歳月」
四十年、五十年、さらにはもっと長いあいだあり続けた家には、家の内部にも外部にも幾歳月の時間が蓄積されて残っている。風雨にさらされた外部は、抽象化された雰囲気を獲得する。
2023年1月24日 00:00 | 電子化計画

