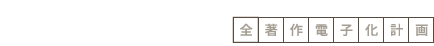写真エッセイ『記憶を撮る』より6作品を公開
写真エッセイ『記憶を撮る』(『日本カメラ』/2006年)より6作品を本日公開いたしました。
街を歩いて被写体を見つけ、それを撮るならば、三十六枚の連続した齣のなかに、撮られた光景が記録として残っていく。撮るのは僕だから、その連続したいくつもの齣は、撮影者であるぼく自身の記録でもある。今回の写真を、いつどこで撮ったか、まったく記憶にないが、この景色が目にとまった理由を求めて、僕の内部に向けて掘り進んでいくと、幼い頃のおつかい体験にまで、さかのぼってしまう。看板が出てる、矢印が描いてある、そのすぐ先の角のところだ、といった母親の言葉を想起しつつ目印をたどっていく、坊やの自分を。
(『日本カメラ』2006年7月号掲載)
アルミ・サッシ。半透明なガラス。カーテンのありかた。ガラス戸のすぐ外にある植物の、緑色の造形。赤い花。花が三つというのも素晴らしいことだし、いちばん低い位置にある花の、なかば隠れたようなありかたは、完璧な偶然というものの仕業だ。カーテンがあったから僕はこの光景を写真に撮った、と僕は言うけれど、この光景の場所で営まれているきわめて個別的な生活に寄り添う、個別的なカーテンという物体を撮ったのではない。それはもはや生活の個別性の記録ではなく、多くの人々に共通する、かなり抽象性を帯びた、日常の日々の記憶、というものの一例になるのだ。
(『日本カメラ』2006年8月号掲載)
僕が子供だった頃の玉電・山下駅の雰囲気や面影、さらには触感などを、この木造の駅舎は充分に伝えている。印象だけで判断するなら、子供の頃の駅そのままだ、と言ってもいい。強烈な懐かしさを覚える人はけっして少なくないだろう、と僕は思う。木造の記憶とは、いったいなになのか。庶民の生活という、取り散らかり始めたら際限のない雑多な現実を、なんとかひとつに結びつけ、それに意味を与えていたのが、生活領域の中に拠点として点在していた、さまざまな木造の建造物だった。現物が消えた後には、記憶としての写真が、かろうじて残ることもある。
(『日本カメラ』2006年9月号掲載)
亀の子束子、まるふく箒。僕は何に反応してこの光景を写真に撮ったのか。記憶に反応した、としか言いようがない。掃除に関して母親にいつもうるさく言われた記憶。なぜ母親という人は常にこうまで厳しいのか、と不思議にすら思いながら、束子でこすって汚れを落とし、箒で塵を掃き集め、塵箱へと捨てていた、遠い昔の子供の頃。今にして思えば、掃除にうるさかった母親は、日常生活のなかで人が守るべきいくつものルールや規範などの秩序世界の、重要な一端を自分の子供に教えこもうとしていたのだ。
(『日本カメラ』2006年10月号掲載)
どこかの銭湯で僕はこの写真を撮った。休みの日、あるいは、まだその日の営業が始まる前の時間だ。その戸は上のほうにだけ模様ガラスがはまっていて、暖簾はそのガラスの向こうにしまってあった。暖簾のぼけ具合はなんとも言いがたく絶妙だ。主として母親から聞かされた昔話によれば、幼い頃の僕は、銭湯をたいそう好んだという。かすかな記憶の底に、銭湯へいくときのうれしさ、そして銭湯のなかへ入った時の楽しさなど、想起することのできるものが、確かにある。
(『日本カメラ』2006年11月号掲載)
食事や酒の店の入口に、「いらっしゃいませ」のひと言が掲示してある様子を、ひと頃の僕はしばしば写真に撮った。いまでも見かければかならず撮る。今回のこの看板にも、「いらっしゃいませ」のひと言が、その冒頭に、かくも明快にうたわれて、とおりがかりの僕を招く。「いらっしゃいませ」のひと言に迎えられてテーブルにつき、「餃子ライスにわかめスープ」という応答をすることによって、その店における一食という社会的な関係は、たちどころにスタートするのだった。
(『日本カメラ』2006年12月号掲載)
2022年11月22日 00:00 | 電子化計画