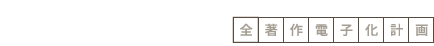【特集】『僕は珈琲』
1月24日、片岡義男の最新書き下ろしエッセイ『僕は珈琲』が発売されました。2018年発売の『珈琲が呼ぶ』は、当時巷で沸き起こったコーヒーブームの一端を担ったとも言われ、この本で片岡義男を知ったという20〜30代の若い人たちが、著者の過去の作品を買い求めるという「逆流現象」まで引き起こしました。『僕は珈琲』は『珈琲が呼ぶ』の続編に位置付けられる作品で、喫茶店やコーヒーが登場する映画、コーヒーをめぐる言葉、コーヒーを飲みながら考えたこと、自身のルーツや作品について、音楽、文具、そしてフィクションを交えたものまで「これぞ片岡義男」というべき要素がぎっしりと詰まった1冊です。また、片岡義男.comの読者にはおなじみのデジタルファースト作品「短編小説の航路」シリーズから、コーヒーが登場する一編『謎なら解いてみて』を特別収録。そのメイキングも一篇のエッセイとして掲載されています。
この特集ページでは、『僕は珈琲』発売に合わせ、現在片岡義男.comで公開中のコーヒーに関するエッセイのいくつかをご紹介します。ぜひ新刊とともにお楽しみください。



■編集者よりひとこと
光文社 篠原恒木
あの『珈琲が呼ぶ』から5年、ついにカタオカさんの深煎り珈琲が出来上がりました。
書き下ろしエッセイは52篇。それらに登場する人、モノ、事のほんの一部を羅列します。
大瀧詠一/スティーヴ・マックイーン/男はつらいよ/刑事コロンボ/植木等/宮沢賢治/ドトールのミラノサンド/大統領の陰謀/植草甚一/歯科診察券/スケアクロウ……
これらが珈琲とどのように結びつくのか、それは読んでのお楽しみ。文章に添えたカラー写真も見どころのひとつです。
エッセイのなかで、僕が特に印象に残った文章を抜粋させていただきます。
「遠く離れたところにぽつんとひとりでいるのが僕だ、と長いあいだ、僕は思ってきた。そのように自分を保ってきた、という自負は充分にあった」
お気に入りの珈琲を片手に、ゆっくりとお読みくださいませ。
(篠原さんによる『僕は珈琲』の裏話はこちらからどうぞ)
◆片岡義男の珈琲エッセイ
2)『珈琲に呼ばれた』
『珈琲が呼ぶ』は発売後、多くのメディアで取り上げられました。その中から片岡義男本人が選んだ5編と、『珈琲が呼ぶ』の新聞広告が第23回読売出版広告賞を受賞した際の審査員のコメントをまとめました。登場するのは鴻巣友季子さん、松本知彦さん(漫画家・松本正彦さんのご子息)、坪内祐三さん、亀和田武さん、中森陽三さんです。(ボイジャー 2020年6月)
3)『なりにけらしな京都』
2018年、旧知の編集者2名と共に何度か日帰りで京都に赴いた片岡義男が、その様子を中心にまとめた、まさに「個人的な京都案内」とも言える書き下ろしのフォトエッセイ。「短編小説の航路シリーズ」を読まれた方なら、きっとニヤリとするシーンがあるはずです。京都の喫茶店を巡りたい、という方にも格好のガイドブックになるはずです。(ボイジャー 2019年12月)
4)『ソリュブルと名を変えていた』
珈琲の登場する小説やエッセイをこれだけ書いているにも関わらず、片岡義男は「これまでの人生で自分でインスタント・コーヒーを買ったことがなかった」と言います。スーパーに並ぶ30種類を超えるコーヒーから選んだ商品には「ソリュブル・コーヒー」の表記が……。ちなみにインスタントコーヒーの一部商品の表記が「レギュラーソリュブルコーヒー」と変わったのは、2013年9月からだそうです。(『酒林』西野金陵 2017年1月号)
5)『歴史上、初めてコーヒーを飲んだ日本人はいったいどこの誰か』
日本に初めてコーヒーが上陸した年は? 初めてコーヒーを飲んだ日本人は誰? 世界最初の喫茶店が開店した都市は? コーヒーに初めてミルクを入れたのは? クイズの問題に出てきそうなこんなコーヒーのトリビア、実は文献などにちゃんと記録があるのです。(『現代ビジネス』講談社 2017年5月21日)
6)『二本の映画と一杯のコーヒー』
かつて新宿にあった16ミリ専門の映画館アート・ビレッジで観た二本の映画の映画評です。『マルタの鷹』(1941)は片岡義男にとっては12歳の頃に原文で読み始め、途中で投げ出したといういわくつきの作品。一方『山河遥かなり』(1948)は主演のモンゴメリー・クリフトが発する、凝縮された熱意のようなものが好きだと言います。そして映画はどちらも期待を裏切らない内容だったようです。タイトルに「コーヒー」とありながらコーヒーも喫茶店も登場しないというエッセイです。(『アップル・サイダーと彼女』角川文庫 1979年)
7)『コーヒーもう一杯』
L・L・ビーンのコーヒー・マグにコーヒーを淹れ、コーヒーにちなんだ3枚のLPから音楽を聞く。中でもキャル・スミスが歌う『コーヒーをもう一杯飲んだら、ぼくはいくよ』は、ひところの片岡義男にとってテーマ・ソングと言っていいほどに「気持ちのこまかいひだの内部にまで入りこんできていた」という曲です。しかし、そのタイトルと歌詞との間にはややニュアンスに違いがあるようです。(『コーヒーもう一杯』角川文庫 1980年)
8)『喫茶店を体が覚える』
昭和30年代半ばに建てられたとおぼしき喫茶店。その内部を過不足なく描写するには、店での自分の体の動きを基準にするのがよいようです。20代の頃、原稿を書くために足しげく通ったその喫茶店に20数年ぶりに立ち寄るようになった際、何か違和感を感じたのは、自分の体がその店を覚えていたからに違いありません。(『音楽を聴く2──映画。グレン・ミラー。そして神保町の頃』東京書籍 2001年)
9)『秋の雨に百円の珈琲を』
10月の雨のある日、友人たちとのイタリー料理店での夕食の席で、コンヴィニエンス・ストアで買える1杯100円の珈琲について話題となります。しかし片岡義男はその珈琲を飲んだことがないと言います。何事も経験、さっそく友人たちと共に実際にコンビニへ行き、100円珈琲を試してみた結果は……?(『抒情文芸』 抒情文芸刊行会 2019年冬号)
10)『あの路地にいまも昔の自分はいるか』
東京・神保町は、作家・片岡義男が学生時代にフリーのライターとして活動を始めた頃から10年近く、仕事の本拠地としていた町です。路地に入れば、今でも50年ほど前の自分に簡単になることができると言います。そこには今も2軒の喫茶店が、当時のままに健在です。(『Honda Magazine』2017年 Summer)
Previous Post
Next Post