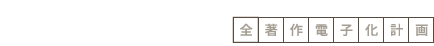連載コラム「アメリカン・マッスル」より11作品を公開
雑誌『Free & Easy』(イースト・コミュニケーション)にて2004年から2006年にかけて連載されたコラム「アメリカン・マッスル」からの11作品を本日公開いたしました。1940年代から70年代頃までの、アメリカを象徴するさまざまなモノや文化、広告などから今はもうない「アメリカらしさ」について考察したものです。真壁一智さんのイラストとともにお楽しみ下さい。
「鹿は一発でしとめるんだよ」
という台詞が、『ディーア・ハンター』(1978)というアメリカ映画のなかにあった。
「鹿撃ちの核心はここにあるんだ。鹿を撃つとは、一発で倒すことなんだよ」
誰の台詞だったか忘れたけれど、鹿を撃つアメリカの男が、そんなふうに言っていた。もっともポピュラーな.30/30の銃弾が、マガジンの中に5発ないしは6発。オートマティックなら標的の鹿に狙いをつけたまま、1秒弱に1発の速度で、撃ち込むことはたやすく可能だ。でも本当の鹿撃ち男には、そんなことは許されないようだ。
(『Free & Easy』2005年5月号)
1943年の『ライフ』に掲載された、ウィリス・オーヴァーランドのジープを主題とした、戦意高揚広告のひとつだ。ヨーロッパでも太平洋でも、ありとあらゆる場所で、軍用車輛としてのジープは大活躍した。ジープが誇ったすぐれた性能は、いくつも列挙することが可能だ。そのなかでも特筆されるべきは、道なき道という極限的な悪路の、走破性能だった。これが欠けていたなら、他の部分の性能がいかにすぐれていても、少なくとも戦場では、使いものにならない。
(『Free & Easy』2005年6月号)
GM(ぜネラル・モーターズ)のシェヴロレー部門が1958年に送り出した、インパーラという車種のコンヴァーティブルが描いてある。この絵のような情景が、アメリカのいたるところで現出された。第二次大戦の間はずっと、少なくとも民間用の一般的な自動車に関しては、新しく開発することはもちろん、従来からの車を製造することも禁じられていた。シャーシから何からまったく新しい設計になったのは、1950年代の後半になってからだった、と僕は記憶している。
(『Free & Easy』2005年7月号)
北アメリカ大陸の大きさを体感するには、グレイハウンドの大陸横断路線にひとりで乗るのがいちばんいい。大陸の大きさとは実は力なのだ、という事実を自分の全身で痛感することが出来るからだ。窓の外の広大な夜のなかに視線を向けたりしているが、やがて眠くなる。うとうとする。ときどき目が覚める。バスはひた走る。外にある夜の闇が、目が覚めるたびに、少しずつ淡くなっていく。そんな時は、太陽が昇るよりも先に目を覚ますといい。
(『Free & Easy』2005年8月号)
ほどよい長さに切ったフランス・パンを水平に切り開く。片側はくっついたままにしておく。土台になるほうのパンの表面に、マヨネーズを充分に塗る。その上にレタスを敷く。スライスされたチェダー・チーズをレタスの上に載せ、トマトのスライス、太いサラミのスライスの半分などを、少しずつずらしながら何度か繰り返して重ねていく。端から端まで具を並べたら、開いてあるパンを閉じ、全体に平均して重みが加わるよう、重しをかける。このサンドイッチを、ヒーロー・サンドイッチという。
(『Free & Easy』2005年9月号)
思いがけず、実に久しぶりに目にしたり聞いたりすると、ほんの一瞬たいそう懐かしい気持ちになる固有名詞、というものが確かに存在するようだ。僕の場合はアメリカのものが多く、人の名前や製品の名称、ブランド名だったりする。「アンスコ」はそのなかのひとつだ。会社名であると同時に、そこで作っていた製品の名称でもあった。声に出して言ったときのその音のなかに、少なくとも半世紀は昔の、アメリカらしさが宿っている。アンスコのカラー・フィルムは、少年の頃の常用フィルムだった。
(『Free & Easy』2005年10月号)
映画『カサブランカ』の中でハンフリー・ボガートはリチャード・ブレインという役を演じた。愛称はリックだ。リックのアメリカン・カフェという酒場を、第二次大戦中のカサブランカで営んでいる。その酒場に、ある日のこと、かつてパリで恋仲で、最終的には自分を捨てた美貌の女性イズラ・ランドがあらわれる。「世のなかに酒場なんていくらでもあるのに、よりによってこの俺の酒場に姿を見せるとは」という台詞は、メロドラマの本質を言い当てた名言として、いまだに忘れられていない。
(『Free & Easy』2005年11月号)
日本を相手に太平洋で戦争をしていたアメリカが、戦場のいたるところで披露していた戦争名場面、とも言うべき情景がふたつある。どちらも1943年の『ライフ』に掲載された戦意高揚広告からのものだ。そのひとつ、ソロモン島の密林で戦うアメリカの海兵隊員たちがシャワーを浴びている様子を捉えたものは、側面から見るとAの字に見える三角形の枠の一方が板張りになってふさがれていることに注目したい。戦場の密林の中とは言え、シャワーを浴びる兵士たちに最低限のプライバシーは保証されているのだ。
(『Free & Easy』2005年12月号)
太平洋戦争中、一般的な雑誌に載る広告はどれもみな、自分たちの会社が戦争遂行にどれだけ深く参加し協力しているかを、徹底して訴えるものとなっていた。この家具製造会社の1943年の広告もそうだ。戦争が終わって本来の仕事へ全面復帰したなら、アメリカの居間をこのようにしてみせます、という広告だ。この居間の絵を当時の日本の人たちが見せられたとして、これが一体何なのか、それがそもそも理解出来なかったのではなかったか。
(『Free & Easy』2006年1月号)
1973年1月の終わりに、ヴェトナム和平協定がパリで調印された。そして3月には国際通貨危機が再燃した。この年の日本は石油ショックの年として記憶されているはずだ。OPECが原油を70パーセント値上げし、生産と供給の制限を決定した。このことが市井に伝わると、トイレット・ペーパーがなくなる、というパニックとなり、スーパーに押し寄せた主婦たちはトイレット・ペーパーを奪い合い、怪我人の出る騒ぎが続いた。同じ年にアメリカで発売されたエル・キャミーノ・コンキスタという自動車は、僕個人にとっては1973年を象徴する、忘れがたいアメリカだ。
(『Free & Easy』2006年2月号)
12歳になる少し前、アメリカの雑誌に掲載されていた広告をとおして、ポータブル・ラジオというものの存在を僕は知った。その造形の魅力が僕をとらえた。日常生活のなかでごくあたりまえに使用するさまざまな物品のなかで、アメリカらしさを僕がもっとも強く感じたのは、この時代のポータブル・ラジオだ。誕生日には何が欲しいかと親戚の人たちに訊かれると、どの人に対しても、ポータブル・ラジオが欲しいです、と僕は答えた。
(『Free & Easy』2006年3月号)
2024年11月29日 00:00 | 電子化計画
次の記事へ