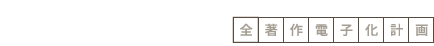音楽エッセイ『Music Gallery』10作品を公開
音楽エッセイ『Music Gallery』(枻出版社『NALU』/2009年7月〜2011年4月連載)全10作品を本日公開いたしました。
40年前、いちばん近いところで25年前、という期間、なぜだか僕は買い込むLPの大半をハワイで買っていた。そこには日本で見たことのないような歌謡曲のLPがたくさん置いてあった。その頃の収穫のひとつが『ハレクラニの夕暮れ』だ。ハレクラニとはハワイ語で「天国という言葉がもっともふさわしい家」というような意味で、ワイキキ・ビーチにあるホテルの名前だ。『エ・フリ・マコウ』『フラ・ブルース』『レイ・フラ』『カ・ロケ』『ムーンライト・イン・ヒロ』『プア・ママネ』など、スピーカーから放たれるのを体内に取り込んでいると、ふとした瞬間、強烈な懐かしさを覚えると同時に、聴くたびに体験する完璧な新しさに、僕は揺り動かされもする。
『The Halekulani Girls – Twilight At Halekulani』
(『NALU』71号/2009年7月1日掲載)
スラック・キー・ギターの伝説的奏者、と呼ばれる人たちがハワイに何人かいる。そのなかで伝説度も名手度もともにもっとも高いと僕が思うのは、レナード・クワンだ。スラックさせたキー、つまり何本かの弦を、本来のチューニングよりもゆるませて下げることによって手に入れたキーで演奏するギター、それがスラック・キー・ギターだ。レナード・クワンがそのようなギターで演奏する曲のなかには、僕が理想とするハワイのすべての要素が、ぎっちりと詰まっている。そのなかで最重要な要素は、哀愁、哀感、悲しみ、悲哀などの感情だ。
『Leonard Kwan – Slack Key』
(『NALU』72号/2009年9月1日掲載)
ラナイ・パウロのこのLPを手に入れたのは、1960年代なかばのことだったと思う。二十代のまんなかという年齢だった僕は、唱歌や流行歌など日本人に広く親しまれた歌曲の傑作を、ピアノで好きなように弾いてはひとり楽しむ、という趣味を実行していた。ラナイ・パウロのLPを久しぶりに聴いて、僕はピアノを弾いてみたくなった。『涙の渡り鳥』『別れの磯千鳥』『荒城の月』『さくら』『旅の夜風』『浜辺の歌』『花言葉の歌』など、選曲はごくおだやかに中道をたどっている。こうしたポピュラーな名曲は、そのどれもが、メロディとともに歌詞も、ある世代の日本人にとってはDNAも同然のものだから、曲想とは歌詞の世界であり、演奏するにあたっては歌詞が演奏の内部に完璧に溶け込んでいなくてはいけない。
『Rene Paulo – Favorite Melodies Of Japan』
(『NALU』73号/2009年11月1日掲載)
ハニームーン、という言葉は死語だろうか。蜂蜜と月の結びついた英語を、片仮名書きした日本語だ。本来の日本語では、蜜月という。死語としての雰囲気はこちらのほうが濃厚だ。アメリカのポピュラー音楽業界が、アメリカ以外の国に材料を求めた時期があった。1950年代の終わりから60年代のなかばにかけてだ。自国内での材料が底をついた、という思いがあったからだろう。キャピトルから発売された『南太平洋の蜜月』は、キャピトルが世界じゅうで録音した数多くのLPのうちの一枚だ。どの国でも人々によく知られたポピュラーな音楽を録音したのだが、編曲と演奏の方向は、アメリカの大衆に向けたロマンティックで心和む音楽、ということだった。当時の世界はまだ広かったが、ロマンティックなイメージをかもし出す土地として、代表的な位置にあったのが、フレンチ・ポリネシアだった。
『The Voices Of The Atolls, The Zizou Bar Trio – South Seas Honeymoon』
(『NALU』74号/2010年1月1日掲載)
このLP『アローハ・サモーア』が録音されたのは1960年代のなかばだろう。僕が買ったのは1960年代終わりの、確かニュージーランドでだった。このLPに収録されている音楽を再生してスピーカーから全身に受けとめるとそのたびに、窓ないしはドアは全開となり、それをとおして日常的には忘れっぱなしとなっている自分を僕は発見する。こういう音楽が心の底から好きだ、という自分だ。単に好きというだけではなく、聴いていると身も心も洗いつくされ、本当に必要最小限の自分に立ち帰ったような、爽快で身軽な幸福感が、体の芯から全身へと広がっていくのを僕は覚える。DNAの長い長い連鎖を過去に向けてたどったその果てには、南太平洋の血とかろうじてつながっている自分がいたとしても、そこに不思議はなにひとつない。
『The Samoan Surf Riders With Bill Sevesi & His Islanders – Aloha Samoa』
(『NALU』75号/2010年3月1日掲載)
ウクレレというハワイ語は、これ以上ではあり得ないほどに、あの楽器に本当にぴったりだと僕は思う。ハワイ語の辞書でウクレレという言葉を調べてみると、ただ単に蚤という意味もあることが、わかる。ウクレレの名手は、かつてもいまも、その数は多い。LPやCDに残された名演奏はたくさんある。どのような楽器編成でどんな演奏をするかによって、ウクレレがその全体に添える雰囲気はさまざまに変化する。大きくふたつに分けて軟派と硬派とがあるとすると、ジェシー・カリーマのウクレレは、少なくともこのLPに限っては、硬派の極みにあると言っていい。『ククナ・オカ・ラ』『リリウ・エ』『ヒロ・マーチ』『コハラ・マーチ』など、僕の好みの曲が、スティール・ギターやヴィブラフォンはもちろん、ギターすらなしで、カリーマのウクレレは打楽器の小気味よさと見事に重なって一体だ。
『Jesse Kalima – Jess Uke』
(『NALU』76号/2010年5月1日掲載)
ヘンリー・マンシーニには100枚を越えるLPがあるという。このLP『Music of Hawaii』のジャケットの絵は下手だと思うけれど、ハワイもののLPのジャケットの絵柄としては、古典的と言っていい位置にある。LP全体の値打ちのうち、80パーセントほどはこのジャケットが生み出している。ワイキキの海岸に、高層ホテルや観光客その他、いまあるものがいっさいなにもない、という絵柄は素晴らしい。海岸の前に広がる海はマラマ湾と呼ばれている。この呼び名は、日本ではまったく知られていない。ジャケットに描かれたランドマーク的な椰子の樹を背にしてマラマ湾と向き合い、やや左寄りに方向を取りながら湾の沖へと出ていくと、そこにはポピュラーズと名づけられたサーフ・ブレイクがある。
『Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Music Of Hawaii』
(『NALU』77号/2010年7月1日掲載)
カントリー・コンフォートというグループによるこのLPを、収録されている『ワイマナロ・ブルース』という1曲ゆえに、僕は忘れることが出来ない。完璧な出来ばえのこの歌曲を聴くたびに、その奥行きは深まり、陰影は複雑さを増していく。グループの最初のかたちは、ワイアルーア育ちの3人の青年たちによって作られた。そこへさらに2人が加わって5人となったのが、1970年代の初めだった。そして1970年代がまだその前半にあった頃、このLPは発売された。ほぼおなじ頃、ハワイを舞台にして物語を作ることから、僕は小説を書き始めた。子供の頃から深く巻き込まれてきたハワイへの思いをなんとかしたい、という衝動に突き動かされて、次々に小説を書いた。そのときすでに、うっすらとは気づいていたはずだが、僕にとってのハワイは、ちょうどその頃、実は終わりつつあったのだ。
『Country Comfort – We Are The Children』
(『NALU』78号/2010年10月1日掲載)
ザ・サンズ・オヴ・ザ・パイオニアズ(直訳して、開拓者の息子たち)はカントリー・アンド・ウエスタンの男性コーラス・グループだ。このLPは1969年のもので、ハワイないしは南の島を主題にしたポピュラー・ソングを11曲、歌っている。1960年代は僕の20代と重なっている。その60年代の終わりに寄り添った歌は、時間順にいくつかあり、どれもがいまも大事だが、いちばん最後のところで僕と一体化したと言っていいのが、ザ・サンズ・オヴ・ザ・パイオニアズの『タイニー・バブルズ』だ。僕をもっとも強くとらえたのは、間奏の部分にあるヴィブラフォンによる演奏だ。『タイニー・バブルズ』を再生して聴くと、1960年代の終わりと、そのときそこに後期青年としていた自分が、きわめて密度濃厚に立ちあらわれる。
『The Sons Of The Pioneers – The Sons Of The Pioneers Visit The South Seas』
(『NALU』79号/2011年1月1日掲載)
セシリオ・アンド・カポノのこのデビューLPは1974年のものだ。僕は次の年にホノルルで買った。このLPから何曲かを、『きまぐれ飛行船』というFM局の2時間番組で、何度か放送した。35年ほどたったついさきほど、僕は聴いてみた。この音楽にハワイを感じるのは難しい。そのかわりに、バブルへの急激な浮上の途上にあった日本で、若年層がこだわった軽さというものは、存分にある。ここではない、という種類のどこかを自分の場所として夢想する人たちにとって、軽さはきわめて重要な要素だった。軽くなければ浮いてはいられないのだから。
『Cecilio & Kapono – Cecilio & Kapono』
(『NALU』80号/2011年4月1日掲載)
2023年5月23日 00:00 | 電子化計画