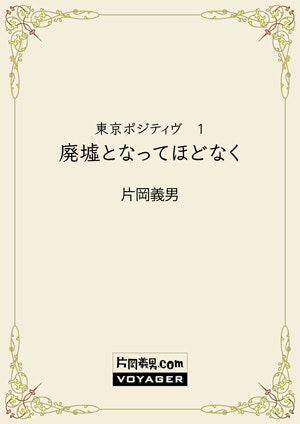写真エッセイ『東京ポジティヴ』より6作品を公開
写真エッセイ『東京ポジティヴ』(『日本カメラ』/2007年)より6作品を本日公開いたしました。
カラー・リヴァーサル・フィルムの1コマの中に写された風景。その風景の記憶は撮影した自分にも残っている。フィルムを覗き込むとフィルムの風景と記憶とが重なり、まるで模型を観察しているような気分になる。現実の景色とは、人々が生活を営み、日々の暮らしを持続させ、それぞれに人生を作っていく現場なのだが、そこからすべての人たちを退去させると、あとに残された人々の生活や暮らしのためのさまざまな建造物の集積は、リアルさをきわめた精密な原寸大の模型、つまり抜け殻でしかない。それは端的に、廃墟と呼ばれる。
(『日本カメラ』2007年1月号掲載)
子供の頃から馴染みのある35ミリ・フィルムの箱やパトローネについて、統一された記憶はない。しかしフィルムを装填していくときの気持ち、装填し終えた写真機を手に持っているときの気持ち、写真を撮るという行為に向けての高揚した気持ち。これらは子供の頃から今まで、なにひとつ変わる部分はなく、僕と写真機を結びつけている。36枚撮りの35ミリ・カラー・リヴァーサル・フィルムとは、少なくとも僕にとっては、このようなものだ。そのリヴァーサルに、晴れた日の太陽光を受けている東京の、順光の景色を無人で、撮りたいと思う景色を撮りたい構図で、半日ほどかけて僕は撮っていく。
(『日本カメラ』2007年2月号掲載)
写真機を持って東京を歩いていて、もっとも数多く目にするのは町名や番地を示した表示板だろう。東京が持っている行政能力の全てが、この小さな金属製の板に露呈されている。カメラのファインダーで捉えると、その光景はなかなかなの出来栄えだ。いま東京にある町名のすべてを、町名所番地表示板のある光景として写真に撮り、東京町名図鑑と仮に呼ぶ一冊の本にまとめる、という空想をいま僕は楽しんでいる。東京をくまなく歩く試みとして、2年もあればすべての町名を拾い集めることが出来るだろう。手始めに東西対抗など面白いかもしれない。
(『日本カメラ』2007年3月号掲載)
下北沢とその近辺に、僕は子供の頃から30年ほど住んだ。この写真にある踏切も子供の頃から知っている。今の風景よりもはるかに素朴で簡素なものだったことをかすかに記憶している。僕の東京生活は、半世紀をゆうに越えている。その半世紀という時間の流れのあちこちに、東京生活の名場面とも言うべき場所とその光景が、いくつかかならずあるはずだ。撮ってみようか、と僕はいま本気になりかけている。そうすれば、そのときどきの自分がまるで化石のように埋まっているのを発見することになるはずだ。
(『日本カメラ』2007年4月号掲載)
いつどこで撮ったか、自分ではまったく覚えていない窓の写真。日常的には縁のない場所へ写真を撮るために出向いていき、そこを歩いているときに見つけた窓だ。窓としての機能はなくなっているが、形はまだ残っており、しかもそれが消えていく過程だ。なんとも言いようがない、素晴らしい窓ではないか。撮りためた東京の光景のなかから、40年ほど前まで一般的だった、古い窓の写真だけを抜き出してひとまとめにしたなら、そのひとつひとつが、そして集積としての全体が、なにごとかを雄弁に語るはずだ、と僕は思う。ほぼ完全に寡黙に、しかしきわめて雄弁に。そのどれもが、怖い風景、と言ってもいいだろう。なにが怖いのか。
(『日本カメラ』2007年5月号掲載)
五十年前とほとんど変わることなく今もそこにある景色、というものはもはや東京にはない。ディテールだけでいいなら、今でもなんとか落ち穂拾いをすることは可能かと思うが、自分がその中へと入っていくことの出来る、立体的な空間としては、昔はどこにも残っていない。昭和を懐かしむ内容の書物が、このところ数多く刊行されている。写真を多用したそれらの書物のなかには、消えていった昭和が確かにある。懐かしいのは、戦後の東京の、激変に次ぐ激変で消えたものではなく、激変の始まる前に存在していたものをめぐる、いまとなってはあるかなきかの、おぼろな記憶なのだ。
(『日本カメラ』2007年6月号掲載)
2022年11月29日 00:00 | 電子化計画