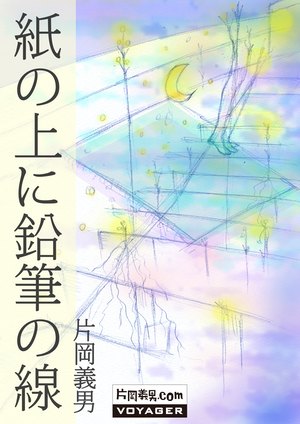『物のかたちのバラッド』8作品を公開!


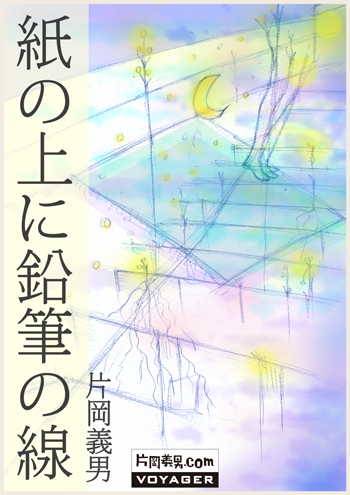

『物のかたちのバラッド』(アメーバブックス/2005年)所収の短編8作品を片岡義男.comで本日公開しました。
これらの作品それぞれに男性の主人公がいますが、共通しているのはいずれも「絵を描く人」であるということ。「あとがき」の中で筆者は「(絵を描くという)行為のなかには、それぞれの主人公の来し方と行く末という、心の営みのすべてが溶け込んでいる」と書いています。そしてどの物語にも女性がもう一方の主人公として登場します。ストーリーの中で彼と彼女がどのように関係しあうのか……どうぞ本編をご覧ください。
『バスを待つうしろ姿』の主人公、北原亜紀男は絵が描けます。絵が描ける人というのは、本当にこんな風に、本人は無自覚に驚くほど全てを「絵」という形で描いてしまうので、自分が絵が描ける事がよく分かっていなかったりします。これは、才能全般に言えることで、文章が書ける人も、映像が作れる人も、どうして自分が、それを出来てしまうのか分からないどころか、出来ているかどうかさえ自分では把握していなかったりします。だから、この物語のように、誰かに「描け」と言われなければ、中々その気になれないものです。同じようにもう一人の主人公である長谷川裕子も、その才能に言われなければ気がつきません。昭和38年の東京では、こうやって才能を発掘してもらえる環境があったのだと思うと、何だか泣けてきます。
『紙の上に鉛筆の線』は『バスを待つうしろ姿』同様、才能と仕事についての物語です。どちらも『物のかたちのバラッド』の収録作で、つまりは「物のかたちを捉える」ことについての小説なのです。『紙の上に鉛筆の線』の主人公は「絵を描くのは作業だと思っています」と言いますが、それは物作りに関わる人全員に言える正しい認識なのだと思います。だから続けられるし、仕事に出来るという訳です。この物語で彼に自分を描いてくれと頼む女性が、果たして、ゴダールにおけるアンナ・カリーナや、ウッディ・アレンにおけるミア・ファロウのような存在になるのか、それは、この物語の中では描かれません。そこが、この小説の肝だと思うのです。
かつて、筆者が30代のフリーライターだった1990年代の終わりには、40代、50代のライターやイラストレーターを編集部で見かけることがほとんどありませんでした。その頃は、ある程度売れると、編プロや事務所を構える人が多かったのです。今は、むしろ若い専業ライターが少なくなっていますが、この『後悔を同封します』の時代、80年代半ばに、事務所を辞めて絵描きに戻ろうとする主人公の決断は、相当の勇気が必要だったはずです。一般的なコースの逆を行くわけですから。その決意と行動について、片岡義男の筆は、リアリティたっぷりに描写していきます。「絵を描く」という現場に戻るために振り絞らなければならない勇気が、元妻へ送るカードに凝縮する、何とも凄まじい小説です。
この『坂の下の焼肉の店』や『バスを待つうしろ姿』、『後悔を同封します』などを収録した『物のかたちのバラッド』は、絵を描く人たちの視点と行動の中から物語を抽出した作品が集められているようです。そして共通するのは、登場する人たちは皆、絵を描くことそれ自体に苦労することはなく、淡々と絵を仕事にして生活しています。『坂の下の焼肉の店』では、自分がなぜ絵を描くことを選んだかという謎が解けた主人公が、「本当の自分を突然に見つけたようで」と言います。選んだ職業の根拠となるような何かは、多分、そう簡単に見つかるものではなくて、だから、それを父親に告げて、一緒に焼肉を食べに行く情景がたまらなく感動的なのでしょう。
消えゆく都電のある風景を絵にして、本として残そうと考える職業画家を主人公とする『都電からいつも見ていた』は、都電そのものがもう一つの主人公のようです。作中で語られる1968年の秋に廃線になり、出版社に通う主人公が起点から終点まで乗っていて、夜の早い時間に人が少なくなるということから、多分、この都電は、九段下と早稲田を結ぶ、都電江戸川線ではないかと思われます。とすると、作中に登場するバー異邦人があるのは、石切橋か東五軒町辺りでしょうか。都電の駅があるから成立していた店や街が、かつての東京にあって、そこで様々な物語が生まれたであろうという記憶を、片岡義男は見事に小説という形で記録しています。
意味が分かると何ともエロチックなタイトルであり、長編小説にもなりそうな人間関係の恋愛小説であり、絵が描けること、見えてしまうことについての物語でもある、この重層的な内容を、サラッと短編小説にまとめてしまう片岡義男の凄みを堪能できる短編小説です。1965年という時代ならではの、性に対して積極的な女性像を、タイプが違う二人の女性それぞれに描き分けることで、「いかにもそういう女性」というステロタイプな表現に対して、さりげなくアンチを表出しているようなカッコ良さと、安易にアーバンラブストーリーへ堕しない、正しく「東京の恋愛小説」であることが両立した、物凄く読みごたえのある小説。コロナウイルスの蔓延で外出しにくいこの時期、じっくりと読んでみてください。
高校時代に大好きだったブロンディというバンドのボーカリスト、デボラ・ハリーの自伝を読んでいて、彼女が筆者の母親と4歳しか違わないことを再認識しつつ、しかし、今の彼女も十分魅力的に見えるなあと、思っていました。片岡義男の『いまはそれどころではない』を読んで、主人公の女性とデビーが重なって、「好きな形」というのは、年齢とは無関係に好きなのだな考えたときに、本作を含む短編集『物のかたちのバラッド』というタイトルで、絵を描ける、つまり形を捉えることが自然にできる男性と、彼に近づく女性の物語を揃えるという趣向の見事さに気がつきました。それは正にバラッドであり、この短編は、それを最も露わに見せてくれているような気がするのです。
短編集『物のかたちのバラッド』に収められた各短編が描いてきた絵が、この『孤独をさらに深める』で、物語となります。絵がかたちを写すものなら、小説は絵の前後に流れる時間を捉えるものだという、歌人荻野景子の言葉は、絵を描く人、文章を書く人の双方に深く響くとともに、希望さえ与える言葉だと思います。その希望は、この小説の最後に記されて、そして絵描きは物書きへと向かいます。それはしかし、ただでさえ孤独な作業であった絵を描くという行為から「かたち」さえもない、時間の流れを見つめる行為への移行であり、「孤独をさらに深める」ことになります。見て、何かを作る行為は、そこにどれだけ魅力的な女性たちが関わったとしても孤独であることに変わりなく、だからこそ、この短編集はバラッドなのですね。
2022年1月28日 00:00 | 電子化計画
前の記事へ
次の記事へ