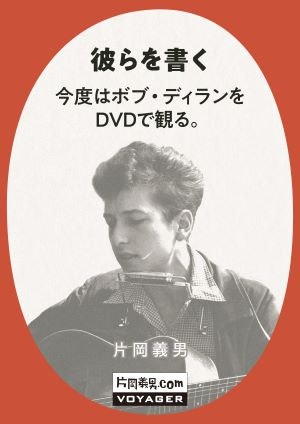『彼らを書く』より「今度はボブ・ディランをDVDで観る。」を公開
音楽エッセイ『彼らを書く』(光文社/2020年)より、「今度はボブ・ディランをDVDで観る。」の13篇を本日公開しました。
※(13篇を1作品として公開しています)
「そこは去らなければならない楽園だった」
1963年のニューポート・フォーク・フェスティヴァルに登場したとき、ボブ・ディランはすでにフォーク・ソングの世界の新しいスターだった。フォーク・ソングの世界は、1961年の1月にディランがニューヨークに出て来たときには、すでに完成していた。完成していたとは、それ以上の展開の可能性はもはやどこにもなかったということであり、あったのは思いのほか早く下降していく時間だけだった。他の場所から来てそこに加わったディランにとって、確かにエデンの園に例えることの出来た楽園だったろう。そこは楽園だった、と書いたディラン自身、フォーク・ソングの歌手と呼ばれて、すでに完成の域に達していた。アクースティック・ギターに代表されるフォーク・ソングの世界全体に関して、当時のディランはすでに明らかな限界を見ていた、と僕は解釈している。完成されたスタイルの内部ではなく、その外側にある不定型さのなかにい続けたいと願うなら、フォーク・ソングの世界からは去るほかない。
・『The Other Side of the Mirror Bob Dylan Live at the Newport Folk Festival 1963-1965』(邦題『ニューポート・フォーク・フェスティバル 1963~1965』/2007)
「意味のつながりなどまったくない配列のなかに」
『No Direction Home』は2005年のマーティン・スコールセッシ監督によるドキュメンタリー映画だ。合計で3時間28分となるが、観る価値は充分にある。英国の町角にひとりでいるディランは、建物の柱のようなところに取り付けてある広告板の文言を目にとめる。ディランはその広告の文言から、自分だけのものである一編の詩を作っていく。きわめて平凡な広告の中の、全く日常的な文言の連なりから何らかの刺激を受けたディランは、その刺激を一編の詩へと作り変える。その作業にディランは成功している。子供の頃のディランはラジオで数多くのカントリー・ソングを聴いた。そこから始まって、ニューヨークでのフォークソングとの出会いに至るまで、そしてその後から現在まで、ディランにあったのは言葉だ。作詩作曲、という日本語を英語にすると、Words and musicとなる。この文脈でのwordsが彼には始めからあった、という言いかたをしておこうか。
・映画『NO DIRECTION HOME BOB DYLAN』10th Anniversary Edition Trailer』(邦題『ボブ・ディラン ノー・ディレクション・ホーム』デラックス10周年エディション予告編)
・『Bob Dylan Word Play - No Direction Home: Bob Dylan』
「頭を明晰にして常に電球を持ち歩く」
『Dont Look Back』という上映時間96分の白黒ドキュメンタリー映画は、1965年のイギリスで行われたボブ・ディランのコンサートを撮影したものだ。ロンドンに到着してすぐ、ディランは空港でインタヴューを受けた。何かの工場で使うような巨大な電球が、なぜだかテーブルの上にあった。"What's your real message?" と、ディランは中年の記者に訊かれた。この質問に対するボブ・ディランの返答は次のようなものだった。"Keep a good head and always carry a lightbulb" 既成のもので満ちている社会のなかに生きる自分は、そのような既製品のひとつだという自覚は、1965年のイギリスには全くなかったようだ。当時は20代半ばの青年だったボブ・ディランとその一行と、イギリスとの間にあった、凄まじく大きな隔たりを感じないわけにはいかない。ふと聴いた歌を、いい歌だ、と思ったとき、That's a good song.と簡単に評することは、誰にでも出来る。しかしボブ・ディランがThat's a good song.と言うときには、そこにあるボブ・ディランの現在とそれまでを総動員した、songにかかわる体験の途方もない量と時間的な長さが、判断の根拠となって機能している。その事実をこの作品は見せてくれる。
・『BOB DYLAN DONT LOOK BACK』(邦題『ドント・ルック・バック』1967)Trailer
「大量生産の構造上の再生」
1965年12月3日、ボブ・ディランはサンフランシスコに来ていた。バークレーのコミュニティ・センターで3回のステージを含め、10日間で5回のステージに出て歌う予定だったという。この項の題名に使った言葉を英語で言うと、Constitutional replay of mass production となる。記者会見の席で、記者の質問に答えたディランが即興的に考え出した言葉だ。サンフランシスコのKQEDというTV局がスタジオでボブ・ディランの記者会見を行い、TVカメラでそれを撮影した。この記者会見は、ディランにとっては初めてTVで放映される記者会見だった。ディランと向き合った記者たちは、『Dont Look Back』で見たイギリスの記者たちと実によく似ている、と僕は思った。人々の感触がよく似ているだけではなく、ボブ・ディランとの間にある大きな乖離感まで、そっくりだった。24歳にしてすでに、ディランはとんでもなく遠いところにいた、とでも理解すればいい。『Dylan Speaks』という題名でこの記者会見は2006年に1枚のDVD作品となり、日本でも市販された。
・『Dylan Speaks The Legendary 1965 Pres Conference In San Francisco』(2006)
「ただ聴く人でしかない自分」
『Bob Dylan 1966-1978 After The Crash』のCrashとは、ディランが起こしたオートバイ事故のことだろう。1966年の7月のことだった。これ以来8年にわたって、ディランは舞台に立って観客と向き合うことを停止したと言われているが、完全に停止したわけではなかったようだ。録音スタジオに入っているときのボブ・ディランには、たいそう強い芯のようなものが常にあると、ともにスタジオで仕事をしたミュージシャンが語っている。誰もが、その強い芯のどこかにつかまることによって、ディランが作ろうとしている音楽の世界に入っていくのだそうだ。完成品を再生して聴く人にとって、創造物であるはずのどの曲についても、細部まで分け入って理解することは、とうてい無理なことだと僕は思う。聴くその人は自分であり、自分が持っている能力の範囲内でしか、聴く作業は維持されない。完成品をそのいちばん外側から聴いただけではわからないことは無数にあり、そのどれをもわからないままにしておくことが、聴く人の特権のようなものになるのだろうか。
・『Bob Dylan 1966-1978 After The Clash』(2006)予告編
「ボブ・ディランがワイト島を沈める手助けを」
1964年5月17日、ロンドンのロイアル・フェスティヴァル・ホールの舞台でボブ・ディランは歌った。23歳のボブ・ディランはまだ親しみやすい演奏と歌の人だった。フォーク歌手やプロテスト歌手と呼ばれるのは本意ではない、という考えはデビュー・アルバムの頃にくらべると、よりはっきりしていた。ディランが出演した1969年のワイト島アイル・オヴ・ワイト・フェスティヴァルの舞台を最初から最後までとらえた映像は現存していない。残っているフィルムの中心はニュースのための映像で、これは白黒やカラーなど統一はなく断片的だ。『After The Crash』の中に、ワイト島のフェスティヴァルを企画して実現させたレイ・フォークの、当時の姿がある。なぜディランが出演を承諾したのか、その理由をレイ・フォークは回想している。当時の自分は20代の半ばで、業界のプロモーターたちとはまるで違う雰囲気だったからではないか、とレイは言っている。このレイによる『Stealing Dylan From Woodstock』という著作が2015年に刊行された。このタイトルは、ワイト島に出演しなかったならディランはウッドストックに出演したかもしれない、という意味だ。
・『STEALING DYLAN FROM WOODSTOCK』
「映像のなかのディランは四年後にはここにいる」
1969年5月、ABCTVでジョニー・キャッシュ・ショーにディランは出演した。僕がDVDで見るボブ・ディランは、1965年の『Dont Look Back』から4年後のここへ、飛んでいることになる。そのショーでディランは3曲を歌った。以前のディランとは、まるで異なっている。髪の作り、表情、ギターの使いかた、そして歌い方など、なにげなくモニターを見ると新人のカントリー歌手かな、と思うほどにかつてとは違っている。編曲はザ・バンド風だ。こんなかたちでもディランは敬意を表されたのだろう。3曲目の「Girl From The North Country」は、すわってキャッシュとデュエットで歌う。歌う、という行為のなかで、当人が自在に操ることの出来る才能の複雑さ、奥行きの深さ、さらには間口の広さなどにおいて、ディランはキャッシュに到底かなわないことを、僕が確認した映像だった。
・『Dylan on The Johnny Cash Show "Girl From the North Country"』(1969年5月1日)
「時代はとっくに変わった」
『Pat Gallet and Billy The Kid』という西部劇映画にボブ・ディランが出演したのは1972年だった。完成してから45年後に、僕は日本で発売されたDVDで、その映画を初めて観た。脚本を書いたのはルドルフ・ウールリッツアーだ。彼は1971年の映画『断絶』で、ウィル・コリーという人と共同で脚本を担当した。撮影されたあとのフィルムをどのように編集しても、違うヴァージョンをいくら作っても、監督が意図した通りにつなぎなおしても、作品そのものの最終的な出来ばえに、変化はほとんどないのではないか。映画は脚本に沿って撮影される。撮影されたフィルムは脚本をほぼ忠実に反映している。脚本を上まわる出来ばえが、撮り終えたあとのフィルムの編集によって、新たに生まれるとは思えない。だから『Pat Gallet and Billy The Kid』は、ここはこうすればもっと面白くなったのに、とひとりで夢想するための材料として、良く出来ている。
・『PAT GARRETT AND BILLY THE KID』(邦題:『ビリー・ザ・キッド/21才の生涯』1973)
「始まりの終わりの始まりの始まり」
1976年の11月25日に、サンフランシスコのウィンターランド・アリーナで、The Last Waltzと呼ばれているザ・バンドの解散コンサートが行われた。後にザ・バンドとなる青年たち5人(ロビー・ロバートソン。リック・ダンコ。リチャード・マニュエル。ガース・ハドソン。リーヴォン・ヘルム)がひとつところに揃ったのは、1961年の暮れだった。彼らは、ザ・ホークスとして1961年からロニー・ホーキンズのバッキング・バンドの仕事を始めた。1963年の後半、彼らは揃ってホーキンズのもとを去った。彼らはカナダへ戻り、そこで仕事を進め、1965年の夏には、いっしょにやらないか、という電話をボブ・ディランから受けた。アクースティックからエレクトリックになったディランは、ともにステージに出るバンドを必要としていた。ザ・ホークスはボブ・ディランに選ばれたのだ。
・『THE LAST WALTS』(邦題『ラスト・ワルツ』/1978[映像は2018年のリマスター版予告編])
「答えはいまも風に舞っている」
1992年10月16日、ニューヨークでボブ・ディランの30周年コンサートが開催された。このコンサート全体の記録が226分のブルーレイのDVDになっている。自分自身についてかつてディランが語った音声と映像が冒頭で紹介される。ひとつは1965年の12月3日にサンフランシスコで行われた記者会見だ。自分をどう捉えていますか、という質問に対して、24歳のボブ・ディランは、ソング・アンド・ダンス・マンです、という返答で応じた。もうひとつは、確か『No Direction Home』からのものだ。ごく短い言葉で自分にレッテルを貼ってみてください、と記者に言われたディランは、僕はギター奏者です、それだけです、と応じた。51歳となっていたボブ・ディランという人を説明してあまりある引用かと思うが、それを越えて僕が痛切に感じるのは、このコンサートの出来ばえに関する、主催者たちが持った揺らぐことのない自信だ。これだけの自信がどこから生まれて来るのか。選曲とその順番、そしてそれぞれの歌を誰に歌ってもらうかという、3種類の選択結果の、これ以上の正解はあり得ないと当事者の誰もが信じたはずの、見事としか言いようのない正解ぶりだ。
・『BOB DYLAN : 30th Anniversary Concert Celebration』(邦題『ボブ・ディラン 30周年記念コンサート』/1992)
「時間に淘汰されることなく残る美しい曲とは」
『Bob Dylan MTV Unplugged』と言う題名のDVDを店舗の棚で見たので購入した。1994年11月17日と18日の2日間で撮影されたコンサートでの、ボブ・ディランの歌う姿だ。ニューヨークにあったソニー・ミュージック・ステュディオスでそのコンサートはおこなわれたという。MTVで放映するヴィデオを撮影するためのコンサートだったか。放映されたときには割愛された4曲が加わって、DVDでは全12曲だ。ディランの歌を聴いていてやがて発見したのは、ディランが作ってきたのは美しい曲だったのだ、という事実だ。単なるきれいなメロディではなく、容赦なく経過していく時間のなかで、淘汰されることなく残っていくという、硬質なものを持った美しい曲だ。そのことをバンドの人たちはよく承知していたようだ。
・『BOB DYLAN UNPLUGGED』(邦題『MTV アンプラグド』/1994)
「答えを探すのはとっくにやめたよ」
2002年6月、ボブ・ディランはネヴァー・エンディング・ツアーというものを行なっていた。そのツアーが休みの期間に、20日間という短期間で、400万ドルの予算のもとに、場所はLAだけで、この映画『ボブ・ディランの頭のなか』は撮影されたそうだ。いい映画だ。ボブ・ディランがこの映画の中で演じているジャック・フェイトという歌手は、重なるのか。別々だ、と僕は判断した。映画の最後の部分で、体のうしろで両手に手錠をかけられたフェイトが、自動車でひとりどこかへ連れていかれる。その画面にBlowin' In The Windの歌が重なる。演じたのはディラン、そして演じられた架空の人はフェイトだ。このふたとおりの人物が、最後の場面でくっきりとふたつに分かれて、立ちあらわれる。いい映画だ、と僕が言うのには、このような意味もある。映画のなかで使われている歌の多くはディランが作ったものだ。そのディランの曲のカヴァーをたくさん聴くことが出来る。ディランの曲のカヴァー集に映画としての映像がついたもの、と捉えて楽しむことも可能だ。
・『MASKED AND ANONYMOUS』(邦題『ボブ・ディランの頭のなか』/2003)
「この僕がいけないのか」
『I'm Not There』という題名は、そこにいるのは本当の自分ではない、という意味だろうか。ディランの自作曲の題名で、2007年にアメリカで公開された劇映画だ。あらすじを日本版のDVDのパッケージから引用してみよう。「詩人、無法者(アウトロー)、映画スター、革命家、放浪者、ロックスター。実在のボブ・ディランのさまざまな人格を投影した6人のディラン。それぞれ名前も年齢も異なる6人のディランがくり広げる6人の物語。やがて明らかになる謎に包まれた伝説のアーティスト、ボブ・ディランの実像とは……」。この映画はこのような内容なのだろうか。当時のアメリカがかかえていた問題を6つ抜き出し、それぞれを6人の男性に演じさせた6つの物語なのか。何がどうなっているのかよくわからない、ということが6つの物語の展開に共通している。だから、ときおりこの映画を思い出しては、実はどうなっているのかを、そのつど考えるための材料としての映画なのか。何ひとつわからないのは、この僕がいけないのか。僕のせいではないように思う。では、何のせいなのか。
・『I'M NOT THERE』(邦題『アイム・ノット・ゼア』/2007)予告編
(以上13篇『彼らを書く 「今度はボブ・ディランをDVDで観る。」』光文社/2020年より)
2024年4月26日 00:00 | 電子化計画