エッセイ『言葉の人生』を公開
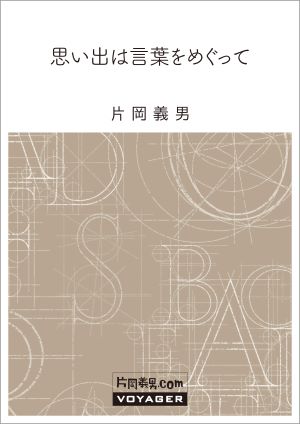



エッセイ『言葉の人生』(左右社/2021年)の89作品を本日公開いたしました。
01 バッテンボーからビル・ライス・テレビの国へ
一九五〇年、「バッテンボー」という言葉が日本じゅうで大流行した。一九四八年に製作された西部劇コメディー『The Paleface』(邦題『腰抜け二挺拳銃』)は、一九四九年十二月には日本でも公開された。主演のボブ・ホープが劇中で歌う『Buttons And Bows』という歌が主題歌はアメリカでも日本でもヒットした。「バッテンボー」は、この歌の題名である「Buttons And Bows」をメロディに乗せて歌うとき、当時の日本の人たちには「バッツアンボゥーズ」と聞こえたことに由来する。
▼こちらからお読みいただけます
02 Zicoとジーコはおなじなのか
かつて日本にジーコという人がいた。日本のサッカーチームの監督をしていた外国の人だ。そのジーコが日本のサッカーチームの監督を辞めてしばらくしてからだったと思うが、英語の新聞を新幹線で読んでいた僕は、スポーツページで「Zico」という綴りを見出しのなかに見た。Zicoはジーコなのだ、と閃いたときの僕が、もうひとつ同時に、きわめて強く感じたのは、外へ向かう力と内へ向かう力、ということだった。
▼こちらからお読みいただけます
03 ミーティングでペンディングとなる
戦後の日本を作ったのは、全国に林立する数多くの会社だった。カタカナ語を受け入れ、自らも大量に作っては、毎日のようにそれを使ったのも、サラリーマンたちだった。日本の会社におけるカタカナ語の生産と需要にはすさまじいものがあり、カタカナ語一つだけでは、間に合わなくなると、二語、三語と連なっていった。
▼こちらからお読みいただけます
04 すべてが片仮名語になった国とは
その多くがもとは外国の言葉であるカタカナ語。これなしには、もはや人々の生活はなりたたない。しかし人々は呑気だから、そんなことは考えてみたこともない。例えばケーキ、というひと言がかつて体現していたのは、どこかにある美しい非日常から、自分たちのいつもの日常のなかへと入り込んでくる、なにか特別な輝かしいものだった。それが多様化の道を辿り、最後にはケーキバイキングという言葉のなかに安住の地を見つけ、あとをスイーツに譲った。
▼こちらからお読みいただけます
05 千差万別という面倒くささをいっきに解決するには
ゲットする。ダウンする。オミットする。クローズする。チェックする。トライする。……カタカナの一語に、動詞として使っていることをあらわす「する」のひと言がついたかたちのカタカナ言は無数にある。アクションの内容は、人によって、場面によって、さまざまに異なり、説明する言葉も異なる。その面倒くささを一気に解決してくれるのが、カタカナ語と「する」というひと言だ。
▼こちらからお読みいただけます
06 のっける気持ちはことのほか大きい
プチプラ服、という言葉を友人に教えられたときには、感銘を覚えた。我が日本語もついにここまできたか、という感銘だ。小さなプライスの服、つまり安い服、という意味だが、安い服なんだけども安い服には見えないでしょう、という気持ちが乗っけてある。プレカンにも、軽い目まい、ないしはたじろぎを僕は覚えた。還暦前の、とは言わずにプレカンと言う。プレカンときわめて簡潔に言うことによってできる余地に、自分の気持ちを乗っけるのです、その意味はさまざまです、とこの言葉を教えてくれた人は解説した。
▼こちらからお読みいただけます
07 思い出は言葉をめぐって
「五十年、六十年と時間がたつと、当時は普及し始めたばかりのカタカナ日本語がいまも現役だったりすると、懐かしさに似た気持ちを覚えますよ。たとえば、ミニスカート、という言葉です」
「ミニスカートより短いのがマイクロミニで、大きくて長いのがマキシだ。タイト。フレア。ロング。バルーン。ミディというのもあった」
「スカートでなければスラックスだったね。マンボズボン。サブリナパンツ。ホットパンツ。パンタロン。クロップド。ワイドパンツ。ベルボトム。これはラッパズボンとも言った。ラッパがベルへと変化したのかな」
▼こちらからお読みいただけます
08 「珈琲」のひと言ですべてが通じた時代
喫茶店でウエイトレスに「珈琲」と伝えれば、すべてこのひと言で完結した時代がかつて日本にあった。一九六〇年代を中心に、一九七〇年代半ばくらいまでの時代だ。このような時代が終わったのを個人的に実感したのは一九七三年だった。仕事の打ち合わせのため近くに見つけた喫茶店に入り、いつものとおり「珈琲」と僕が言ったら、「豆を選んでください」と、カウンターの中にいた青年に怒ったような顔で言われた。
▼こちらからお読みいただけます
09 いまでは聞かないし見ない言葉
死語ではないが、そう言えばもう何年も接してないな、と誰もが思うような言葉。電車で座席にすわり、ぼんやりしているときなど、思いつくままに手帳にメモしていくと、楽しい。どっこいさ。チャンネルをまわす。やったぜベイビー。イカスぜ。ごろつき。宿六。…どの言葉もすべて、発展の途上にあった人たちの言葉だ。日本はこのような言葉が昼夜を分かたずに飛び交う国だった。それ以後、日本はどうなったのか。
▼こちらからお読みいただけます
10 男性とは明確に区別された生き物がいる国
「女」のひと文字が頭につく言葉が「女」の項目にあげてある。女をこしらえる。女形。女嫌い。女癖。女狂い。女気。女心。女殺し。女坂。……こうした言葉を観察してやがてわかるのは、男性とは明確に区別された生き物として女性がとらえられている、という事実だ。少し長い語句になると、日本社会の本性があられもなく露わになる。それは男性のほうから女性を、低く見るためのものだ。自分よりも蔑視される人は、自分とは明確に分けられている必要がある。固定観念としてきめられた役割を女性たちに押しつけ、狭い枠組みのなかに彼女たちを閉じ込めて、男たちは安心する。女性の潜在能力に彼らはおびえているのだろうか。
▼こちらからお読みいただけます
11 俺を中心にすべては堂々めぐり
正直言うと。ここだけの話だけど。俺はお前のためを思ってるんだ。こんなことを言うのもお前のことを思えばこそだぞ。もろもろよろしく。いつもバタバタしてましてすいません。また声かけてよ。それはぜひやろう。……現役の勤め人たち数人の協力を得て、いくつものサラリーマン用語を集めてみた。彼らは常にこのような言葉を多用するという。僕が受けた第一印象は、彼らの生産性は低く、大事なのは俺であり、その俺を中心に、すべては堂々めぐりをしている、というものだった。
▼こちらからお読みいただけます
12 ブンブンでロカボにノスヒロ
レンチンという言葉を最初に見たときには、もう日本語は終わりだ、と僕は思った。日本語が終わるなら、日本文化も日本そのものも終わらざるを得ない。電子レンジで調理する、という意味だ。チンは出来ましたよ、と知らせる電子レンジの音で、それに、する、をつけてチンするとはこれいかに。チンから三十年は経過している。ひたすら下降する三十年、つまり失われた三十年のなかを、誰もがいま生きている。
▼こちらからお読みいただけます
13 僕には読めなかった漢字
「所以」これがユエンだと知ったのは四十代に入ってからだ。「若干名」ワカボシナとは、なにか。中学三年のときまだ読めなかった。「水馬」アメンボと読むそうだ。ついさっきまで知らなかった。「年末」これは長いあいだトシスエと読んでいた。ネンマツだと知ってひどいショックを受けた。このショックのたびごとに僕は、正しい読みかたを知っただけではなく、書きかた、つまり漢字も、学んだのだと、いまつくづく思う。
▼こちらからお読みいただけます
14 酒にまつわる言葉について
酒の酔いかたに、日本語は興味を持っているようだ。酔いかたとは、ごく端的に言って、「酒ぐせ」のことだ。言葉はその様子をすくい取り、映している。酒ぐせは、あるひとつの方向のなかで多様だ。すべては「ほろ酔い」から始まる。「千鳥足」「酔っぱらい」「酔漢」「とろんとした目で」。「もうやめとけ」と周囲の人たちが忠告するのも聞かずにいると、「足を取られる」「まっすぐ歩けない」「ふらふらしてる」「立ってられない」「目がすわってきた」「いびきをかいて寝てるよ」というような状態となる。
▼こちらからお読みいただけます
15 僕はきまり文句を使わない人なのか
知ってはいるけれど自分では使わない言葉は、たくさんある。その数多い言葉は僕にとってどんな機能を発揮しているのだろうか。使わないのだから機能してないのではないか、と短気に思ってはいけないようだ。自分が持っている日本語能力の底辺をかたちづくっている、という説はわかりやすい。使わないけれど知ってはいる言葉が無秩序にたくさん、長い時間のなかで重なり合い、そのなかで化学変化にたとえてもいいようなことが起きると、自分の日本語能力の展開に対して、本人にもとうてい自覚できないようなかたちで、かならずや影響をあたえているはずだ、という説だ。
▼こちらからお読みいただけます
16 僕はそこに論理を感じない
数字は論理のはずだが、数を取り込んだ言葉の数々に僕は論理を感じない。感情の日常的な起伏が作りだす凹凸に数がわかりやすく当てはめてある。誰にでもある気持ちの綾。心の動きのさざ波。数字のある言葉はたとえ話だと思えばいいようだ。一騎当千。二人三脚。四方八方。五里霧中。七人の侍。五十の手習い。噓八百。四万五千日。……数字はきわめて具体的なものだ。どの数も、多くの人にとって、実感をともなう。数字によって、自分のなかに眠っていた実感が、呼び起こされる。実感は自分のなかにあるのだから、それはなんとも言い難く、わかりやすい。
▼こちらからお読みいただけます
17 あまりにも素晴らしい出来事
ワンカップ大関という清酒がいまも市販されている。透明なガラスの容器に入っていて、個別に包装されている。その容器はカップに見えなくもない。だから僕はワンカップという商品名を、ひとつのカップに入った清酒、と理解した。一九六四年に定価八十五円で市販されてからごく最近まで、その理解はゆるがなかった。ある出来事をきっかけに、ひょっとしたらこのワンカップは、一杯やりましょう、と日本の人たちが言うときの、あの「一杯」という言葉を、英語に直訳したものなのではないか、と思うようになった。
▼こちらからお読みいただけます
18 そしてすべてを水に流しましょう
十二月一日から大晦日の三十一日に向けて、どの年であっても確実に暮れていく。年末に向けてすべてが押し迫っていく実感は、日々に強まり深くなる。紅白歌合戦。カウントダウン。こうしてめでたく十二月三十一日は一月一日の元旦となり、明けましておめでとう、と人々は言い合う。時間の経過は止まらない。新しい年、あるいは、年があらたまる、というのは単なるものの言いかただ。なにひとつ新しくはならない。むしろ年末と正月との、年に一度の大ルーティンを通過して安心することによって、事態は悪化していく。
▼こちらからお読みいただけます
19 コカ・コーラを飲みましょう
二十八年まえ、編集者と写真家そして僕の三人は郡上八幡にいた。町のどこだったかは覚えていないが、半透明なカヴァーをつけた蛍光灯のすぐ下に、鉄製の丸い広告板が下がっていた。それがコカ・コーラの広告板であることは、すぐにわかった。コカ・コーラのあのロゴが、赤錆に覆われたえんじ色の丸のなかにあり、そのロゴの上に、ごく真面目にもの静かに、DRINKのひと言が添えてあった。ロゴの下には日本語があった。コカ・コーラを飲みましょう、とその日本語は読めた。これを見た瞬間、自分のどこか深いところに届いた衝撃のようなものを、僕はいまでも忘れていない。DRINK Coca-Colaという英語を、当時の日本の人たちは、コカ・コーラを飲みましょう、と訳したのだ。
▼こちらからお読みいただけます
20 「最低限の会話能力」とはなになのか
外国から働きにくる人たちを日本は受け入れている。日本政府は、外国の人たちの入国要件として、彼らの日本語能力を試験している。最低限の会話能力とはどのようなものなのか……。いつもの自分の日本語が、いともたやすく外国語に転じ得る可能性について、多くの日本人は思いもしない。日本語が苦労して少しずつ学んでいく外国語である状況など、彼らにとっては完全に埒外のことであり、想像してみることすら出来ない。言葉は自然に覚えるものだと彼らは言うが、言葉ほど不自然なものはなく、それの習得などもはや不自然さのきわみだ。しかしその不自然さのなかに、どこの国の言葉であれ、それぞれの文化を持っている。
▼こちらからお読みいただけます
21 彼らのその後の人生は
雨のブルース。熱海ブルース。赤と黒のブルース。別れのブルース。思案橋ブルース。……かつて題名にブルースのひと言がある歌はたくさんあった。かつて多くの人に受け止められたこれらの歌の主人公たちは、その後どうなったのだろう。彼らは健在なのか。いまどこで、なにをしているのか。歌のなかの架空の人たちではあるけれど、気になった。そして、刺し身の盛り合わせを食べていくつれづれに、かつて巷で聞いたブルース歌謡曲の数々を、僕は思い出していった。
▼こちらからお読みいただけます
22 「インイチガイチ」の衝撃を受けとめる
小学生の頃の僕はごくたまにしか学校へ行かなかった。教室で先生が言ったことのうち、いくつかはいまでも覚えている。九九の表を初めて見たときも衝撃を受けた。上の数字と左の数字を任意に選んで掛け合わせると、数字の列と行が交差するところに正解がある、というしかけだった。まず最初の、一掛ける一は一、という部分が音声では、「インイチガイチ」となるのを知ったときの、小学校一年生の僕の驚きはすさまじかった。
▼こちらからお読みいただけます
23 チャーリー・ブラウンは直球の投手だ
もう何年にもわたって『PEANUTS』の日めくりカレンダーを使っている。土曜日と日曜日は共通の一ページだが、それ以外の日は、すべて一日が一ページで、その一ページには平均して四コマのコミックスがカラーで印刷してある。主人公はチャーリー・ブラウンだ。二〇一八年三月十六日、シーズン最初の試合で投手のチャーリー・ブラウンは第一球を投じ、ホームランを打たれる。このとき彼は、あの名台詞である、Good grief!(やれやれ!)のひと言を口にする。これしかないだろう、と彼を知る誰もが思う。僕もそう思った。
▼こちらからお読みいただけます
24 日本語にとって「三」とはなにか
冒頭に三のつく言葉を国語辞典から書き写すだけで、二百は超えるだろう。三位一体。三振。三周忌。三段論法。三人三様。などの言葉だ。どこか途中に三の隠れている言葉もある。日本語にとって三とはなにか。神聖な意味でもあるのかと思ったが、そうでもない。広辞苑には「数の名。みつ。みっつ」とあるだけだし、新明解国語辞典第六版には「二の次の数」とあるだけだ。
▼こちらからお読みいただけます
25 国際都市で天麩羅定食を食べる
一九七八年五月に成田空港が開港し、成田はこれから国際都市になるのだ、とメディアは盛んに報じた。二年後、五月の曇った日、久しぶりに訪れた成田は僕が知っていた成田とまったく同じ門前町だった。坂道の途中に、天麩羅を中心にポピュラーな和食を提供する大きな店があった。ウインドウの料理サンプルの前に立っているカードには天麩羅定食とだけあり、その下に値段の数字があり、さらにその下に、明らかに間に合わせで打ったタイプライターの英文字があるのを、僕の目はとらえた。The Tempura Setとその英文字は言っていた。
▼こちらからお読みいただけます
26 六十八年ぶりの日本と日本語
カリフォルニアに在住の日系の作家、ナオミ・ヒラハラの『ヒロシマ・ボーイ』をペイパーバックで手に入れ、読んでみた。マス・アライというカリフォルニアに住む日系のガーデナー(庭師)を主人公にしたミステリー・シリーズの七作目で、シリーズ最後の作品だった。アライさんは移住した両親のもと、カリフォルニアで生まれた。三歳のときに広島へ移ったそうだが、彼のような人たちを当時の日本人はひとまとめにして、帰米、と呼んでいた。
▼こちらからお読みいただけます
27 深い意味はない、しかし俗世間はよく見える
一、つまり「いち」について広辞苑は「自然数の最初の数」と説明している。この「一」のつく言葉が日本語には多い。いくつかの意味があり、読みかたも「いち」「ひとつ」「ひと」「いっ」など、変化する。自然数の最初の数なのだから、なにか深い意味でもあるのかと思ったが、そんなものはないようだ。論理も脈絡もない。いきあたりばったり、手当たり次第に、世間のあれやこれやに合わせて言葉を作るとこうなる、ということの見本のようだ。だから「一」のつく言葉をたどっていくと、日本の像が少しずつ浮かんできて楽しい。
▼こちらからお読みいただけます
28 読んでみた。面白かった
『コーヒーとボク』(相原民人、双葉社、二〇一九)という本が友人から送られてきた。この本に、著者の相原さんが京都に開いたお店にやってきた、ダークスーツにソフト帽の男性の話がある。「フツウのブレンドをちょうだい」とその男性は注文する。この言葉からして、ある程度以上の、年齢を感じるではないか。店にはブレンドはない。対応した青年の説明に「あー、もうええ」と客は言い、席を立ち、店を出ていく。店の同僚は「ホットとかブレンドでコーヒーが出てこないことがストレスなんですよ」と解説した。「コーヒー」とひと言だけ告げれば、やがて一杯のコーヒーをテーブルに置いてくれた時代が、五十年ほどまえの日本には確実にあった。
▼こちらからお読みいただけます
29 クヨクヨ、イキイキ、オイオイ、グッタリ
熱熱。冷え冷え。そこそこ。まあまあ。ごしごし。どくどく。というような言葉が僕は好きだ。もっとも日本語らしいのはこのような言葉だ、と思っているのではないか。例えば熱熱だが、意味はふた通りある。食べ物に関して、おいしさの土台として使われるときの熱熱と、あの二人は熱熱だから、という、男女二人の相思相愛の関係が頂点にある、と言う意味の二つだ。否定的な意味合いを持ったものもたくさんある。これらの言葉を日常のなかで、なんの反省もないままに使っている人たちがたくさんいるのかと考えると、恐ろしい。
▼こちらからお読みいただけます
30 お焼き加減はいかがなさいますか
言葉の冒頭に「お」の字をつけて丁寧語にする、という習慣を僕はまったく持たない。友人とステーキの店に入り、友人はサーロインステーキ、僕はテンダーロインを注文して、「オヤキカゲンハイカガナサイマスカ」と、若い日本女性のウエイトレスに言われた。なんのことだか、とっさにはわからなかった僕が、いけないのだろうか。「オヤキカゲン」という音声は初めて耳にする日本語だったが、「お」の字を取り払うと、焼き加減でしかない。よく焼いてください、という僕の言葉に対して、ウェルダンですね、とそのウエイトレスは言った。
▼こちらからお読みいただけます
31 甘からの汁を肴にして
甘から、という言葉には意味がふたつある。ひとつは、菓子などの甘いものと酒の両方が好きな人のことだ。両刀遣い、と呼ばれている。もうひとつは、砂糖、醬油、塩、香辛料など、甘いのとからいのと両方がはっきり感じられる状態に調理したものだ。大きな魚のあたまを甘からに煮たものが居酒屋のメニューにある。これをひとつ取り、「僕は汁だけでいい」と言って小さな皿に甘からの汁を取る男性が、友人にいる。いっさい食べない。酒を飲むだけだ。割り箸にしみこませた甘からの汁を肴にして。
▼こちらからお読みいただけます
32 男性の存在が前提にされている
六十二年前の高校時代、卒業後に大学へ進学した女子生徒はいなかった。ほぼ全員が就職した。就職したとは、やがてどこかのサラリーマンと結婚した、ということだ。高校三年生の女性たちは、卒業して就職し、五年以内に結婚しないと、いき遅れ、と呼ばれた。売れ残り、という言いかたもあった。年齢を重ねた女性たちは、いかず後家、と呼ばれた。結婚して子供が出来ないと、それは男性のほうから言い出す離婚の理由になった。いまでもそうではないか。離婚して実家へ帰ってきた女性は、出戻り、と呼ばれた。どの言葉もじつにひどい、と僕は思う。
▼こちらからお読みいただけます
33 まもなくの発車となります
電車に乗り、男性車掌による車内アナウンスを聞くともなく聞く。次に停車する駅名を告げたあと、「お出口は左側です」と彼は言う。この場合の「お出口」とはドアのことだ。そして左側とは、その電車の進行方向に向かっての左側、という意味だ。ドアとは言わず、「お出口」と言ったほうが好ましい場面の要請に合わせただけなのだが、日本語の使いかたの具体例のひとつとして、かなり高度だ。続いて、外国人女性による録音アナウンスがある。Doors on the left side will open.と彼女は言っている。これを聞くたびに僕が不思議に思うのは、willというひと言の存在だ。
▼こちらからお読みいただけます
34 無邪気な直訳はホラーである
「ヒラメは英語でなんと言うか知ってます」と、友人が言った。確かflatfishのはずだが、「知らない」と僕は答えた。「フラット・アイズです」と友人は答えた。平たい目だ。「コハダは?」「それも知らない」「スモール・スキンです」
友人がどの方向へ話を持っていこうとしているのか、そこまで聞けば僕にもわかった。笑い話の方向だ。マグロの「マ」は「真」と解釈してそれを英語にするとトゥルーだという。「グロ」はクロだからブラックでいいとして、全体は、トゥルー・ブラックとなる、と友人は解説した。
▼こちらからお読みいただけます
35 男子と女子に分かれてせいの順に
子供が日本語を学習していくにあたって、学校が果たした役割は大きい。「男子と女子に分かれてせいの順にならびなさい」と校庭で何度となく言われた。せい、とは背丈のことだろう。男子と女子に分けるのが先生たちはほんとに好きだった。掌握しやすくなるからだろう。ホームルームの時間には先生がいつも「先生からはそれだけだ。なにか質問はあるか」と言っていた。これがそっくりそのまま、現在の会社のなかで現役だと、会社勤めの人が教えてくれた。何かについて報告した人が、私からは以上ですがなにかご質問はおありでしょうか、と決まりごとのように言うそうだ。
▼こちらからお読みいただけます
36 わずか三画のなかに日本のすべてがある
上という字には「ウエ」と「ジョウ」のふたとおりの読みかたがある。上下は「ジョウゲ」と「ウエシタ」だ。「ウエシタ」の場合は、上と下が単に逆になっている場合の表現に使う。「それじゃ上下が逆じゃないか」というふうに。天丼の上を注文するとき、「ウエ」をください、とはまず言わない。僕は中にします、と言いたいとき、僕は「ナカ」にします、と言う人はいないのと、同じ原理だ。これほどに高度な使い分けを、普通の日本人は、成長していく日々という完全な成りゆきのなかで、なんの苦労もなく、いつのまにか身につけていく。
▼こちらからお読みいただけます
37 外国人たちは日本語に接近している
アメリカのTVのニュース番組のアンカーが、トヨタのことをタイオーラと言っていた。TOYOTAを英語ふうに読むと、そうもなるのだろう。しかしこれはすでに昔語りだ。今では日本人と同じく、トヨタと言っている。カラオケの出始めの頃は、カリフォルニアではカリオーキだった。いまでは日本人と同じく、どこにも強拍を置かずフラットに、カラオケだ。ゲイシャにフジヤマ、あるいはスキヤキ、テンプラ、スシ、ウナギの時代は、遠く去って久しい。タイオーラやカリオーキの時代も充分に遠い。
▼こちらからお読みいただけます
38 豚肉の生姜焼きとポーク・ジンジャー
街を歩いていたら洋食の店があった。料理サンプルのならんだウィンドーに歩み寄って僕は観察した。豚の生姜焼きがあった。おなじ街をしばらく歩くと、ふたたび洋食の店があった。さきほどの店の、豚の生姜焼きとほとんど変わらないものが、この店ではポーク・ジンジャーだった。なぜ、ポーク・ジンジャーなのか。なかみはほとんどおなじだ。しかし言いかたは異なる。言いかたが違えば、託された気持ちも違うのではないか。それはどのように違うのか。
▼こちらからお読みいただけます
39 その日本語は原語を超えている
日本語への翻訳で最初から親しみ、従って日本語ではよく知っているけれど、原典ではなんと言っているのか知らないことが、僕の体験のなかでも、いくつかある。「赤毛のアン」という、日本のTVで放映されたアニメーションは、そのひとつだ。もとはカナダのものだが、このアニメーションでは、人物たちの台詞その他、すべてが日本語だった。登場人物のひとりに、マシュー・カスバートという年配の男性がいる。彼の口癖と言っていい「そうさのう」という言葉を、あるとき僕は、英語で知りたくなった。
▼こちらからお読みいただけます
40 大人たちが教えてくれなかった言葉
子供は漫画を読んではいけない、と身辺にいた大人たちに何度も言われたのを、いまでも僕は覚えている。僕も漫画をよく読んだ。子供が日本語を学んでいくにあたって、漫画の果たした役は大きい。「おい」「おい、こら」「おい、待て」「おい、待たぬか」漫画の主人公の子供たちは、大人たちから「おい」と呼ばれていた。僕が子供の頃はそうだった。「おい」「やい」「こいつ」「あいつ」「やつら」といった子供たちはすべて、「やっちまえ!」とか「やっつけろ!」などの対象だった。現実の世界には、このような言葉はなかった。漫画を子供が読むと悪い言葉を覚える、と言っていた大人たちを、いまおぼろげに僕は思い出している。
▼こちらからお読みいただけます
41 ノット・オンリー・バット・オルソー
ジョン・スタインベックという作家が書いた小説にEast of Edenというのがある。映画になってジェイムズ・ディーンが主演し、時代の象徴にもなった。この小説は『エデンの東』として知られているが、『東のエデン』だと主張する人が僕の知り合いにいる。Eastは「東」ですよ。これはこれでいいです。ofは日本語にするなら自動的に「の」となります。Edenはエデンですから、頭からぜんたいをひとつにつなげると、『東のエデン』となりますよ。これをどうしてくれるんですか、とその人は僕にも語気強く言った。エデンのなかで東に寄ったあたりがエデンの東なのです、とその人は力説する。冗談としてはかなり面白い。
▼こちらからお読みいただけます
42 手間は出来るだけ省きましょう
企業の部長である彼のところに、貰った名刺がたまっていく。名刺を整理しながら、この数年で気づいたことがひとつある。それは、営業、という言葉が消えていきつつある、ということだ。営業、という漢字が消え、片仮名語になる。新しい言葉が主として英語で次々に外から入ってくる。該当する日本語はない。しかも考えていると間に合わないから、かたっぱしから片仮名書きされていく。片仮名で書かれたとたん、それは日本語だ。こうして片仮名語が際限なく増えていく。
▼こちらからお読みいただけます
43 街を歩けば謎にあたる
ドトールの店舗まで自宅から歩いて五分だ。恵まれてますねえ、と感心した人がいた。このドトールにミラノサンドという食べ物がある。かねてよりこれに僕は惹かれてきた。Aが四百四十八円、Bが四百八十九円、そしてCが四百二十七円だ。BとCとの間に六十二円の差がある。六十二円の差はミラノにおいては大きい。AとCとの間には二十一円の差がある。AとBとの間には四十一円の差がある。この三とおりの差額を、僕はミラノサンドの謎として受けとめている。かつてドトールで珈琲一杯が二百円だった頃、僕はまだドトールの客になっていなかった。二百円だと知ったとたん、閃くものがあった。一杯が二百円の珈琲は小説に使える、という閃きだ。
▼こちらからお読みいただけます
44 きまり文句ですべてが間に合う
きまり文句が果たす機能は、すでにとっくに決まっている一定の枠を、どの人生にも当てはめることだ。きまり文句は結論でもある。きまり文句が登場すると、それは結論でありそこから先に話が進まなくなる。僕が子供の頃には、大人たちは誰彼なく、きまり文句を使っていた。状況ごとにきまり文句を当てはめるという、きまり文句で維持される社会だったのか。きまり文句は、当てはめさえすれば、それでいい。うまく当てはまると、達成感すらあったのではなかったか。
▼こちらからお読みいただけます
45 日本語はけっして曖昧ではない
日本語は曖昧だ、としばしば言われる。日本人自らが、日本語は曖昧だから、などと平気で言う。いったいどこが、曖昧なのか。日本語はきわめて端的だ、と僕は思っている。どの言葉も、言い当てている、という表現がまさにふさわしいほど、見事なまでに、端的だ。ぼかした表現をするときは、話者もそれを受け取る相手も、ぼかした表現であることを充分に承知している。ぼかした表現が原因となって深刻な誤解を生む、というようなことは、日本人どうしではまずあり得ないのではないか。
▼こちらからお読みいただけます
46 彼女を納得させるのは大変だからなあ
チャールズ・M・シュルツが一九六九年の一年間に描いた『PEANUTS』が、二〇一九年の日めくりカレンダーに転用されていた。その十二月三十一日の四コマ目、つまりその年の最後のコマは、チャーリー・ブラウンの嘆息で終わっていた。吹き出しのなかには入っていなかったから、チャーリーがひとり胸のなかでついた嘆息だ。「彼女を納得させるのは大変だからなあ」とライナスが言っているコマがあった。彼女とはルーシーだ。英語ではこの台詞は、She's a hard one to deal with.となっていた。やりにくい相手、という意味だが、その意味を拡大して、納得させるのは大変だ、という日本語の言いかたを当てはめてみた。
▼こちらからお読みいただけます
47 こういう言葉には頭を抱えるほかない
体のあちこちを引き合いに出した言葉が日本語にはたくさんある。目、口、鼻、耳、胸、手、背中、腹、…など、実に多彩だ。いちばん頂上にあるのが頭だ。その頭をめぐる言葉を探すと次々にあらわれた。髪の生えている部分を頭ととらえるなら、頭を刈る、という言いかたは、散髪することを意味する。いちばん初め、という意味の頭なら、頭から、という言いかたがよく知られている。頭出し、という言いかたは、録音テープを再生するにあたって、録音されたものの最初がすぐに再生されるように用意するという意味の言葉だ。
▼こちらからお読みいただけます
48 なんだ、そんなことも知らないのか
「なんだ、そんなことも知らないのか。きみは教養のないやつだなあ」。二十代の僕は、ひとまわりは年上の編集者から、何度かこう言われたことがある。教養という言葉はいまでも現役だろうか。柴又の寅さんが、あの軽い調子で、ときどき言う。「お前は教養があるねえ」と。「インテリの言うことは違うよ」という言いかたをするときもある。いずれの場合でも、言いかたはきわめて軽い。これが教養だと多くの人たちが勘違いしているものすべてを、寅さんは軽くからかっている。この軽さは注目に値する。
▼こちらからお読みいただけます
49 流れる川の水にすべてを託す
『小さな竹の橋で』は一九三六年にニューヨークのヒット・ソング業界で作られたもので、一九三七年にルイ・アームストロングがアンディ・アイオナと共演してレコードを作って、評判になったという。一九五一年の日本でこの歌がヒットしたそうだ。橋があれば、その下にあるはずの川の流れを、日本人は見てしまう。そしてそのときの自分の心情を、流れる川に託すのが、たいそう好きなようだ。川の水の流れにそのときの自分の心情を託した文章として、日本でもっとも広く知られているのは、鴨長明という人が十三世紀に書いたエッセイの、最初の一節だ。
▼こちらからお読みいただけます
50 戦争の経済的負担はとてつもない額になる
アメリカ軍は兵士たちに配付する腕時計として、電池式で本体はプラスティックの、軽量な腕時計を採用した。電池がなくなったら、電池を交換するのではなく、それはそのまま捨ててしまい、新品を使うのだ。だからこその、disposable watchだった。電池がなくなったら新品と交換したほうが、はるかに安くあがり、しかも簡単なら、ためらいなくそうするだろう。現実にそうしたのだ。disposable watchの、タイメックスによる正確な復元製品は、戦争とはまずなによりも先に、経済的な負担がとてつもない額になるものだということを教えてくれた。
▼こちらからお読みいただけます
51 日本語は滅びていくのだろうか
「だいじょうぶです」というひと言を、じつに多くの人が使っている。便利なのだろう。口をついてこの言葉が出てくる、という状態になっている。多くの人がいろんな状況のなかで使っているうちに使用範囲が広がっていく。同じ言葉が時には反対の意味にもなる。使用範囲が広がれば、意味も違ってくるのは当然だ。
▼こちらからお読みいただけます
52 英語を学ぶ教材としての英字新聞
英字新聞、という言葉に僕が初めて遭遇したのは中学生の頃だった。それまでは知らなかったものがまたひとつ増えた、という妙な感慨があったのを記憶している。日本国内で発行されていて、日本に住む外国人記者が日本の記者と協力して日本人の英語の勉強用に、あるいは日本にいる外国人のための情報源として編集しているのが英字新聞だ。しかし英字新聞、という言葉にはいまだになじめない。
▼こちらからお読みいただけます
53 日本語にならない英語というもの
『PEANUTS』の日めくりカレンダーで、眼鏡をかけたライナスが登場する。僕はかなりの衝撃を受けた。その次の日も主題はライナスの眼鏡だった。
I’m sorry that you have to wear glasses, Linus.
と、チャーリー・ブラウンが言っている。これに対してライナスは、
Don’t feel sorry for me, Charlie Brown.
と応じている。このふたつのSorryは日本語にならない。アイムソーリー、と片仮名で一語に書いて日本語にしてしまう、ということをいま僕は思いついた。
▼こちらからお読みいただけます
54 「俺」はしぶとく生きのびる
自分を意味する「俺」という言葉は、同輩や身内の人たち、あるいは目下の人たちのなかでのみ用いるくだけた自称だ。オレオレ詐欺は「俺」という言葉が身内でいかに多用されているかの証明だろう。流行歌や映画あるいは娯楽小説の題名のなかで、「俺」や「おれ」「俺たち」は静かに過去へと遠のいていく。日本の男たちによって、音声で放たれる「俺」は、まだ健在だろうか。日本全国に林立する会社のなかでは、彼らはまだ生きているようだ。
▼こちらからお読みいただけます
55 頭に「かね」のつく言葉を探してみた
かねは金という漢字になっている。かねのからんだあれやこれやは、俗世間のしがらみの典型ではないか。おかねの話をするにあたって、日本語は言葉に不足しない。かね目当て。かね次第。かねの出し入れ。かねのかからない。かねのために働く。かねに転んだ……。書き出したものを見ればわかるとおり、どちらかと言えば、かねはない。かねが充分にはない状態のなかで、こうした言葉を使う人たちの誰もが、生きている。ないかねをいかに工面するか。それが人生の醍醐味だ、ということにしておこう。
▼こちらからお読みいただけます
56 よろしかったでしょうか
ごく最近の出来事だ。僕に友人ふたりを加えて三人がカフェに入り、おなじ種類のコーヒーを注文した。「お砂糖とミルクはお使いになりますか」とウエイトレスに訊かれて、三人とも、どちらも使いません、と答えた。やがて三人のコーヒーがテーブルに届いた。「お砂糖とミルクはよろしかったですね」とそのウエイトレスは言った。彼女のこの言葉が僕には理解出来なかった。少なくとも、ただちに理解することは出来なかった。…話者である彼女が省略した言葉を、それを受けとめるほうの僕がおぎなうまでに、三秒ほどの時間が必要だった、ということだ。
▼こちらからお読みいただけます
57 丁寧さと正確さ、そしてご理解のはざまで
「まもなくしての発車となります」とアナウンスされるのを僕は初めて聞いた。「まもなく」のあとに「の」のない「まもなく発車となります」というアナウンスメントが、ある期間行われたあと、「まもなくの発車となります」と言われるようになったのではないか。「まもなくの発車となります」という言い方へと変えればより丁寧になり、しかもより正確になると話者が思えるようになる。このように思えるか、それとも、思えないのか。ここがもっとも大事なのではないか。
▼こちらからお読みいただけます
58 思っていないで答えをくれ
小説以外ではエッセイと呼ばれる短い文章を依頼されることが多い。「僕」という一人称で書くから、文章のあちこちで、「と僕は思う」と書いてきた。「と僕は思う」という言いかたには、現在の自分のすべてがある。ところがいまでは、「と僕は思う」は、可能な限り使いたくない言葉になっている。なぜなのか。そうなった最初のきっかけは、アメリカのジャーナリストが日本のサラリーマンを説得する現場に同席したことだ。「思う」という日本語の意味は広く、使いかたは多岐にわたる。それを「思う」のひと言で間に合わせているのだから、そこに問題を見るなら、問題は数多くある。
▼こちらからお読みいただけます
59 日本語能力試験N5に合格するか
日本語能力試験は英語ではJapanese Language Proficiency Testと言い、JLPTと略す。一九八四年に始まり、二〇一〇年から新しくなったという。外国の人が日本語の知識を使って、どのくらい日本の人たちとコミュニケート出来るのかを試すのだ。言語知識という問題はもっとも基本的なN5からいちばん難しいN1まで揃っていた。二十五分と五十分の二冊になっていて、N5の二十五分のほうはなぜだかすべて平仮名だ。もんだいようし、げんごちしき、もじ、ごい、などと印刷してある。五十分のほうは漢字で、言語知識(文法)・読解、などとある。僕にとっていちばん面白かったのは、二十五は「ふん」で五十は「ぷん」となっていたことだ。
出典=日本語能力試験公式ウェブサイト(https://www.jlpt.jp/)。
▼こちらからお読みいただけます
60 お前はネクタイがいつもゆるんでいる
大学を卒業して東京の商事会社に就職した僕は、二十三歳の五月の初めには新入社員としてひと月が越えた頃だった。ある日、僕は部長に呼ばれた。部長がまず言ったのは、お前はいつ見てもあくびをしている、というひと言だった。ネクタイがいつもゆるんでいる、いまもそうだ、ちゃんと締めろ、と部長は言った。ゆるんでいるのではない。苦しいからゆるめていたのだ。ゆるめているタイは、ゆるんだタイに見えてはいけない。この点に関しては、僕は反省した。タイのゆるめかたのうまい人になろう、などと思いながら、カタオカさん、電話です、通商代表部から、という電話に僕はその場を救われたのだった。
▼こちらからお読みいただけます
61 空飛ぶ円盤の時代は過ぎ去ったか
日本語でいちばん好きな言葉は、空飛ぶ円盤、という言葉だ。英語では空飛ぶ円盤はフライング・ソーサーと呼ばれた。ソーサーとは受け皿のことだ。公式な呼称は頭文字をとってUFOと書き、音声ではユーフォーと言い、日本語ではそのまま、未確認飛行物体、と訳された。受け皿が空を飛ぶずっと以前に、絨毯が空を飛んでいたような気がする。空飛ぶ絨毯、つまりFlying Carpetだ。このFlyingの翻訳が、空飛ぶ、だとしたら、それはそれで優秀な翻訳だ。空飛ぶ円盤の時代は過ぎ去った。しかし言葉の上に積もりかけた埃を払うなら、言葉そのものはいまも輝きを失ってはいない。
▼こちらからお読みいただけます
62 歌のなかの女性たち
歌われている女性主人公の名前が、題名あるいは歌詞に出てくる歌謡曲の、いちばん初めのものは『カチューシャの唄』だろう。一九一四年に中山晋平が作曲し、女優の松井須磨子が芝居の劇中歌として歌った。日本の歌謡曲はここから始まった、と言われている。『マノン・レスコオの唄』が一九二八年だ。中山晋平が作曲し西條八十が歌詞をつけた。マノンの血の涙が可愛い、と歌われている。一九四〇年には『お島千太郎旅唄』が盛んに歌われた。そして一九四二年には『湯島の白梅』が発表された。すごいではないか。歌謡曲の題名あるいは歌詞のなかに登場した女性たちは、外国の女性か、さもなくば、歴史的な事情のなかにその身を置かざるを得なかった女性たちだ。
▼こちらからお読みいただけます
63 母親をめぐって話はつきなかった
「べつになにかを教わったわけではないんですよ。いろんなことを教わりましたけれど、系統立てたものではないし、ひとつのことをいろんな視点から見る、というようなこととも、無縁でした」……僕が話を聞いている彼らは、ひとつの会社で勤続三十年ほどの男性たちだ。彼らが語る母親とは、こんな母親がかつて日本中いたるところにいたということであり、彼らはそんな時代に、母親とともにいる子供だった、ということでもある。
▼こちらからお読みいただけます
64 「こころ」について学習する
夏目漱石の書いた長編小説に、『こころ』という題名のものがある。「なぜ漱石は心という漢字を使わなかったのか、意見を述べよ」という試験問題があったなら、それはたいそう良い問題だ、と僕は判断する。こころ、とは、なにか。簡単に言うなら、精神作用を総合的にとらえ、なにからなにまで押し込んだ結果のものが、こころだ。昔は精神作用はすべて心臓が司る、と思われていた。こころはどこにありますか、と問われて頭を示す人は、まだ少ないだろう。
▼こちらからお読みいただけます
65 進駐軍の残飯の日々
『米陸軍日本語学校』(ちくま学芸文庫 二〇二〇年)の著者、ハーバート・パッシンは、シカゴ大学で人類学を教えていた。友人の助言に従ってアメリカ陸軍の語学研修生となり、戦後の日本でGHQの民間情報局に配属された。日本に進駐したアメリカ兵たちが目の前に見たのは、敗戦後の日本における食料の決定的な不足、つまり進駐軍の残飯を目ざした日本人たちの姿だった。パッシンは当時の日記に次のように書いた。「二〇人ほどの婦人たちと数え切れないほどの子供たちが、軍隊食堂の後ろの屑入れをあさり、残飯を欲しがった」。戦後の日本人が最初に体験した進駐軍の味や香りは、進駐軍の残飯だった。
▼こちらからお読みいただけます
66 はるかに遠く子供たちが遊ぶ
僕の左の拳ほどの大きさのトマトだった。赤く熟れていた。洗ってへたを取った僕は、そのトマトにかぶりついた。トマトをナイフで切ったりせず、そのままかぶりついて食べることをするのは、いったい何年ぶりのことになるか、と僕はそのトマトを食べながら考えた。子供のとき以来ではないか。ジャンケンをしてないなあ、と僕は思った。イシカミハサミ。グーチョキパー。ジャンケンポン、でイシカミハサミのどれかを出す。イシはハサミに勝つ、と言いたければ、Rocks win over scissors.と言わなければならない。イチ、ニ、サンと数えてサンで全員が出す、と言うなら、at the count of threeと言ったあと、ワン、トウ、スリーで全員が出す。このジャンケン何十年もしていない。
▼こちらからお読みいただけます
67 受話器に飛びついたのは、いつだったか
知ってはいるけれど自分では一度も使ったことのない言葉がじつにたくさんある。ということだった。知ったのは子供の頃だ。身辺にいた大人たちから学んだ。彼らはそのような言葉を使っていた。一九四〇年代そして一九五〇年代にかけての、僕がゼロ歳から二十歳にかけての期間だ。仕事として自分の言葉を使う作業を始めたのが二十歳からだ。大人たちから学んだ昔の言葉と、そのような昔を抜け出したあとの、自分なりの平明で単純な言葉の両方に、僕は時代的にまたがっているようだ。
▼こちらからお読みいただけます
68 スヌーピーが果した役は大きい
アメリカの新聞連載漫画『PEANUTS』は一九五〇年の十月二日に、いくつかの新聞で開始した。作者のチャールズ・M・シュルツは二十七歳だった。連載は五十年続いた。シュルツは実にさまざまな人物を作り、連載のなかに登場させた。主人公のチャーリー・ブラウンから始まって、ルーシー、ライナス、スヌーピー、その他、すべての人がシュルツだっただけではなく、彼らに託して連載のなかに描いたことのぜんたいがシュルツだった。あらゆるアイディアがじつは自分そのものだったことを表現する言葉として、シュルツはauthenticityという言葉を使っていた。
▼こちらからお読みいただけます
69 犬も歩けば棒に当たる
「人を見たら泥棒と思え」という諺がある。すごいではないか。他人は信用するな、という知恵を日本語はこんなふうに表現する、などと書くのは、現在の人が都会のなかですることだ。かつての日本つまり農村では、他人への不信は根本精神であり、それは排他精神として日本を作った。「人を見たら泥棒と思え」という表現は単純で誰にでもわかる。しかも生活のなかでの具体性をしっかりつかんでもいる。諺をわかりやすくするために、当時は人々の身辺にいくらでもいたはずの動物たちが、たくさん登場する。馬。蛙。猫。豚。猿。蛇。虫。狸。犬。鳥。蝙蝠。虎。それぞれ諺をよどみなく言えるかどうか。
▼こちらからお読みいただけます
70 花道はもはやどこにもない
「この世に男と生まれて」という言いかたはまだ現役だろうか。「あなたは男なんだから」そんなことはしなくていい、と母は言う。「あなたは男なんだから」そんなことは知らなくてもいい、とも彼女は言う。なんにも知らない、なんにも出来ない男たちが、こうして大人になっていく。「男はつらいよ」と柴又の寅次郎が言う。なにがつらいのか。今回も恋は成就せず、自分は道化を演じただけだ。そのことがつらいようだ。顔で笑って心で泣く、と言う彼の個人的な感慨を昇華させると、「男の涙は見せない」となる。
▼こちらからお読みいただけます
71 曇りガラスに必ずこう書いた
窓のガラスが湯気で曇っているような状態、つまり外は寒くてなかは暖かい、というようなとき、窓のガラスは曇っていた。その曇ったガラスに指先で文字を書くなら、それはバカという片仮名ふたつではなかったか。ごく簡単に、誰にでも書くことが出来た。図形を描くときには、へのへのもへじ、にきまっていた。馬鹿のつく言葉は多い。ざっと数えて三十は下らない。どの言葉も思いのほか外を向いている。馬鹿のつく言葉を眺めていると、楽しい。馬鹿が持っている側面のひとつが、こちらに乗り移ってくるからだろう、と僕は判断している。
▼こちらからお読みいただけます
72 知らなかった言葉を知るとき
ナポさん、という言葉を僕が最初に受けとめたのは、ナポさん、という音声だけだった。知らない言葉だ、と思うと同時に、知っていなければならない言葉でもあるだろう、と思った。あのときから五十五年ほどの時間が経過している。『0011 ナポレオン・ソロ』というTVのシリーズ・ドラマが一九六四年にアメリカで放映され人気だった。日本では一九六五年に放映されて人気を博した。その際には全編が日本語に吹き替えられていた。主人公の相棒の役を担当した声優の日本語の台詞のなかに、ナポさん、という言葉があった。イリアがナポレオンのことを、こう呼んでいたのだ、と謎は解けた。
▼こちらからお読みいただけます
73 人が生きるから人生なんだよ
一生、と書いて、イッショウ、と読む。イッセイやカズオは男性の名前としてはあり得る。ヒトナマ、イチナマ、イチオなどとは、かつての僕ですら読まなかった。しかしいまならごく普通にいるかもしれない、とふと思う。自分はすでに一生というものに関して、すべてを知っている、という気持ちにさせる言葉、それが一生だ。人生、という言葉についても、ほぼおなじことが言える。この言葉を見たり聞いたりして、すべて自分は承知している、分かっているつもりだ、という気持ちになる人は多いだろう。
▼こちらからお読みいただけます
74 ライナスは眼鏡をかけている
僕がいま使っている『PEANUTS』の卓上の日めくりカレンダーの、九月一日の最後のコマので、チャーリー・ブラウンの胸から顔にかけての高さのところで、ライナスが地面と平行に、空中に浮かんでいる。あまりのうれしさにライナスは空中に浮かんでしまったのだ。ライナスをこのように描いたのは、作者のチャールズ・M・シュルツにとって、これが唯一だったのではないか。最初のコマでライナスは「ミス・オーマーが戻って来るんだって!」と喜んで叫びながら両手を上げ、チャーリー・ブラウンに駆け寄って来る。ミス・オーマーはチャーリー・ブラウンやライナスの通っている学校の先生で、彼らのクラスの受け持ちだ。ライナスはこのミス・オーマーをたいそう気に入っていた。
▼こちらからお読みいただけます
75 未来への明かるい希望
LOVEがラブとなった日は特定出来るのではないか。一九六七年にザ・ビートルズが、All You Need Is Loveという歌を発表した。日本での題名は、『愛こそはすべて』というものだった。ザ・ビートルズのこの歌は、偉大な許可書のように機能したのではないか。あの四人がこう言ってるんだよ、と。この年、アメリカの軍隊が南ヴェトナムのメコン・デルタに、初めて侵攻した。デトロイトでは史上最大の黒人暴動があり、ワシントンでは平和行進が十万人を動員していた。未来への明るい希望などはどこにもなく、どうにもならない、という現実だけがそこにあった。だからこそと言うべきか、一九七六年の夏はsummer of loveだった。LOVEの対極に存在しているもの、それは戦争だった。日本ではそこが完全に抜け落ちたままに、LOVEは愛と訳され、流通することとなった。
▼こちらからお読みいただけます
76 サービスはまだ生きている
サービス、という言葉が日本語になってから、ずいぶん時間が経過した。サーヴィス、と書く人もいるが、サービス、でいい。なにしろそれは日本語なのだから。もとは英語の単語であるserviceが日本語になったのは、戦後すぐのことだろう。国語辞典で「サービス」を調べると、直接に物を作るのではなく、生産者と消費者とのあいだにあって、おたがいの便宜をはかる仕事、とある。そしてもうひとつ、本来の仕事を越えて特別の便宜をはかったり気配りしたりすること、という意味が説明されている。日本語としてのサービスという言葉の出発点はここにある、と僕は判断している。
▼こちらからお読みいただけます
77 一拍子、二拍子、四拍子
僕の自宅にある固定電話の十桁の番号のなかに、2という数字が四つある。自分のこの番号を電話で人に伝えるとき、僕は2を「ニ」と発音している。最初からだ。しかし復唱する相手は、いかなる場合であろうとかならず、2を「ニイ」と言う。このことに僕が気づいてから十年近くたっている。2と5そして9は「ニ」「ゴ」「ク」ではなく、「ニイ」「ゴオ」「キュウ」と発音される。4を「シ」と言う人はいるかもしれないが、その場合は「シイ」であり「シ」ではない。数字のどれもが、たとえるなら「トン」という一拍にならないといけない、という至上の命題が日本語にはあるからだ。
▼こちらからお読みいただけます
78 かつてはよく使っていたはずなのに
「とばっちり」。ちゃんと漢字がある。迸り、と書く。小学校一年生くらいの頃に知った。当時は人との関係が密接だった。身のまわりにいつも何人かの人がいた。だから自分が何か失敗をしでかすと、周囲の人たちがとばっちりを受けた。
「半ドン」。土曜日の午後は休み、という意味だ。ドンとは大砲の空砲の音だ。午後からは休みであることを人々に知らせるために、空砲とはいえ大砲が打たれた。その音を聞いて、ああ、午後は休みなのだ、と人々は思った。土曜日が休みであることがあたりまえの時代に、半ドンという言葉は、冗談まじりに由来を説明するときにしか、もはや出番はない。
▼こちらからお読みいただけます
79 アカンベーにレロレロバー
「アカンベーと言いながら、どんな動作をしたか、知ってますか」と、女性に訊かれて、僕は知らなかった。「知らなければ日本人の恥ですよ」とまで彼女は言う。アカンベーと言いながらある種の動作がとっさに出来るかどうかは、その人が日本人であるかどうかを分けるという。なぜ、僕は、そんなことを知らないのか。知らないと言えば、レロレロバーの意味や使い道も、僕は知らなかった。言葉は知っていた。レロレロバーだ。アカンベーと似ている。しかし、領域はまったく異なるという。
▼こちらからお読みいただけます
80 失敗は七回まで許される
『「猿も木から落ちる」そのほかの日本の諺』という本を購入した。日本で広く知られている諺を百編選び、そのどれにも英語訳をつけ、巻末にはその百編に対して、よく似た諺、というものをGB(イギリス)やUSA(アメリカ)に古くからある言いまわしから選んだ一覧がある。「猿も木から落ちる」はEven monkeys fall from trees.だ。和文英訳の試験に出したらいいのではないか、と僕はふと思った。「一寸先は闇」という諺の英語訳は、闇は一インチ前方に横たわっている、というものだ。一寸は一インチになっている。「おなじような諺の一覧」には、自分の未来を知る人はいない、という言いかたがあげてある。
▼こちらからお読みいただけます
81 自分にとって面白い日本語とは
「さー」「ささ」「さーっ」「さっ」「ざあ」「さあっ」「ざあっ」「さらさら」……。ひとつの音による言葉。それに半濁音や濁音がつくのかつかないのか。ふたつの文字で作る音を繰り返す言葉。半濁音や濁音はどうなるのか。子供の僕はこのような言葉に対して、最初の面白さを感じたようだ。こんなことをノートブックに書き、たとえば雨の日の午後、自宅で過ごす時間に、あちこち読んでは楽しんでいた。そしてこのことが僕の日本語能力の基礎を作ったのだと、いまでも真剣に考えている。
▼こちらからお読みいただけます
82 喋る人ではない、考える人なのだ
『PEANUTS』に登場するスヌーピーは単に喋れないのではない。彼は考える人だ。その考えを、自分で自分に言うだけではなく、スピーチ・バルーンのなかの台詞として、読者に伝えている。そしてそこに、スヌーピーの独自性がある。屋根の上で仰向けに横たわるスヌーピーを理解するためには、腹ばいになっているときのスヌーピーを理解しなくてはいけない、と僕は考えている。屋根の上で腹ばいになっているスヌーピー、というものがあるからだ。考えていることは明らかに異なる。姿勢の違いは思考の違いだ。
▼こちらからお読みいただけます
83 省略しなければやってられない
スーパーマーケットで買った商品の代金を支払ったりするカウンターは、レジと呼ばれている。僕がこの言葉を知ったのは二十代の初めだったろう。レジという日本語は、およそ六十年をへていまも現役であるだけではなく、ごく当然のことのように、完全な日本語になっている。そのレジにいる女性店員に、「レジ袋はいかがなさいますか」と言われた僕は、とっさにはその意味が理解出来なかった。きまり文句という定型をあてはめるだけ、という形の省略の向こうには、省略でもしなければ言うべきことが多すぎる、という事情がある、と僕は思う。
▼こちらからお読みいただけます
84 バイリンガルはこんなふうに発展する
京都・高島屋の建物に横長のポスターが貼られていた。このポスターの左のほうに、赤い英文字で次のような英文が読めた。Rising again. Save the world from Kyoto JAPAN.
外国の人がこのポスター全体を写真に撮り、短い感想とともに、電子メディアに掲載した。「ふたたび蜂起する。京都が世界をやっつける」と、この英文は翻訳出来る。英語としては単なる誤用だけれど、一見したところ英語風に英文字で表記された日本語、というものが、すでに日本の中で普及しているのではないか。日本特有の、としか言いようのないバイリンガルの、新たな発展の方向だ。
▼こちらからお読みいただけます
85 悲惨な現実と幸せな空想と
ドラえもんがドラ焼きを食べている様子を描いたコマを僕はいま見ている。このドラえもんのひとコマには、ドラえもんがドラ焼きを食べるときの擬音が、すでに描き込んである。パクパク、という擬音だ。モグモグ、モリモリ、ムシャムシャ、というものもあった。ドラえもんは一九三三年生まれの藤本弘さんの作品だ。食べるもののおいしさやまずさ、あるいは自分の好みのおやつなどに目覚めてそれを展開させていく年齢が、五歳から十五歳の十年間だとすると藤本さんの場合は一九三八年から一九四八年までであり、例えばその中の一九四四年について書くなら、当時の日本はアメリカと戦争をしていて、おいしい食べものなんてどこにあるの、という状況だった。
▼こちらからお読みいただけます
86 人の意志や態度を表す「腹」という言葉
わかりやすい日常の具体性で誰をも説得してしまう言葉。それが日本語だ。その場ですぐに思いいたるはずの、人間の体の各部を材料にした言葉が実に多い。腹、というひと文字は、見るからに日本語が好みそうだ。いまここで問題にしている腹とは、人の意志や態度だ。世俗のあれやこれやに、次々と対応していくのが人生というものだ。ほとんどの場合、かたちどおりのほぼ自動的な対応でやりすごせるが、意志や態度をはっきりさせないといけないとき、そこに腹が登場する。
▼こちらからお読みいただけます
87 彼女のコロッケ、彼のメンチカツ
ザ・キングストン・トリオの Ballad Of The Shape Of Things という題名の歌を初めて聴いた頃の僕は、短編集を一冊作ろうとしていた。『物のかたちのバラッド』という日本語訳を、そのままその短編集の題名に使った。アメリカやイギリスの歌の題名の日本語訳を、僕は何度か自分の短編の題名にしている。数多くの題名のなかに統一感はまったくない。物語はひとつずつ違っている。だとしたら題名もそれに準じるのは、当然のことだ。
▼こちらからお読みいただけます
88 ギョウニンベン
ギョウニンベンという日本語を突然思い出した。僕が十歳くらいの頃か、もっと早く七歳ほどの頃だったか、母親から教わった。行人偏と書く。同時に人偏という言葉も教えてもらった。左側の狭い空間に書くのだから、「人」は縦長になる。幼い僕の日本語のなかに漢字が入ってくる年齢だった。それまでは知らなかった漢字をひとつ知ることを、いまの僕の言葉で表現するなら、そこに穴がひとつあき、その穴から外を見るような気分だった、とでもなるだろうか。
▼こちらからお読みいただけます
89 『言葉の人生』あとがき
言葉は人によってさまざまに使われるものだ。人によって使われた言葉、というものは厄介をきわめる。この僕は日本語を使ってきた。日常の現実を生きるにあたっては日本語を使い、その日常のなかでなにほどか創造的な世界を作り出すにあたっても、日本語を使ってきた。人によって使われた言葉、というものが、自分のなかにあるではないか。僕が使ってきた日本語。それは、なになのか。日常はほかの多くの人たちとさして変わらないとして、なにほどか創造的な世界を作り出すにあたって用いた日本語は、僕ひとりの日本語なのだから、独特なものなのだと言っていいだろう。
▼こちらからお読みいただけます
2023年12月22日 00:00 | 電子化計画

