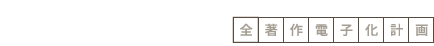【特集】 片岡義男のエッセイで読む ボブ・ディラン
2025年2月28日(金)、ボブ・ディランの伝記映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が公開されます。1961年の冬、19歳でミネソタからニューヨークへとやってきた無名の青年ボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)が、ニューヨークのフォークシーンに飛び込み、独自の音楽性で時代の声となるまでを追った映画で、1965年7月のニューポート・フォーク・フェスティバルでの衝撃的なパフォーマンスで世界に衝撃を与えるまでが描かれます。
片岡義男はボブ・ディランとほぼ同世代であり、ボブ・ディランが23歳の時に書いた『タランチュラ』(初版1973年、2014年再刊/角川書店)で翻訳を担当しています。その後、ディランの音楽や、彼が出演もしくは彼を扱った映像作品については折に触れエッセイや評論の形で書いてきました。そして2020年の『彼らを書く』(光文社)では、ボブ・ディランが登場する映画、ドキュメンタリー、ライブ映像など13作品を取り上げ、ディランへの想いを存分に綴っています。
この特集では片岡義男がボブ・ディランについて書いたエッセイと評論からいくつかを紹介します。映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』をご覧になる前の予習として、すでにご覧になった方は復習を兼ねてぜひご一読ください。ボブ・ディランと映画への理解がより深まるはずです。
1)「ロバート・ジンママン」(『エルヴィスから始まった』より)
現在でも「ロック愛好家のバイブル」として読み継がれている『エルヴィスから始まった』。第8章「1960—1970 アメリカ」の「〈5〉ロバート・ジンママン」の項で、ボブ・ディランの生い立ちとその時々に彼と関わった人々の証言、インタビューの断片などがまとめられており、出生から1970年頃までのディランの軌跡を大まかに把握できます。ちなみに「ロバート・ジンママン」はディランの出生時の本名です(現在は戸籍上の名前もボブ・ディランに改名)。また、他の章にも時折ディランの名前が登場します。
(『エルヴィスから始まった』ちくま文庫/1994年、『ぼくはプレスリーが大好き』(三一書房/1971年)改題)
2)『「タランチュラ」あとがき』
ボブ・ディランが23歳の時に書いた初の文芸作品『タランチュラ』の日本版で、片岡義男は翻訳を担当しました。本編には目次もなく散文詩のような文章が続くため「難解」というイメージが定着してしまっていますが、片岡はそのイメージを払拭すべく「あとがき」の中で「『タランチュラ』のなかにメッセージをさがすのは愚挙だし、みんながあれほどまでにボブ・ディランに求めつづけたこたえも、ありはしない。だが、ひとりの表現者としてのボブ・ディランがなにを言おうとしているのかは、充分すぎるほどに聞きとどけることができる」と書いています。「あとがき」ですが、本編を読む前に読むことをお勧めします。
(角川書店/1973年、2014年に復刊)
3)『What's he got to say?』
2005年に公開されたマーティン・スコセッシ監督の映画『ボブ・ディラン ノー・ディレクション・ホーム』の映画評です。この映画はボブ・ディラン初の本格的な自伝的長編ドキュメンタリーであり、これまでカメラの前でインタビューを受けなかったディランの貴重な証言と数百時間に及ぶ資料映像から構成された3時間20分という長尺の作品です。インタビュー自体は2004年から2005年に行われていますが、映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』でも描かれている、1965年7月のニューポート・フォーク・フェスティバルの翌年をこの作品の終着点としたことで「ディランは時間を飛び越えた超越的な存在となっている」と片岡は綴っています。この翌年(1966年7月)、ディランの身に何があったのかは、多くのファンが知るところでしょう。
なお、タイトルの「ノー・ディレクション・ホーム」は、ディランの1965年の曲「ライク・ア・ローリング・ストーン」の歌詞の一節から採られています。ちなみに片岡義男も「ライク・ア・ローリング・ストーン」をタイトルに使った小説を1973年に書いています。
(『現代詩手帖』2018年8月号掲載)
4)『新しいリスナーのためのボブ・ディラン』
『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』を観てボブ・ディランに興味を持ち、これから彼の曲を聴いていこうとする方にぜひ読んでいただきたい作品です。
このエッセイが書かれた2007年の時点でボブ・ディランのCDは36作品、映像作品DVDも多く存在し、ディランについて書かれた本は資料によれば500冊近くあるそうです。しかも「笑うべきところでは笑えるほどの英語能力」も必要となれば、ディラン初心者は途方に暮れてしまうかもしれません。このエッセイはそんな方への作品理解の一助になるはずです。特に彼の歌詞は時代背景も相まってメッセージ性が強いとよく言われますが、片岡は「彼からメッセージを受け取ろうとしてはいけない」と明確に否定しています。
また、『彼らを書く』の編集者・篠原恒木さんとの会話の中でも「ディランの聴き方」について話しています。
(『Switch』2007年11月号)
5)『彼らを書く「今度はボブ・ディランをDVDで観る。」』
『彼らを書く』は、ザ・ビートルズ、ボブ・ディラン、エルヴィス・プレスリーが主演あるいは登場する映画から31作品を取り上げ、片岡義男独自の筆致で内容の紹介と共に映像の中の「彼ら」について綴ったものです。
ボブ・ディランについては13作品を取り上げていますが、この中にはドキュメンタリーやライブの記録映像だけでなく、彼が役者として出演し音楽も手掛けた西部劇映画『ビリー・ザ・キッド 21歳の生涯』(1972)や、同じ西部劇ながらコメディーである『ボブ・ディランの頭のなか』(2003)なども含まれるなど、片岡流の作品選択のセンスも効いています。音楽だけでなく映像からもディランを追いかけたいという方や、その時代ごとの音楽シーンの雰囲気も併せて知りたい方には格好のガイドです。なお、編集者の篠原恒木さんによるメイキングも併せてどうぞ。
(『彼らを書く』所収、光文社/2020年)
6)『ロックンロール・ミュージック』
1973年発行の『10セントの意識革命』に収められた一篇です。ロックン・ロールが出現した1950年代半ばから60年代半ばまでのそれぞれの時代を代表するエルヴィス・プレスリー、ボブ・ディラン、ザ・ビートルズの3組のアーティストを軸に、ロック音楽の歴史を概観しています。アメリカ社会の変化とロック音楽の関係について考察したものですが、『エルヴィスから始まった』の「ごく短いダイジェスト」としてもお読みいただけます。
注)作品中、今日からみれば不適切と思われる言葉や表現がありますが、作品が書かれた時代背景と作品的意義を考慮し、原文のまま公開しています。
(『10セントの意識革命』所収、晶文社/1973年初版、2015年改版))
7)『サウンドスケープを歩く 8』
「サウンドスケープを歩く」は音響機器メーカーのBOSE(ボーズ)とのコラボレーションとして雑誌連載されたオーディーオ・エッセイです。この回ではボブ・ディランのデビュー・アルバム『ボブ・ディラン』と2作目『フリーホイーリン』のCDを「BOSE・125ウェストボロウ」スピーカーで聞いた際の感動について書いています。
(『Coyote』No.23 2007年12月号掲載)
8)『レノン。ディラン。プレスリー』
片岡義男.comで2017年12月〜2021年3月まで連載されたオリジナルの写真エッセイ『東京を撮る』の一篇です。連載途中にコロナ禍に見舞われ、本来の「外出して東京の写真を撮る」というコンセプトの軌道修正を余儀なくされた後のものですが、ボブ・ディランの日めくりカレンダー、片岡義男も翻訳に携わった『絵本ジョン・レノンセンス』とその原書、50年ほど前に古書店で手に入れたプレスリーの歌本という3つのアイテムをメインに、身の回りの小物をデジタルカメラで撮影しエッセイを添えてあります。それにしてもボブ・ディランの日めくりカレンダーというものがあるとは知りませんでした。
(『東京を撮る』ボイジャー/2020年4月)
Previous Post
Next Post