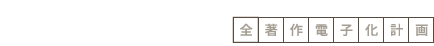No.18|大竹昭子「写真の無意識に導かれて」
週末の夕方、学芸大学駅前のビストロで食事をし、食べ終えて外に出ると、東急目黒線に乗れば家のある四谷まで一本で帰れるのに気がつき、沿線のどこかの駅まで歩くことにした。地図もスマホも持たずに、おおよその見当をつけて歩きだしたところ、途中で興味深い道に入ったりするうちにわけがわからなくなった。道が錯綜している上に、もともと不案内なエリアであり方向感覚がない。最後は歩きつかれて通りかかったバスをつかまえ目黒駅に出て帰路についたのだったが、迷いつつ歩いたその夜の道行きはすばらしく、これほど確かな歓びがほかにあるだろうかと叫びだしたいほど満ち足…
前の作品へ